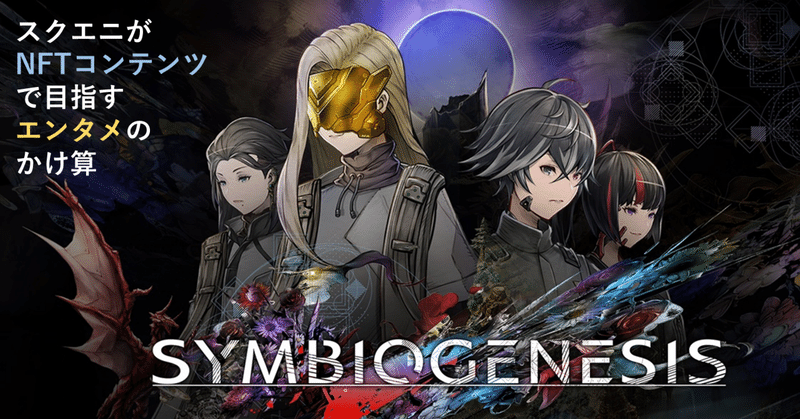
スクエニがNFTコンテンツで目指すエンタメのかけ算、「SYMBIOGENESIS」開発現場の思い(コラム)
スクウェア・エニックスは近年、ブロックチェーン・エンタテインメント領域の推進に注力しており、2023年12月には同社初となる NFT コレクティブルアートプロジェクトであるファンタジーアドベンチャー「SYMBIOGENESIS(シンビオジェネシス)」を本格展開しています。エンターテイメントにブロックチェーン技術を掛け合わせることでどのような価値創造を目指しているのか、インキュベーションセンター ブロックチェーン・エンタテインメントディビジョン ディレクターの畑圭輔さんと、同部署所属でSYMBIOGENESISプロデューサーの玉手直之さんに話を聞きました。
NFTアートを保有して遊べる楽しさ
――スクウェア・エニックスがブロックチェーン事業を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
畑:2018年に松田洋祐代表取締役社長(当時)の声がけでブロックチェーン領域のタスクフォースが立ち上がったのが最初です。松田はブロックチェーンという新しい要素技術から新しいエンタメを生み出せるのではないかと考え、当時、全社的な支援をする業務部にいた私がメンバーに選ばれました。
約3年、通常業務と並行しながらトレンドや要素技術のレポーティングをしていましたが、このままレポーティングを続けるよりも自分たちの手でプロダクトを作り、世に出した方がいいのではないかという気持ちが芽生えるようになりました。2021年から具体的に企画を考え、同年10月に同社初のNFTデジタルシール「資産性ミリオンアーサー」をリリースしました。

――初のNFTプロジェクトにはどんな狙いがあり、その結果、どんな成果があったのでしょうか。
畑:ミリオンアーサー自体は、初作品「拡散性ミリオンアーサー」を2012年にリリースして以降、アジア圏を中心にファンを獲得し、これまで様々なプラットフォームで展開するなど多くのチャレンジをしてきたIPです。そういった背景があったからこそ、ブロックチェーン×IPで新たなチャレンジを考えた時に、最初に浮かんだIPでした。
我々はNFTの特性である保有情報の証明に着目し、デジタルデータをコレクションして保有する楽しみをミリオンアーサーのIPで提供できればと考えました。コレクションだけでなく、ユーザー自身がデータをカスタマイズできるところもポイントとして設計しています。実際に販売してみるとユーザーからの反応は良く、販売も好評だったことから、事業部を立ち上げて開発を進める機運が一気に高まり、2022年2月にブロックチェーン・エンタテインメント事業部(現:ブロックチェーン・エンタテインメントディビジョン)を新設しました。すぐに新しいプロジェクトの開発を始め、2023年12月に「SYMBIOGENESIS」を本格展開しています。
投資の側面から興味を持った新しいユーザー層
――SYMBIOGENESISは、多数のキャラクターが共生する浮遊大陸が舞台となったプロジェクトであり、ユーザーはDiscord上で情報交換をしたり、隠されたアイテムを探したりしながら物語を進めます。販売しているキャラクターはNFTコレクティブルアートになっており、ユーザー自身が価格を設定して二次販売ができるようになっています。このSYMBIOGENESISはどのような価値提供を目指して開発されたのでしょうか。

玉手:資産性ミリオンアーサーを一つの成功体験として、NFTアート市場に新しいエンタメを届けられないかという着眼点から企画が始まりました。特にNFTアートで価値を保存するという点に注目しました。金銭的な価値はもちろんですが、思い出的な価値という捉え方もできるのではないでしょうか。NFTアートは10年後、20年後も価値を保存できるものですし、「当時の自分はこのキャラクターで遊んだな」「あの時、あの選択をしたな」など、NFTアートが当時の記憶や思い出を形にし、ユーザー同士のコミュニケーションのきっかけにもなればと考えました。
ブロックチェーン技術の活用とはまた別の話になりますが、一般的なNFTアートプロジェクトとの違いとして、SYMBIOGENESISではキャラクターの魅力やコンテンツとしての面白さにとことんこだわりました。キャラクターデザインは1万体にも及びますが、AIなどでジェネラティブに作るのではなく、世界観、物語、土地、種族、職業、人物を踏まえて1体1体、人の手でパーツを組み合わせて丁寧に作っています。つまり、その土地にその人物がいる合理性を突き詰めてデザインしているという意味です。シナリオについては、小説に換算すると20冊分にも及ぶ膨大な物語を収録しており、それを読んで遊ぶ仕組みになっています。物語はキャラクターと密接にリンクしており、セットで楽しめるところが大きな魅力です。

――従来のゲームとSYMBIOGENESISでは、ユーザー層に違いはありますか。
玉手:従来のゲームは純粋にゲームが好きな人、もしくはアニメや漫画からゲームに興味を持った人が大半ですが、SYMBIOGENESISには投資としての可能性も含むことから、金融知識を持つ人や投資的な興味から始めた人も一定数います。とは言え、投資的な興味から入った人も、コンテンツとしての面白さを軸足としてSYMBIOGENESISに親しんでいるようです。
一般的に、投資的な興味からプロジェクトに参加した人の場合、Discordではトークンの価値やキャンペーン、次買うべきプロジェクトなど、投資的な話で盛り上がる傾向がありますが、SYMBIOGENESISのDiscordでは、どのように楽しむか、どうしたらクリアできるかなどというゲームコミュニティ的な会話が中心になっています。ローンチから約3カ月でキャラクターは約500体発行され、中には一人で10体以上保有しているユーザーもいますが、平均して一人1~2体のキャラクターを保有しているという状況です。

NFTを推し活への手段として
――ブロックチェーン・エンタテインメントディビジョンとして、今後の方針を教えてください。
畑:ブロックチェーン・エンタテインメントは引き続き重点投資領域として取り組んでいきます。新しい領域であるため、事例づくりからビジネスとしての収益性まで、どのような可能性があるのかは早期に結果を出していこうとしています。
――今日では様々なタイトルのNFTゲームがあり、楽しみ方も多種多様になっています。ゲームにブロックチェーン技術が加わる過程の中で、プロダクトの作り手として変化を感じることはありますか。
畑:ゲームに投資的な側面が加わると、自分が保有するNFTでの利益にエンゲージメントを置いているユーザーも一定数現れますし、それも一つの楽しみ方だと思っています。一方で、エンタメが好きで、IPやキャラクターへの推し活への手段としてNFTを活用するというムーブは一つあると考えています。我々が従来のようにゲームやサービスを作ってユーザーに提供するだけではなく、そのNFTのオーナーシップがユーザーに渡るという意味で、事業運営にユーザーが介入できるようになってきたというのも一つの変化だと思います。ゲームやサービスを提供する側として、NFTを活用したユーザー同士のコミュニティや活動を盛り上げる仕組みづくりも必要だと感じています。
玉手:従来のゲームエンタメは、豊かな体験や楽しい時間を提供する側面が大きかったと思いますが、そこにプラスして投資的な可能性も含んだゲームを展開できれば、新しいゲームエンタメの可能性が開けていくでしょう。エンタメはファンがいてこそなので、ファンに楽しんでいただくことが第一ですが、ブロックチェーン技術を加えることで、ファンの資産が増えていくと私たちが提供するエンタメの価値も上がっていくという相関関係が生まれます。プロダクトの作り手として、そうした二軸の価値創造にトライしていきたいと考えています。
取材協力:株式会社スクウェア・エニックス

Web3ポケットキャンパスはスマホアプリでも学習ができます。アプリではnote版にはない「クイズ」と「学習履歴」の機能もあり、よりWeb3学習を楽しく続けられます。ぜひご利用ください。
▼スマホアプリインストールはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
