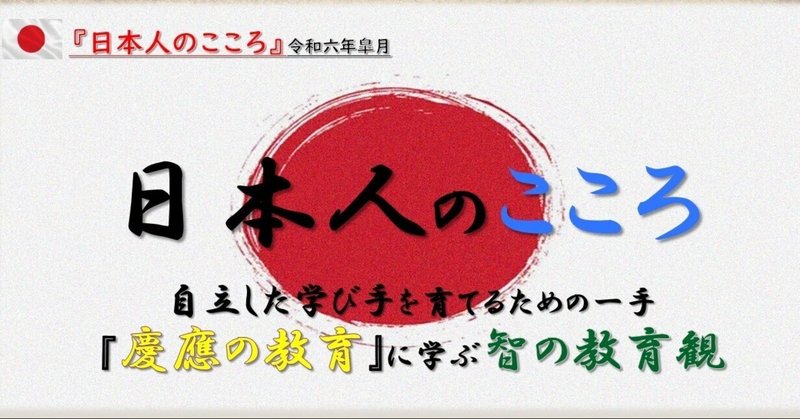
自立した学び手を育てるための一手『慶應の教育』に学ぶ智の教育観(前編)~勉強するのは何のため?~ー『日本人のこころ』18ー
こんばんは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

5月のゴールデンウィークに入ると、
田植えをするご家庭が増え、
夜風といっしょに流れてくる自然の心地よい香りが何とも言えません。
改めて我が国の自然の美しさ。
自分の住んでいる国への感謝の気持ちが湧いていきます。
ゴールデンウイークとは、
祝日の連続からなるものです。
そして、その祝日一日一日には意味があります。
2000年以上続く我が国は、歴史が長い分、
世界各国と比較しても祝日の数が多いです。
それほど、我が国にとって大切な日だということです。
そのような我が国の歩みに思いを馳せて、
今日も学んでいきたいと思います。
今回もよろしくお願いいたします。


突然ですが、質問です。
私たちはなぜ勉強をするのでしょうか?

例えば、
「いい大学やいい会社に入るため」
「テストでいい点数をとるため」
「自分のことをもっと知るため」
「忍耐力をつけるため」
「記憶力を磨くため」
「論理的思考力をはぐくむため」
「いろんな人が必要だと言っているから…なんとなく…」
様々な答えが出てきますが、
どれもなんだか正解のようで的外れな気がする…。
「なんで私たちは勉強なんかしなきゃいけないの?」
この問いは、だれでも一度は考えたことがあるけれど、
でも同時に多くの人が途中で考えるのをやめてしまった問いではないか
と思います。
だって考えても答えなんか出ないし、
結局なんだかんだ言って
「しないといけないものは、しないといけない。」
ということになっているのだから。
もしかしたら、
「学校の勉強なんて意味がない!」と
いさぎよく勉強をやめてしまった方も多いのではないでしょうか?

みなさんは
一回始めてしまうと面白くて面白くて熱中して
何時間も没頭してしまった経験をしたことはありませんか?
例えば、ゲームです!
ゲームにはまってしまうと、1時間があっという間!
下手したら寝なくても大丈夫なほど没頭してしまう思いを
したことはないでしょうか?
誰かに「やるな!」と言われてもかくれてでもやってしまう。
今のゲームは本当によく進んでいて、
離れている友達とも一緒にプレイすることができちゃうのだから
本当に楽しいものですよね!

ゲームだったら、
1時間でも3時間でも10時間でも熱中してできるし、
むしろ自分から進んで取り組んでしまうのに、
なんで勉強となると、10分で眠たくなってしまうのか?

答えは簡単です!
ゲームは面白いから何時間だって、何十時間だってできます。
親がやるなと言っても隠れてでもやります。
でも、勉強はつまらないと思うから10分も続かないのです。
ちなみに、
ある調査によると、社会人の平均勉強時間は約6分であり、
勉強している人の割合は1割未満という衝撃的な数字も出たりしています。
親がやりなさいと言ったってやりたくたいものはやりたくない。
ということは、どういうことかというと、
勉強のおもしろさを発見してしまえばよい!
ということなのです。
学ぶということは、本来は面白いものなのです。
でも、みんな面白くないと思っている。
だから、
勉強のおもしろさを知ることが大切なのです!
では、
どのような考え方を持つことができれば、
学ぶことがおもしろくておもしろくてしょうがない!
自分から進んで勉強をしちゃう!
そのような学び手を育てることができるのでしょうか?

今回は、
「自立した学び手を育てるための一手 『慶應の教育』に学ぶ智の教育観」
という主題でお話をしていきます。
最後までお付き合いいただけると嬉しく思います。
次回以降、詳しくお話をしていきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国民一人一人が良心を持ち、
それを道標に自らが正直に、勤勉に、
かつお互いに思いやりをもって励めば、文化も経済も大いに発展し、
豊かで幸福な生活を実現できる。
極東の一小国が、明治・大正を通じて、
わずか半世紀で世界五大国の一角を担うという奇跡が実現したのは
この底力の結果です。
昭和の大東亜戦争では、
数十倍の経済力をもつ列強に対して何年も戦い抜きました。
その底力を恐れた列強は、
占領下において、教育勅語と修身教育を廃止させたのです。
戦前の修身教育で育った世代は、
その底力をもって戦後の経済復興を実現してくれました。
しかし、
その世代が引退し、戦後教育で育った世代が社会の中核になると、
経済もバブルから「失われた30年」という迷走を続けました。
道徳力が落ちれば、底力を失い、国力が衰え、政治も混迷します。
「国家百年の計は教育にあり」
という言葉があります。
教育とは、
家庭や学校、地域、職場など
あらゆる場であらゆる立場の国民が何らかのかたちで貢献することができる分野です。
教育を学校や文科省に丸投げするのではなく、
国民一人一人の取り組むべき責任があると考えるべきだと思います。
教育とは国家戦略。
『国民の修身』に代表されるように、
今の時代だからこそ、道徳教育の再興が日本復活の一手になる。
「戦前の教育は軍国主義だった」
などという批判がありますが、
実情を知っている人はどれほどいるのでしょうか。
江戸時代以前からの家庭や寺子屋、地域などによる教育伝統に根ざし、
明治以降の近代化努力を注いで形成してきた
我が国固有の教育伝統を見つめなおすことにより、
令和時代の我が国に
『日本人のこころ(和の精神)』を取り戻すための教育の在り方について
皆様と一緒に考えていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
