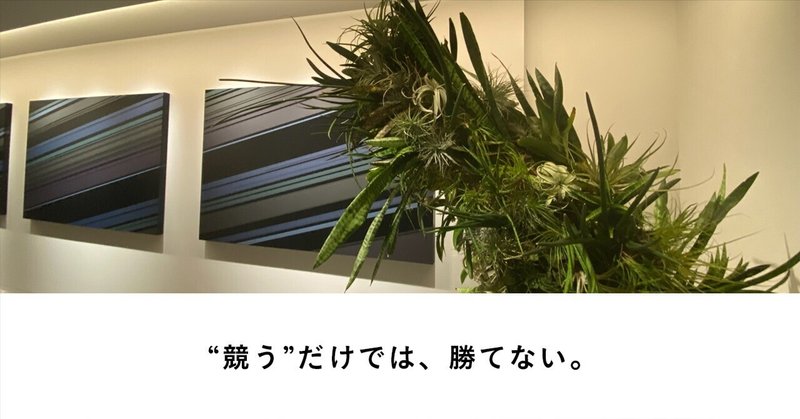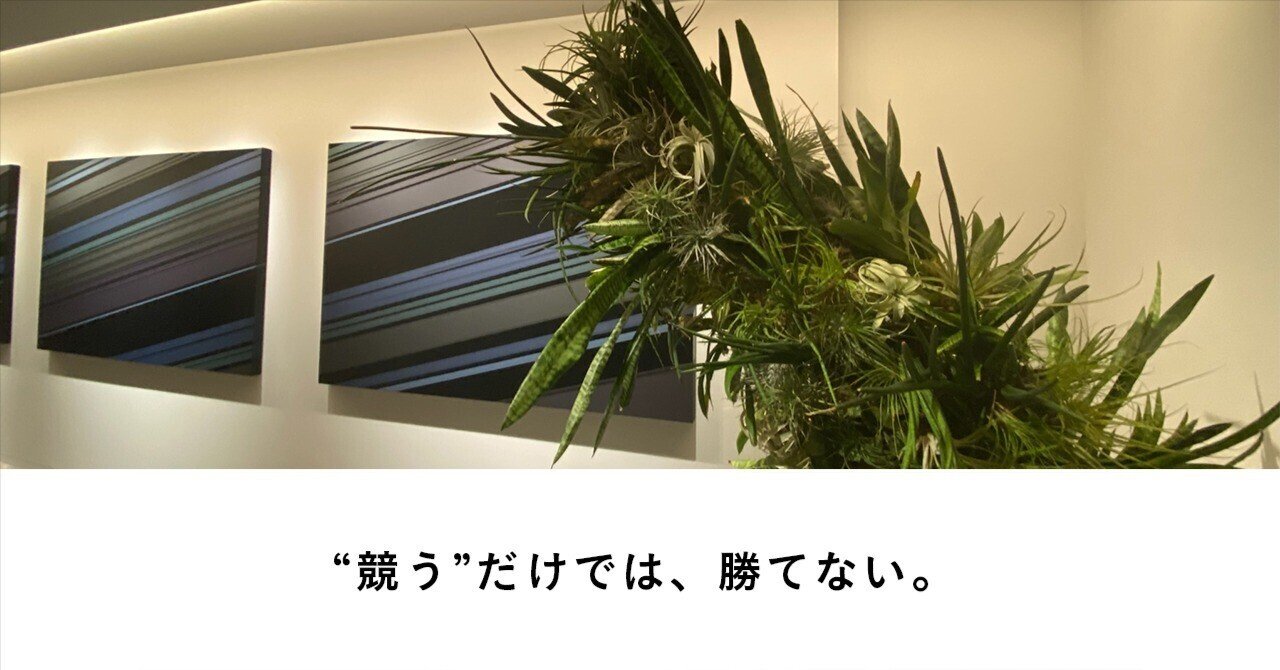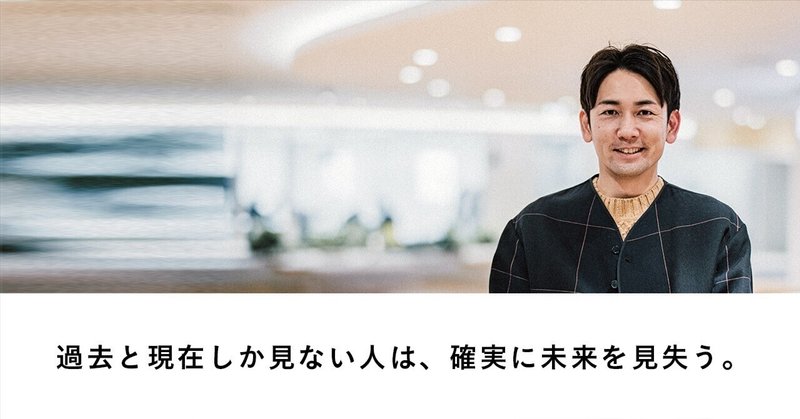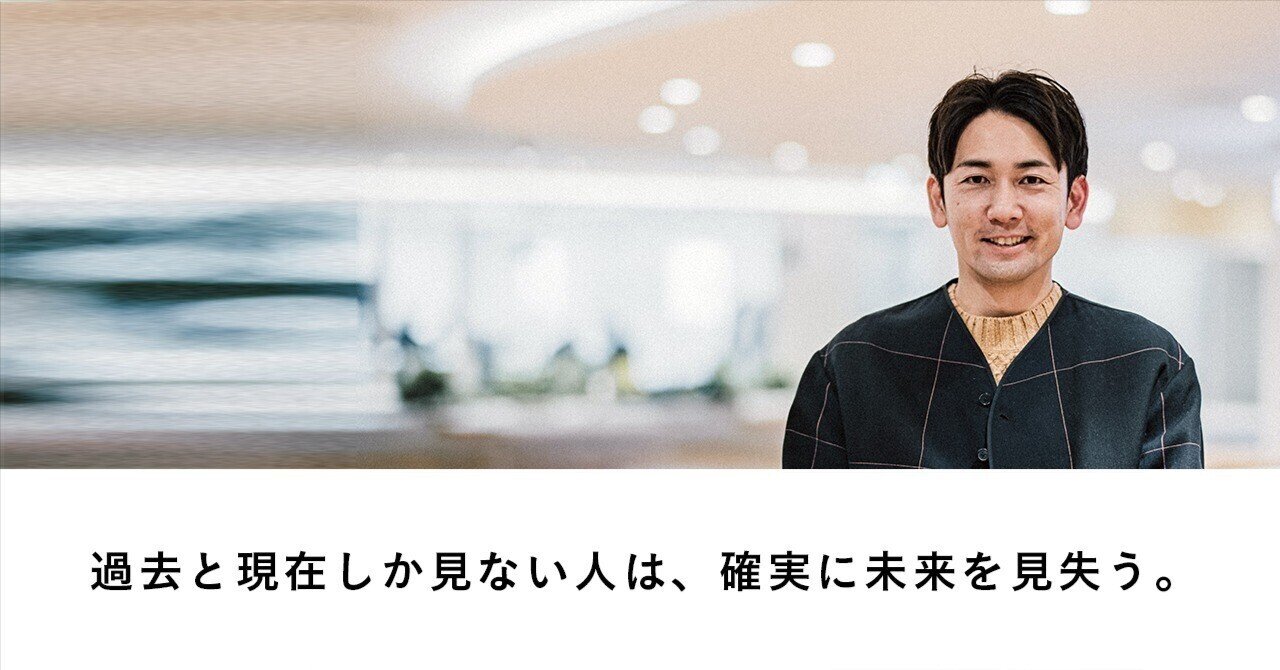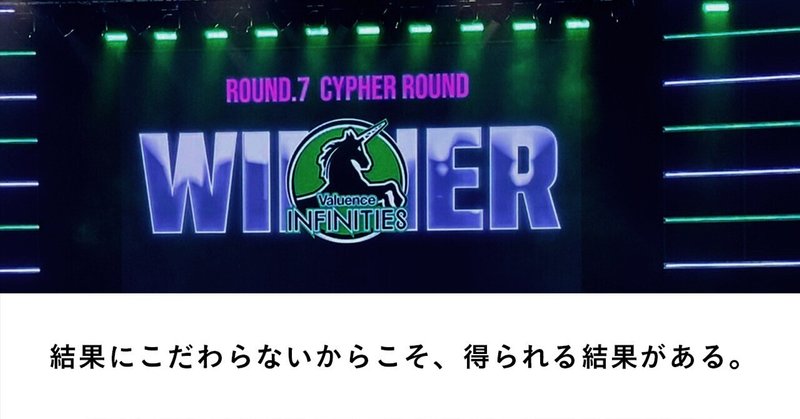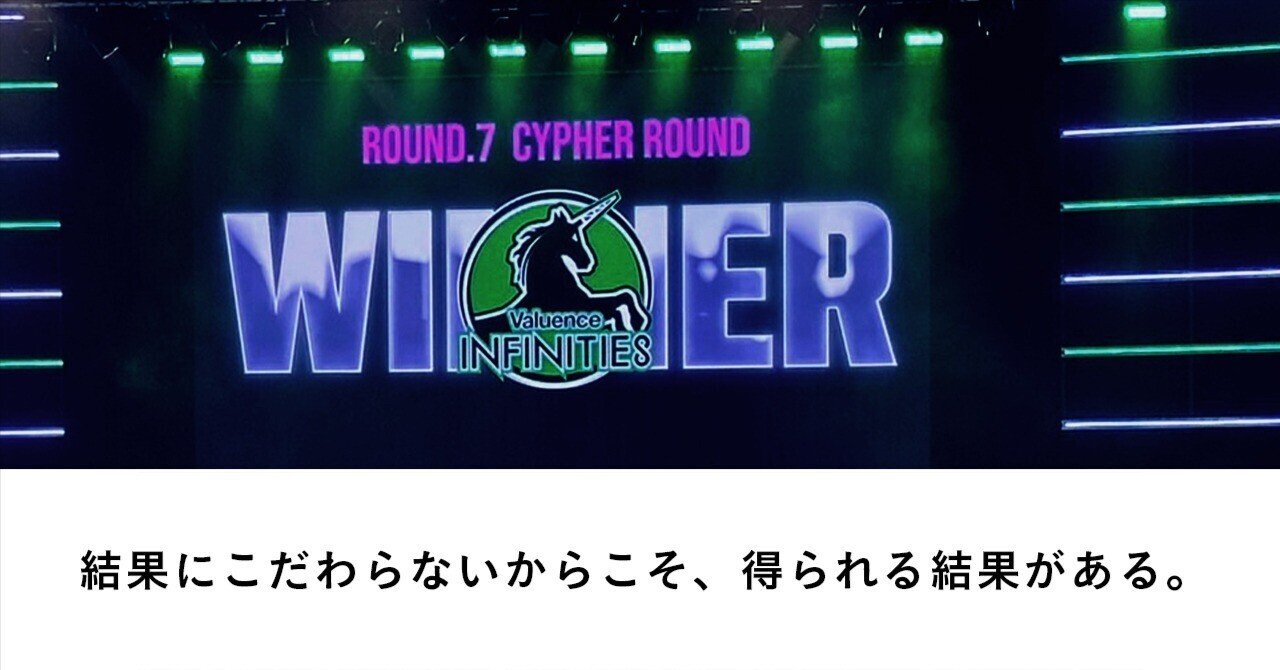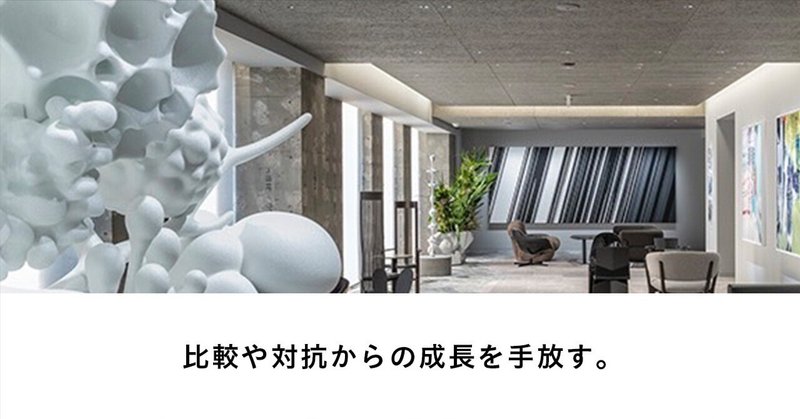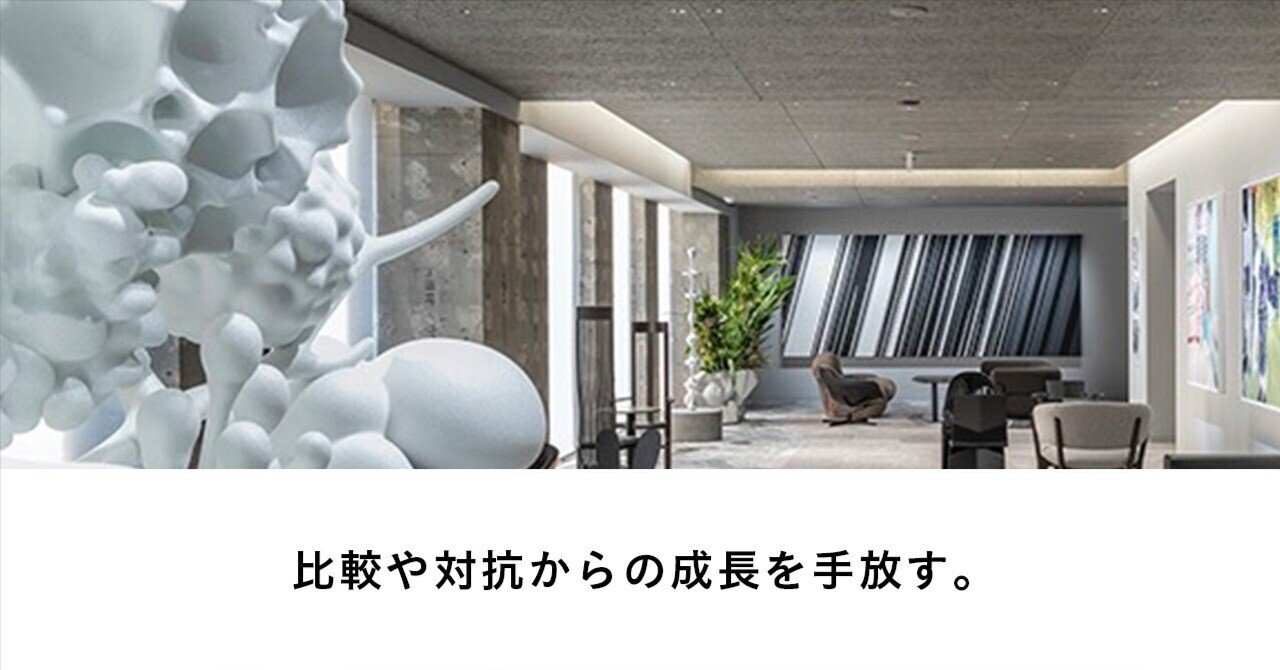最近の記事
- 固定された記事

フリマアプリ、オンラインでの取引が当たり前でも、“フィジカル“なリアル店舗が重要な理由〜戦力外Jリーガー社長の道のり31
2000年代後半から2010年代に大きな成長を遂げたバリュエンスは、直接的にはブランド買取、販売のリユース業が主業ですが、この期間に発展を遂げた多くの企業と同じように、IT化、デジタル化、インターネットを活用したテック企業の側面もあると思っています。 テクノロジーの進化とバリュエンスの成長その時々で”使えるテクノロジー”を自分たちのビジネスに活用してきたバリュエンスグループでは、そのテクノロジーを取り出し、実物資産管理アプリ「Miney」の開発やバリュエンスグループ全体の膨