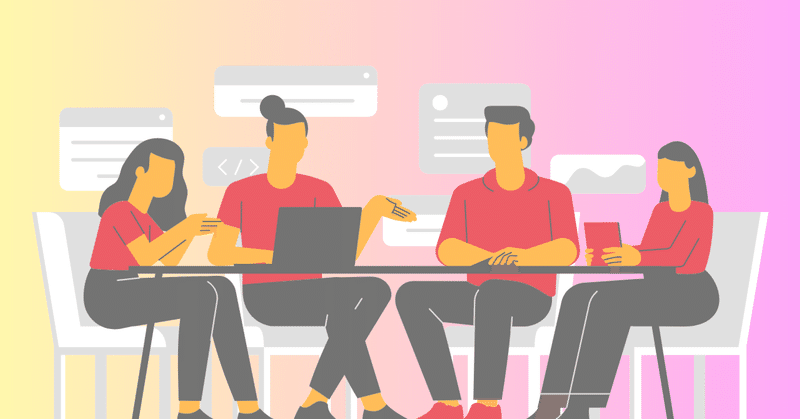
特別研究員コラム②:持って生まれた才能ほど、自分では気づけない!?
皆さん、こんにちは!VCラボ特別研究員の黒木です。暑いですね…毎日ヘトヘトでベトベトな中年学生にとって、ピチピチの20代現役学生達が爽やかに暑がっているのを見ると、自分の成熟具合に感慨一入です。。。
さて、気を取り直して、今月のコラムは、ビジネスに役立つ心理学パート1です。
ビジネスに役立つ心理学
今回は、持って生まれた才能ほど自分では気づけない、だからこそ、心理学が役に立つ、というお話ができればと思います。皆さん、心理学というと、何だか怪しい学問で、最終的に高い壺を購入するよう誘われるような印象を持っていませんか?
実は、心理学は科学的根拠に基づく学問で、ビジネスシーンに転用できる沢山の知見が集積されています。今回は、その中でも、組織運営、人材育成、適職診断に応用できる脳内神経伝達物質と気質のお話をしたいと思います。
気質と脳内神経伝達物質
「気質」という言葉から、皆さんはどんなイメージを連想されますか?職人気質、昔気質といった言葉に馴染みがある方も多いかと思います。この場合、「気質」の読み方はカタギですね。心理学で研究されてきた「気質(キシツ)」は持って生まれた、性格の土台を形成しているものと言われています。「性格」と聞くと急に馴染みのある言葉になりますが、実は、この「性格」の約半分は、生まれた時に既に決まっていて、決めているのは脳内神経伝達物質と呼ばれる、何だか小難しい名前の物質です。この脳内神経伝達物質は、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンの3種類があります。こんな3つのカタカナ語で自分の性格の半分を決められたくない、と私は思います。もちろん、3つの組み合わせ×残り50%で性格100%ですので、環境や努力で良いも悪いも変化させることができます。でも、もともと持って生まれてきたものって、当たり前すぎて分からないですよね。そうなんです、それが皆さん一人一人の強みであり、才能なんです。意識して頑張ろうとしなくても、自然とできてしまう、誰にでも備わっている強みには、この3種類の物質が関わっているんです。

3種類の物質が決め手になる気質
では、3種類の物質が決め手になる気質って、どういうものなの?ということをご紹介します。
【ドーパミン:新奇性追求】※冒険好き 心のアクセル
新しいものを追求しようとする性質です。冒険好きで、新しいものや珍しいものを探して行動します。このスコアが低ければ、思慮深く計画的な行動をとる反面、考えや行動が硬直化しやすくなります。高すぎると我慢が苦手で、行き当たりばったりの行動になりやすい傾向があります。
【ノルアドレナリン:報酬依存】※人情家
人から認められたい=報酬を求める気持ち(承認欲求)が強いです。情が厚く、人にほめられることがうれしくて何でもやってしまう。スコアの低い人は冷静で客観的な行動が取れる反面、他人に対して冷たいと見られてしまうことがあります。高すぎると、相手の悩みを自分の事のように悩み、依存的になったりする傾向があります。粘り強さにも関連している可能性があるとされてます。
【セロトニン:損害回避】※心配性 心のブレーキ
損害を避けようとする性質です。心配性や怖がりを意味します。「心配だから…」と行動を止めてしまいます。緊張しやすく、将来のことをあれやこれやと悩みやすい傾向があります。反対に、スコアが低い人は、大胆な行動が取れる反面、楽天的になりすぎて失敗してしまうこともあります。
「気質」という視点から、振り返って観察してみましょう!
ご紹介した3つの物質の組み合わせで「気質」が決まるとされています。皆さん、何か物事を判断しなくてはいけない時、何を基準にして決めていますか?ものすごくロジカルに主観を排除しまくって判断しているように見える場合でも、実は根底には、この3つの気質が影響していることがあります。みなさんは、どんな気質タイプですか?生まれた時から意識せずとも当たり前にやっていることなので、なかなか自分で気づくのは難しいかもしれません。でも、今まで決めてきた、あんなことやこんなことをじっくり振り返って、ご自身と向き合ってみてください。心配性だから、今まで通りのやり方で…(損害回避型/セロトニン)、上司のAさんに認めてもらいたいから頑張ろう…(報酬依存型/ノルアドレナリン)、今までとは違う遊び心を加えて…(新奇性追求型/ドーパミン)などなどなど、ご自身の判断一つ一つをじっくり振り返り、自分がどんな基準で行動しているのか観察すると、何に動機づけられやすいのかが見えてくるのではないでしょうか。また、意識しなくても得意で、できてしまうこと、人が思いつかないようなアイディアを思いついて実行できる(新奇性追求型)、協調性に富んだリーダーシップを発揮できる(報酬依存型)、ミスのないよう着実に行動できる(損害回避型)、などと言った才能にも、この気質が関係している可能性があります。当たり前にできてしまうことなので、自分では気づきづらいかもしれませんが、「気質」という視点から意識してチームを眺めてみることで、チームマネジメントにも役立てることができます。例えば、Bさんはいつも着実に仕事をこなしているが、心配性で今一瞬発力に欠けるから(損害回避型)、ミスは多いけど、エネルギッシュに攻めるCさん(新奇性追求型)と仕事を組ませてみよう等、部下の「気質」から得意不得意を見極め、そして「気質」を活かすマネジメントに役立ててみてはいかがでしょうか。

目新しいものにすぐ飛びつく(新奇性追求型25%)
後からやっちまったぁと小心者が顔を出す(損害回避型10%)
私はきっと、こんな人…
特別研究員プロフィール
黒木 貴美子 (クロキ キミコ)
ビジョン・クラフティング研究所 特別研究員
某大学院にて臨床心理学勉強中
精神保健福祉士

