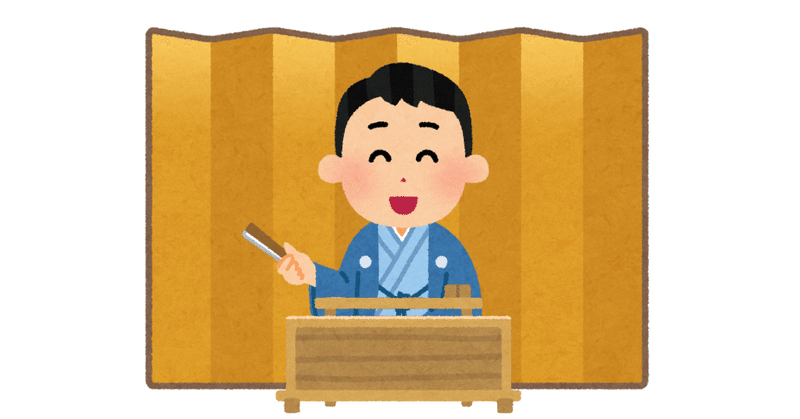
エディターコース「書く人あれば読む人あり」~オチ~
※〈ちょこっと倶楽部・エディターコース〉メンバー向けの限定記事です
※メンバーでない方も途中まで無料でお読みいただけます
今日は「オチ」について考えてみたいと思う。
そもそもnoteの記事にオチが必要かというのはひとまず置いておくとして、やれ話にはオチが大切だとか、やれ今のオチんかったなぁとかいう、この「オチ」とはなんぞや。
オチとは漢字で書けば「落ち」であり、「話の結論」を意味する。
最後に読み手・聞き手を納得させる文章・言葉が「オチ」というわけだ。
納得することを「腑に落ちる」「腹落ちする」というが、この「落ち」が「オチ」に近い意味といえるだろう。
「腑」も「腹」も内臓のことであり、納得することを、食べものを飲み込んでストンと落ちていく感覚になぞらえた秀逸な言葉と思う。
そうしたオチのある(=結論のある)話の芸が「落語」というジャンル。
落語という言葉自体、「落ちのある話」という意味であり、落語は別名「落とし話(噺)」ともいう。
落語の多くが滑稽を扱うから、「オチ=笑い」という図式ができあがった。
しかし、本来のオチは必ずしも笑いを誘うものである必要はなく、読み手・聞き手の納得感をしっかりと生むことができれば、それがオチ。
ここまでくればもうお分かりだろう。
noteの記事にオチはやっぱり欲しい。
たとえそれが笑えるようなものでなくとも。
そうした広義のオチ(結論)については、小学校で習った「起承転結」を意識すれば誰でもある程度書けるようになるものである。
あるいはビジネス用語(就活用語?)の「PREP法」では、結論すなわちオチをことのほか大切にするから、そちらでもいい。
多くの大人はこれまでに結論の大切さをいろんな場面で学んできたはずだ。
ところが、笑えるオチについてはどうだろう。
日々、話を下げ、オチを拾わなければ日常生活に支障を来す関西人を除き、一般的には笑えるオチを生み出すのはハードルが高そうだ。
なら今日は、笑えるオチのトレーニングをしようか。
とあるフォロワーさんとの何気ない会話の中に「なぞかけ」があった。
〇〇とかけて〇〇と解きます、その心は…というあれだ。
これだ! これこそが笑いのオチを生むトレーニングに最適だ!
高校生の頃、とてもかわいい教育実習生とどうしても話がしたくて、友達といっしょに放課後の実習生控え室を訪ねたことがある。
「女子にモテる方法は何ですか?」
何をバカなことを訊くのだろう。
でも教生の先生は前のめりで教えてくれた。
「そんなん決まっとうやん! ものごとの2面性を捉えられたら楽勝!」
黒板消しを見て——ちょうど目の前に黒板消しがあったのだ——「黒板をきれいにするもの」という本来の役割以外にもう一つ、たとえば「履いたらサンダル」というのが瞬時に頭に浮かべば女子にモテるらしい。
さぁそれが万国に共通する「女子にモテる方法」かどうかはさておき、「楽しい人になる方法」としては十分使えるかもしれない。
「なぞかけ」はまさにその2面性を使った高等な笑いのテクだ。
うどんとかけて坊主と解きます。
その心はどちらもつるつるでしょう。
初恋とかけてビールと解きます。
その心はどちらもふらないで!
うどん(A)と坊主(B)に共通するつるつる(C)という構造だ。
初恋(A)、ビール(B)、ふらないで(C)も同じ。
まったく別個のものである(A)と(B)を並べ、んん?と思っているところにその共通項である(C)を見せてハハハとなるのがなぞかけ。
え? そのどこが女子を釘付けにする2面性?
それはつまり(C)の言葉の2面性の部分。
「つるつる」は、うどんをすする音であり、坊主の頭の様子でもあり。
「ふらないで」は、don't break upであり、don't shakeでもあり。
言葉の2面性などというとかっこいいが、要はダジャレである。
そういえば…
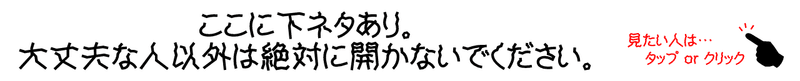
不適切な例を思い出してしまったところで、課題だ。
エディターコースのメンバーで我こそはと思うかたはぜひ次の課題に挑戦してほしい。
課題
「夏」をお題にしたなぞかけを作ろう。
「夏」をお題にするというのは、夏から連想される言葉、夏に関係する言葉をなぞかけの冒頭の「〇〇とかけて」に入れるということだ。
上の解説でいうところの(A)の部分。
つまり「かき氷とかけて…」とか「プールとかけて…」みたいな。
さぁ、爆笑なぞかけが作れるか?
できた!というメンバーの方は、ぜひ次のフォームから5/12までに応募をお願いしたい。
ここから先は
サポートなどいただけるとは思っていませんが、万一したくてたまらなくなった場合は遠慮なさらずぜひどうぞ!
