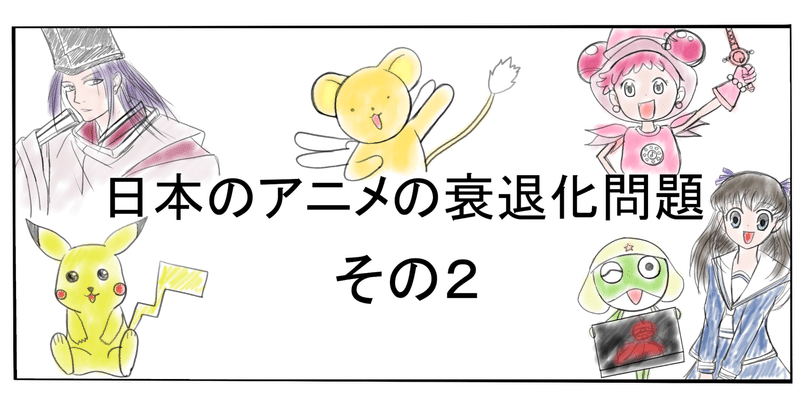
No.016『日本のアニメの衰退化問題 その2』
○はじめに…
前回に引き続き、【日本のアニメの衰退化問題】について語って行く。
今回は、日本のアニメーションの技術の衰退化・劣化・消失について語るが、『作画』と言う1分野について、記事を書いていると考えている以上に長文となってしまったため、今回は、『作画』と言う分野について記事にする。
4:技術の衰退化・劣化・消失
日本のテレビアニメが放送されてから60年(現在24年)経ち、多くの作品が制作されて来た。
しかし、その結果、日本のアニメーションは、一般視聴者やオタクと呼ばれるアニメに詳しい視聴者にすら気が付かれずに産業の重要な技術が衰退化して行き、10年前、20年前、30年前の作品にすら到底並べられないような粗悪品しか制作できなくなってしまった。
この背景には、多くの原因が存在する。
まず、日本のアニメーションは技術職である。
つまり、アニメを作るには、それ相応の技術や知識、教養、そして、経験が求められる。
しかし、現在の日本のアニメ産業で働いているアニメーターを含め、監督、演出家、脚本家など、全てのアニメに関わるスタッフには、アニメーションの基本知識の共有化がなされておらず、各個人ごとに、その知識量はまちまちである。
この原因は、アニメ業界の体制そのものに原因があるが、アニメーションの技術継承を行うための知識の共有化を図るための措置が日本のテレビアニメが放送されてから60年以上経っても、誰にもできなかったことが原因だと考えられる。
○アニメーションの技術継承
日本のアニメーションにおいて、日本のアニメ技術を学ぶことは、現状不可能だと考えられる。
この理由は、日本のアニメーションについての知識の共有化がなされていないことが原因であるが、簡潔に言えば、日本のアニメーションには、教科書と呼べるものが存在しないことがそもそもの原因である。
つまり、日本のアニメーションを学ぶために必要なある程度の基礎知識がまとめられたものが存在せず、誰にも教えることができないことが原因なのである。
*2つの問題点*
① 教科書が存在しないこと
② 教える教師が存在しないこと
① 教科書が存在しないこと。
アニメーションにおける技術や歴史などがまとめられて書かれた書籍が存在しない。
ここ数年間に、そのような書籍が販売されてはいるが、多くのアニメ関係者やアニメファンに、そのような書籍があることや知識の共有化がなされていないことから教科書と呼べるまでに至っていないことが伺える。
② 教える教師が存在しないこと
アニメーションを教える大学・専門学校に行っても、その大学や専門学校の教員にアニメーションを教えられるだけの知識や教養がない場合が多い。
現場で働いているスタッフを教員として雇っていたとしても、その教員は制作スタッフとしては、技術はあるが、教師として人に「もの」を教える立場に立った場合、どうすれば、学生が学び成長できるかを知らず、教えることができない人が多いことが原因である。
そもそも、教員としての教育や資格がないことも原因であり、後で語るが、優れた作品を生み出すためには、2つの側面が求められる。
それが『本質的側面』と『技術的側面』である。
しかし、この2つの側面については、内部から知った者は外部に教えてはならない隠しざるおえない裏事情が存在するため知ることは現状不可能だと考えられる。
つまり、この2つの問題を解決しない限り、日本のアニメーションの劣化、衰退化は止められないのである。
では、具体的に技術の衰退化・劣化・消失について、分野ごとに、どのような技術が失われたのか、筆者である私が知る限りのことを語る。
○分野ごとの失われた技術
日本のアニメ業界は、細部まで分業化された結果、アニメを作るための知識や技術、考え方を知る機会が失われ、多くの優れた先人たちの技術が失われた状態にある。
今回、失われた技術について、以下の枠組に分けて説明することができる。
(1)作画(「人物」・「動物」「乗り物」「エフェクト」「構図」「芝居」)
(2)キャラクターデザイン
(3)脚本
(4)背景
(5)演出
(6)音楽
(1)作画
作画の分野において、失われた技術は、以下のものが考えられる。
・「人物」
・「動物」
・「乗り物」
・「エフェクト」
・「構図」
・「芝居」
「人物」
アニメーションにおいて、人物とは、作中で登場するキャラクターたちのことを言う。
主にアニメーターが描く作画の大半が、この人物=キャラクターを描くことであり、決められた設定資料通りに同じ絵を描くことが求められる。
しかし、現在、日本のアニメ業界において、衰退化・劣化・消失しつつある技術の一つに、この「人物」の作画が挙げられる。
この件に関して、描けていると指摘する視聴者が多いが、24年現在の作品と1980年代の作品を比べると、その力量の差は歴然であり、衰退化したと言うしかない。
では、アニメーションにおける「人物」作画とは何か?について語る。
1:人材とお金の問題
○アニメーターの技術・人数不足
まず、アニメーションは技術職であり、ただ絵を描けるだけではアニメーションは作れない。つまり、動かす技術が求められるのである。
さらに、そこにちゃんと設定資料通りそのキャラクターを描くだけの画力が求められる。
しかし、現在の日本のアニメ産業において、その両方を満たしたアニメーターは少ない。
また、人材不足のため、描けるアニメーターの数は一握りだと言える。
その数少ないアニメーターを大量のアニメ化作品が奪い合い、足りない部分を外注や絵が描ける素人に描かせることで産業を回しているのが今のアニメ産業なのである。
○制作費
アニメーションを制作するには、膨大な制作費が求められる。
例えば、1クール(12話)のテレビアニメを制作するのに約3億円ほどの制作費が求められる。
しかし、ここで、ネット上でもっと安く作れると言う意見が出て来るだろう。
だが、その意見に対して、大きな疑問を抱かなければいけないのである。
なぜなら、10年前から1話のコストを下げても約2000万円ぐらい必要だと言われており、その額で当時のテレビアニメ作品を制作しいていた時よりも、さらに額が下がると言うことはあり得ない。
さらに、24年、現在、物価高と人件費の高騰化により、アニメ産業も確実にこの影響を受けて、人件費などの制作費が上がっていると考えるのだが、なぜか、そのような経済環境の中においても、制作費が下がると言う意見が見受けられる。
ここがアニメ産業の矛盾点の一つなのである。
アニメは大きな投資の一つである。
テレビアニメを1つ作るのに、巨額のお金がかかるものである。
なのに、時代の変化や経済の影響を受けているはずなに、日本のアニメ産業だけ制作費が10年前や20年前と変わらなかったり、逆に減ることなどありえない事なのである。
つまり、そこには、産業全体が隠している暗黙の了解があると言うことなのである。
だからこそ、そのことを忘れてはいけない。
2:「人物」作画における技術的な衰退化・劣化・消失
日本のアニメーションの作画=絵の大半は、人物である。
つまり、キャラクターが登場し、画面の大半を支配していることになる。
しかし、その大半が、顔のアップ、バストショット、ウエストショットなどの同じようなカットばかりを多様化しており、あまり動かない。
この理由には、以下の4つが該当する。
1:背景を描かないようにするため
2:予算問題=動かす=枚数が増えると制作費が増えるため
3:演出の問題
4:アニメーターの画力問題
※ここから先、キャラクター=人物と表記する。
1:背景を描かないようにするため
アニメーションは、漫画と違って、人物以外に背景を描く必要がある。
漫画の場合、ページ数やコマの大きさなどの問題や背景を描くことで漫画が読みづらくならないように、なるべく絵を省略化して、背景を描かないようにすることが求められる。
しかし、アニメなどの映像作品の場合は、全てのカットに対して、背景を描くことが求められる。
それが映像と言う分野における最大の魅力であり、背景を省略して漫画みたいに白い背景の中に人物を配置してしまうと、カット同士が繋がらなくなってしまう。
つまり、映像は漫画と違って省略できないのである。
次に、背景を描く作業量は膨大である。
アニメ産業において、アニメーターの仕事は作画だけであり、背景は背景を担当する人が描いている。
しかし、実際に、アニメーターには、人物と一緒に背景を描く技術までもが求められる。
人物を動かす時、必ず人物の配置や建物のパースを考えることが求められる。
その人物がどこに立っているのか、そして、動いた時、人物の見え方がパースを意識して描かないと、画面に奥行きや人物の動きが不自然になってしまう。
そのため、アニメーターにはある程度の背景を描く技術が求められる。
しかし、それだけの画力を持つアニメーターは少ない。
また、どんなに優れたアニメーターでも、大量の絵を描くだけの体力はない。
さらに、背景担当もパースなどを考えて、アニメーターが描いた原画と絵コンテを照らし合わせながら背景を描くが、アニメーターの描いた原画が悪いと、そこで一つのトラブルが発生する原因となってしまう。
そのため、アニメーターはある程度のパースを意識した背景と人物の配置を描いた絵を描けるだけの技術が求められるのである。
そこで、その作業量を減らすために、顔のアップを多用して、背景を描かないようにする工夫が生まれた。
パースなどを考えていなくても、顔のアップにより、舞台における人物達の配置やその場で見える背景の位置などを誤魔化すことができる。
さらに、漫画原作の場合、顔のアップやショルダーカットなどが多いため、その絵と同じ構図を流用しても、原作のファンである読者は気にならない。
そのため、顔のアップが多様化されると言う訳である。
つまり、顔のアップは手抜き技法のひとつなのだ。
また、2012年頃からは、CGにより、レイアウトの段階で絵コンテを元に、物の大きさや人物の大きさを正確にする工夫がなされるようになっている。
しかし、この工夫は一見、パースを正確にするためには良い手段に見えるが、実際は、構図の概念において、面白みのない絵に変える手段に他ならない。
それだけ背景と人物を合わせられるアニメーターの画力、技術は優れていると言うことである。
2:予算問題=動かす=枚数が増えると制作費が増える
日本のアニメーションは、動かないことで有名である。
これは【リミテッドアニメーション】と【フルアニメーション】の違いだが、この件は読者自身が各自で調べて頂けると幸いである。
日本のアニメーションは、必要最低限の枚数で動いているように観せかけるアニメーションである。
つまり、必要最低限の絵しか求められない。
この絵の枚数において、アニメーターが好きなだけ絵を描くことはできない。
絵の枚数は、あくまで制作費の額で決まり、制作費が少なければ少ないほど、絵を動かすことができなくなる。
この問題は昭和のアニメーションにおいては違っていた。
1990年代以前は、動かせば動かすほど良いと考えられていたため、アニメーターは、人物を好きなだけ動かすことができていた。
しかし、1990年を過ぎた頃から制作費の問題が発生し、作画枚数に制限がかかり、動かしても、アニメーターに余計な枚数分の賃金は支払われなくなったと言われている。
つまり、現在のアニメーションにおける動きの悪さは、この制作費が大きく影響していると言うことである。
3:演出の問題
ここまで顔のアップばかり描く理由を上げてきたが、最大の理由の一つが、日本のアニメーションは、漫画の表現を主に参考にして制作していることが問題だと考えられる。
現在のアニメーションを作っている制作スタッフの大半が、映像技法の表現方法を知らない場合が多い。
また、制作費や制作時間を考慮して、なるべく絵を動かさず、描かないようにするために、このようなカットが増えてしまったと考えられる。
しかし、このことを知っておいてもらいたい。
『1:背景を描かないようにするため』で語った通り、漫画の表現において、顔のアップを描いていることが多いが、これには漫画と言う表現媒体における大きな問題・理由が存在する。
漫画にはページ数、コマの大きさなどの制限が多くあり、セリフも声優が喋るのではなく、吹き出しを使って語らせる必要がある。
そのため、その吹き出しが、誰から発せられた言葉なのかを読者に理解してもらうために、登場人物に直接、吹き出しをつけて描くことが求められる。
その中で一番効果的なのが顔のアップであり、コマの制約があるため、全身を入れて描くことが困難になるため、顔のアップを多様化することでその問題を解決している。
しかし、日本のアニメーションは、そのことを理解できていない制作スタッフや視聴者が多く、漫画の表現(絵)を直接引用して、抜き出して描くことが多い。
その結果、テレビアニメの大半で手抜きが多様化され、その人物が喋っていると言う事実だけを求められた結果、顔さえ描けていれば作品として成り立つようになってしまった。
さらに、近年では、綺麗に描くことばかりに囚われ、口パクの顎の動きすら描けなくなってきている。
そして、最後は、声優の演技力に依存するという一連の悪循環の流れになり、紙芝居的なアニメーションを制作する結果となってしまったのである。
4:アニメーターの画力問題
アニメーターの技術=画力に対して、上手い下手は人それぞれである。
例えば、『手』を描くのは難しく、アニメーターごとに上手い下手が激しいため、なるべく手を描かなくて済むように配慮されることもある。
例えば、『わたしの幸せな結婚』第1話において、使用人の女性が洗い物をしている場合、その作画量を減らすために、敢えて、「洗い物」が見えないようにする工夫がなされている。

手の部分を画面で切ることで、手の作画を描くことを省き、余計な労働力を減らすことができる。
また、洗い物の設定や皿や桶、水の色などの設定も省くことができる。
物語上、それほど必要のない内容の場合において、手間を省く手法としてよく使われる方法である。
さらに、最近では、コップや物などのアップを描いたとしても、地面を描かないようにするために、地面すれすれを切り取って、パースを見せない工夫をしている。
例:『聖女の魔力は万能です。』2期・3話

こうした工夫の背景には、作画を行うアニメーターの技量問題が付いて回る。
しかし、このような手抜きばかりして、綺麗な止め絵ばかり描いて来た結果、人物を動かす技術は衰退化する一方である。
「動物」
日本のアニメーションにおいて、失われた技術として上げられるのは、動物の作画である。
1990年代までは、動物の作画はできていた。
どの作品も動物が登場し、鳩や渡り鳥のような鳥類、犬や猫、家畜である馬や牛やリスなどの小動物に至るまで、日本のアニメーションは、ちゃんと作画して動かしていた。
しかし、時代が経つにつれて、現在(24年)には、動物を描くことがほとんど少なくなり、さらには動かす技術までもが失われてしまっている。
○ 24年現在の動物作画の現状
現在、動物を描く場合、ほとんどが止め絵か、それほどの枚数(動かすこと)を必要としないシーンのみに使用される。
また、CGなどによる手抜きが多くなり、さらには、制作スタッフや原作者(主に漫画家)、視聴者の大半が、動物を描くことの重要性を理解できなくなり、作品全体において、動物の必要性が低下している。
○動物の動き
動物の作画において、動物の動きには、現在2つの考え方が存在する。
「1:本能の動き」
「2:人間味のある動き」と命名する。
「1:本能の動き」
「本来の動き」とは、生物が持つ生存本能の赴くままに動く動きのことである。
動物は基本的に、哺乳類、鳥類、魚類、昆虫類のことである。
その動きには、生きるために必要なものしかなく、余計な動作や思考などが入っていない動きであり、生物が持つ生存本能そのものを現した動きだと言える。
また、アニメーションにおける動物の動きとしては、私達人間と違って、常に動いていることが求められる。
まず、私達人間を含め、動物は常に動いている。
しかし、人間の場合、テレビを観ている時や寝ている時など、静止しているようで、どこかしら常に動いているのだが、アニメーションにおいては、そのような微細な動きは人物作画においては、求められておらず、動かなくても観ている人には、その人物が生きていると認識して観られているため、微細な動きは省略されている。
しかし、動物の場合はその理屈は通らない。
動物は常に動き続けており、動いていることが自然な表現になるのだ。
例え、寝ていたとしても、腹を上下に動かして寝ていることを見せたり、尻尾を振ったり、毛繕いをしたりするなど、常に動かし続けなければ、動物のリアルな姿・野生的魅力を視聴者に伝えることができない。
これが人間と動物の動きの違いであるが、この動きを追求する場合、多くの問題が発生する。
それが、制作費、作画枚数の問題であり、嫌がられる理由の一つでもある。
また、動物の動きは、人間を描くより難しく、種類も多いため、動きを全て理解して作画することは並大抵の技術ではない。
現在、日本のアニメ業界を含め、動物の動きを描けるアニメーターがほとんどいない。
あまりにも、動物を描いてこなかったため、現在のアニメーターのうち、ベテランの年配アニメーターくらいしか、その動きを知らない人が多い。
また、過去の名作を視聴していない若手アニメーターが多いため、動物の動きの考え方を知らないことも原因である。
さらに、作画枚数の問題も発生して来る。
例えば、動物の野性的な動きを追求する場合、馬や牛などの草食動物を描いている時、物語の進行上、その場に留まった場合、頭を上下左右に動かしたり、雑草が生い茂るような場所ならば、地面に生えている雑草をむしゃむしゃと食べている姿が自然な動物の動きと観える。
また、リスなどの小動物なら鼻をピクピク動かしたり、頭をくりくり回す動作をして、ぴょんぴょんと軽やかに動き回っている。
カエルなら喉を膨らませて呼吸をしている。
これらの動きは全て、ちゃんと1990年までのアニメーションが自然と描いていたものである。
しかし、時代が進み、予算や技術的な問題が発生し、そこに作画枚数の制限を設けてしまうと、動かせなくなってしまう原因となり、その結果、少ない枚数で表現するために、顔のアップや脚やお尻一部を映し、声優の芝居や動物の鳴き声で誤魔化すことが多い。
(24年)現在までの日本のアニメーションにおいて、動物が描かれる例としては、馬が多く描かれる。
その理由は、『なろう系』の作品の大半が『異世界もの』であり、移動手段として、馬車が登場するからである。
しかし、馬の作画は、作画ではなく、CG処理された馬しか描かれることはない。
例え、馬を作画しても、そのほとんどが止め絵になっている場合がほとんどである。
さらに、馬車を動かすだけの作画技術や時間がないため、どうしても、CG処理に回ってしまうことが多い。
しかし、その結果、悪い例が多く生み出される結果となってしまった。
例えば、『シュガーアップル・フェアリーテール』と言う作品がある。
この作品には、馬が登場するが、馬の作画は描きたくない為、CG処理されている。
これは馬車が登場するために、馬車の作画を軽くするための処置である。
しかし、この作品がいかに幼稚でクソアニメなのかは別で語るが、馬や馬車のことを理解できていないことは作品を観ていれば一目瞭然である。
まず、登場する馬車は、主人公が銀砂糖を作るための調理場であり、現代で言う、公園などで移動販売する時に使われる『キッチンカー』である。
しかし、このような重量があるものを果たして、馬一頭で運べるか、と言う問いに対しては、答えは 無理/不可能 と断言できる。



実際に調べればそのようなことは一目瞭然であり、さらに、過去の名作や映画やドラマなどの実写でも馬車が登場する作品を見ていれば、すぐに馬の必要頭数が理解できる。
この作品で重量がある馬車を引くためには、最低でも2頭の馬を登場させる必要があるが、作者や製作スタッフの教養の無さによって、そのようなミスは修正されてはいない。
この問題点において、指摘し修正しないのは、「馬」を「生き物」として見ているのではなく、私達の私生活で言う、「車」と同じ存在としてしか見ていないからである。
「車」がまだ、存在せず、「馬車」で生活していた時代では、「馬」は大切に扱われていた。
それは、『赤毛のアン』などの世界名作劇場を見ていればすぐに分かる。
でも、この作品は、「馬」を「動物」として、「生き物」として見てはおらず、名前も付けず、「馬」の面倒をみず、そのような動きを一切描いていない。
作品で描く部分はあくまで人間ドラマだからである。
だが、その人間ドラマはあまりにも酷く酷評の嵐を受けており話にならない。
そして、全ての名作はこのような「馬」を大切に扱うところまで描いて初めて名作になるのである。
だからこそ、この作品は、放送終了後、人々の記憶から消えていくのである。
もし、この『野性的な動物の動き』を描くことができれば、迫力のある映像が生み出すことができる。
現に『もののけ姫』がその典型的な例に当たる。
迫力ある猪の突撃するシーン、狼の肉食獣としての獣の動き、架空の生き物だが、ヤックルと呼ばれる大カモシカの動きは、日本の鹿やアフリカのサバンナなどで見られるガゼルの走る姿と重なる。
動物が本来持つ動きがこの作品には、全てあり、それぞれの動物たちを輝かせている。
だからこそ分かることがある。
なぜ、狼や熊が私達人間にとって危険視されているのか、なんでそのような牙や爪を持っているのか、その生物が持つ肉体的な優位性をちゃんと描いた作品がないからこそ、視聴者の大半が分からなくなってしまっている。
だからこそ、そこに新たなドラマ、葛藤を生み出す原動力があると考えられる。
例えば、『悪役令嬢レベル99~私は裏ボスですが魔王ではありません~』と言う作品には、たくさんの魔獣と呼ばれる敵が出て来る。作中多く登場したのが、狼みたいな魔獣である。
しかし、制作費、作画時間の確保などの理由で、その全てがCG処理された魔獣であった。
CGのモデリングも今の時代だと、クオリティ的にはそれほどでもないが、圧倒的に動きが酷すぎた。
ただ倒されるだけの役割しかなく、魔獣として、獣としての動きは一切求められておらず、ただ動いて、倒されるだけの存在でしかなかった。
もし、この魔獣の狼を作画で描き、迫力ある姿で描くことができたとしたら、確実に、この作品の評価も少しは違ったものになったのであろう。
もし、この動物の動きを描くことができるようになれば、例え救いようのない「なろう系」の作品だとしても、見応えある作品に変わるであろう。
そして、そのことを理解できるようになった時、モンスターや魔物として登場した狼や熊のような猛獣のキャラクターを簡単に倒したり、色々な変な設定を付けて強そうに見せるような安易なことはなくなると考えられる。

「2:人間味のある動き」
人間は動物と違って、思考し、行動することができる。
例えば、お昼に何を食べるのか考える。ラーメンを食べるのか、カレーを食べるのかと言ったことを考えて、そこから何を食べるか決めてからその食べ物を食べる。
逆に動物の場合、お腹がすき、目の前に食べ物があればそれを食べる。
つまり、人間は動物と違って、本能の赴くままに生きているのではないのである。
さて、動物の動きに戻るが、このように人間と同じように思考して行動してしまうと、
動物なのだが、人間性を感じさせるようなコミカルな動きになってしまう。
さらに、その動物のキャラクターデザインが、人間と同じように、デフォルメされ、リアルな絵から可愛らしいデザインになってしまうと、野性動物の持つ野性味が失われ、動物らしさを感じさせないものになってしまう。
そうなると、外見も動きも、「1」で語ったような動物の本来の姿が失われてしまう。
日本のアニメーションにおいて、この絵の変動には歴史があり、
1990年代以前の作品においては、動物は主人公の相棒やマスコットキャラ的な存在・立ち位置として描かれることが多かった。
しかし、徐々に動物の姿でなくなり、ぬいぐるみや妖精的な人間と同じような思考と動きをするキャラクターとして求められる姿に変わり、動物の動きの必要性が失われてしまった。
例えば、『世界名作劇場』やジブリ作品においては、実際にいる動物が登場し、リアルな動きを追求される。主人公と意思疎通はできるが、それはあくまでにペットとしての役割
までしかない。
しかし、『美少女戦士セーラームーン』の黒猫のルナのように、人間の言葉を話す動物が登場し、動きも猫の動きから人間のような動きの愛くるしさがにじみ出るようになった。
そこから『カードキャプターさくら』の封印の獣ケロべロスのケロちゃんや『デジモンアドベンチャー』でのデジモンや『ポケットモンスター』のポケモンなど、人間と同じように意思疎通ができる中間的な要素を持った生き物が登場する作品が大量に生まれ発展し、最終的には人間のように二足歩行をして、人間の言葉が話せるようになり、動物がモチーフなのに、動物の持つ野性的な部分が完全に排除された外見は人間ではないが、人間のような中身を持ったキャラクターにまで発展した。
その典型例が『プリキュア』シリーズの妖精だと考えられる。
この時代の変化とアニメーションの作品の進歩によって、動物の野性の動きは、人間臭い動きに変化してしまったと言える。
例えるならば、『魔女の宅急便』の黒猫のジジが、最初、魔女のキキと話ができている時の姿と、話せなくなり本来の猫の姿に戻った時の違いのようなものだと考えると、分かりやすい。


「乗り物」
日本のアニメーションにおいて、衰退化・劣化・消失しつつある技術の一つに車などの「乗り物」の作画が挙げられる。
ここで言う「乗り物」とは、車・飛行機・船などのことを指す。
CG技術が対等する前までは、全ての乗り物の作画は全て人の手で描かれて来た。
そのため、乗り物の作画は日本のアニメーションの技術として優れたものであった。
特に、マニュアル車のギアチェンジを操作する動きは有名であり、『ルパン三世』などの有名作品で動かしていたことが印象的である。
しかし、CG技術の発達と共に、2000年代から実験的にCGによる「乗り物」の作画が行われるようになって行き、最初は車の手描きの作画からCGに替わり、やがて、飛行機、船と、「乗り物」の大半がCGで描かれるようになった。
この「乗り物」の作画をCGで描くようになった理由は、単純に、「乗り物」をアニメーターに描かせるよりも、CGで動かした方が、遥かに作業量は少なく、また、大きさの変化や難しい角度の絵を表現することができるためである。
これにより、アニメーターはCGに向かない人物や動物と言った作画に力を注ぐことができるようになった。
しかし、CGに頼り切った結果、「乗り物」を動かす技術が衰退化し、今では描くことができなくなってしまった。
また、止め絵で街中に車を描くこともできず、CGで作られた車を置くことで、作業量を減らす手抜きの工夫が多くなってきている。
つまり、車や飛行機などの「乗り物」を描けるアニメーターがいなくなってきていると言うことだ。
また、近年のロボットアニメにおいて、ロボットの作画すら描く余裕がなくなったのか、今まで、手描きで描いていたはずなのに、CGでロボットを描くようになって来ている。
これは、【ロボットアニメ】の危機的状況を現しているとも言える。
○求められること
結局、CGを多用することは、現在の日本のアニメーションにおいて、手抜きの代名詞となってしまっている。
「乗り物」を描くことができないと、人物と「乗り物」の大きさや配置などで作画ミスを誘発させる。
「乗り物」を手描きのアニメーションで描くことのメリット性は、「乗り物」に人の意思や感情を宿らせることができることだ。
現に、「乗り物」の作画が行われた作品において、操縦する主人公の意識が宿ったかのように、人間のような生き生きとした動きをして、多くの視聴者を圧倒することができることは、『ルパン三世・カリオストロの城』などと言った作品で証明されている。
つまり、「乗り物」の作画は、主人公の心理状態を描くことにうってつけだと言うことだ。
また、「乗り物」の作画を描くことは、画面全体を作り込むことを意味している。
現に、私も、「乗り物」のアニメーションを実験的に作ろうとした時、「乗り物」である車の作画のみが重要だと考えていたが、実際は、車と背景の両方の作画が必要であることを学ばされた。
要するに、車を動かすことは、背景を作り込むことを意味しているのだ。
それだけ、「乗り物」を描くことは、アニメーターにとって、重要な技術の一つだと言える。
「エフェクト」
アニメーションにおける「エフェクト」とは、雨や雪や風に揺れる木の葉などの自然現象や映像に加えられる爆発、火、液体、煙、発光などのことを言う。
例えば、木の葉が舞い散るシーンやカーテンが風で揺れるシーン。
暖炉の火、必殺技の光線、さらには、雨や雪などが降るシーンなども、「エフェクト」作画に該当する。
そして、これらのアニメーションの「エフェクト」技術は全て手描きによって再現されて来た。
しかし、現在の日本のアニメーションにおいて、その全ての「エフェクト」作画がCGやアフターエフェクトによるデジタル技術によって再現されている。
これはアニメーターの作画量を減らすための措置として、主に編集作業を担当する編集によって制作されている。
しかし、その結果、今のアニメーターには、1990年代までにあった「エフェクト」作画の技術が完全に衰退化してしまい描けなくなってしまった。
つまり、今のアニメーターには、「エフェクト」を表現するだけの作画技術がないのである。
この「エフェクト」技術は、一見重要な要素に観えないが、この「エフェクト」作画だけで、多くの心理描写や登場人物が置かれている状況を説明することができる。
例えば、『雨』と言う「エフェクト作画」例にあげる。
通常、雨の降り方は縦方向に短い線をたくさん引き、描いた線に対して、直線状に地面に落ちるまでの動画を描く。
あとは、1枚1枚のタイミングを何コマ程度で撮影するのかを調節して雨のループ作画を行う。
この雨の作画において、雨の降り方に、緩急を付けたり、地面にできた水たまりの波紋の数を大きくしたり、たくさん小さな波紋を描くことで雨の量や降り方の強さを表現できる。
勿論、音も関わっているが、音響がいくら頑張っても、絵が悪ければ音も生かされないし、表現することもできない。
このような雨の作画の調節を編集作業で表現することは難しく、今でも、重要な場面などでは、ベテランアニメーターが描いている。
つまり、PC作業には、この雨の強さなどの微調整を行うことは不可能だと言うことだ。
そして、「エフェクト作画」を使いこなすことで、多くの情報を視聴者に与えることができる。
先程の雨のシーンなら、雨の降り方と登場人物の心情をシンクロさせることができる。
登場人物の心情が悲しみの底ならば、豪雨にして、雨をたくさん降らし、悩みや苦悩から解放されたのなら、雨が止み、葉っぱや屋根から滴る水滴がポツンポツンと地面に落ちる姿を描くことができる。
窓のカーテンが風で揺れるシーンは、緩やかでのどかな雰囲気を伝えたいなら、カーテンがゆらゆらと風で動いているシーンを見せれば、その場の空気感を表現できるし、強風が来たのならば、カーテンを凄まじく揺らせば、風が強いことを表現できる。
つまり、エフェクト作画によって、その場の状況や登場人物の心情などの情報を絵と言う形で伝えることができると言うことだ。
しかし、現在のアニメーションにとって、エフェクトに力を入れることよりも、人物作画を綺麗に観せて、維持させることに力がそそがれている。
そして、誰一人、この「エフェクト作画」の重要性、良さに気が付かなかった結果、誰も描くことができなくなってしまったと言うことだ。
「構図(コンポジション)」
絵画や写真などの画面の構成のこと。
その要素は、色・形及びそれらの組み合わせ、有機的結合、遠近法などで、作者の感覚、内的必然性によって特定の傾向を持つことが多い。また、広くは芸術作品の諸要素の組み合わせ、構成の仕方を言う。
この「構図」の概念において、アニメーションにおける構図とは、画面全体のこと指す。
○アニメーターへの一言
まず、ここでアニメーター全員に言うことがある。
アニメーターの仕事は、今観ているアニメ作品の画面を作ることであると言うことを私は言いたい。
このことを理解してアニメーションを作っているアニメーターは非常に少ないからである。
この理由は、誰一人、今観ている画面を全て自分一人で作るものだと言うことを知らないこと、そして、教えなかったことが原因だと言える。
この画面全体を作ることを意識できなくなった理由は、アニメーションの制作工程の全てが分業化されてしまったことが原因である。
画面に映る登場人物、背景、小物、色、など画面に映る全てを本来は一人のアニメーターが描くことが本当のアニメーターの仕事なのである。
しかし、それだと作業は大変になるし、人間誰しも得意不得意があるし、絵をある程度同じにするために分業しなければいけない。
例えば、人物と背景のように。
だけど、この画面全てを本来自分で作ることを意識して理解できていれば、描かれるそれぞれのカットの絵に対して、色々と考えるようになり、絵の観せ方について考えるようになるであろう。
○アニメーションの画面構図
アニメーションにおける構図について語る前に、アニメーションの歴史の流れを少し語る。
日本のアニメーションは、海外アニメのディズニーアニメから来ていることは調べれば分かることである。
このディズニーアニメに憧れて、手塚治虫がアニメ作りを目指し、日本で初めてのテレビアニメ『鉄腕アトム』に繋がったのである。
他にも東映アニメーションの『白蛇伝』もその一つである。
つまり、日本のアニメーションの始まりは、ディズニーアニメが根幹にあることを理解しなければいけない。
そして、今度はディズニーアニメのことを理解しなければいけない。
今回語るディズニーアニメは、『白雪鏡』『シンデレラ』『眠れる森の美女』などの作品が該当する。
これらの作品の画面構図において、日本のアニメーションとは大きく違うが、この考え方の流れは日本のアニメーションの中に取り入れられていることは理解してもらいたい。
ディズニーアニメの画面構図は、どのカットも面白いことに全ての絵が絵画のように完成されていることである。
どこから映像を止めても、全てが一枚の絵画や絵本の挿絵として申し分もないほど完成されている。
つまり、アニメーションの構図の概念は、絵画の構図が基本にあると言うことだ。
そして、日本のアニメーションの手塚治虫の『鉄腕アトム』は、この流れを受け継いでいるが、そこに独自の要素が組み込まれている。
それが『漫画的表現技法』である。
他でも語ったが、顔のアップなどの絵の多様化は、漫画表現の影響が強い。
つまり、日本のアニメーションは、『絵画的表現』と『漫画的表現』の2つの要素が組み合わさってできているのである。
しかし、ディズニーアニメのように、たくさんの絵を絵画のような構図を意識しながら描くことは至難の業である。
そこで、顔のアップを利用し、顔の絵、口パクの閉じ口・中間口・開け口の計4枚の絵で喋っているように観せるシステムが生まれた。
これを【バンクシステム】と呼ぶ。
最初のバンクシステムは、今では、当たり前に描く顔のアップが始まりなのである。
ここで注意しておくが、当時はセル画の時代であり、発展途上であることを理解してもらいたい。
今のアニメ制作方法は、絵を紙かPC上で描き、簡単に色を塗ることができるが、当時は、1枚1枚人の手で塗っていたことを理解しなければいけない。
それには膨大な制作費が求められる。
しかし、当時のテレビアニメを作っている時にディズニーアニメと同じだけの制作費を用意することなど不可能である。
だからこそ、絵を使い回す【バンクシステム】が考案されたのだ。
この使い回しのやり方は、成功し、多くの日本のアニメーションの誕生と発展に貢献し、多くの悲劇と問題を生み出した。
こうして、日本のアニメーションは独自の進化と発展をしたのである。
さて、アニメーションの構図について、話を戻す。
演出の分野でも語るかもしれないが、ディズニーアニメの絵画や絵本のような絵の構図の考え方は、ハリウッド映画の撮影技法から来ている。
つまり、実写や映画の撮影技法が大きく関わっているのである。
そして、日本のアニメーションは、独自の発展を遂げて、2つの技法を取り込んで1980年代に完成を迎える。
それが、『漫画的表現技法』と『映像的演出技法』を合わせたものである。
日本でテレビアニメが放送され始めた当時、まだ、日本のアニメーションは独自の方向性を持ってはおらず、ディズニーアニメのようなフルアニメーションでの作画を行うだけの技術も予算もなかったため、独自に絵を使い回す【バンクシステム】や【リミテッドアニメーション】の技術を編み出して制作していた。
そのため、一番の参考資料となったのが実写映画やテレビドラマになる。
映画やドラマなどの撮影技法をアニメ制作をしていた当時のスタッフは、参考にしてアニメーション制作に取り込んでいった。
その結果、日本のアニメーションは実写にも劣らないほどの独自の文化としてまで発展して行ったのである。
この技法が完成したのが1980年代の作品を観れば分かる。
しかし、1990年代から2000年代にその技術の継承はされず、まだ独自の方向に向かいながらもスタジオジブリだけは継承していたが、それは監督の宮崎駿や高畑勲がいたからであって、監督と言う仕事を担えるだけの人材育成をしなかった結果、ジブリでの新作は制作できなくなってしまう。
また、技術も継承されず失われてしまった。
つまり、日本のアニメーションは2つの考え方の技術が丁度いい具合に合わさって完成されたものであったのだが、現在では漫画の表現ばかりアニメに取り入れられ、ハリウッドなどの映画で使われる撮影技法については、一切学ぶことができなくなった結果、衰退してしまい最後は消失する可能性があるのが現状である。
その証拠が日本のアニメーションの特徴であった『バンクシステム』が作れなくなったことが何よりも証拠になる。
○バンクシステム
『バンクシステム』とは、一言で言えば、同じ素材を使い回すことである。
一度完成された同じ絵やシーンを使い回すことで、絵を描く量を減らす目的があり、日本のテレビアニメが誕生した時に生み出され、多様化された技術である。
しかし、時代が経つにつれて、手抜き手法だと視聴者に叩かれ以降、なるべくバンクシステムを使用しないようになり、その結果、バンクシステムが使われなくなってしまった。
1枚1枚新たに絵を描く試みは良いが、その全てが顔のアップなどの手抜きに代わり、使い回して使用できるような魅力的な絵が失われてしまう結果を生み出してしまった。
例えば『デジモンアドベンチャー』において、デジモンの進化するシーンは、全てバンクシステムで作られている。
一見、手抜き手法に見えるが、これは、魔法少女物の変身シーンと同じく、作品の魅力の一部であり、このバンクシステムの変身シーンはこの作品の一つの魅力でもあった。
しかし、なぜか、リメイクされた『デジモンアドベンチャー』においては、そのバンクシステムの劣化が激しかった。
そもそも、このリメイク作品自体に問題が多かったが、バンクシステムで作られた変身シーンは10年以上経ち、技術や機材の進歩があったのにも関わらず、あまりにもリメイク前と比べて落ちぶれてしまっている。
また、構図の代名詞と言える『バンクシステム』において、使い回せる絵にはそれだけの魅力が求められる。
例えば、『機動戦士ガンダムSEED』シリーズにおいて、大量のバンクシステムが使用されているが、どのカットも使い回したとしても、物語は繋がるため、それだけの力を保持している。
『バンクシステム』で使用できる絵を生み出すには、『構図』の概念が深く求められ、人物と背景の組み合わせと全体の動き、そして、撮影技法に関わる演出技法の全てが求められる。
しかし、手抜きを覚え、顔のアップばかり描き、背景を描くことを拒否し、アニメーションの知識の共有化をしてこなかった結果、『バンクシステム』で使用できるような魅力的な絵を生み出すことができなくなってしまった。
つまり、『構図』と言う分野において、その技術の衰退化を招いた理由は、制作費、制作スタッフの技術不足、視聴者の手抜き発言(アニメの制作の不理解)、手抜き手法などの結果によって、このような状況を生み出してしまったのである。
この『構図』の概念を取り戻すには、絵の『構図』について、学び直す必要がある。
しかし、そのような教育環境は現在の異常なアニメ産業には存在しない。
「芝居」
日本のアニメーションにおいて、衰退・劣化・失われた技術の一つに「芝居」の技術があると考えている。
○芝居とは
劇場や演劇、あるいは演技のこと。
もともとは、猿楽等の芸能を寺社の境内で行った際、観客は芝生に座って鑑賞していたことから、見物席や観客を指して「芝居」と呼んでいた。
これが徐々に能楽や舞踊等の諸芸を行う場所全体を指す言葉になり、そこで行われる芸能(特に演劇)や、演技の意味にまで転じた。
「芝居を観る」という表現は現代でも非常に一般的で、商業的な演劇、歌舞伎やオペラ等、演技を含む舞台表現全般を劇場で鑑賞する場合に使われる。
詐欺行為やいたずらで人を騙すために演技することも「芝居」と呼ばれ、「ひと芝居打つ」等の表現がある。
*名前の由来*
室町時代、神事である「翁」や、田楽・猿楽などの興行は、
人が集まりやすい寺社境内で行われていました。
当時は客席などありませんので、人びとは芝生の上に座って見物しました。
このときの「芝生に居る(座る)」から「芝居」という
言葉が生まれたといわれています。
○日本のアニメーションにおいて、『芝居』
日本のアニメーションにおいての芝居とは、画面上に登場している人物の動きのことを主に言う。
勿論、人間以外に動物やロボットのような機械も同じく、動くものは全てアニメーターの芝居の一つに該当する。
『エフェクト』で語ったように、エフェクトもアニメーターの芝居に該当する。
背景のような止め絵のように動かないものは芝居に該当しない。
誰かが動かすと言うことは、そこに人の意思が入り込むと言うこと、アニメーションにおける芝居とは、動かすアニメーターの芝居そのものなのである。
さて、24年、現在の日本のアニメーションにおいて、キャラクターを動かすことは難しい。
その理由は以下のものがある。
・キャラクターデザインの線が多過ぎること。
・制作費(予算)
・アニメーターの技術不足
予算とアニメーターの技術不足は何度も説明しているので省くが、重要なことは、描くキャラクターの線画の量に問題がある。
まず、歴史を語る。
1980年代までの日本のアニメーションを制作していたアニメーターの考え方は、動かすことがアニメーションだと言う考え方であった。
しかし、1990年代から2000年代になるまでに、その考え方は変化して、動きではなく、物語で観せることが重要視されるようになった。
この結果、日本のアニメーションに動かすことの概念は衰退化して行くことになる。
この原因は、1990年代からアニメーションに対しての予算問題が発生していたと言われている。当時は動かせば動かすほど、給料が払われていたため、アニメーターでも頑張れば一軒家も買えるほどの猛者もいたと言われている。
しかし、この時期からいくら描いても、制作費の問題で作画枚数を制限されるようになり、当時より動かすことができなくなっていった。
そして、話を戻すと、近年のテレビアニメの特徴として、デジタル作画が可能になった影響もあるが、キャラクターデザインの線画の量が増加してしまった。
アニメーションにおいて、今でも絵を動かすのはアニメーターの仕事である。
いくらAIやPCなどの機材が発展したとしても、その部分を任せることはできない。
しかし、アニメを観ている視聴者や偉そうにアニメのことを語るユーチューバー達は理解しようとしていない。
線が多ければ多いほど、1枚の絵、つまり、原画や動画を描くのに時間がかかるのだ。
また、動かすにも、それ相応の時間もかかる。
そのため、線画の量が多いキャラクターデザインはアニメーターに嫌われる要素の一つなのである。
有名な話で、東映アニメーションの『スイートプリキュア』の話がある。
このプリキュア作品の主人公たちは、線の量が多く、当時のスタッフに嫌われていたらしい。だが、動かすための秘訣があると言われている。
キャラクターデザインにおいて、線画が多いと魅力的な絵に見えるが、実際は動かすことに不向きなデザインである。
例えば、漫画のデザインをアニメーションに求めるファンが多い。
しかし、実際にそのマンガの絵をアニメーションに持って来ることは不可能である。
量が多ければ多いほど動かすことができないためである。
そのため、アニメーションを作る際、キャラクターデザインの線をなるべく省略して、描きやすい絵に描き直す作業が求められる。これがキャラクターデザインと言うアニメーションの仕事である。
必要な線を必要なだけ見抜き、抜き出して一つのデザインに起こす。これがキャラクターデザインの仕事である。
○「アニメーター」=「役者」
まず、アニメーターとは、一種の「役者」である。
画面に登場する人物から「もの」まで描くもの全てがそのアニメーターのさじ加減で全てが決まってしまう。
そして、「芝居」と言う概念で語ると多くの例が存在し、「歩き」や「走り」などの動作だけで、その人物が何者なのかを表現できる。
例えば、「歩き方」の場合、男性と女性の歩き方には、違いが出て来る。
その歩き方の違いをキャラクターの動きだけで表現することがアニメーションの面白さでありアニメーターの実力だと言える。
例として、『キャッツ・アイ』の第1期の第7話『ラブサインは華やかに』において、美術館に立て籠もった爆弾魔の要求で、人質として、女性警官が弁当を爆弾魔の元まで運ぶように言われる。
そこで、刑事の内海俊夫は、女性刑事に変装して、犯人の元に向かうが、その時の動きは、女性の恰好をしていても男性の動きをしており、視聴者にもそのことを動きだけで表現して伝えることができている。
これが本物のベテランアニメーターの実力なのである。
しかし、そのような技術は現在の日本のアニメーションには何一つ受け継がれておらず、動きだけで男女の違いを表現できるアニメーターは非常に少ないと考えられる。
次に、【グルメもの】に分類される作品として、『ダンジョン飯』と『異世界食堂』の例をあげる。
この2作品は共通して、題材がファンタジー作品であり、食べ物=グルメについて語られている作品である。
そして、この2作品の比較こそが、アニメーターやその演出家、監督の実力を図る物差しになる。
『異世界食堂』においては、今回のお題となる食べ物についての話が語られる。
しかし、アニメーションとしては、お題の料理は奇麗に描くが、一つだけ大きなものが欠けている。
それが食べる演技である。
グルメ系の作品において、料理を綺麗に描くことは重要なことであるが、その次に重要なものこそが、食べる演技である。
この作品は、この食べる演技ができていない。
ただ、パクパクと料理を美味い美味いと食べるだけで、食べる演技としての見せ場がないのである。
では、もう一つの『ダンジョン飯』について語る。
ダンジョン飯も料理の作画は、見事に描かれている。それだけではない。
料理を作る過程も描いているのだ。
『異世界食堂』はそこが求められていないので比較対象にはできないが、料理を作るために、食材を刻んだり、煮込んだり、漬けたりするなど、丁寧にその工程を描いている。
近年の日本のアニメーションにおいて、珍しい作品である。
そして、重要な「食べる」演技である。
この演技に対して、一切の指摘をさせずに作品を観せている。
例えば、肉を噛み切る演技、スープをすする演技などただ、パクパク食べるのではなく、食べる食材の特徴を生かして食べているのである。
この演技に矛盾がなく、ちゃんと描けているからこそ、文句のつけようがない作画なのである。(まぁ、そんなことも分からない視聴者と自称アニメ評論家は指摘しないけどね)
そして、最後に、日本のアニメーションには、『転ぶ』芝居が存在する。
作中で、登場人物が歩いたり、走っている時に転ばせることで、人間らしさを出すことができる。これは昔のアニメから編み出された技法であり、キャラクターを転ばせることで、人間らしさを描くことができる技法なのである。
世界名作劇場やジブリ作品に多く見られるが、現在は失われた技術の一つであると言える。
○時代によるアニメーターの動きの基準
私が学生の時、教授からある課題で出された。それが『柵越え』である。
牧場などにある柵を男の子が乗り越える演技の課題である。
しかし、この動きを現在の若手アニメーターは描くことはできない。
この理由は、そのようなシーンを観たことがないことが原因である。
この柵越えをしていたのは、主に『世界名作劇場』のような作品で行われていた動きであり、現在の若者はこのような動きを観たことがないため、どのように柵を超える演技を描けばよいのか分からない。
そのため、私も、当時はどのように描けば良いか分からなかったが、『世界名作劇場』をたくさん視聴した結果、動きの概念がようやく理解できるようになった。
それだけ、先人達の優れた動きを観なければ描けないし、それだけ、今のアニメーションには、そのような動かす概念が存在しないのである。
演出のところで語るが、このことが「絵コンテ」問題に繋がる。
*まとめ*
現在のアニメーターには、キャラクターを動かす概念が失われ、綺麗な絵を描くことばかり求められた結果、本来のアニメーションが持つ動きの面白さ凄さの技術が失われてしまった。
この技術を取り戻さない限り、日本のアニメーションが立ち直るのは相当大変だと言うことだ。
アニメーターの技術とは芝居であり、その芝居は、そのアニメーターの空想力と経験がものを言う。
例えば、『機動戦士ガンダム』のガンダムが動くシーンにおいて、ガンダムと言うロボット兵器は実際に存在しない。
だからこそ、どう動くのかは、描くアニメーターの技量で決まる。
つまり、アニメーターとは、空想を実現させる力を持った技術者だと言うことだ。
今回は、アニメーションの作画部門だけで、相当の量があるため、ここまでとする。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
