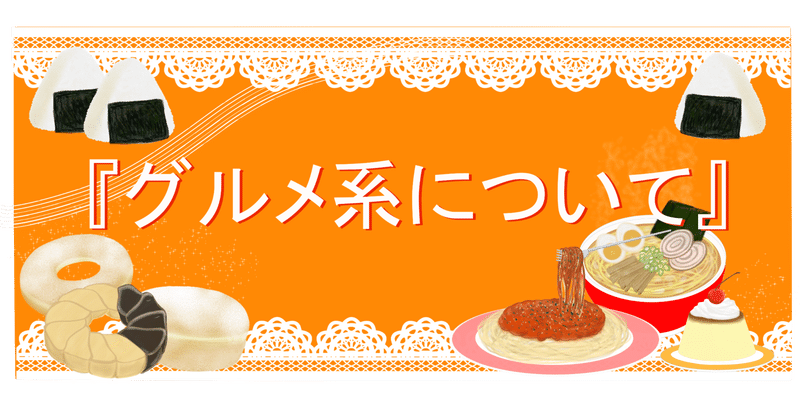
No.017:【グルメ系】について
○初めに
前みたいにカテゴリーについて語ろうと考えている。
今回【グルメ系】について語ることにする。
グルメ系とは、一言で言えば、料理や食材を題材にした作品のことを言う。他のカテゴリーとは、違って独自の作風を持つのが特徴がある。
では、具体的に解説して行く。
【グルメ系】
アニメや漫画などの作品におけるカテゴリーの一つ。
主に漫画ジャンルにおける『料理漫画』『グルメ漫画』の両方の要素を持ち、作品数そのものが少なく、差別化が難しいため、同じカテゴリーに分類している。
主に料理や食べ物・食材などを題材にした作品群のことであり、料理、料理人、食材など『食』に関することを主題にした作品のことを指す。
*定義*
【グルメ系】の作品は、主に「衣食住」の中でも最も人間の根源に近い欲求である「食」を中心とした内容となる。
それをアニメや漫画という仮想世界で満たすことを目的として制作される。
まず、漫画での分類とされている『料理漫画』『グルメ漫画』のそれぞれの漫画の立ち位置で求められるものには、以下の要素がある。
「料理漫画」
対決や(飲食店の)経営、(食事をつくる相手への)愛、
(食材についての知識をもとにした)謎などのテーマが描写される。
「グルメ漫画」
三大欲求の食欲と並ぶ性欲と関連付けられた作品も多く、女性が食べた時の蕩けるような表情が描かれる。
「美味しいものを食べた時のとても幸せな様が、そう表現されるのは食欲を性欲の代わりとして見立ている」との解釈もある。
つまり、物語の中心には、必ず、料理や食べ物・食材などが中心になり、料理を作る過程での対決や経営、他者に振る舞われる食材への愛情、食材の知識や調理過程などの専門知識を持つ主人公が活躍すること。
または、その料理を主人公が食べて、いかに読者/視聴者に美味しそうに見せ(魅せ)ることが目的とした作品であり、そこが作者の腕の見せ所だと言える。
これが【グルメ系】の内容である。
○表現方法
主に、【グルメ系】の作品において、料理や食べ物・食材の表現方法には、以下のものがある。
1)絵
2)セリフ
3)リアクション
1)絵
【グルメ系】の作品の最大の特徴は絵である。
料理の味や香りは絵に描けないので、当然「料理の美味しさ」そのものはアニメや漫画にすることができない。
そのため、料理を視覚だけで美味しそうに見せ(魅せ)る必要性が求められる。
しかし、これは大変難しいことであり、ある程度画力がないと「本当に美味しそうな料理」を描くことはできない。
そして、料理をテーマにする以上「美味しそうに見えない」というのは、キャラクター、設定、ストーリーと言ったその他の要素以前の大問題であり、こう言った部分ができていない作品は(ネタ的にはともかく)名作には、なれない。
2)セリフ
料理の見た目や味、調理している時の料理人の巧みな技などを「絵」と言う表現以外に私達は「言葉」=「セリフ」と言う形で表現することができる。
解説文やセリフだけで読者に美味しそうと見せることは可能(料理関連の本や小説等がそうだし)であるが、【グルメ系】の作品において、重要なことは、「絵」があることが重要なので「セリフ」は、それほど重要視されていないことは理解する必要がある。
3)リアクション
料理を見た、食べた、嗅いだ時の反応=リアクションと言う表現方法がある。
例えば、テレビ番組で、食レポするアナウンサーやタレントがその料理を食べた時に感想やオーバーな芝居(リアクション)を取る。
これと同じく、紙と言うメディア媒体である【グルメ系】にも、このリアクションが存在する。
「絵」には、料理の見た目と言うごく一部の側面しか描写できない。それを克服する手法として料理を食べた人の感想や解説、「リアクション」が求められる。
これは、テレビ番組の食レポと似ているが、アニメや漫画と言う表現方法を使用した場合、現実を通り越した非現実的な表現でリアクションを描き魅せることができる。
例えば、『焼きたて!!ジャぱん』のように、メロンパンを食べてブリッジするようなオーバーなリアクションを取ったり、挙句の果てには絶命するなど、ギャグに近いようなリアクションを食した人物が行うことでその料理の美味さを感想をただセリフで言う以外の、独自の表現方法で表現している。
*まとめ*
【グルメ系】の表現技法には、「絵」「セリフ」「リアクション」の3つの方法があると言うことである。
○作風
【グルメ系】の作品には、独自の物語の展開が多くの作風が存在する。
1)「ドラマ型」
『料理』を物語の軸にし、そこにドラマ性を持たせた作品のこと。
例えば、「○○○を食べてみたい」「これこそ本当の○○○」など、料理そのものにスポットを当てることによって、物語の起点(起承転結の「起」)を作り、ドラマ性を高めるために、その『料理』に対して、値段や食材、調理過程などについて描いて行く。
主に高級な、いわゆる「グルメ料理」(寿司、ステーキ、伊勢海老、河豚、フカヒレ、キャビアなど)を扱うことが多い。
その料理がどのように誕生したのか、本物の料理人がどのように調理するのか、食材に対するこだわり方などが描かれ、その料理に対する知識を深めて行く。
主に『美味しんぼ』が典型的な作品例になる。
主に男性青年誌を中心に執筆され、人情劇や料理に関連する雑学も絡めてゆったりと展開されるパターンが多く、全体的にファンタジーのようなフィクション要素が少ない。
人の心情をリアルに描いた人情ものが多く、アニメ化よりも実写ドラマ化された作品の方が多い傾向となっている。
*作品例*
『美味しんぼ』
2)「料理対決型」
最初期の料理漫画において、『包丁人味平』から連綿と受け継がれる最も伝統的なグルメ系の作風。
主人公の料理人が次々と現れる変態ライバル料理人と料理対決する物語になっている。
見た目にもハッキリと勝敗が分かれるバトル漫画やスポーツ漫画と違い、「味」という概念的なものを比べ合うので、そこをいかに面白さに繋げるかが重要であり、「ただ審査員が飯食って点数付けるだけ」だとあまりに絵面が地味なため、大抵は大仰すぎるリアクション芸でその味への衝撃が表現される(その極みが『ミスター味っ子』)。
*特徴*
①先攻で審査されるのは負けフラグ
絶賛されるが、後の主人公の料理の方がさらに絶賛されて
敗北する。
②調理
料理シーンも常人離れしたすさまじい変態芸で進行することが多く、ヘタなバトル漫画よりも現実離れしていることが多く、料理を美味しく作ることと何も関係ないよねという技も多い。
料理店としては、早かったりパフォーマンスがあること自体は妥当なのかもしれないが、ただ本当に調理過程や料理の見た目と言ったパフォーマンスの是非について取り上げる場合もあり、その場合は「派手な調理はあくまで演技」「料理は見た目が全てではない」という展開が起こりやすい。
*作品例*
『美味しんぼ』(本来はドラマ型だが「究極vs至高」でのバトルが多くなった)
『ミスター味っ子』
『食戟のソーマ』
『中華一番!』
『焼きたて!!ジャぱん』
3)「日常もの」
日常生活のちょっとしたトラブルに対して、料理を通して解決する的なノリの作品のこと。大御所の『クッキングパパ』が代表的。
基本的には家庭料理の範疇なので、「簡単」「美味しい」「失敗しない」料理が中心になる。
どちらかと言えば、登場人物たちの日常生活を描いていくのが主体で、料理はそこへのアクセントと言ったところであり、真似しやすい、実現しやすい料理も比較的多い。
*作品例*
『クッキングパパ』
4)「食レポもの/グルメ解説系」
料理や店舗についての解説や知識に重きを置いた作品のこと。
主に実在する料理店や商品への知識や解説をメインとしており、そのため他の分類に比べるとドラマ性や誇張的な美味しさの表現は薄く、作品によっては食事しているシーンより解説しているシーンの方が多いこともある。
通常の料理漫画が調理や食事しているシーンを楽しむことがメインであれば、こちらは料理や商品への知識を得ることを楽しむ蘊蓄漫画であり、漫画版のグルメガイドブックとも言える。
しかし、実在する店舗や商品をテーマとして扱うため間違った知識は許されず、作者のテーマへ対する知識の深さや取材力が試されるジャンルでもあるため、作品数は他から見ると少なめで、その道の専門家が監修やアドバイザーとして協力していることも多い。
要は単なる食レポを漫画にしただけである。
元々「安かろう、悪かろう」系なので、漫画家の画力に相当差があるのが難点であり、イマイチな漫画家に当たってしまったお店の人はご愁傷様であるが、それでも、美味しそうなお店を探す手掛かりにはなる。
*作品例*
『今日もカレーですか?』
『めしばな刑事タチバナ』
5)「飯テロもの」
食欲をそそるような食べ物などの画像で、読者の空腹感を刺激する表現をした作品。
ただ飲食物の画像を出しただけではインパクトに欠けるため、それらを登場人物が「ただひたすら美味しそうに食べる」ことで、読者を空腹へと誘う作品がほとんどである。
代表作は、『孤独のグルメ』がある。
一応料理漫画だが、「ただオッサンが飯食っているだけ」なので、ドラマ系でもバトル系でもない異色の作風を持ち、強いて言うなら「飯を食うところを読む漫画」であるが、ネット上を中心に根強い人気を博している。
食材への蘊蓄もバトル要素も無く、ひたすら「飯を食べる」部分に重点が置かれているため、ある意味「いかに美味しそうに見せるか」という手腕が最も問われるジャンルともいえる。
「孤独のグルメ」を皮切りに、近年はこの系統の作品が相次いでドラマ化されるなど台頭著しい系統ではあるが、前述の通り「飯を食べる」だけという非常に狭い部分に重点を置いているため、展開が似たり寄ったりになりがちな弊害も発生しており(現代日本を舞台にした作品は特に)、「『孤独のグルメ』の二番煎じ」と見做されてしまう作品も少なくない。
また、「飯を食べる」部分に重点が置かれている関係上、キャラクターの食べ方の描写に対しての批判が出ることもある(例:食べながらやたらとアヘ顔や変顔をする、クチャラー、子供のようにボタボタこぼす…など)。
さらに、「日常もの」と作風が似ているため、近年では両者の境目が曖昧になってきている感もある。つまり、「日常もの」の発展型とも呼べる。
「何が面白いのかさっぱり分からないけど、なぜか面白い」という不思議な魅力を持った作品群だが、ブームに乗っかった粗製乱造も多い。
特に元々グルメとは関係ない作品からスピンオフした飯テロものは賛否が分かれがちであり、美味そうに食べるところを描こうとしているのは分かるが、かえって下品に見えると批判されている作品もある。
食事で性的快感でも得てるんじゃないか?と思ってしまうようなアヘ顔寸前の表情で飯食うような作品なんかなおさらヘイトの的である。
その視線で見ると、『孤独のグルメ』の井之頭五郎は「豪快だが汚さを感じさせない」気持ちのいい食べ方をしていることが分かる。
*作品例*
『孤独のグルメ』
『野原ひろし 昼メシの流儀』
『SUPERMAN vs飯 スーパーマンのひとり飯』
6)「経営もの」
料理や食材、料理人を主題としたものと違って、接客やコスト面、第一印象、安定性などの店舗経営を主題とした作品のこと。
要するに、お店(料理店)として経営して行くための教訓などを含んだ内容のこと。
【グルメ系】に分類されるのは、料理や食材などの食べ物に関するものを取り扱っているため。
作品としては、『ラーメン発見伝シリーズ』が有名であり、特にシリーズ1作目『ラーメン発見伝』はこの方向性を突き詰め、「マンガで読むラーメン屋経営の指南本」とも言える内容になっている。また、初期の『美味しんぼ』などで、ひょんなことから知り合いの潰れかけた料理店や場末の旅館に、コストのかからない名物料理を提案して建て直しに繋がるという話などがこの作風に該当する。
*作品例*
『ラーメン発見伝』
7)「料理人もの」
板前、シェフ、パティシエなどのプロの料理人が仕事をする様子を中心とした作品のこと。
「料理バトルもの」と並び、料理漫画の代表的なジャンルのひとつになっている。
「料理バトルもの」の展開が含まれる場合や「経営もの」の要素も含まれる場合もあるが、基本的には職場・職業として料理をする現場を中心に描かれることになり、ヒューマンドラマ的要素が強めな作品であることが特徴。
ただし、料理が作られる経緯や過程、その背景などが重視されがちで、作られる料理の細かい説明が無い場合も多い。
*作品例*
『江戸前の旬』
『味いちもんめ』
『ザ・シェフ』
8)「フードファイト(大食い)」
主に、食べる量や速さを競う作品のこと。
料理自体の評価は少なく食べやすさや早く食べるための作戦などが中心となる。
テレビ番組で言う『大食い選手権』がこの作風と同じだと言える。
*作品例*
『フードファイト(ドラマ)』
『大食い甲子園』
『格闘ディナー』
9)カテゴリーの合成
【グルメ系】の作品は、常にネタ切れや使い古された題材が多く、新鮮味や新しいネタを出すのは難しい傾向がある。
しかし、他のカテゴリーと併合することによって、オリジナリティーを生み出す方法がある。
例えば、「なろう系」で良く扱われる「異世界もの」と「グルメ系」を合わせた作品がある。
題材として毎回扱われる料理は『とんかつ』や『カレー』などの定番の使い尽くされたネタだが、食べる人物が異世界人で、「現実世界の常識がほぼ存在しない世界」を用意することで「現実世界の素晴らしさ・優れた点を描き出す」ことができる。
そのため、『とんかつ』や『カレー』などの料理は、我々の世界(現実世界)では、珍しくないほど日常に親しんだものだが、そんな“当たり前”なんて欠片も知らない異世界人からすれば「なんだ、これは!!!」と、驚愕することになる。
また、味の感想においても「いたって普通のトンカツだ」では終わらず、トンカツを“未知”として味わった場合の感想を語らせることができる。
つまり、この種の作品は、料理漫画の悩みの種である『料理のアイディア』『奇抜な料理』に悩むことがなく、誰もが知っている料理の数だけネタにすることができると言う利点がある。この作風の代表作として、『異世界食堂』と言う作品が存在する。
異世界に突然現れた現代日本にある洋食店に土曜日だけ繋がる扉を通して、異世界人が料理を食べに来ると言う作品である。
しかし、「知らない人から見た驚き」がメインであるため、他の料理漫画ほど大仰なリアクションはされない傾向にあり、さらに、料理を作る調理過程や食材のこだわりなどの【グルメ系】の持つ特徴を一切必要とされない傾向がある。
ただ、専門知識がなくても描くことができる作風であることも事実である。
*作品例*
『異世界食堂』
『異世界居酒屋「のぶ」』
『ダンジョン飯』
10)「その他」
上記のジャンルのどれにも該当しない作品のこと。
どれも料理やレストランなど食事に関わる場所を舞台にしているのだが、作風や内容が普通の【グルメ系】と分類しずらい作品のため、このように「その他」として扱うことになる。
また、料理漫画じゃないのに料理の描写が凄くて料理漫画扱いされてる作品まで存在する。例えば、『トリコ』と言う作品が存在する。
「飯を食うために強くなる」飯バトルものであり、ジャンルとしては、バトル漫画に分類される。だが、作中の架空食材を扱うことにより、【グルメ系】にも分類されることになる。
このような食べ物や食材を扱っているが、【グルメ系】と言うカテゴリーとは、内容が合わない作品も存在する。
他にも、『キラキラ☆プリキュアアラモード』『デリシャスパーティ♡プリキュア』と言った作品も存在する。両作品共に、「スイーツ」や「料理」をテーマとしており、調理や食事シーンもしっかりと存在するのだが、本作は「料理そのものを守るために戦うバトル作品」と言った方が正しく純粋な料理漫画やアニメとするのは難しいものも存在する。
つまり、【グルメ系】を題材としているが、作中で描かれる内容が、【グルメ系】の作風であげたような内容と違うように捉えられる作品全般のことを指す。
*作品例*
『トリコ』
『キラキラ☆プリキュアアラモード』
『デリシャスパーティ♡プリキュア』
○求められるもの
ここまで、【グルメ系】の作品について、作風などについて語って来たが、【グルメ系】の作品において、一番大事なものが存在する。
それは以下の2つある。
1)食材や料理の作画
【グルメ系】の作品において、完成した料理の作画は作中で一番重要な部分になる。
料理を美味しそうに見せる作家の画力が全てであり、ここでちゃんとした料理を描けなければ作品内でいくら登場人物達が料理を美味いとべた褒めしても説得力が生まれない。
だからこそ、料理の作画は重要視される。
2)食べる演技
【グルメ系】の作品において、次に重要視されるのが食べる演技である。
日本のアニメーションにおいて、大半の作品は完成した料理や食材の絵に力を入れるが、本当に重要なことは、その先の食べる演技である。
ただ、やみくもに出された料理をパクパク食って、美味しいと言わせることが【グルメ系】の作品ではない。
その料理を食べる時、食材ごとに食べ方をきちんと描き見せることが重要なのである。
例えば、ラーメンなどの麺類を食べる場合、麺をすすったり、
硬い食べ物(煎餅、リンゴ)ならば、音や動作で硬いものを嚙み砕く演技が求められる。
熱いものならば、熱いとリアクションさせてから、ふ~ふ~息を吹きかけて冷ましながら食べたりするなどの演技が求められる。
これらの全ての演技を絵で表現して動かすことが重要なのである。そして、そのアニメーターの大変さ、苦労を視聴者に指摘されたり、違和感を出さないで描いた作品こそが本物の力ある【グルメ系】の作品になる。
つまり、食材を調理して、食べるまでが【グルメ系】の作品において重要なものとなる。
しかし、この食べる演技において、現在の日本のアニメ産業はその技術の大半を消失しつつある。
*作品例*
『美味しんぼ』
『ミスター味っ子』
『食戟のソーマ』
『中華一番!』
『焼きたて!!ジャぱん』
『クッキングパパ』
『異世界食堂』
『異世界居酒屋「のぶ」』
『孤独のグルメ』
『野原ひろし 昼メシの流儀』
『SUPERMAN vs飯 スーパーマンのひとり飯』
『衛宮さんちの今日のごはん』
『ラーメン発見伝』
『江戸前の旬』
『味いちもんめ』
『ザ・シェフ』
『大食い甲子園』
『格闘ディナー』
『トリコ』
『キラキラ☆プリキュアアラモード』
『デリシャスパーティ♡プリキュア』
*まとめ*
このように【グルメ系】の作品は、独自の作風を持つカテゴリーであることが分かる。
また、料理を美味しそうに描く技術はあるが、食べる演技ができていない作品が多いことも問題である。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
