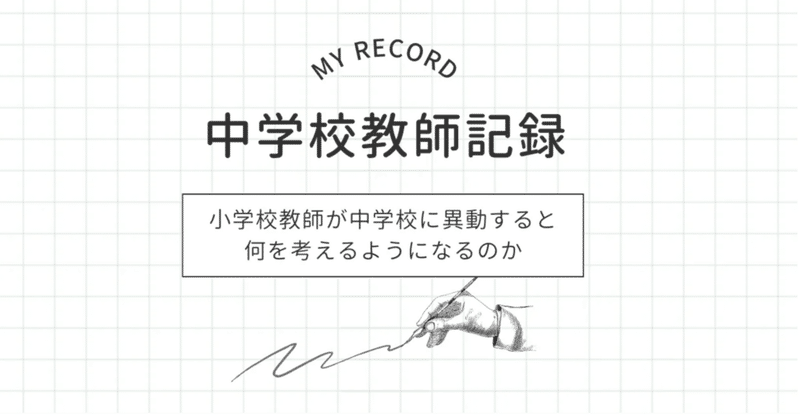
中学校教師 #57 成果を出した生徒・停滞した授業
令和5年の4月から中学校で勤務しています。
いずれは小学校に戻ることを考え、この経験を記録に残そうと思います。
異動の経緯や考えは下記参照
GWが終わり、4日間と登校。
生徒たちは思ったよりもいつも通りの姿で安心です。
今週は、学習を通して見えた生徒の姿から考えてみます。
成果を出した生徒
今週、初めて単元テストを行いました。
昨年度と変更した点は1つ。
単元テスト前に予想問題を提示し、練習をする時間を設けたことです。
しかも、練習で終わることなく、分析や類似問題を通して練習することができるようなワークシートを活用することにしました。(けテぶれを意識)
3年生、数学、式と計算の単元テストは2つに分かれています。
前半の「式の展開」だけ単元テストを実施しました。
ある生徒が印象に残りました。
この生徒は昨年度の後半、かなり無気力な姿で授業を受けていました。当然、数学に対しての苦手意識もあり、基本的な計算技能もそれほど高くありません。
その生徒が、テスト中にペンを止めることなく計算を続けていました。
基本的な内容の部分だけだと、得点はなんと90点!(知識技能100点満点のもの)
そして、テストを返却すると悔しそうな表情を見せました。
何かが変わった。
本気になった姿を見ることができました。
今年度の授業の中で、この生徒が変化するきっかけがあったと思います。
学びが自分のものであるという自覚が持てるような授業展開は有効だったと感じています。このあたり、詳しく言語化できないですが、またの機会に…。
停滞した授業
3年生の数学で公開授業をしました。
他校の先生と教育委員会から数名。
式と計算の後半、「文字式を利用して説明する」という内容を扱った授業を行いました。
簡潔にいうと、授業では生徒の学びが停滞してしまい、反省点の多い授業でした。
もう少し考えたらできそう…という思いと、
あぁ、諦めちゃっているなぁ…という思いとが交錯しました。
(人が見ている授業なんて関係ない!)と思い、生徒の手を止めて語りました。
・課題が難しいと感じているなら、何が分かって、何が分からないか、きちんと言葉にするべきだ。
・相談したり、聞いたり、ヒントを見たりするなど、解決するための手段はいろいろある。一つに固執する必要はない。うまくいかないなら執着せずに変更するべきだ。
このような話をしました。
授業の導入や課題提示については、私自身の実力不足でもう少し改善する余地があったと感じています。しかし、それと同じくらい生徒の学び方・学ぶ姿に改善の余地もあること、もっと成長できると信じているからこのようなことを語りました。
今回見えた課題は生徒理解には役立つと考えています。
課題を改善して、また皆さんにお伝えできるように努力します。
ガーデニングな1日
草刈機を購入して、長くなった庭の雑草を刈り取ったり、娘と一緒に野菜を育てる準備をしたりと、ガーデニングな1日でした。土を触ったり、草花を触ったりするって素敵です。夕方は、芝生に水やりをしたついでに、子どもたちにも水を浴びせ、うわぁーーーって盛り上がりました。
休日の充実が平日の頑張り・踏ん張りにつながります。
明日は母の日。
子どもたちと一緒に感謝を伝える計画を立てたので、実行します!
【「えがお」を大切に 焦らず、誠実に、前向きに】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
