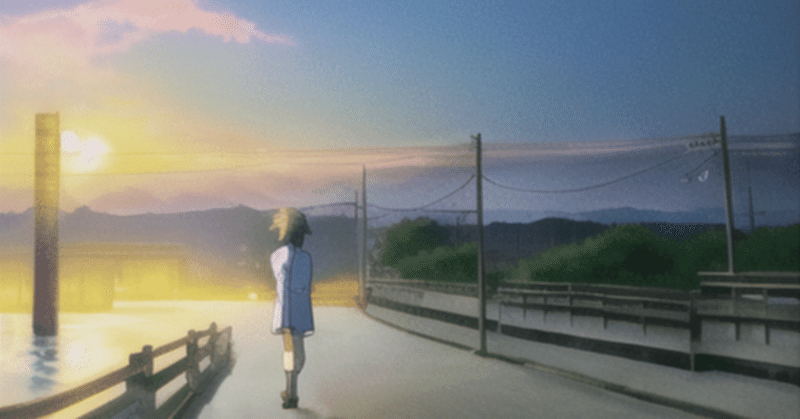
【小説】ひとつではない世界で(中)
※はじめにおことわり…
本作は前後編の二編で構成する予定でしたが、後編が長くなってしまったので、前・中・後編に編成し直します。お詫びするとともにお伝えいたしますので、何卒宜しくお願い致します。では、以下から中編がスタートです。
「手が…手が痒いの。」
「シャンプーのせい?」
「そう。」
「手を見せて。」
私は、ノラの前に両手を差し出した。
私の掌と指は、皮がむけてボロボロになっている。
「可哀そうね。痛い?」
「痛いわ。夜、眠れないぐらいに。」
「痛いのは、手だけではないわね。心も痛がっているのね。」
「うん。」ボロボロと、面白いぐらいに涙が零れてくる。
「こんなはずじゃなかったもんね。」
「うん。」
ノラは、私の涙がおさまるまで、左手で身体を抱き締めて横に寄り添ってくれた。
ノラの腕は力強く、それが何だか安心感をくれた。
「もう、大丈夫?」
「うん。」
「仕事がツラいから、ユウタ君の店に行くようになったの?」
「初めは、たまたまだったの。店の先輩に連れられて。新宿の飲み屋街なんて、行った事なかったから。それに、あの時はまだ、私、お酒、殆ど飲めなかったし。」
「でも、一回行ったら、それからは、ずっと行くようになったのね?」
「そう。店がお休みの土日以外は、毎晩。」
「どうして?そんなにお酒が好きになったの?」
「確かにお酒はたくさん飲めるようになったわ。でも、それだけじゃない。」
「何?」
「優しかったから。」
「…」
「ユウタ君が、優しくしてくれたから。」
「優しい?例えば?」
「私が、初めて手の痒みに気づいた日の夜、店に行ってその話をすると、ユウタ君はすぐに店で作っている梅酒の大きな口の瓶を出してきて、梅酒をおしぼりに浸してそれを痒いところに付けておくといいと、言ってくれたの。」
「へえ、それで、痒みはなくなったのかい?」
「いや、でも、その時は痒みを忘れたわ。」
「それで?」
「それからは、店に行く度に、ユウタ君は色んな方法を試してくれた。」
「どんな?」
「熱湯に浸したおしぼりに酢をかけて、それを痒い所に巻くとか、アロエの木を買ってきてくれて、アロエを痒いところに塗るとか…」
「でも、全然効き目はなかったんだろう?」
「…」
「どうして、皮膚科の医者にかからなかったんだい?」
「病院には行ったわ。でも…」
「でも?」
「これを治すのは無理だって言われたの。今の仕事を続けている限りは…」
「ああ、そう。」
「でも、私、美容師になりたかったの。だから…」
「毎晩、ユウタ君の店で色んな方法を試したという訳かい?」
「そう。」
「ユウタ君とはそれだけかい?」
「いや、違う。私はユウタ君が好きだったの。」
「だった?という事は、今は違う?」
「そう、今日の朝早くに好きな気持ちを捨てたわ。ユウタは、バイセクシャルで、ユラ君は彼のパートナーの一人だった。」
「二人は、結婚していた?」
「いいえ、二人ともバイセクシャルだったみたいで、ユウタ君もユラ君も男も女も、オープンな付き合いをしていたみたい。」
「その付き合いの中に、アンタもいたという訳?」
「そう。でも、私はユウタ君を独り占めにしたかった。私だけのユウタ君でいて欲しかった。」
「それを彼に伝えた事はあるのかい?」
「ええ、何度も。」
「でも、彼はアンタだけのものにはならなかった?」
「なったフリだけをしてね。」
「フリ?」
「彼は優しいわ。私が夜中に寂しくなって、彼に電話すると、私の気が済むまで話に付き合ってくれたり、私の手のかぶれだって、彼は本当に直そうとしてくれて。色んな人に訊いて、効きそうな薬を買ってきてくれたり。いつも、私の事だけを想ってくれてるフリをしたわ。」
「どうして、フリだと分かるんだい?」
「彼は、みんなに優しいのよ。皆に嫌われたくない。だから、彼がみんなに優しくすればするほど、無理が生じるの。どうにも辻褄が合わなくなるのよ。で、私は気づいたの。彼は優しい嘘ばかりをついてるって。」
「ああ、所謂八方美人というヤツだね。分かるよ。優しくしなきゃあいけない人が多くなればなるほど、時間も縛られるし、自由度はなくなるもんだからね。」
「そう。昨日って、月曜日でしょう。ユウタ君の店、先週は金曜日を休みにしてたの。私には、先祖の墓参りに地元に帰るって、説明していたわ。だから、金曜日を休みにして、元々休みな土日と合わせて、三日間で。」
「それが違ったのかい?」
「そう。昨日、待ち焦がれて私、店に行ったのね。そしたら、「金曜日、休んじゃってごめん、これ、お土産。」って、私に小さい箱をくれたのよ。」
「何だったの?」
「中国の漢方薬の軟膏。マカオのお土産だって。痒みに効くからって。」
「マカオ?彼はマカオ生まれなの?」
「まさか、彼は生粋の日本人よ。」
「じゃあ、何故?」
「分からない。でも、彼は私に地元に帰る話をしてた事をすっかり忘れてたわ。」
「それにね。私、知ってんだあ。うちの店のオーナーのリョーコさんって、女社長と、私の先輩のシズカさんも週末、マカオに行ってた事。」
「えっ、じゃあ、彼も一緒に?」
「多分。それにパートナーのユラ君も一緒だったと思う。リョーコさんとシズカさんもカップルだしね。」
「そうなの。」
「そう。リョーコさんと、シズカさんは、マカオに行く事を私が知ってるなんて、知らないけどね。」
「内緒だったんだね。」
「バックルームで二人が話してるのを偶然聞いたんだ。楽しそうだった。」
「そう。」
「ユウタ君も、マカオで楽しかったんだって、言ったんだ。いいなあ、みんなで楽しそうでって、思った。何か、悔しい気持ちになって、イラついて…」
「それで、アンタはどうしたんだい?」
「私、どうすればいいのか、分からなくなって。夜中にユウタ君の店を飛び出して…自分の部屋には帰りたくなくて。新宿をふらついてたら、バッグの中に、もらった軟膏があるのを見つけて。」
「何で、どうしていいのか、分からなくなったの?」
「だって、ユウタ君だけじゃない。オーナもシズカさんも私を騙してたのよ。ユウタ君もユラ君も、みんな、私に本当の事を言わなかった。私は、何とか美容師になろうと頑張っているのに。手が痛くても、痒くても、頑張っているのに。頑張る勇気をくれてた人もみんな、みんな、私を騙してた。どうすればいいのか分からなくならない?ユウタ君、ユウタ君だけは信じていたかったのに。」
「そう、そうね。」
「これまでもユウタ君は、小さい嘘を私に一杯ついた。私を傷つかせないためについた嘘なんだけど…私は嫌われたくなくて、ずっと調子を合わせてきたんだけど…嘘は、嫌。もう、疲れた。」
「それで、彼の部屋に行ったのは、何故?」
「もらった軟膏を返すためよ。箱に、手紙を書いてね。」
「何て、書いたの?」
「人を騙すヤツは、最低だ!」と、書いたの。
「「人を騙すヤツは、最低だ!」だってえ?そいつは愉快だねえ。胸がすーーっとしたろう?」
「うん。とっても。でも、その後に気づいたの。」
「何をだい?」
「私、今まで自分が大切だと思ってきた事を今日、全部失ったと。」
「失った?」
「もうユウタ君の店には行けない。それだけじゃなくて、私の勤めてた美容室にももう行けない。ディスっちゃったから。きっと、いじめられる。シズカさん、性格悪いから。」
「いじめられる?決まってんのかい?」
「多分…」
「で、自分の全部をいっぺんに失ってしまったと、絶望している?」
「そう。」絶望と聞いて、どっと涙が溢れた。
絶望。
確かに。
行く先を失った望み。
「それは、違うね。アンタは何も失ってない。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
