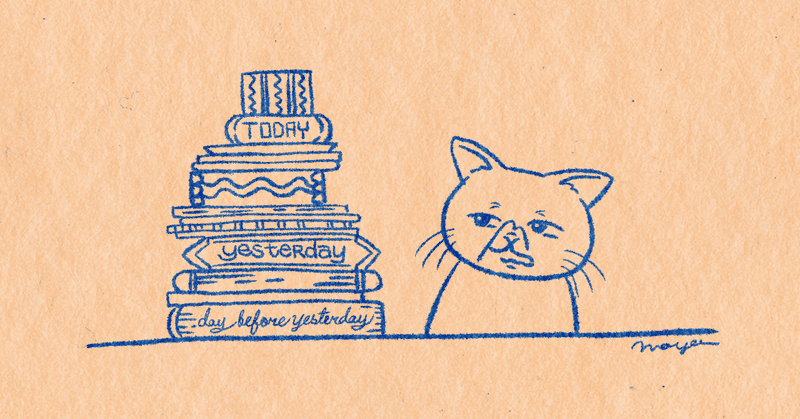
しごとを変えたはなし 前
こんにちは、uです。
今回はタイトルの通り、仕事を変えた話をしようと思っています。
私は、今はいわゆる会社員なんですが、実はこの身分になったのはこの4月からでして。
今年の3月までは、私立高校の非常勤講師をしていました。国語科の担当で、高校1年生から3年生まで満遍なくお世話になっていました。
もう手前味噌にもならないんですけど、あの高校の子達はみんな本当に人間ができていましてね。きっと私は彼らにとって、いち教員というより「なんかフラフラしてんなぁ、しゃーねえ助けてやるか……」と思うような、しょうもない身近な年上のポジションだったろうなぁと思っています。
で、そんなフラフラ教員生活を新卒から5年ほどしていたのですが、この度ふと思い立って転職することにしたんですね。
「何だ急にどうした?」という思い立ち方をしたように見えますが、それでも私なりに転職したいなぁと思う理由はありました。
ですので、ここから先は私の転職理由と、実際どうやって転職活動をしていたのかをお話しようかなと思います。
ちょっと1つにまとめると長くなりそうなので、前後編に分けています。だからこの記事は「前」とついているわけです。
さて、まずは転職理由から。
「なんで5年教員やってたのに、今更転職しようと思ったの?」ということですが、
ものすごく端的に言えば、「飽きてしまった」からです。
ちなみにこの理由、前職でデスクが隣だった同僚に白状したら大笑いされました。
「最高の理由」だそうです。良かった怒られなくて!笑
教員の仕事、特に非常勤講師の仕事は「授業をすること」なので、ほぼルーティン化できるんですね。
① 仕事のルーティン化
非常勤講師の主な仕事の流れは、大体こんな感じです。
シラバス発表or確認 → 授業準備 → 授業
プラスアルファでテストや課題の作成、くらいかな。
保護者対応や生徒指導は基本的にありません。人によっては部活動指導に駆り出される先生もいましたが、私はそういうのもありませんでした。
人聞きの悪い言い方ですが、私立学校の非常勤講師は、多分教員の働き方の中でかなり割に合う、なんならコスパの良い働き方だと思います。
それはさておき、ルーティン化できるこの仕事の内側で、個性を出すことももちろんできます。
たとえば授業準備で、指導用資料以外にどんな論文や文献を調べるかにも個性は出ますし、どんな教え方を選ぶか(座学中心かグループワーク中心か、など)にも個性は出ます。
それでも、これもまたルーティン化はするんですね。
どういうことかというと、「その時担当しているクラスの特徴に合わせて、どんな資料や教え方を選ぶのかはある程度固定される」ということです。
たとえば、「座学中心の授業をすると生徒の大多数が寝てしまうクラス」があったとしましょう。
このクラスでも、扱う単元によっては座学を取り入れなければ仕方がないことはありますが、それでもこうしたクラスは、大体において「グループワーク中心の授業」を選びます。
「授業全部寝てたからテストなんて解けません!」と言われてしまったら、まあそれは寝ていた生徒の自業自得ではありますけれども、生徒の大半が寝てしまう授業を放置していた教員にも少しは責任があります。
教員の授業における仕事は、「限られた時間内に定められた単元の内容を(完全な理解へ導けなくとも)その場の生徒に周知する」ことですから、生徒がほとんど寝てしまうというのはちょっと困るわけです。彼らが起きて授業を受ける環境を、整えなくては仕方がない。
もちろん、教員がどんな授業をするのかは自由ですし、クラスによっては、どんな授業をしようが食らいついてくる猛者ばかりがいたところもありました。
それでも、そうではないクラスの方が圧倒的に多いのであれば、この作業(個性が出せる部分)もまた、ルーティン化せざるを得ない。
これに私はちょっと、飽きてしまったんですね。
生きている人間相手に話をしているわけですから、毎年どころか毎回の授業ごとに生徒の反応はちょっとずつ違います。それを見るのは確かに面白かったですが、それでも私の「飽き」はあまり解消されなかった。
そしてこれにプラスして、こうも思いました。
「この仕事をずっと続けていたら、私の社会の認知って歪むんじゃないか?」と。
② 認知の歪みへの恐怖(1) - 外の世界を知らない
実は、転職活動を始めた時、エージェントさんやカジュアル面談相手の人事の方に話していた転職理由はこちらでした。
この「社会の認知って歪むんじゃないか」という部分をもう少し展いて言葉にすると、
「このまま教員以外の世界を知らないまま、『先生』の目線が板についてしまうと、一般社会で生きていくのが難しくなってしまうんじゃないか?」
ということになります。
先述しましたが、私は新卒から5年ほど教員を続けてきました。教員以外の世界を、私は知りません。
大学生の時にバイトはしていましたが、それも図書館と塾講師でしたから、そこまで「商業的な世界」に触れてきたこともないんですね。
しかし、社会人になった人間が触れる世界って、結構広範囲で「商業的な世界」だよな、と思いまして。
一般企業は基本的に営利団体、ビジネスの世界にあるものです。しかし学校はあまりそういう側面がない。
確かに私立学校はぶっちゃけ営利団体ですが、そうは言っても売り上げ目標があったり、ノルマがあったりはしません。
年度はじめの職員会議で「GMARCH合格者◯%以上を目指しましょう」などの目標が立てられることはありますが、これだって達成には生徒の力を信じる部分が大きいですから、教員ばかりがめちゃくちゃ頑張るというのは何だか違います。若草物語の名言を引っ張るまでもありません。
また、私はこの教員業界の中で「先生」として過ごしてきました。ずっと「先生」と呼ばれるのには違和感を覚え続けてきましたけれども、違和感を覚えるよりだんだんと、怖くもなってきたんですね。
③ 認知の歪みへの恐怖(1) - 肩書きに感じた重荷
これもまた先述しましたが、非常勤講師は「授業をする人」です。
つまり、仕事中に話す相手のほとんどは「生徒」になります。
私は、「先生」として「生徒」を見ている時間が長い、ということに「慣れる」のが、どうにも怖くなってきてしまったんです。
無論(というのも本当になんですが)、私は生徒に大変お世話になったタイプのしょうもない教員でした。
だからこそ、生徒に対しては「対等な人間」として接しようと思っていました。
特に、私の在職していたところは高校でしたから、生徒は私とせいぜいがまだ10歳ほどしか離れていません。彼らに対して、歳の離れた弟妹を見るような気持ちになったことは数えきれません。高校生っておもろいな〜ノリが元気だな〜と思いながら眺めることが多かったです。
それでも、教員である以上、私は彼らに対して一定の距離を取る必要がありました。
教員という肩書きを持った「大人」として彼ら「子ども」を見る、というのが表現としては適切でしょうか。
多分、私はこの表現の後半部分なら、何も考えずに受け入れられるのだと思いました。18歳以下の青少年は基本的に社会から守られてしかるべきだ、「大人」は「子ども」を見守るのが普通だ、と私は自然な気持ちで思っています。
しかし、前半がちょっと重かった。邪魔だった。
要するにこの部分が、私の手には余ったんです。
だったら「教員」であることを捨てた方がいいな、と思いました。
外の世界(商業的な一般社会)を知らない、ついでにルーティン化した仕事にも飽きてきている。
なら、もういいんじゃないか、と思いました。そうして「転職しよう」と強く思い始めたわけです。
さて、大変長く話してしまいました。
まとめますと、
新卒からずっと教員一本で働いていて、外の世界を知らないことに危機感を覚えた
「教員」という肩書きが重荷であると感じ始めた
ルーティン化されつつあった仕事に飽きてきた
ということが、私の転職理由になります。
次の後編では、「じゃあどうやって転職活動したの?」という点を、「どこを目指したのか」というところを含めて話していこうかと思います。次も長くなりそうだなあ……ごめんなさい。
後編では、お世話になったエージェントさんや転職サービスについてもちらっと触れていこうと思いますので、もしご興味ありましたら、ゆるっと更新をお待ちいただければ嬉しいです。
それでは、今回はこの辺りで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
