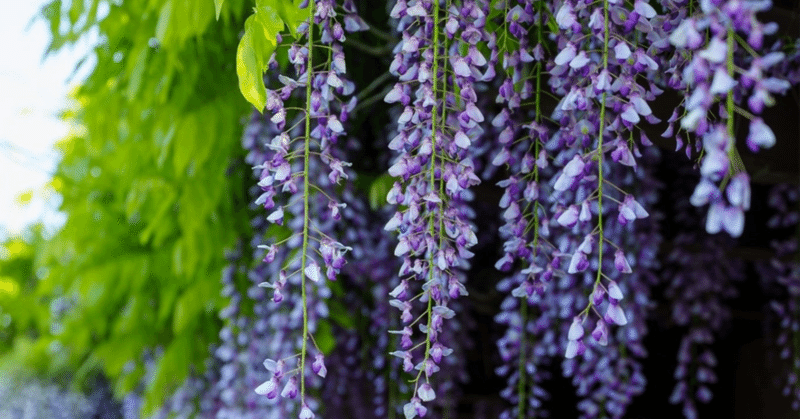
反転
「いつもと反対をやってみればいいんだよ」
そう先生は言った。
先生といっても、具体として存在する塊ではない。私が私の頭の中で作り出した、想像上の霞であることをことわっておく。わたりのついた銀縁の眼鏡をかけた、齢40から50くらいの人である。もともと思い浮かべていた誰かがいるわけではない。
世間に口ごたえをするのに慣れていたので、先生の言葉はひどく胸に刺さった。そうか自分はいつも半か丁かの片方にしか賭けていなくて、もう一つの可能性を棄て続けていたんだと思った。そうして、いてもたってもいられなくなって、階段を駆け降りて手頃なスリッパを履いて外に出て、町内の周りを走って戻ってきたら、初めて自分が何者かになれたような気がした。
そこから私はよく先生と話をするようになった。先生はいつも私にそれまで見たこともない、あらゆる不思議を教えてくれた。それは文学であったかもしれないし、あるいは科学であったかもしれない。そのどちらでもなかったこともあったと思う。感じるたびに私は喉を鳴らして唸った。先生はどこか悲しげな顔で私を見つめていた。そうしていつも私が完全に納得しきる前にどこかへ行ってしまった。
私は変なもやもやを残し続けるほかなかった。というのは、先生は一度話したことは二度と教えてくれないのである。私がメモを取るまでもなく話は進むから、自分の感覚に交わるところを優先的に記憶していくしかない。
そうすると今度は興味のなかったところをすっぽりと忘れてしまう。私はいけないと思った。といって何か行動を起こすこともできない。忘れ忘れるたびに、私の頭の中にはいつか先生が言った「いつもと反対をやってみればいいんだよ」が響いていた。
あるときふと気になって、先生には奥さんはいるのですかと尋ねてみた。すると先生は一言、「それは答えにくい質問だ」と黙ってしまった。
思い返すと先生の口から先生本人のことを聞いたのはこれが最初であった。ひょっとすると先生は生涯独身を誓うふうな人種なのかもしれないと思いを巡らせていると、気だるそうに背中を丸めて先生が戻ってきた。
いるかもしれないし、いないかもしれない。
不機嫌そうな顔をしてそう答えた。
この頃より少し前から私には先生の何たるかがわかってきていた。それはおそらく未来の私であるらしかった。未来の私が、まだ未熟な私に助言をしにきているのだ。そしてこの質問への答えから、私の仮説が根拠をもった1つの論に変わっていた。
先生が先生自身のことを答えられないのは、それが巡り巡って自分になるからだ。先生を決めているのは先生と話している自分でしかないのだから、干渉するわけにはいかない。ここでいると言ってもいないと言っても、2つに1つの可能性を絞ってしまう。先生には「いつもと反対をやる」ことはできないのだ。
私はただ一言、こうつぶやいた。
「先生はその答えを知っているはずです。なぜ答えないのか」
それから先生は姿を見せなくなった。いつも座っていたあの肘掛けのついた黒い皮の椅子にも、六畳間の隅にも、ジャスコの青果コーナーにもいなかった。
私は大人になったのだと思う。
それを先生が教えてくれたのだと、別れを惜しむよりも前を向こうと決意した。
いま、これを書いている私は、このたび50歳の誕生日を迎えた。最近は加齢も進んできて、少し走るたびに膝が痛むようになったが、まだまだ現役として足を動かしていかないと営業の世界では生きていけない。
50年の月日を振り返って、「先生」を思い出す。
先生はいまの頃の自分であったはずだった。しかし昔の自分と話ができるなんて仕組みがあるわけがない。眼鏡はかけていないし、家に和室もなければジャスコはイオンになっている。
虚空に向かってあっかんべえをしたら、あの日の先生のかけていた眼鏡のレンズがきらりと光った気がした。
「おとうさん」
息子が部屋からこちらを覗いていた。急いでたばこの火を消して戻る。掃き出し窓を跨いだそのとき、清涼感のあるミントの香りが、仄かに匂った。
「これも違うんだろうなぁ」
ベランダに向き直ってもう一度あっかんべえした。今度は何も見えなかった。
サポ、サポ、サポート。 ササササポート。 サポートお願いします。
