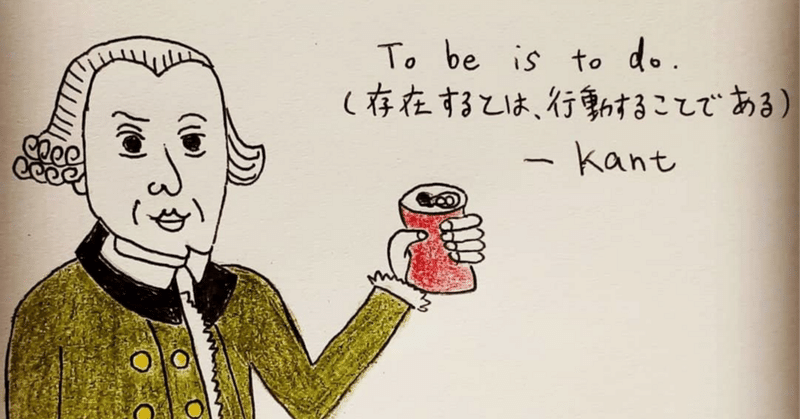
私が大切にしている「テスターとしての批判精神」について
はじめに
昨年、採用面接を受けている中で「QAエンジニアとして大切にしていることは?」と聞かれて、「QAエンジニアとしてではなくテスターとして大事にしていることはあります。それは批判精神です」と答えました。
「批判精神」がなんなのかは哲学的な定義とかありそうですが、その辺は抜きにしてもうちょっと具体的に何を大切にしているかを書いてみようと思います。
批判精神とは
ここでいう「批判精神」とは、今書いてる時点では「同調圧力に屈せず必要ならば批判的な態度を崩さない」くらいに捉えています。
批判とは
批判とは、国語辞典での批判の定義を調べて貰えばいいのですが、もう少し私の使い方として付け加えたい注釈があります。以下の点です。
批判対象物の改善を促すために行う活動である
批判はなんらかの根拠を持って実施される
批判には客観性がある
批判対象として人は取らない
批判的な態度とは
批判的な態度とは「客観的な根拠を元に疑いを持ち続ける」ということだと思っています。
「疑いを持つ」というのは、悪いことだと思っている人もいると思いますが、違います。
例えば科学の場では何か新しい法則や成果が示された時に、すぐに追試を行い、それらの有効性や再現性を確認します。それは「疑いを持っている」ことに他なりません。
「この野郎」と思ってやってる人もいるかもしれませんが、基本的には人類の発展のために疑い、その真偽を確かめているわけです。
人と人との繋がりの中で「疑い」は悪いことかもしれませんが、何かの成果物や成果をそのまま受け入れることなく、「疑い」を持って批判的に見ることで、それが本当に有用なのかを立証する手がかりになるのです。
批判精神を持ったテスター
ソフトウェア開発をする中で、様々な同調圧力にさらされます。
納期、社内政治、受発注、開発者との信頼関係など。
そうした中で、「本当に正しいものが作られているか?」を問い続けられるのが「批判精神を持ったテスター」だと私は思っています。
似たようなことは「ビューティフルテスティング」の「テスターはお役に立っていますか?」の章に記載されているので、ぜひそちらもご覧ください。
実際にテストをしていると「このような報告をして大丈夫かな…」「私はこう思うけど自信がないな…」と思うときが私はあります。
ただ、その時も「自分は正しく批判しているか」と自分自身を批判的に見ることである程度解決できます。テスターが「報告」するのは製品やサービスをより良くするためであり、テスターが思うことは根拠を持ってきちんと言語化され、正しく批判であるべきだと考えます。
「自分自身を批判的に見ること」これも私が大切にしている批判精神です。
批判にはリスペクトがあった方がいい
作り手へのリスペクトがあってこその批判
「批判ができる」というのは「誰かがそれを作ったから」です。
なので、批判するテスターとしては、作り手へのリスペクトをすることが大切だと思っています。
むしろ作り手をプロとしてリスペクトするからこそ、批判する動機があると思っていいでしょう。
批判するテスターは作ってくれる人がいないと成り立たないものであり、リスペクトを欠いた批判によって、やる気をなくしてしまうといったことがないように細心の注意を払うべきだと思っています
リスペクトが"あった方がいい"の理由
と、書きましたが、批判にはリスペクトがない批判も含まれると思いました。
それは「相手を黙らせるために行う批判」です。
例えば、誰かを傷つけるような言葉を吐いている人がいた場合、それらに対してリスペクトを持って建設的に批判することが難しい場合があります。
あまりに害が大きい場合、相手を封殺するような強めの批判が必要な場合があると考えました。
リスペクトのない批判は、人類全体の改善を志向していて、その人の成果物の改善はされず、却下され、もう二度とその人を発言させない性質のものだと考えます。
批判をするなら言論の自由を認める
「批判」について少し考えると、これらの土台になっているのは「言論の自由」というものな気がしてきました。
その上で、「批判のあり方」を「批判」する「メタ批判」をしてしまうと、相手の「言論の自由」を侵してしまわないか?
それは自分自身の批判も否定することに繋がらないか?と思いました。
なので、個人としては「リスペクトがあることはマスト」だと考えますが、全てのテスターが「リスペクトを持っていないといけない」と考えるのはやめにしました。
批判的な精神が協調を生む
「賛成」と言うことが協調だと考えている人がいますが、それに関しては私は違うと思っています。
何かの意見に対して、批判を行い、よりよい道(ジンテーゼ)を模索して、非批判者と批判者が持つ共通の目的を達成することが協調だと私は信じています。
「賛成」自体は否定しないですが、その裏には「無関心な賛成」があるということを私は危惧しています。
「飯どこ行く〜?」「どこでもいいよ〜」(どこでもよくない)というやつですね。
テスターとしてそれが本当に正しいかどうかをしっかりと批判して、より良い道を模索することが、本当の協調だと私は信じています。
テスターの倫理観として、「人を批評しない」ということ
ちょっと脱線しますが、私が大事にしている「人を批評しない」というところにも触れておきます。
テストをしていく中で、「これあんたが悪いんじゃないの?」とか、「hogehogeができていないんじゃないの?」とか「それでいいと思ってんの?」とか言いたくなることがあると思います。
でもそれはBad Testerです。
決して相手の能力や人格を否定するのではなく、成果物の批判にのみフォーカスするのがGoodなテスターだと思っています。
どうしても「相手がミスをした」ことに言及しないといけない場合にも、「ミスをしてしまう状況はどのようなものだったのか」をきちんと言語化して、決して他責にせず、「なら仕方ないよね」にするのが私のGoodなテスター像です。
批判精神とその先
本記事では「テスター」というロールを協調していました。
それは「QAエンジニアでは本当に批判が必要なのだろうか?」について自分の中で答えが出ていないからです。
QAエンジニアが何を担うかについては別の記事で記載するとして、例えば仮にQAエンジニアが「組織全体の価値の最大化」を目標とする場合、「政治や人間関係のことや自分で気づいてもらうことを考えて敢えて批判しない」といったバランスも必要になるのでは?と考えました。
「批判」というのはあくまでプロダクト志向であり、QAエンジニアはプロダクトを作るプロセスや文化にも注意を払わなければいけないのではないか?と考えます。
そうした時に、「批判精神」が常に大切にされるべきかは私には答えが出ていません。
おわりに
ある人との面接で「批判精神」という言葉を出してしまって、いつかこういう記事を書きたいと思っていました。
また批判については以前から気になっているテーマでもあります。
JaSST OnlineでもOSTに上げたことがあります。
多分、これから引き続き考えることなので、記事自体は修正するかもです。
本記事の批判をお待ちしています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
