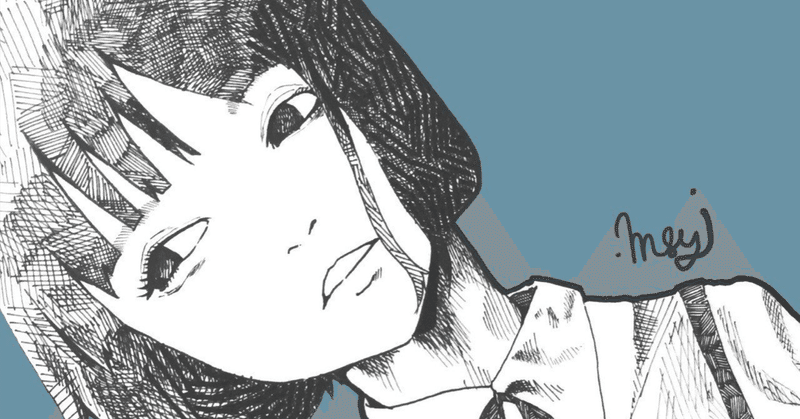
「視座の暴力」〜抽象度ハラスメント〜
僕らが本当にやりたいことってなんだったっけ?
はじめに
本記事では、私が「視座の暴力」と名付けた抽象度ハラスメントについて解説します。
人と議論していると物事の抽象度が行ったり来たりします。
WhyではなくHowの話になったり、Howによって Whyが歪められたり、いろんなことが起こります。
しかし、それは議論している本人の多くは悪意を持って行われるわけではありません。
そんな中で議論に参加していなかった人が私頭いいですみたいな顔して「ちょっと〜問題と課題が入れ混ざっているよww」みたいなこと言う人がいます。
それについて思うことを話します。
具体と抽象
言語には「抽象度」という一つの軸が存在します。
「抽象」とはコトバンクを参照
経験されたもののなかのある特性に注目してこれを取出し,ほかを捨てること。
https://kotobank.jp/word/抽象-97265#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
言語とは何かの表象であり、すでにそれは現実世界から抽象化されたものとも言えます。
言語を使った言葉の中で、より現実を現したものを「具体」と私は呼んでいます。
それらの「具体」から相対的に本質と呼ばれる部分、例えば共通していたり、枝葉を切り捨てたり、ある目的のために誰でもわかるようにしたことを「抽象」と私は呼んでいます。
誰かと言葉でコミュニケーションをする一つの形である「議論」とは、物事の抽象度を変更する行為、「具体と抽象を行ったり来たり」するということを繰り返す性質を持ちます。
「具体と抽象の行ったり来たり」は訓練でできるようになる人もいますし、生まれつき脳の構造が元々そうなっている人もいます。そういう人を頭がいいと言ったりもします。
抽象化能力が高い人間
自覚する抽象化人間
抽象化能力が高い人は多くの場合、それを自覚しています。
抽象度の高い思考力を持つ人は、具体的な言葉で言い換えることができますが、抽象度が低い人がそれが難しいことが多いです。
そのため、抽象化能力の高い人は「自分はわかっている」「相手のレベルに合わせている」といった自覚を持つようになります。
そして、抽象化能力が高い人は、自分が「バカの壁」の内側にいることに気がついていません。
抽象化能力と「バカの壁」
バカの壁とは以下の書籍を参照してください。
バカの壁の詳細は省きますが、この文章では少し曲解して、「自分はわかっていると思い込む」ことを指します。
抽象化能力の高い人間が、自分で抽象度を設定して「わかっていると思い込む」ことは私は「バカの壁」であると思っています。
「抽象度が高い」の真実
前述のように、言葉は現実の表象であり、すでに抽象化されたものです。
「抽象化」とは、具体から必要な情報を取捨選択することです。
「抽象化」とは、「抽象化の技術を持った人間」からすれば、大きな世界が見えているように思っています。
それは間違いです。
実際は「見たいように現実を解釈している」にすぎないのです。
手段と目的が違う人々
営業の例で説明します。
架電のためのトークスクリプトを編集するための会議をしています。
その中で、最初の挨拶の後に「何かお困りのことはございますか?」と言うのか、「弊社では〇〇を紹介しております」と言うのか、白熱した議論がされています。
そんな時、抽象度の高い人はこんなことを言います。
「ちょっと目的が見失っていない?この会議は営業のアポ数を増やすためにどうすればいいか?と言う話でトークスクリプトの編集は本質じゃないよね?」
抽象度を変えることの意義
上記の指摘は正しいです。
この会議の背景には「営業のアポ数を増やす」という問題意識があります。
それらに繋がる課題は、架電のトークスクリプトの問題だけでなく、架電先の選定や電話のタイミングかもしれません。
あるいは、「架電」という手段は重要ではなく、メールでのアポイントが必要かもしれません。
「営業のアポ数が低い」という現実が前提にあることも読み取れますが、それはフィールドセールスの営業担当が少ないだけかもしれません。
そういった様々な選択肢や可能性を提示するために、「抽象度の変更」というのは有効です。
人間は見たいように見て判断する
「会社」という組織では、大雑把に言えば「売上と利益を上げる」という割と絶対的な目的があるので、「売上を上げる」ために「営業のアポ数を高める必要がある」という目的の親子関係があるため、ほとんどの抽象度の高い指摘は大抵は成り立ちます。
しかし、「架電のためのトークスクリプト」を作っている人間にとっては「架電のためのトークスクリプト」を作ることに意義があったのかもしれません。
もしかしたら「家電のための完全なトークスクリプト」を作ること自体に会社を超えた特別な価値があることかもしれません。
これらは「客観的な正しい」ではなく、「主観的にどう思っているか」が重要になります。
彼らに「営業のアポ数を高める」という問題意識があること自体を期待することに一方的な決めつけはないのでしょうか?
これこそが「見たいように現実を解釈している」です。
抽象化は「その人の主観の範囲の限界でしか客観視できない」と私は思っています。
抽象化能力が高い人の弊害
抽象化能力の限界
「抽象化ができる」ということは大きな武器だと思っています。
また、その人の能力の高さにつながる点は否定しません。
しかし、私は「その人の主観の範囲の限界でしか客観視できない」と思っています。
主観の範囲外にあるような価値観や世界で動いている人間に、「抽象化」というのは無力なのです。
抽象度の違いが生み出す「分断」
「問題と課題が違うよ〜」や「手段と目的が入れ替わっているよ〜」という発言をする人が度々います。
これらは抽象度の不一致のパターンを言語化したにすぎません。
実際に「問題を課題として扱っている人」「手段が目的化している人」にとって、それは正しく、大切なのです。
繰り返し言います。
「客観的に正しい」ではなく「主観的にどう思っているか」が重要なのです。
そんな彼らの主観を無視して、自分の主観の限界によって客観視したパターンに当てはめるのは、具体的な人々にとって「決めつけ」であったり、「レッテル貼り」と思えてしまう場合があります。
経験上、抽象度の不一致のパターンをそのまま連語する人は、前提としている問題が移り変わっていることについていけていない人です。
「問題と課題が違うよ〜」や「手段と目的が入れ替わっているよ〜」は前提の分断を色濃く表現するだけになってしまうのです。
視座の暴力
力関係と抽象化
上記の「分断」に「力関係」が伴うと、それは「言葉の暴力」として認識されると思っています。
「あなたは私の主観で定義した期待や視座に合っていません」ということを婉曲に表現し、言い方によっては茶化しているように見えます。
これらは相手のプライドを傷つけ、人格を否定するように取られても仕方ないと考えます。
抽象化とは暴力的なのです。
高い視座からの一方的な暴力
抽象度の低い人にとって、より高い抽象度を捉えることは困難です。
「抽象度の指摘」は、抽象度の低い人にとって、まるで目に見えないところから不意打ちでボディブローを食らったような気分になるのです。
視座の高さはどこから来るのか
「視座の高さ」を持てるのは、ほとんどの場合、その人が優秀だからではありません。
その人の役割やミッションがたまたまその視座であったり、たまたま議論の当事者でなかっただけにすぎないことが多いです。
仮に超頭が良くて抽象度が高く生まれたとしても同様です。
たまたま頭の良い親から遺伝して、頭のいい頭に育っただけで、その人が特別な意味を持って生まれてきたわけではありません。
あるいはその視座を持つだけの経験をしたのかもしれません。
たまたま「その場」で「その状態」でたまたま「視座を高く持っている」だけに過ぎないのです。
視座の暴力をしないために気をつけていること
実は私自身、視座のDV彼氏になりうることを自覚しています。
ここからは私が「視座の暴力」をしないために、また発生させないために気をつけていることを記載しようと思います。
自分の抽象度の高さを客観的に見る
抽象化とは、「見たいように現実を解釈している」にすぎないと述べました。
なので「自分が現実をどのように見ているのか」も客観的に解釈することが可能なはずです。そうしてください。
その場合に使える言葉は「偏見」と「価値観」です。
「私は今こんな偏見を持っているな」
「この人はこういう価値観で話しているな、私はそういう認識を今したな」
ということを認知することが、簡単に自分を客観的に見る超簡単な方法になります。
上記のポイントはどちらも「客観」を表現する言葉ではなく、「主観」を表現する言葉であることです。
どれだけ抽象化ができる人間でも、「見たいように現実を解釈している」という事実からは逃れることはできないと私は思っています。
あくまで自分自身を客観的に表現する方法として、「自分は主観に囚われている」ということをいつも捕捉することが大切になります。
抽象度の表現方法を工夫する
抽象度の高いところからの指摘は暴力にはなりますが、効果的であることを「抽象度を変えることの意義」の章で述べました。
大切なのは「抽象度の違いを指摘する」のではなく、「抽象度が違うことを認識してもらう」です。
ここでは自分の主観的な行動に照準を当てるのではなく、客体として相手のことを考えて表現することが必要になります。
これをするには、相手の言葉を使いながら「さりげなく聞いてみる」ことがいいのではないかと思っています。
例えば以下の感じです。
「どちらもトークスクリプトとしては良さそうですね。ところで私はどちらがアポ数を獲得できそうか、ということも気になったのですが、その観点ではそれぞれどう評価できるでしょうか?」
勘のいい人なら、上記で「ああ、これが目的だったっけ」と自分で気がつきます。
それでもわからない人がいたらこんなアプローチもしてみるといいです。
「今日はこの場でどちらのトークスクリプトを採用するか決めたいと思っています。どちらにするか決めて実際に試してみましょう」
これが使えるかは場合によりますが、いくつかのパターン化の手法を使っています。"ゴールを定義すること"と"試してみようという落とし所"です。
ゴールを定義することで、特定の抽象度に囚われた視点からふっと頭が上がる経験は少なくないと思います。
その上で、"試してみよう"でゴールの重みを軽くすることで、なんとか落とし所に繋げるという手法を私は提案しています。
相手との信頼関係
色々言いましたが、実は視座のDVも通報されない場合があります。
相手と信頼関係がある場合です。
相手との信頼関係がきちんとあり、「自分をメタ認知してくれる」や「壁打ち相手なんだ」という認識をもらっていると、「それって手段と目的入れ替わりだよ〜」って言っても受け入れられます。
視座のDVする人はその辺の距離感掴めていないおじさんが多いのは事実ですが、なんなら相手に対して「私はこういうこと言うよ」と宣言してもいいかもしれません。
なんにせよ相手との信頼関係があれば、言葉の暴力は許されます。
ただ、それを見ている関係のない人は等しく暴力を受けます。
なので、視座の暴力はクローズな場でDVとして行うべきだと私は考えます。
視座の暴力以前の問題
そもそも相手をリスペクトしてたら視座の暴力なんてしません。
おわりに
私はいろんな会議に出ている中で、「視座の暴力」によってチームの信頼関係やプライドをめちゃくちゃに引き裂かれる人々を何度も目撃しています。
そうした人を一人でも救いたいと思って執筆しました。
この文章に対する視座の暴力は、どうかDVでお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
