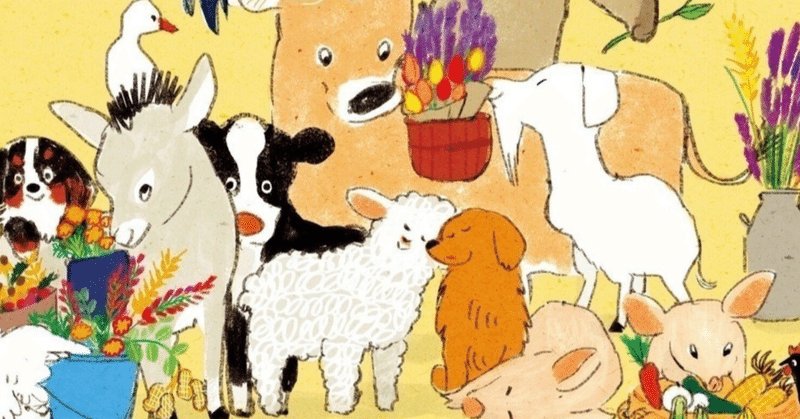
打ち返さないで受容する
何を書こうかと悩むことはあまりない。内側に、何か書いた方がいいことがありそうだと感じた時に書き始めるからだ。
書いてみて、それが思ったよりもささやかであれば下書きを消してしまうこともある。
上手く書けないけど今後発展の可能性を感じたような時は保存しておく。
泡沫の思いを文字にして留めておく価値があるかどうかは、形にしてみるまではよく分からない。
形にした方が良いのか、しないままが良いのか、書きながらなんとなくわかることがある。
眠らせておいて、相応しい重量で描き取れる時にまた引き上げるのも良い。
ーーー
息子の感情が揺れる度、悲しい?お腹減った?寂しかった?眠たい?散歩行こうか?退屈してきた?絵本読む?いろんな言葉を投げかけてみる。
少しづつ選択肢は狭まるようになってきた。
子どもは感情の塊で、未来の計画は持たない。今だけを生きている。感情と反応が一体化していて、だからこそ自分でも感情の理由が整理、自覚されてはいないようだ。反応に猶予がない。
悲しい?寂しい?興奮してる?とか、優しく感情を受け止める声掛けをしていると、彼の心が安定していくのが分かる。当たるかどうかよりも、受容してもらっているというのが伝わるのだ。
大きくなって、自分の気持ちを自分で考えて、親に言葉で伝えられるようになったなら、素晴らしい成長である。
息子の気持ちを受容する。妻の気持ちも受容する。イライラするね、悲しいね、疲れたね、眠たいね。
感情を持つことそのものに善悪はない。それで他者を攻撃する場合は良くない。良くないけど「そう言われて悲しいな、こうしたらいい?」と穏やかに対応する。我慢するのではなくこちらの気持ちも素直に落ち着いて伝えて、受容してもらう。
我々は敵ではなく、皆味方で、同じ側にいるのだ。
ーーー
①これが、すごくイライラする、と伝える。
(自己理解、表現)
②それがイライラするんだね、と受け止めてもらう。
(他者による受容)
③少し落ち着く。
(感情に居場所が生まれ、整理される)
④少し後で、「あなたは、あれが、イライラしたんだよね?」と尋ねられる。
すると、その時にはもう感情そのものが変化している。
感情の表現と受容には上のような効果がある。癇癪とかパニックとかヒステリーのような感情に呑まれた状態から、感情が箱に収められた穏やかな状態へと移してくれる。(逆に、感情が受容されないままだと癇癪やパニック、ヒステリーに向かいやすくなる。)
受容と整理を繰り返すと、「激しい感情もいつかちゃんと治まる」という予測を持って対処出来るようになっていくのではないかな。
愛するというのは、素直な感情をともかくも受け止めて、またこちらも伝えて受け止めてもらうというやり取りのことではないだろうか。
素直であること。そして感情を受け止め、お互いに気持ちよく過ごせるように、楽しく工夫すること。
言葉と感情は、愛をやり取りするために非常に重要な要素である。(当たり前。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
