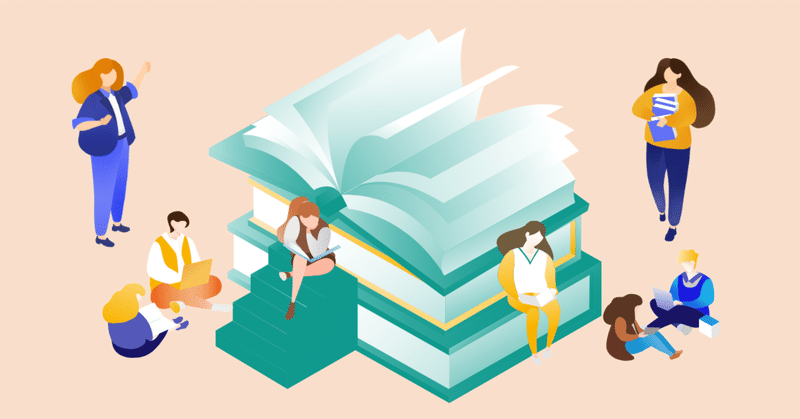
高校生とのワークショップで教えてもらった『人が育つために大事なこと』
こんにちは、かみちゃん@WSD40期生です。
5月の月イチ note更新です。
今回は、先週末に行ってきた高校生のキャリア教育合宿とそこで実施したワークショップのお話をしたいと思います。
ワークショップデザイナーに関する学びに加え、若者のキャリア教育に携わり、人の成長とは何かを改めて知る機会になりました。
加えて自身で企画・運営したワークショップの中で、これまでのところのベストワークになりました。(あくまで今の所のベスト。課題はまだまだ多い。)
キャリア教育合宿の概要
娘が通う高校はとてもキャリア教育に力を入れており、日頃から授業でも折に触れてキャリアを考える機会が作られています。今回はその中の重要イベントの1つである、高校1年生対象のキャリア教育合宿でした。
キャリア教育合宿のテーマ
実際の大人の仕事・会社のリアルな課題に触れ、その課題解決のアイデアを考えることを通して、これからの自己のキャリア形成やキャリア構築につなげる、というようなものです。
どんな形態?
・「実際の大人の仕事・会社のリアルな課題」を提示する保護者1人につき、生徒が20人前後つく。私の他にファシリテーションのサポートで保護者1名、大学生1名がついてくれました。
・4人1組のグループ(クラスとかはごちゃまぜ)になり、課題に取り組む。
・企画書を作り、最後に6分間のプレゼンをする。
・実質、朝から晩までの丸1日でやりました。
ワークショップ概要
自分の仕事に関係していることと、若い方からアイデアをもらいたいと思えるテーマにしました。
テーマ
「新入社員を爆速でデジタル人材にする方法」
でした。

これをテーマに選んだ理由としては、以下の3つです。
・「デジタル人材」について考える事は、日本の生産性の低さや人材不足という社会課題に結びついているため、単に企業の課題とするよりも意義を感じてもらえると考えた。
・実際に、新入社員を多く採用している自社の課題として育成スピードの問題を感じていた。
・「新入社員」は、高校生にとって比較的近い将来の自分なので、自分ごととして考えてもらいやすいのでは?と考えた。
娘からは「地味なテーマだから、選ぶ生徒が少なそうだね。」と言われ、返す言葉がなかったです(笑)。でも、結果的には人材について考えることに興味のある生徒、デジタルに関係する職に就きたいと考える生徒たちが選んでくれたようです。
プログラムと流れ

01:課題を知る
「足場架け」のパートです。
興味をもってくれた生徒がいたことは良かったのですが、とはいえ高校生には少しハードルが高いと思えるテーマでしたので、「足場架け」としてインプットを最初に厚めに行いました。
例えば以下のようなことについて、エビデンスを提示しながら話しました。
・なぜデジタル人材を育てなくてはならないのか?
・それがどう日本の社会や経済との課題に結びついているのか?
・DXとは何か?
・その具体例

当然ずっとこちらの説明だと飽きられると思ったので、途中に「身の回りのDXについて具体例を挙げる」グループワークを入れたりしました。
02:ヒントを得る、方向性を定める
もう一つ、ピンとこないだろうなと思ったのが「育成」についてです。
当然働いたことが無いですから、新入社員ってどんなレベル感なのか?普通の会社ではどんな研修をやっているんだろう?
こういったことなどは最低限インプットしないと感覚がつかみにくいと思いましたので、実際の新入社員の感覚や新卒研修のイメージなどの共有に更に時間を使いました。

その上で、少しドキッとする質問も入れたりして。

03:アイデア・プランを考える
そしていよいよ企画の作成です。
さあ、企画にまとめるぞ、といってもここにもハードルがありそうなので、企画検討についてもいくつかの段階を設けました。
1st step : 企業の求人情報等から、今回「爆速」で育成する対象となる、デジタル人材の職種を調べ、グループで1つに決める。
例:任天堂、ユニクロ、トヨタなど
2nd step : その人材の育成が早くできない理由や課題を上げ、ロジックツリーで、課題分析を行う。
3rd step : 企画書シート的なものにポイントをまとめる。
ここまでの整理をもとに、以下の企画書シートに書いてみる。それをテーブルセッションで共有しFBをもらい、またブラッシュアップ。

Last step : 6分のプレゼンを想定した企画書を作成しまとめる

企画書自体はフリーフォーマットで作ってもらいました。
CanvaやGoogle slide、keynoteを使って、手早く共同作業をする様子には驚かされました。
04:発表する
いよいよ企画書が完成。
夕方2~3時間、次の日の朝の時間を使って書き上げていました。
お見せ出来ないのが残念ですが、課題の背景から自分たちの着眼点、そして育成のスピードを上げる解決策までを網羅し、6分の説明には十分かつコンパクトな内容でどの班も仕上げてました。
そして、プレゼンをしてもらいました。
プレゼンも慣れたもので、台本を事前に書き上げる班もあり、堂々と説明する姿に感心しきりでした。
このグループワークでの共同作業と合意形成、それを企画書にしプレゼンまで難なくこなしてしまうのは、学校の方針と日ごろの取り組みの賜物なのだと思います。
以上で、実質1日半くらいのワークショップとそのファシリテーションが終了。
もちろん途中で集中力が落ちる場面もありましたが、終始真剣に取り組んでいた生徒たち。それに向き合った自分はもう精魂尽き果てるくらいへとへとでした。。。
高校生たちからのアウトプット
外形的なアウトプットの出来の良さ以上に、中身が素晴らしかったのです。
幾つか出てきた視点や解決策を紹介します。
・デジタル人材であっても、その会社・事業の現場に早めに行き学ぶべき。
(例:販売をしている会社ならお店に立つなど)
・責任ある立場の経験を早めに体験できないか?そうすれば格段に責任感や当事者意識が上がるはず。小さい業務であっても責任ある仕事を。
・「最後までやり遂げる力を持つエンジニア」とう応募要件があった。
であれば、複雑な課題の解決に取り組む経験が必要。だから入社前に、地域おこしなどインターンやNPOで経験を積む方が良いか。
などなど、デジタル人材に限らず社会に出て働く際の姿勢や経験して欲しい事の本質的な数々が出てきました。
働いたことないのになんでそんな考えに行き着いたの?というものばかり。
アイデアの例では
・新入社員はそもそも社会人生活に慣れること自体が大変。であればその解消と集中的にスキルを身に着けるために、1か月の寮生活をしたら爆速になるのではないか?
・早くお金を稼げる人材になってもらうなら、研修も大事だけどZ世代ならではの得意分野(SNS、動画など)を生かした仕事を作る。
etc
こちらもハッとさせられる視点ばかりでした。
大事なことは、知識 < ポータブルスキル
具体的なデジタル人材(職種)に必要なスキルの習得方法が具体的に浮かびにくい、という事も影響していると思いますが、高校生たちの多くの視点は「知識の習得自体は難しくない。そういったものは自己学習等で高めて、いかにポータブルスキルといわれるような思考力や発想力、やり抜く力、調整力などを磨くことに時間をかけ更にスピード上げるべきではないか」という
ものでした。
分かってはいたけどやっぱりそうだよなーというのと、短時間でこの着眼点にたどり着いてしまう生徒たちの洞察力・想像力に驚くばかりでした。
月並みですが、日本の未来は明るい!そして、若者のポテンシャルはとてつもなく高い、これをいかに引き出し社会や事業の力にするかが、私たちの大事な役目でありそれをしっかり果たさねければ!と背筋をピンとさせられた機会でした。
最後に、ワークショップデザインの視点でも、ゴールに至るまでに適度な足場架けをしながら徐々に熱中してもらえらるように考えた構成と、当日2回ほど様子を見てアレンジしたファシリテーションにより、事前の想像を超えるアウトプットにたどり着けた事で反省点はあるものの一定の自身になりました。
そういった意味でも貴重な経験をさせてもらいました。
ということで、引き続き熟達した場づくりの専門家(ワークショップデザイナー)になるための旅を続けていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
