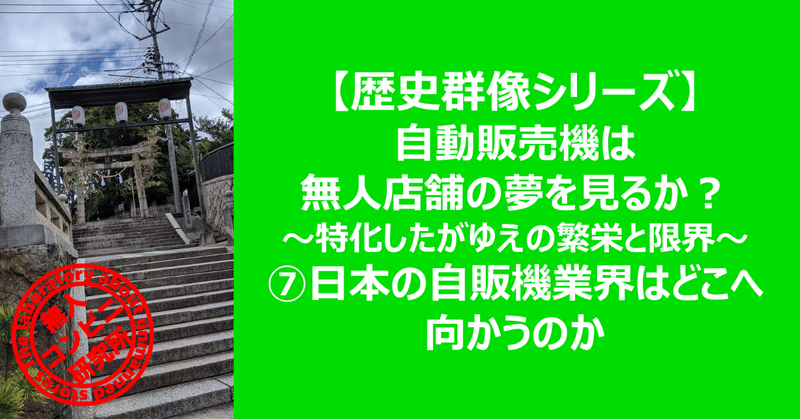
【歴史群像シリーズ】自動販売機は 無人店舗の夢を見るか?~特化したがゆえの繁栄と限界~⑦日本の自販機業界はどこへ向かうのか
サンデンリテールシステムさんがバイアウトされたニュースはこの業界にも少なからぬインパクトをもたらしましたが、ここ数年ずっと新台出荷が右肩下がりのこの業界で、各プレイヤーはどういった戦略を描き、何をしているのか…このタイミングで今回はこの辺りを急遽深堀していこうと思います。
■サンデン・リテールシステムがバイアウト~業界2位の陥落
サンデンホールディングスは冷蔵ショーケースを中核事業とするサンデン・リテールシステムを投資ファンドのインテグラルにバイアウトしました。事業自体はバイアウト後も継続されるとのことですが、これにより過去から自販機事業を継続している企業は事実上富士電機とパナソニックの2つになりました。
これまでにも何度か業界の危機を迎えては乗り越えてきた自販機業界ですが、国内市場は完全な頭打ちで、かつどこも自販機の償却期間を延ばしたことにより新台への交換が激減しているという完全な逆風下の中、業界2位のサンデンさんですら抗えなかった状況であることを露呈しています。
■既に国内から脱出を図っている富士電機
では業界1位の富士電機さんはいったいどうしているのでしょうか?
…実は日本国内から事実上の撤退をしています。国内の工場は中核工場である三重工場以外すべて閉鎖、「国内自販機業界最高の頭脳」と言われた三重の研究所も中核メンバーはすべて中国に移動。三重工場はメンテナンス工場として機能するに留まり、国内における新規事業はほぼ停止している状態だと聞いています。
それを端的に表すのがクボタさんの買収。国内では全く振るわないクボタさんでしたが、実は5年以上前からインドネシアでの自販機事業に力を入れていました。インドネシアは意外と飲料自販機の需要が高くそこに目を付けたクボタさんがが地道に市場を開拓、富士電機さんはアジア地区での自販機販売数増大を目指していたためそのインドネシア事業を買収したようです。
(これによりクボタユーザの中で少なからぬ混乱が起きるのですがそれはまた別の話…)
富士電機さんは伸び盛りの中国市場メイン市場と捉え、中国を足場に東南アジアにも勢力を伸ばしていくことで生き残りを図っていると思われます。
■高機能化する自販機
それでは自販機はこのままなくなってしまうのかと言うと恐らくそうはならないと思います。どこでもすぐに冷たい/温かい飲み物が手に入るという文化は決して廃れることはないでしょう。しかしながら、ネットワーク化に乗り遅れ、機能強化を怠り価格競争のみに邁進してきたツケは新台出荷台数減少と言う形で払わされる形となりました。このままだと供給側の疲弊により業界が衰退してしまう危険性はあります。
その状況下、自販機を使う側(主には自販機オペレータ)は何を思っているのかと言うと、自販機が「単に無人でものを販売できるもの」ではなく「もっといろいろなものが売れて、かついろいろな情報が集められる」ことを希望し始めました。
その1つの答えがブイシンクさんの「スマートベンダー」だと思います。ネットワークと接続しセレクションボタンの編成から料金まで自由に変更可能、サイネージ上には動画広告なども流すことができ、電子マネーはもちろん対応など、今までは難しかったことをクリアすることに成功した自販機だと思います。
ただ、残念なことに扉部分以外は古い自販機のままであること(特別機を除く)、価格が非常に高額であること(300~500万程度)がネックとなり普及が難しい状況ですが、イオンさんなどで半標準機として投入されているので今後に期待だと思います。
■市場は更なる「無人販売だからこそできること」への脱却を希望
しかしながら市場は更なるものを求めます。ブイシンクさんのスマートベンダは旧式自販機から見るとかなり高機能になっているのですが、どうしても今の自販機の枠組みを超えるものにはなりませんでした。よりいろいろなものを、より大量に、そして誰が買ったのかを知りたい、そういう希望が商品を提供する側の製造メーカーを中心に強くなってきました。
これまでは単に「利益率の高い販売ルート」として自販機は認識されてきましたが、市場が飽和状態になり提供台数の多さが正義だった時代が終わったこと、アウトロケ中心からインロケ中心に市場が流れていることなどから、より少ない台数でより高い販売力を維持することが求められるようになります。
こうした考え方の変遷は自販機オペレータよりもむしろ飲料メーカーの動きから読み取れます。コカ・コーラさんの「CokeON」やダイドードリンコさんの「SmileSTAND」などはその典型例ではないでしょうか。ポイントやスタンプによる無料販売をフックにしつつ、そこから吸い上げた個人の購入情報をマーケティングに転用するやり方は一般店舗におけるID/POS分析のそれであり、そうした情報を莫大な投資をしてでも欲しがるメーカーの姿をそのまま映していると思われます。
これまで自販機の普及を強くけん引してきたのはこうした飲料メーカーさんの貸与機であり、これが一大自販機市場を構築してきたことを考えると、次の世代の自販機もまた彼らのよってけん引されることは自明であるように感じます。この流れをいかに握り、コントロールしていくか、これが今後の自販機業界のカギを握るのではないでしょうか。
■業界団体は新しいムーブメントを作ることができるのか?
もはや旧式となった現行自販機はこれ以上伸びないことだけは分かっており、各社とも次を探して暗中模索状態ではあるものの、「どこの自販機を買っても大体メンテナンスは同じ」と言うある意味で自販機利用の敷居を下げ普及に貢献した過去の仕様がある限りなかなか新しいことはできないと思われます。
ここから問われるのは業界団体の筆頭格である「日本自動販売システム機械工業会(JVMA)」の動きだと思われます。そもそも今の自販機の仕様を作ったのはこのJVMAですが、この古く錆びついた仕様をどこまで新しく時代に合ったものに変えられるのかが今後の勝負の分かれ目になる気がします。折しも新仕様がそろそろ出てくるのではないかと言う噂もあるので、まずは動向を注目したいところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
