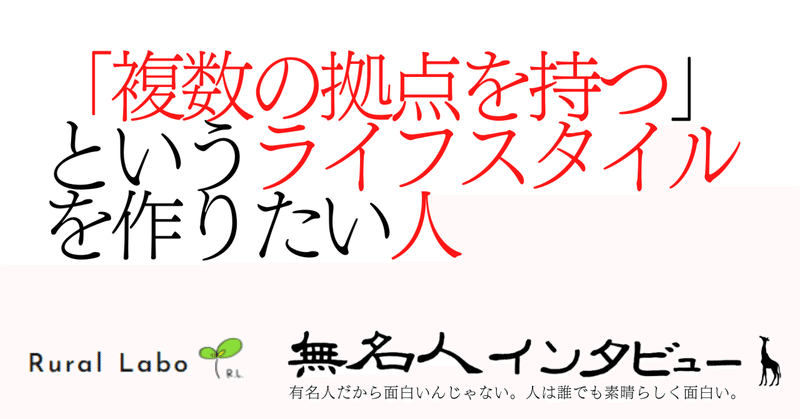
「複数の拠点を持つ」というライフスタイルを作りたい人
いきなり始まったRural Laboさんとのコラボインタビュー!
↓↓↓企画意図↓↓↓
その人の現在過去未来を聞く無名人インタビューは、参加者の「心の現在地の写真」みたいなものです。参加者本人にとっては自分がどんなことを考えているかわかるし、インタビュー記事を読んだ人は参加者の考えや過去がわかる。
これを、ある集団のメンバーにしてみたらどうなるのか?
予測1:お互いのことを知ってコミュニケーションしやすくなる。意見を言いやすくなる。
予測2:話しやすくなった結果、集団作業がしやすくなって成果があがる。
予測3:みんな平和。楽しい。最高!
ということで私qbcが声をかけさせていただいのたは、以前インタビュー受けていただいたメロンソーダさんが所属していたRural Laboさん:全国の地域活性化に関心のある若者が集うコミュニティです。2022/5/5現在295名の方が所属されています。
Rural Laboさんと、Rural Laboさんが関わっている地域の人たち。
地域というひとつの場所を中心した人々のインタビューを集めて、読んでもらって、それは前向きな力を生むのか。見ましょう! 見ていてください。実験です。
とは言え、インタビューひとつひとつはいつもの無名人インタビューですよ。ある集団に所属していたとしても、その人は、その人です。むしろ、その集団に属していない無名人的部分を知りたいと考えているのが無名人インタビュー。
ということで第1回はRural Labo代表の方ということでインタビューを始めたのですが、冒頭からいきなり、Rural Laboだけではない、ご自身の持つ目的から始まりました。お楽しみください!(主催:qbc)
今回ご参加いただいたのは 小菅勇太郎 さんです!
現在:場所にとらわれないライフスタイルを作る人
ナカザワ:今、何をしている人でしょうか?
小菅:ライフスタイルを作っている人、ですね。
ナカザワ:具体的にどういったライフスタイルを作ってらっしゃるんでしょうか?
小菅:自分の作りたいライフスタイルは、行きつけの田舎が複数あるような生き方なんです。
ただ、多拠点とか居場所が複数ある生き方って、1人ではなかなか実現するのが難しいんです。金銭的にも、人間関係的にも。
例えば、地方に1人で行っても孤独なだけで、結局現地に知り合いだったり、仲がいい人だったり、価値観の合う人がいるっていうことで初めて、居場所として成り立つと考えています。今、そのために、事業としてそういうコミュニティを作っています。
Rural Laboとは別なんですけど、Rural Laboも結局居場所を作っているもので、そういう行きつけの田舎とか、場所にとらわれない生き方の第一歩ですね。
ナカザワ:なるほど。
小菅:前提として、そもそも1つの地域で暮らさなくてはいけないとか、都市にいないといけないっていうような固定概念を壊したいなと思っています。別に全員がそれをする必要はないんですけど、地方や田舎と関わるっていうことが、選択肢として当たり前に存在する社会にしたいなっていうふうに思っていて。
まず、少しでもそういった地域に関心のある人たちが、思ってるだけで終わらないように、しっかり仲間ができる環境を作っていく。人をつなげることによって地域へ入っていけるように誘導してっていく。そういったことで、地方と関わることを、より身近でハードルが低いものにしていくっていうことをやってます。
ナカザワ:主に、今地方にいない人がターゲットになっていて、そういった人に対してのライフスタイル提案っていうようなイメージなんですかね?
小菅:そうですね。
ナカザワ:ちなみに、今、小菅さん自身は、何拠点での生活をされてるんでしょうか。
小菅:自分は、現状まだ2拠点で。普段は長野県の辰野町にいて、月に1-2回東京の実家へ戻ってるっていうような感じで。今年中には3拠点目を持ちたいなと思っています。
いろんな地域にRural Laboのメンバーだったり、友達がいたりして、そういう地域に行くことも多いので、実際は、月の半分が長野で、4分の1が東京で、4分の1が別の地域みたいな感じになっています。
ナカザワ:多拠点で生きられる社会を作るために、地方に入っていきやすくする。具体的にはどんなことをされているんでしょうか?
小菅:事業の方で言うと、まだ立ち上げ中ではあるんですけど。プロットしているのが、1人で地域に行くのは結構孤独なので、1つ行きつけの田舎があるようなライフスタイルを送りたい、という同じ価値観に集まる人たちで先に集まっておいて、コミュニティを作る。
例えば、共同で古民家を買い上げて一緒に再生していくことだったり、共同で畑を運営したりとか。みんなでお金を出し合って、同じ場所を持って運営していくようなコミュニティを作ろうとしています。
ナカザワ:なるほど。
小菅:行きつけの田舎っていうコンセプトが出てきたきっかけが、僕がマレーシアに住んでたときの経験なんですけど。そこの暮らしがほんとに自分にとって幸せで。
そこでは、毎週金曜日の夜に、ビーチにある公園兼バーみたいなところに、学校中の友達とその家族が集まって、遊んでから一緒にご飯食べる、みたいな習慣があって。そういう思いっきり遊べる環境とか、そこに自分の一緒にいたい人たちがいるっていうコミュニティが、定期的にあるっていうことで、安心感だったり、自分を解放できる楽しさだったりを感じられる。
でも、東京へ帰ってきたときに、それがなくなってしまった、と感じたのがきっかけです。
ナカザワ:うんうん。
小菅:東京にいる人たちの場合、どうしたらそういうサードプレイス的な場所ができるか考えていたときに、やっぱり、定期的に自然の中に行くのは必要だなっていうところ、で場所としては地方になりました。
月に1回でも2カ月に1回でも、そういう行きつけの田舎みたいな場所へ行ったら、自分の顔なじみで、価値観の合う人たちがそこにいて、一緒に楽しくリフレッシュできるみたいな、そういうものを作りたくて。
行きつけの飲み屋みたいな感覚で地方へ行って、顔なじみのメンバーがいる、という状況を作りたいです。
ナカザワ:なるほど。
小菅:最近「なんか似てるんじゃない?」って言われたのはスナックですね。
1つの場所があって、その場所の中でやっぱりいろんな人が混ざり合って、コミュニティを形成していって。そこが1つ、自分のサードプレイス的な場所になっていくみたいなイメージです。だから、場所を作るっていうよりは地方が集合場所になっているみたいなイメージですかね。
ナカザワ:集合場所となった地域で、さらにそこから地元の人だったり、他の人とのつながりが広がっていくことはありますか?
小菅:多いですね。
居場所を作るうえで、1つのコミュニティから人を連れてきてというだけだと、居場所にはなるんですけど限定的だなって思っていて。
いろんなコミュニティから人が1つの場所に集まって、混ざって。その場所でつながった人たちと、新しいちょっと緩くて広いコミュニティが次第に形成されていったときに、そこがもっと場所として機能していくんじゃないかなってふうに考えています。
ナカザワ:なるほど。
小菅:例えば、辰野町だったら、Rural Laboの地域活性化に関心のある若い人がいるところに、友達の起業家が来たり、大人の経営者が来たり、といったことがあって。さらに地域の人たちとも交流ができて、一緒に鍋つついたり。
そういう、違う世代だったり、違う価値観を持ってる人でも、何かしらの共通の価値観で結びついて居場所になっていくっていう環境を作ろうとしてます。
ナカザワ:今おっしゃったような、地域の中でのもう1歩先の繋がりっていうのは、自然発生的につながっていけるんですか? それとも、ある程度の声かけたりとかしてるんですか?
小菅:どっちもありますね。自分たちが若い人を連れてきてるとか、地域活性化に取り組んでいるっていうので、興味を持って「ちょっと応援するよ」と話しかけてきてくださる方もいますし。
逆に、やっぱり僕たちが来てる側なんで、町の中で活発な人とかに、自分たちから挨拶に行ったり話しかけに行ったりしたときに、ぜひ今度一緒にご飯食べましょうとか、そうやってつながりができていくこともあります。
ナカザワ:基本的な質問なんですけど、小菅さんの住民票って今東京にあるってことですか?
小菅:そうです。今はまだ東京にあるんですけど、5月中には移す予定です。
ナカザワ:拠点が複数あるときのハードルって、その辺もあるんでしょうか。
小菅:ありますね。それこそ、田舎はゴミを出すのが結構厳しかったりして。住民票ないとゴミ袋が買えなかったりとか。
あと、お子さんがいる家庭だと、保育園に入れるのが難しいとか。政策提言的な動きも、実はちょっと絡んでるんですけど、そういうこともやっています。
ナカザワ:当然といえば当然ですが、住民票がないと選挙も行けないですし、いろいろそういった問題もありそうな感じですね。
小菅:そうなんです。
ナカザワ:多拠点で生きたいとか、行きつけの田舎が欲しいっていう人は、田舎でどんな暮らしをしたいと思っている方が多いんでしょうか?
小菅:多拠点とか複数の田舎を行き来したい人で言うと、やっぱり一番多いのは、単純に、ずっと都市にいると、なんだか疲れてしまったり、考え方が凝り固まってしまったりということがあるので、定期的に、地方とか自然のあるところでリフレッシュしたい、というケース。ワーケーションのニーズと結構似ていますね。
移住者だと農業をやりたい方もいるんですけど、リフレッシュを求めている人が多いですね。
ナカザワ:小菅さん自身も、最初はどちらかというとリフレッシュだったり、自然の中で暮らすことが目的だったんですか?
ナカザワ:自分も東京メインで、定期的に長野へリフレッシュに行くぐらいを想定してたんですけど、気づいたら長野メインになってました。(笑)
ナカザワ:今、長野の方が多いんですもんね。
小菅:そうですね。
ナカザワ:長野でもお仕事をしつつ、必要に応じて東京に行って、という感じなんでしょうか?
小菅:そうですね。
2拠点とか多拠点の良さって、やっぱり自分の所属してるコミュニティとか居場所が複数あるっていうところです。
交互に行き来したり、移動し続けることによって、自分の思考も凝り固まらないで、常に新しい刺激を得られる。すごく楽しいし、柔軟になる。
人と会う機会だったり、イベントだったりはどうしても東京の方が多いので、自分の場合はそっちも捨てがたくて、そういうイベントがあるたびとか、どうしても会いたい人がいるときに、それに合わせて東京へ行ってるっていう感じです。
ナカザワ:長野県と東京都って、行き来はどうですか?
小菅:辰野町って、新幹線は通ってなくて。高速バス1本で3時間でまあ行けるっていう感じで。
特急になると、もうちょっと楽なんですけど。ちょっと高いんで、たまに乗るぐらいですね。
ナカザワ:ちなみに、なぜ今、辰野町を選んで住んでらっしゃるんですか?
小菅:最初は本当に、ただただ人のご縁で繋がったっていう感じでした。
コミュニティ立ち上げ時に関わってくださったメンバーの1人が、辰野町の地域おこし協力隊の方と、高校の同窓生だったんですね。その辰野町の地域おこし協力隊の方が関係人口づくりのプロジェクトをやってたときに、東京の若い人とつながりたいって言っていて、その時につながったのがきっかけです。
ナカザワ:なるほど。
小菅:最初、3カ月間ぐらいプロジェクトを一緒にやることになったんですけど、実際にそこで辰野へ来て、3カ月間関わると、辰野でやりたいことがいろいろできてきたんです。
その後東京に戻ると本当に無力だなって感じて、もっとしっかりまちづくりに関わりたいと思ったのが1つと、単純に、地域のおじいちゃんたちが、めちゃくちゃカッコ良かったんです。
80歳を超えているような人たちが、体を張って最前線で里山を守るための活動をしていましたし、このままだと地域を次の世代に繋げられないとみんなが自覚していて、新しくFacebookの使い方を勉強して、Facebookで発信をしてるおじいちゃんがいたりとか。シェア畑を組織してるおじいちゃんがいたりとか、新しいことを頑張って取り入れようとしていたり。
その流れで、僕たちみたいな急に外から来た若者にも本当に真摯に向き合ってくれて。わからないところは、見栄を張らずに、素直に「わからないから教えてくれ」みたいな、全てさらけ出して、それぐらい本気で地域を守りたいんだなって感じました。その姿勢がすごくカッコ良くて、この地域で自分もまちづくりに関わりたいなって思うようになりました。
ナカザワ:辰野町へ行くきっかけになったプロジェクトっていうのは、今もやってらっしゃるRural Laboのことですか?
小菅:Rural Laboで、当時、長野県の関係人口創出みたいなことに関わらせてもらっていて、その当時Rural Laboはまだ10数人とかだったんですよね。
ナカザワ:今、人数はかなり増えてらっしゃいますよね。
小菅:長野でプロジェクトを持ったのがきっかけで人が集まるようになって、成長期に入ったっていう感じです。
ナカザワ:Rural Laboの活動自体は、今、立ち上げからどのくらい経っているんですか?
小菅:あと2カ月ぐらいで2年になります。
ナカザワ:そしたら、すごい急成長。
小菅:わかんないです。どこと比べるべきなのか、わからないので。
ナカザワ:長野の関係人口創出のプロジェクト自体はいつ頃のことですか?
小菅:それが、2020年の9月から12月とかです。
ナカザワ:めっちゃコロナの時期ですね。
小菅:そうなんですよ。もう大変でした。
ナカザワ:おそらくどの自治体も、そのころ一番てんやわんやだったんじゃないかと思います。あ、2020年9月だとちょっと落ち着いてたぐらいかな。
小菅:そうなんですよ。ちょうどその3ヶ月が微妙に落ち着いていて。12月以降、また緊急事態宣言が出ちゃって関われなくなりました。
ナカザワ:でも、そこがきっかけで、そして今に至るんですね。
Rural Laboを始める前から2拠点生活されてたのかと思ったけど、そういうわけではないんですね。
小菅:なんなら、自分がこの2拠点が理想だなっていうふうに気づいたのも、長野と関わるようになってからですね。
自分は起業に関心があったので、こういうライフスタイルを提供したいなって思い始めたときに、最初は、それこそADDressさんみたいなサービスを作ろうとしてたんですよ。
※ADDressは、日本各地の空き家を活用した、全国どこでも住み放題のサブスクサービス。
ナカザワ:プラットフォーム系の事業をやろうと思ってたってことですね?
小菅:そうです。ただその事業は全然詰まりきらなくて。
それで、自分を振り返ったときに、そもそも当時、自分が事業をつくるためとかインターンとかで、東京でひたすら朝から晩までパソコンと向き合う生活をしてて。自分が理想の生き方を全然できてないのに、人に理想の生き方を届けられるわけがないなと思って。
漠然と、2拠点生活とかって大人になってからするものだと思っていて、そもそも、大学在学中でもできるっていう認識がなかったんですけど。
ナカザワ:はいはい。
小菅:よく考えてみたら、特にできない理由がなくて。お金も、やっぱり地方ってそんなにめっちゃかかるわけではないんで。
そしたら、やっぱりまず自分がやらなきゃと。いつか、って言ってても、ずっと自分の理想の生き方はできなさそうだなと思って。逆に、理想の生き方をできるとしたら、大学生とか、もうそういうの関係なく、今から毎日理想の生き方を生きていないといけないんだろうなと。それで、2拠点してみるか、と思い立ちました。
ちょうどRural Laboで辰野と関わって、ちょっと距離が空いてしまってた時期で、辰野の人たちから、半分冗談半分本気で「そろそろ古民家借りないの?」みたいに外堀を埋められてて。冗談として受け流してたんですけど、自分と向き合ったときに、もしかしたらありなのかもしれない、と。
過去:日本は刺激が足りなかった
ナカザワ:ここから過去の話というか、今までのお話をお聞きしていこうと思います。
多拠点で生きられる社会って、あんまり普通の人は思いつかないかなと思ったんですけど、ご自身のどういった経験からそういう考え方になったと思いますか?
小菅:自分の親が転勤族で、生後半年のころから数年おきに国内外ずっと転々としていたので、そもそも生きる場所が1つに固定されるっていう感覚が自分にはなかったんですよね。その上で、海外だと周りに欧米系の家族もいたんですが、基本的に日本よりも時間がゆっくり流れていて。そういう経験から、いろんなライフスタイルを見ていましたし、やっぱり自分の家族も住む場所によって生き方とかQOLが変わっていることを実感していたんです。
ナカザワ:なるほど。
小菅:特にマレーシアにいたときは、すごく良かったんですよね。本当に、自分の家族とか友人とか、自分が一緒にいたい人たちが、どう時間やお金を使いたいか、どこの場所にいたいかっていうのを中心に生活が成り立っていたんだなって感じて。
その後、東京へ戻ってきたときに、急に家族内のコミュニケーションも全然なくなったんです。みんな仕事だったり、塾だったりで忙しくなったんですよ。
でも、結局それって自分で選択をしてるようで、実は社会の当たり前とされる生き方の枠にはまってた部分もあるなって感じたんですよね。
それがちょっと不自由に感じて。もっと自由に生きられないのかなって考えるようになったっていうのが、原体験としてあります。
ナカザワ:マレーシアから日本に戻ってきたのは、何歳ぐらいのときの話ですか?
小菅:マレーシアは、小5から中2です。
ナカザワ:なるほど。中3とかから日本に戻ってくると受験ですね。
小菅:そうなんですよ。いきなり受験で。
ナカザワ:中3でマレーシアから日本に来て以降は、基本的に日本に住まれていたんですか?
小菅:東京です。
ナカザワ:ご実家が東京でしたよね。実家は、ふるさとっていうより、きっと、ご両親だったり、家族が東京に住んでる場所っていう意味ですよね。
小菅:そうです。僕と、あと妹が2人いるんですけど、教育環境で東京を選んでるっていう感じなので、妹が大学へ行ったら、たぶん実家も東京からなくなる。
ナカザワ:東京って、世界の中でも有数の、かなりせかせかしてる街ですよね。
そもそも急に中学校3年生で日本に戻って来て、どういう経験を日本で積まれたんでしょうか。
小菅:中学生で戻ってきて最初に感じたのは、学校がつまらないなっていうことでした(笑)
授業が本当に暗記メインで、そのまま受験勉強に突入して。結構受験を頑張ったのでそれはそれで楽しかったですけどね。
僕、環境はひたすら変わり続けてたので、日本の中学のときもあまり疑問を抱かずに順応してました。ただ、やっぱり日本と海外は違うなと思いながら過ごしてて。
ナカザワ:きっと他の人よりも環境が変わることに対して抵抗がないんですね。
小菅:本当にないですね。ひどいときは1年とかで引っ越ししてたんで。なんなら、中学も転入して半年で学級委員やってました。
ナカザワ:自分で何かを選ぶっていうことをしなくても、かなりいろんな経験をされてきたのかなと思ったんですけど。それに対して、ご自身で良かったとか悪かったとか、思うところはありますか?
小菅:自分としては、いろんなところを転々としながら育ったのは、めちゃくちゃありがたかったなっていうふうに思っています。
環境と自分の性格、どっちが先なのかわかんないんですが、自分は性格的に、すごく好奇心が旺盛で。やっぱり新しい世界を知るとか、新しいことを学んで、今まで見えてなかった景色が見えるようになるっていうところに、すごく快感を覚える部分があるんですよね。
なので、最後のマレーシアに関しては、行く前がもう中学受験の時期で、自分は日本で勉強していたので、父親と一緒にマレーシアへ行くか、父親が単身赴任でみんな日本に残るかみたいな選択肢はあったんです。やっぱり自分的には、もっと知らない世界を見たいなって思って「マレーシア行きたい」っていうふうに言ってついていったんです。本当に、その環境に感謝しています。
ナカザワ:なるほど。
小菅:でも、高1の終わりまでは、本当にレールの上を走っていて、親の言うことは全部聞く、いい子だったんですよ。
なので、受験勉強も、高校までは親に言われた通りに勉強して、それなりにいいところへ入ってみたいな感じでした。
たまたま、高1のときにその高校で、「日本中国ティーンエイジ・アンバサダー」っていう。高校生が、日本の大使の活動をして中国に行く、交換留学のようなプログラムがあって、それに参加したんです。
3校くらいで合同だったんですけど、他の参加者の高校生たちはほんとに学校外でいろいろ活動をしている人たちでした。それこそ起業してたり、社会活動やってたりとか。その人たちに出会って、初めて学校外でそういう活動を自分でやるっていう選択肢があるんだって知って、そこから、結構自由に動けるようになったと思います。
ナカザワ:そういうふうに自分もなりたいと思ったんでしょうか?
小菅:なりたいとも思ったし、たぶん、自分の好奇心が学校だけだと満たされていなかったんですよね。もっといろいろな景色を見たいなっていうのはずっと思ってたんで、高1までは、その選択肢が自分の中にはなかったんですよね。
ナカザワ:高1の終わりで、そういった出会いがあって以降、行動はどのように変わったんですか?
小菅:実は、高1の間いい子にしてたとは言いつつも、結構自分にしてはレベルの高い高校にギリギリで滑り込んじゃったので、ずっと成績最下位で。
部活もサッカーをやってたんですけど、引っ越ししすぎてて、日本でずっとサッカーやってた人たちに、全然敵わなくて、もうボロボロで。勉強もスポーツもできない人みたいになってたんですよ(笑)
外の世界を知ったときに、そういうところで勝負したいなっていうのが、やっぱりあって、高1の終わりに、まずサッカー部をやめました。
あと、本当に高校生っぽく、友達と毎日LINEを深夜までしたりとかしてたんですけど、そういうのもなくして、勉強時間を増やして、塾へ通い始めて。
あと、自分のfacebookとかtwitterとかでイベントを探して、いろいろ参加しました。模擬起業をしたりとか。空き家再生のプロジェクトに関わったりとか。
少しずつ、そういう活動を始めた時期です。
ナカザワ:もともと地域活性だったりとか、住む場所についての関心が高かったんでしょうか?
小菅:まちづくりに関心はありました。住んでいる町によって生き方が違ったなっていうところで。アラブ首長国連邦にも住んでいたんですけど、そこはちょうど街が急成長してたんです。そもそも、日本にいると、まちって最初からあるものだっていう認識だったんですけど、ドバイに住んだ時、まちって作られてるんだって知って、結構興味を持ちました。
ナカザワ:建物がリアルにどんどんできていくってことでしか?
小菅:本当にどんどん街並みが変わってましたね。
ただ、高2になった段階とかでは、まだそんなに興味分野が定まってなかったので、模擬国会みたいな政治系へ顔を出したり、プログラミングを勉強したり、音楽ライブを企画して経営してみたりとか。すごく幅広く手を出してました。
ナカザワ:大学は、何年生のときに休学されたんですか?
小菅:1年間通って、2年に進級した瞬間に休学しました。この4月から休学2年目です。なので、同年代は今、3年生の代です。
ナカザワ:大学生になったときに、やっぱりまちづくりをやりたいとなったんですか?
小菅:そうですね。僕は大学がAO入試だったので、その段階で、自分は何をやりたいんだろうみたいな、すごく考えさせられてたんですけど。
高2で、めちゃくちゃ幅広く手を出して。その中でやってるうちに、これは自分に向いてないなとか、これはあんまり興味ないな、みたいなことが、だんだん分かってきたんですよね。高3のときには、やっぱりまちづくりがやりたい、というところに落ち着いてました。ただ、当時は都市計画とかもかじってたりはしてたんですけど。
ナカザワ:違う種類の町づくりですね。ハード面の都市計画と、ソフト面の町づくり。
小菅:そうですね。当時は、まだどっちも興味があって。しっかり地方って目が向いたのは、やっぱり大学に入ってからですね。
本当は、大学へ入ったらすぐ海外へ行こうと思ってたんですけど。留学とか、単純に自分で例えば世界一周とか行きたい国に行くとか。
高校3年間と中学の1年間は日本にいたので、自分としてはちょっと刺激が足りなくて。やっぱり、知らない景色をもっと見たいなっていうのがあって。
ただ、コロナで行けず。代わりに1年間で、日本を18地域ぐらい回ったんですよ。大学もオンラインで暇だったんで。
ナカザワ:なるほど。
小菅:ちょうど入学式もコロナでなくなって、ちょうど、コロナの始まりのときですね。
やっぱり日本を回っていたら、日本の田舎いいなっていう思いにいたって、地方創生っていう分野へ入っていったって感じですね。
ナカザワ:そのときは、どんなところを見て回ったんですか?
小菅:ゲストハウスへ行って、そこの人たちと話したり、復興ツアーみたいなのに参加したりしました。災害復興ボランティアにも参加して。
あとは、大学に入って2ヶ月でRural Laboを立ち上げたとき、やっぱりまちづくりに漠然と興味はあったんですけどまだ定まっていなかったので、経営の知識をつけたいなって思って、大学生社長のもとで、最初はインターンとして会社に入ったんですよ。そこの会社が、都市と地方をつなぐっていうのをコンセプトしてた会社で、そこで出張として地方に行って、特産品を調べてくることもありました。
ナカザワ:Rural Laboの構想は、高校3年生でまちづくりに興味を持つ中でやろうと思ったんですか?
小菅:いや、高校のときは全然考えてなくて。そもそもコミュニティとか、あんまり考えがなかったんですけど。高校のときから、そういう同じ価値観の同年代の人とつながりが全然ないと漠然と思っていて。
大学に入ってすぐにインターンで入った学生社長の会社で、社長さんに「コミュニティ的なものがあったら面白いよね」みたいにポロって言われて、それだ! ってなった感じです。
ナカザワ:なるほど。
小菅:最初立ち上げたときは、本当にそんなに長く続くとも思ってなかったんですよ。やっぱり転勤が多かったんで、長く続けた経験が何もなかった。
なので、今回もやってみて、でもどうせ数カ月で終わりだろうなと思っていたら、なんだかんだ続いています。もうすぐ2年っていうのは、自分が一番びっくりしてます。
未来:地域を盛り上げることはゴールではない
ナカザワ:将来の話をしたいと思います。
こんなに続くと思わなかったとおっしゃっていたんですが、例えば5年後10年後、叶えたいビジョンはどのようなものでしょうか?
小菅:10年後は先すぎてわからないですけど、5年後で言うと、1つの地域でずっと生きないといけないっていう固定概念は、もうなくなっている状態を作りたいなと思っています。
生きる場所は選べるものなんだっていうのが当たり前であって、しかも、それも1つを選ぶ必要もなくて、2つでも3つでも自分が好きな地域を選んで、行き来しながらっていうのが普通になる。誰かがどう生きようって考えたときに、パッと選択肢に上がってくる社会を作りたくて。
ナカザワ:うんうん。
小菅:実際にそれをやっていく際に、一緒にやる仲間が集まる環境を、自分が事業として作って行きたいと思っています。それが、今、長野で自分が作っている事業もそうですし、Rural Laboを通しても作っていく。
例えば、大学卒業して就職して東京、みたいなシンプルな当たり前の世界じゃなくて、そもそも仕事を東京で得るか、地方で得るかみたいな選択肢があったり。
東京で仕事するにしてもどこに住むかっていう選択肢とか、あるいは仕事を2つ持つことも、たぶん今後は増えていく。そういう、生き方がもっと自由になっていく社会を作りたいなって思ってます。
ナカザワ:現状の社会は、おっしゃっていただいたいたところまではいっていない状況かなと思います。ご自身では、どういった課題がそれを阻んでると思いますか?
小菅:一番大きいのは、マインドセットというか、文化的なところだと思っています。「今までの当たり前」っていうのがすごく強く残っている。最近少しずつ、そういう当たり前じゃない生き方っていうのが増えてきてはいるんですけど。やっぱりそこがもうちょっと増えていって、あの人もやってるし、この人もやってるみたいな状況にならないと、当たり前の状況にはならないなと思っています。
そこは根気強く、そういう生き方をしたいなってちょっとでも思ってる人から順番に実現できる環境を作っていくっていうのが必要だと思っています。そうやって個人だったり民間が動いていく中で、最後は法律面とか国の制度的なところも動いていく必要があるなっていうのもありますね。
ナカザワ:さっきお聞きした住民票の話だったりだとか。教育とか福祉関係が一番大きいですかね。
小菅:そうですね。教育・医療と、あと税制ですね。
ナカザワ:それを変えようとすると、国の方の仕組みを変えないといけないので、なかなかすぐは変えられないかもしれないですね。
小菅:今は国の方でも提唱している人が出始めていて、動き始めているように感じますね。
総務省と、観光庁も今動いていて、観光省が今メインに置いてるプロジェクトが「第2のふるさと創りプロジェクト」っていうので。旅と暮らしを融合させる視点、観光の方面からも提唱されています。
ナカザワ:確かに、コロナの影響でワーケーションとか、2拠点まで行かなくても普通に田舎で暮らして、リモートで仕事をするライフスタイルもアリだよねっていう空気にはなってきましたね。
小菅:自分としては、めちゃくちゃ不謹慎ですけど、コロナは、自分の理想としている社会の到来を5年ぐらい早めた感覚です。
そういう意味では、自分が関わっているところでは、5年後、長野だけじゃなくて全国にそういうコミュニティとか場所を作りたいと思っていますし、海外にも行きたい。世界的に生き方がもっと自由になって、流動性が高まっていったらいいなって考えてます。
ナカザワ:うんうん。
小菅:あと、今日はずっと動く側、都市側の人間の話をメインでしてるんですけど、そういう生き方が当たり前になった先で、地方の持続可能性みたいなところにもつながっていくと考えています。
地方が人口の取り合いをしてても、先がないとはずっと言われてますけど、それに対して、そういう2拠点というか多拠点的な生活、住んではいないけど、同じように地域に対して愛着を持っていて、毎月とか2カ月に1回とか、そういう定期的に訪れて地域と関わる人たちの人口が増えていくと、地域の担い手不足だったり、経済だったりっていう部分も改善されていくんじゃないかなって思うので、そういう社会にはしていきたいです。
ナカザワ:地域の活性化というと、小菅さん自身は、動くタイプの人ですよね。動いてきた結果、そこに来た人、まちづくりでは「よそ者」とか言うと思いますけど。そういった立場の方が入ることによって町が変わっていくということは、実感されることはありますか?
小菅:まちづくりにおいて最近言われているんですが、旅人が風の人で、地域の人が土の人だとしたら、関係人口的な人が水の人だっていう考え方があるんです。
自分は、その水に当たるなっていうふうに思っていて。
自分が辰野町でどういう役割を担っているかっていうと、地域に関わりたいっていう外の人たちと、地域の中をつなげるパイプ役になっている。
その結果、人の流動性が上がってきたりとか、今まで辰野にはあまり来ていなかった若い人が、最近だと毎月10人とか20人とか来るようになったみたいな、そういう変化は作れているなと思っています。
ナカザワ:なるほど。
小菅:今はまだ、ちょっと活気付いてきたなとか、若い人を見るようになったなっていうぐらいの心理的な変化しか与えられていないんですが、この先では、それこそ今の時期とかだとお祭りの人手不足とか継承者不足みたいなところに、若い人が一緒に関わっていく。夏にかけて里山の保全とかで、本当に肉体的な労働なんですけど、人が足りないというところを支えるとか、少しずつ助け合える関係性が作れていったら理想的だなと思ってます。
ナカザワ:水の人側も心地よい暮らしをしつつ、土の人、地元の人側も地域で暮らす人手が増える。お互いのメリットを感じ合える関係性でしょうか。
小菅:そうですね。
観光客ってやっぱり一時的に地域に関わるだけなんですけど。水の人、関係人口とか2拠点的な暮らしをする人って、継続的に地域と関わるので、一部その地域に対して責任を持つ。きっと愛着の裏返しなんですけど、責任も担って、その地域を守る側にも関わっていけるようになる関係性が、一番ベストだなっていうふうに思っています。
ナカザワ:小菅さん自身のビジョンは、最終的にはライフスタイルを自由に選ぶ人が増える社会ですよね。そこから、一見ちょっと関係ない印象も受ける地方活性化に実はつながって行ったという感じでしょうか。
小菅:そうですね。最初は、自分が2拠点先で地方に行くときに、前提として、その地域の人たちが幸せじゃないと自分も幸せにならないなっていうところからはじまったんです。
やっぱり自分が関わっている、暮らしてる地域が暮らしやすい地域であって、地域の人たちもみんな幸せにしそうにしていて、そういう地域の間で、2拠点生活をするっていうのが理想だと思いました。
その上で、自分たちが関わっている地域において、担う役割ってなんだろうとか、どうしたらその地域がより豊かになっていくのかな、っていうふうに考えるようになった。
なので、理想のライフスタイルを作るっていうところの条件の1つに、その地域が豊かになっていくっていうのが、やっぱり必要なのかなっていう感じです。結構、エゴですけどね。
ナカザワ:お互いにメリットがないと、絶対に続かないですよね。見落とせない視点だと思います。
小菅:Rural Laboを立ち上げた当初は、自分でも地域活性化っていうのは地域のためにっていう感じで捉えてたんですけど。やっぱり途中で行き詰まった。
どうしてこんなに自分はやってるんだっけ、みたいなところがわからなくなって。そこで自分と向き合っていたら、やっぱり自分は地域を盛り上げたいっていうよりも、自分が生きる環境を豊かにしたいし、そういう生き方が作りたいなっていう、ライフスタイルの方だったんだって気づくことがあって。
これが結構、今のRural Laboのバリューみたいなところにもつながってます。
ナカザワ:暮らしてる人がハッピーな地域じゃないと住みたいと思わないっていうのは、本当にその通りですね。その理論で行くと、地域の活性化っていう概念がいらなくなるのが一番良い状態なのかもしれないですね。
小菅:そうですね。Rural Laboも分かりやすいので地域活性化コミュニティって名乗ってるんですけど、あんまり地域活性が目的ではないんです。
Rural Laboでは、地域活性化っていうのはあくまでもそこに関わっている人たちが、自分たちの自己実現だったり、生きたい生き方を送っているところに、周りの人たちを巻き込んでいった結果として、地域がより幸せとか豊かになっていくと、結果として地域が活性化されるっていうか、その結果の状態だよねっていうことは、ずっと言っていて。地域活性化っていう言葉が、ちょっといびつな部分はあると思います。
ナカザワ:「地域の活性化」という活動は終わると思いますか?
小菅:概念自体は残りそうですけど。地域活性っていう言葉通りの地域活性をしようとしている地域とかは、あんまりうまくいってない印象があって。国から見て、地域をどう活性化させるかみたいなところに予算をつけて、お金を入れてみたいな地域活性化をしていても、結局、やっぱり持続可能になってないところが多くて。
逆に、持続的に人が流れてきてる地域とかは、やっぱり1人1人が自分にとっての豊かな暮らしという問いを立てて、地域と付き合っている場所なんじゃないかなっていうのは感じています。
ナカザワ:最後に、何か言い残し、伝え残しはありますでしょうか?
小菅:たぶん、ないと思います。自分の中でも思考の整理ができました。
ナカザワ:ありがとうございました。
小菅:ありがとうございます。
アンケート回答にご協力ください!
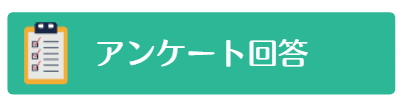
Rural Laboさんの情報はこちらでご確認ください!
あとがき
Rural Laboさんへのインタビュー企画初回として、代表の小菅さんのお話を伺いました。地方創生に関わる団体の代表者、肩書きで言えばそう表現されるかもしれませんが、本人の目には、「生きる場所を選ぶライフスタイルを作っていく」その1点が見えていて、今進めている事業もその手段のひとつとして機能しているものです。この辺りの、何が本質か考え抜く力が、いろんな社会を見て過ごしてきた小菅さん底力の一つなのかもしれません。
「まちづくり」「地方創生」というものは、きれいな言葉で、前向きな意味でずっと使われていますが、なかなか誰が望む地方創生なのか、という視点の話はされにくいものです。改めて考えると、わかっていると思ってわかろうとしていなかったのではないかと、そういう気持ちにもなりました。個人的にはエゴと言い切った小菅さんの言葉にどこかホッとしました。
変な話、人口がどんどん減っていく中で、本当に全ての地方が機能を維持し続けることが望ましいのでしょうか? 誰の目から見て、望ましいものなのでしょうか?
地方出身者として、まちづくりの一端を担う人間として、大きな宿題を出してもらいました。そして、幸運にも、地方創生に関わる方へのインタビューをこれからもさせていただけるということで、死ぬ前に納得できる回答を提出したいと思います。
ご感想は、コメント欄にてお待ちしています。
インタビュー担当:ナカザワアヤミ
編集協力:有島緋ナ
#無名人インタビュー #インタビュー #自己紹介 #地域創生 #古民家 #古民家 #RuralLabo #地域活性化 #地方移住
マガジンで過去インタビューも読めますよ!
インタビュー参加募集!

いただいたサポートは無名人インタビューの活動に使用します!!
