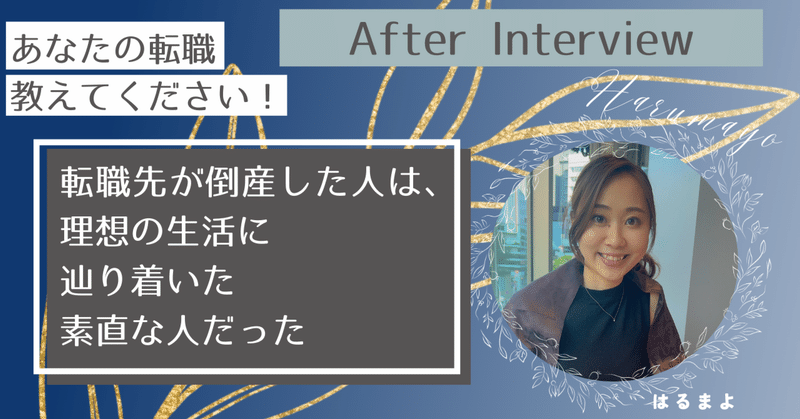
【アフターインタビュー】「転職先が倒産した人は、理想の生活に辿り着いた素直な人だった」
この記事は、はるまよさんのインタビュー記事、【あなたの転職、教えてください!】転職先が倒産した人は、理想の生活に辿り着いた素直な人だったに対するアフターインタビューです。
インタビューを体験しながら自分自身のコミュニケーションスタイルを見つめなおすという変則的なワークショップのようになってきましたが。
これもインタビューというものの形の一つかと。
皆さま。お楽しみいただければ幸いです。
まえがき:qbc(無名人インタビュー主催・作家)
インタビューの中の気持ちと事実
qbc:インタビュー、どうでしたか?
はるまよ:行動とか経歴自体がすごい面白い、興味深い方だったんですけど、本音がうまく引き出せたのかな、という気持ちが残りましたね。
状況を飲みこむことばかりに時間を取られてしまった気がしています。
qbc:なるほど。
はるまよ:やっぱり、私はまだインタビューが2人目なので、技術が足りてないのもあると思うし。
でも、なんか、インタビューって、当たり前ですけど、インタビューを受ける方によって全然違うなと思いました。
どういう時間になるのかが、全然違うなと思って。
1回目の時は、参加いただいた方の本心を聞いて、二人の間で化学反応があった感じがしたんですけど、今回はうまく本心に触れられた気がしていなくて。お話自体の面白さや、気づきもあったんですけど。
琴線に触れる部分があったかなかったかというと、まあ、あったんですけど。でも、1回目よりかは少なくて。
事実を知っただけに留まった感じで。
qbc:1回目と、どう違いましたか?
はるまよ:どっちが良い悪いではないんですけど、
一人目の方は、心が通じ合ったような気が、勝手にしてて。人としてわかり合えたような気持ちがして、すごくわくわくした部分がありました。
二人目の方は、事実を知るっていうところで言うと、読まれる方の参考になるだろうし、興味深かったんですけど。
qbc:オッケー、わかりました。
では、インタビューの中の要素として、「主観的な感情」と「客観的な情報」があったとして、それぞれをインタビュー参加者から聞きたいとする。
そうしたら、何が必要だと思います?
はるまよ:まず、感情で言うと、双方の心がオープンであることですよね。自分の気持ちを言語化することもそうですし、自分の気持ちに向き合おうっていう態度が必要かなと思います。
情報の方は、例えば今回だったら、自分の知識にない業界の話が出てきて、それは事前に下調べをして、情報を補っていればもっとくっきり話が自分の中で浮かびあがっていただろうし。
まあでも、今回のインタビューが悪かったかって言われたら、別にそうは思わないんですけど、どうなんでしょうね。
qbc:全然悪くないですよ。むしろしっかり聞く姿勢ができていて良かったです。
はるまよ:やっぱり、1回目と2回目で、種類が違ったって感じかな。
qbc:今回のインタビューで、もっと聞きたかったところって、振り返ってみてありますか?
はるまよ:その時の気持ちとか、自分の中での反応はどうでしたか、っていう部分です。
qbc:感情ですね。
感情を聞く時の基本は、先に自分から胸を開く、ということです。ここは自分の内面をさらけ出しても、大丈夫な場所、安心安全な空間だっていうことを感じてもらうことですね。
自己開示はまず自分から、というのは人間関係のお話ではわりとよく出る話ですが。
はるまよ:なるほど。でも、それでもご自身の感情を言ってくださらない場合は、どうしたらいいですか?
qbc:あーそしたら、いろいろ思いつくけど。
今回のような、転職インタビューで倒産の話をしにきていただいたわけですから、もう「どうして転職インタビュー受けていただいたんですか?」って聞くのも一つのルートですかね。
で、その時に自分の内面を話すことも大事。
だから、「お話お伺いして、非常に胸を打つ内容だったんですか。それは、私の父の会社も倒産したことがあるからなんですが。ところで、今回はどうしてインタビューを受けていただいたんでしょうか。もし、伝えたいことが明確であれば、その方向性にもっと合わせた質問や、編集をしたいと考えていますので」あたりを糸口にするというのがいいんじゃないかな。
はるまよ:インタビュー参加の理由を聞いてしまう?
qbc:そうですそうです。
そうすることによって、結論、同じ目的を持ったチームになるってことです。二人なんでパートナーシップって言い方でもいいけど。
最初、赤の他人から始まって、話をちゃんと聞くことで、この人はちゃんと話を聞いてくれる人だという信頼感の小さな核を作る。
で、さらにすこし時間をかけて、その二人の関係性をならす。
で、その状態にしたところで、自分から自己開示、自分の立場を表明して、良ろしければあなたのインタビューの目的を達成するお手伝いを、もっと明確な形でさせてくれませんか? というルートですね。
はるまよ:なるほど。
qbc:まあ口で言うのは簡単だけど、こういうのは概念を頭に入れて、モデルとして理解して、いつでも取りだせるようにしておくといいですね。
あ、このモデルの出番かも、みたいにして、状況確認する感じね。
結局、知識は知識でしかないから。覚えたら実戦でて、もがいてあがきながらして、仕込んだ知識が使えたり使えなかったりを繰り返しながら、
インタビューフルネス
はるまよ:もう一度確認していいですか? 参加者の方の心を開くには、自己開示をしたらいいんですか? どうしてインタビューを受けたかの理由を聞いて。
qbc:まあ、そうだけど。それ以前に、なんというか、自分の心がこわばって自己開示できてないってことも、あったりするし。
今回、はっきりいってしまえばはるまよさんとインタビュー参加者は親子ほどの年齢差があって、父と娘みたいなもんですよね、なかなかお互いに心を開きにくくなったり、まあしますね。
はるまよ:はい。
qbc:実際、インタビューとしては、事実と本音ではなくとも、その人の思ったことが聞ければ、まあオッケーなんだよね。本音が聞けて、なんだか心が通じ合った、みたいな感覚がなかったとしても、インタビュー自体はうまくいったな、という結果にはなる。
はるまよ:そうですね。実際、今回のインタビューも悪かったという感覚はないです。
qbc:いちおう、私の中では言葉を作ってあるんですよ。客観的事実も聞けて、主観的な感情も聞けて、さらにお互いの心も通じ合ったのではないか、という満足感の境地のことを「インタビューフルネス」と呼んでいます。
インタビューとマインドフルネスをくっつけて造語した言葉なんですけど、インタビュー中にね、相手と一体感を感じるというか、自分なんだけど自分ではないような感覚で、不思議な満足がある状態というか。
まあ定義も曖昧なんだけど、そういう境地あるよね、という存在をしめすためにインタビューフルネスという言葉を置きました。
はるまよ:面白いですね、インタビューフルネス。感じたいですね。
今の話をお伺いすると、私は今回、気負っちゃったと思うんですよね。相手の空気感に飲まれちゃって慌てていたというか。
だから、自分がフラットでいられなかった。
qbc:まあねえ、インタビューというのも、日常的な空間ではないと思うから。
私だって、インタビューを始めさせての数分間は、違和感を感じたりしますもの。
はるまよ:違和感ですか。
qbc:そうそう。
最初の質問の何回かは、相手のことがほとんどわからないし、あれこの質問でいいのかな、これかな、あれかな、って、相手となじまない感じがあって。
で、そのなじまない原因っていうのが、自分がインタビュアーモードになってないから、みたいな。気持ちが、相手に向かっていこうっていうのがない違和感ね。
相手にフィットしてそうな質問が思い浮かばないって違和感ではなくて、そもそも自分がいい質問をしようっていう意欲が持ててないことに対する違和感というか。
で、その違和感に気づいて、自分にスイッチが入るみたいな。
はるまよ:なるほど。
転職インタビュー企画の終了
はるまよ:実は、私、やりたいことが見つかりまして。大学院に行きたいなと思っているんですよね。
あとは、編集って結構しんどいなと思っていて。インタビューは全然やりたいんですけど。
qbc:なるほど。今、無名人インタビューチームは「インタビュープラットフォーム」というコンセプトで活動をしているので、全然、編集をチームで行うのはオッケーですよ。
むしろそちらを推奨してます。インタビューしたい人、インタビューの編集したい人、それぞれ集まってもらっているので。
はるまよ:ありがとうございます。
結局、私にとってはインタビューフルネスが大事なんだなって、今日すごい思って。わかりやすい言葉ですね。
qbc:今実は、無名人インタビューの音声版を正式にたちあげようと思っていて。noteでやってるテキスト版の無名人インタビューの他に、スタエフやPodcastを中心として音声版無名人インタビューね。
そっちのほうで、転職テーマにしばられずにインタビューするっていうのがいいんじゃないかなと。
はるまよ:全然いいと思います。記事の編集も必要ないですし。
qbc:じゃあ、まあ、やりましょうか。
終わりに
ということで、次回はどこでお会いするのでしょうか。
たぶん違うプラットフォームで。
というかこのワークショップはほんと、商品化できるのではないかと思った次第。
いくらで売るのか。
制作:qbc(無名人インタビュー主催・作家)
いただいたサポートは無名人インタビューの活動に使用します!!
