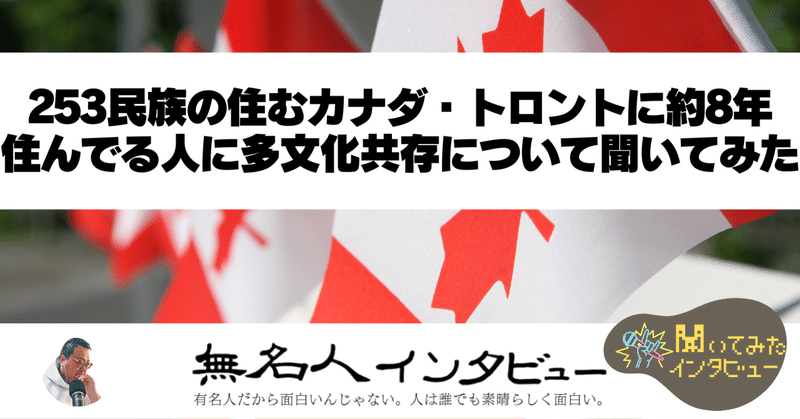
【カナダ】253民族の住むカナダ・トロントに約8年住んでる人に多文化共存について聞いてみた
今、私qbc、ちょっとですね、考えごとをしていまして。
「人口減少している地域で、
・その地域に元々住んでいる人たち
・その地域に新しくやってきた人たち
がいる中で、この人たちが違う考え方をしていたとして、その考え方の違いをどうやって共有するか」
というテーマです。
あ、「考え方の違いをどうやって共有するか」というか、「インタビューを使って考え方の違いを共有することができるかどうか」ですね。
例えば、ある地方の話を聞くと、学校で、新しく来た人は活発で、元々住んでいた子供はそこまで活発ではないことが多く、新しく来た子供の意見が強くなったり、という話も聞きました。
でもこれは実は東京でも見かけていて。たとえば東京郊外にタワーマンションができたとして、その近辺の公立小学校では格差がやっぱり出てくるみたいで。iPad買ってもらえて長期のお休みに海外に行く子と、そうではない子とかね。
こういう環境の中で、インタビューというものは、コミュニケーションツールとしてどう貢献できるのか。
で、先日インタビューしたharuさんですが、haruさんはカナダのトロントに住んで約8年。そしてトロントは200以上の民族(haruさん情報だと253らしいです)が住んでいる、世界で一番多民族だと言われている場所。カナダで生まれ育った人がいたとしても、お父さんお母さんの世代とか、おじいちゃんおばあちゃんの世代が移民だという世界。第一言語は全然違う、宗教も違う、人種も肌の色も全部違う人たち同士は、一体何を共有しながら生活しているのか。
あ、これはもうインタビューしたほうがいいなと。
先のテーマのヒントになること間違いないでしょう、と。快くインタビューをオッケーしていただいたharuさん、ありがとうございます。
まえがき:qbc(無名人インタビュー主催・作家)
200民族以上が居住するトロントの普通

qbc:今、ハルさんの住んでいるカナダで、どうやって色々な考えの人たちが共存しているかを知りたいです。
どんな工夫があるのかと思って。
haruさん:例えば、小学校の校内に”Everyone is different, everyone is awesome!!”というスローガンが掲げられてるんですよ。日本語訳すると「みんな違ってみんな素晴らしいんだよ」ってことなんですけど。
それが子供の頃から自然にすりこまれて、社会全体がお互いを認めあう仕組みになっていますね。
qbc:なるほど。
haruさん:それから、日本だと例えば、先日私、子供を日本に連れて帰ったんですけど、周りの人から「カナダと日本のハーフかわいいね」みたいに言われたりするんですけど。
カナダは元々みんな混血なので、ハーフという言葉がないんですよ。ミックスって呼びます。私のパートナーも、カナダ、イタリア、ポルトガル、トリニダードトバゴと、今思い浮かぶだけでも4カ国が混じっています。
カナダでも、バックグラウンドは何なの? みたいな話はしますけど、カナダに住んでる以上、みんな仲間なんだ、という意識が強くあるんですよね。
留学生として英語を勉強しにここにきたのか、難民として生きるために逃げてきたのかわかんないですけど、みんなカナダに何か理由があって来ているんだから、何人なのかは関係なく、仲間として一緒に生きる、というのが文化になっていますね。
qbc:具体的には、どういうところで感じますか?
haruさん:一人一人みんなの意見を聞くことに時間を費やしているんですよ。
3歳とか4歳のころから、あなたの意見は? っていうのをすごい聞きます。“why”と”because”で、なぜと質問されて、なぜならばって返す文化がしっかりできていますね。
行政のことに関しても、地域レベルに落としこんで、みんなが意見を言う場ががある。平等に発言をする場が与えられていますね。
みんなが言いたいことを言って、しかもリスペクトして意見をちゃんと聞くって事がしっかりと行われています。
話し合いの場も、学校とかが開放されて提供されるんですよ。夜に開放されたりとか。オンラインも増えてきたし。
qbc:なるほど。
haruさん:今、私は子育て中なので学校のところでいえば、月に1、2回は、子供たちの教育について先生に意見を言うミーティングがありますね。
親として学校に自分の意見を聞いてもらえるチャンスがある。その集まりに参加できないんだったら、個別で電話でもいいよって。
1対1もありますが、グループですると一人10分とか15分ぐらいしか与えられてないんですけど、意見交換したりとか。全ての意見が通るわけじゃないですけど、妥当な意見であれば実際に学校運営に反映されます。自分の意見が反映されるなら、積極的に参加したいと思いますよね。
qbc:日本だと、意見を言い損みたいな風潮もありますもんね。
haruさん:実際に学校で、私の発案で異文化交流の集まりを毎月開いてくれることが決まったりしました。
ニューカマーズプログラム

qbc:カナダに来た人は仲間だ、というお話でした。しかし、カナダに来たいわけではなかった人たちもいますよね?
haruさん:自分の国が本当は好きなのに、生き残るためにカナダ移住してきている人たちもいますね。なじもうと思ってない人たち。むしろ、紛争やいろいろな事情が落ち着いたら、早く帰りたい人たち。
子供たちは学校で触れあっていくうちになじんでいくんですけど、例えば英語が話せないという親御さんたちには、ニューカマーズプログラムがあります。自分の母国語で話せる窓口で相談できますね。なじみにくいんだったら、なじみにくいなりに、そういうケアがある。
qbc:ちゃんとシステムとして用意されてるんですね、そういうのが。ただ、都市部以外の、地方ではどうなんでしょうかね。
haruさん:難民とかだと、体制が整ってないと受け入れられないので田舎では受け入れをしてないとは思うんですけども。
私の日本人の生徒さんで、地方の人の話を聞くと、体制はあまり整ってない部分はあるけれど、日本人同士のコミュニティがしっかりあるみたいですね。オンラインや電話で日本語で相談できるサービスがありますね。あとは日本語のメーリングリストもありますし。特に地方の人ほど、そういったオンラインサービスを利用しているようです。
qbc:さらに、元々そこに住んでいた人たちは、どういうケアがあるんでしょう? 先に住んでいた人たち。
haruさん:先住民ですね。私も、学校で習いました。私、カナダに来てもう1回大学に行ったんですよ。そこでカナダの歴史と一緒に先住民についても学習しました。
先住民の言語もまだ残っていて、6代前から住んでいる人たちをネイティブカナディアンとしているんですけど、TAXの面で優遇されていたりとか、そういうルールがあるみたいです。
自分たちはネイティブなんだと誇りを持てるような施策が行われていますね。
カナダの公共サービス

qbc:カナダの公共サービスは、どんな感じなのでしょう? 日本でいう市役所の窓口みたいなものは。
haruさん:日本だと、法的に決まったことを一方通行な感じでサービスを提供するという印象ですよね。決まったのでこれに従ってください、従えないんだったらもう方法はないです、みたいな。
カナダは、人によって臨機応変に対応しますね。対応に対して意見があると、あなたの場合はこうだよね、と話し合いになって対応が変わります。そこが全然違う。言い方変えると、いい加減ではあるんですけど。でも、その「いい加減」にめちゃくちゃ救われるんですよ。提出期限を1日待ってもらったりとか。
qbc:なるほどね。
haruさん:この感覚は、家族にエマージェンシーがあった時の対応にも似てるかもしれませんね。
子供の体調が悪かったり、家族に何かあった時、カナダでは家族を大事にする意識がすごく高いから、すぐお休みが取れます。証明を見せろとかも言われませんし。こちらの緊急事態を快く受け入れてくれます。
qbc:日本もだいぶ家族第一の考えになってきてるとは思いますが、言いにくそうにしている人はぜんぜん見かけますね。
haruさん:カナダでは、いたるところで「一緒に社会を作っていく」感じを受けるんですよ。
例えば発達障害の人たちも、カナダの中に普通に溶けこんでますからね。一緒に生活して、一緒に仕事している。
カナダでは、発達障害の子も普通のクラスに入れちゃうんですよ。ただ、1人に対して1人のケアワーカーをつける。それも公共サービスなんですね。有料のサービスもありますけど。だからみんなの中に溶け込んで、発達障害を個性として認められる。
日本のように特別学級とか支援学級を作っちゃうと、そこにいる人たちはどんな人たちで何をしてるんだろう、というのが分かんなくなってしまうんですよね。
qbc:うんうん。
haruさん:でも、カナダではみんな一緒に遊んで騒いだりしている。だから、発達障害の人の個性も受け入れられるんですよね。
日本ではクラスを分けてしまうことで、その個性を知るチャンスを奪っている気がします。だから社会に出た時に、その個性を理解してあげられないし、歩み寄れない。
カナダの人たちが共有しているもの
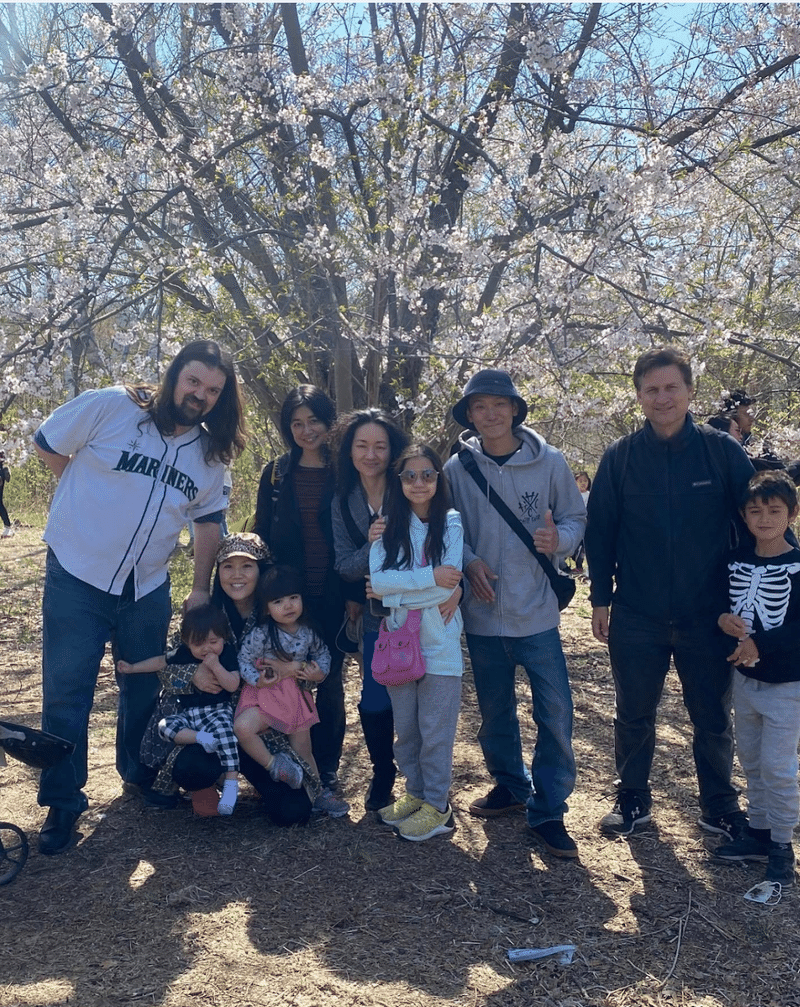
qbc:私なりの社会に対する見解に「何かを共有しないと人は集団を作れない」というのがあるんです。
この考えに従ったとして、カナダの人たちは、いったい何を共有しているんでしょうかね?
haruさん:価値観として「みんな違ってみんないい」の考え方を共有していますね。一緒に何かするとしても、協調を強制しない。自分らしく生きることや、その人の価値観をリスペクトすることで意識統一されているんだと思います。
それぞれみんな違う価値観を持っていてもいいから、相手を否定せず、相手をちゃんと受け入れる。
qbc:なるほど。
haruさん:例えば、話をしていた時に、この人は言葉を理解していないと思ったら、単語を変えてみたり、話すスピードをゆっくりにしてみたり、相手を尊重することは忘れないですね。
この部分はカナダの暗黙の了解で、国民に根付いてるんじゃないかな。
qbc:やっぱり、教育の部分から「みんな違ってみんないい」というメッセージを伝えていると、違うもんですね。
haruさん:それから、自分の住んでいるカナダという国が好きなんだと思いますよ。カナダの国旗の服とか、カナダの国旗の帽子とか、カナダって書いてあるものを、生活していてよく見かけます。
日本ではあまり見かけないですよね。
qbc:日の丸は、思想的な意味が強いですからね。
haruさん:カナダは、移住してきた人にとっては元々自分の国じゃないんだけど、ここは自分の居場所なんだ、ここは温かい場所なんだっていうことを、みんなが誇りに感じているんだと思います。
カナダは今、建国156年だったかな、新しい国だからこそ、この価値観が成り立っているところもあると思いますけれど。
haruさんのお仕事
qbc:haruさんは、カナダに来てもう8年ということですけど、あらためて日本とカナダを比べて感じることはありますか?
haruさん:そうですね。日本の考え方で、ちょっと面白いなと思ったのが、海外に行くイコール英語を勉強する、と思ってる人がすごい多いことですね。英語を話すだけなら、オンラインで学んだり、方法はいくらでもあるし。
qbc:はい。
haruさん:海外に行くことには、考え方だったり、生きる力だったり、人間力を養う意味もあるんですよ。
1週間でもいいんです。日本を離れてみると、日本の良くないところに気づきます。同時に、日本ということにがいかに恵まれているのかということがわかるんですよ。なんて綺麗に統一されていて、なんて素敵な国なんだろうって。
1週間くらいの海外滞在でも、日本に帰ってきたら、また違う気持ちで毎日を頑張れます。
qbc:なるほどね。
haruさん:1回ちょっと外を見てみるか、くらいの気持ちで海外に行くのもアリかなって思います。
これは、私が将来やりたいことの一つですね。誰しもがもっと気軽に手軽に、日本を離れて、海外をちょっとだけ経験できる導線を作る。安く、気軽に使えるサービスとして、ですね。
移住しろとまでは思わないけど、日本だけしか知らないのはもったいないよ、って。
qbc:確かに。
haruさん:私自身、日本の嫌いな部分だったりキツいと感じる部分が、日本を出たことで変わりましたから。日本の良いところを、客観的に見られるようになりました。だから、みんなにもそういう経験をしてもらいたい、と思っています。
qbc:あ、そうか。そもそもharuさんは留学生の受け入れのところでお仕事されているんですものね。
haruさん:そうです。留学センターのマネージャーをしているので。
別のインタビューで聞いたharuさんの5つの顔
1.トロント留学カウンセラー
2.バイリンガルスクール校長
3.脱教科書英語Harunglish!の企画、運営
4.モチベーショナルスピーカー、モチベーター
5.二児の母
haruさん:実際に、私が声をかけて1週間だけ来られた方もいます。夏休みとか有給を使ってね。社会人や、小学生中学生高校生。学校に通えていなかった子が、1週間トロントにきて、自分の中の世界が変わった、って言ってくれたり。
「世界が変わった」は、みんな言いますね。
日本だけが自分の世界ではないし、日本で生きていけなかったら別のところで生きていけばいいし。日本での経験で、自分の人生は終わりなんだ、負け組なんだって思ってた人たちが、まだ自分が生きてゆける場所があるんだ、もっと頑張れるんだ、と気づくんです。それだけでいいんですよ。
qbc:異世界体験ってすごいですね。
haruさん:視野が広がる、考え方が変わるんです。
語学学校なら、1週間単位でも行けるし。でも行かなくてもいいんです。観光したりとか、自分の好きなことをすればいいんです。
qbc:好きなことって、どんな?
haruさん:美術が好きなら美術館行ったり、カフェでのんびりするだけでも、英語が聞こえてくるし。観光地にも、無理に行かなくても大丈夫です。
トロントの街には、韓国語で書いてある看板があったら、その隣はイタリア語だったり、日本語の看板もあったりとか。いろんな国の看板が入り混じっているんですね。その街を5分10分歩いただけでも、十分に今とは違う世界を感じることができますよ。
qbc:あ、なるほど。そうか、haruさんは留学生のコーディネートって言ってるけども、語学学校以外にも紹介できることはたくさんあるんですものね。結局、トロントの案内人なわけだから。
haruさん:そうです。ホテルに泊まるんじゃなくて、地域のおうちにお邪魔したいとなったら、ホームステイのアレンジもしますし。そうしたら、一般家庭でどんなものを食べてるのか体験できるし。ネットやガイドブックに載っていない経験ができるじゃないですか。
qbc:面白いですね。意外に幅のあるお仕事で。
haruさん:相談は全部完全に無料ですよ。例えば語学学校にその人を紹介したら、学校側から紹介料をもらう仕組みなので、相談ではお金がかかりません。
qbc:相談無料! なお良いですね。
haruさん:留学だけに限らず、何でもできちゃうので、気軽に相談いただきたいですね。
トロントの観光ガイドをしたこともありますし、フィギュアスケートの羽生結弦くんも長くトロントに住んでいたんですけど、依頼があって羽生くんが出る大会のチケットを購入したりとか。
トロントの街にコネクションがあるので、いろいろな人に繋いであげたりもできますね。
qbc:めちゃくちゃ最高じゃないですか。
haruさん:特にカナダは、日本人であればパスポートだけで6か月間は滞在できますから、なおさら気軽にご相談ください。
qbc:ありがとうございます! 無名人インタビューの拠点をカナダに作る際には、相談させてくださいませ!!!!!
haruさんへのトロント留学、トロントで〇〇したいなどのご相談は、こちらのinstagramアカウントへDMしてくださいませ!
カナダ留学相談のinstagram
モチベーショナルスピーカーのinstagram
haruさんの無名人インタビューはこちら!
あとがき
いやあ勉強になりましたありがとうございます!
やっぱ仕組みがあるんだなと思いました。
制作:qbc(無名人インタビュー主催・作家)
#無名人インタビュー #インタビュー #聞いてみた企画 #カナダ #トロント #留学 #海外 #生きづらさ
いただいたサポートは無名人インタビューの活動に使用します!!
