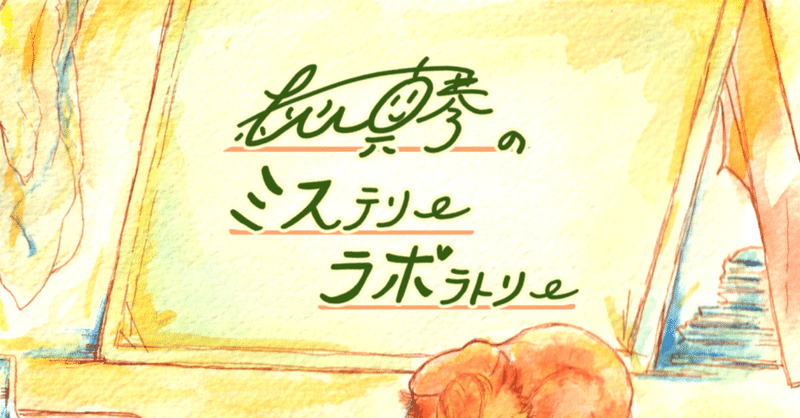
マーダーミステリーが滅びるとき
みなさん、こんにちは。秋山です。
この連載『秋山真琴のミステリーラボラトリー』では、推理ゲームに関して考えたあれやこれやを書き綴っています。
今回はジャンルとしてのマーダーミステリーが滅びるときについて考えてみます。

本題に入る前に、いつもの前置きです。
本記事の序盤は無料でお読みいただけますが、途中から『アナログゲームマガジン』の定期購読者のみが読める形式となります。試し読み部分で「面白そう!」と感じていただけましたら、ぜひ定期購読(月額500円、初月無料)をご検討ください。
定期購読いただきますと本記事だけでなく、わたしが『アナログゲームマガジン』で過去に書いた全記事、わたし以外のライターが書いた全記事も読み放題になります。よろしくお願いします。
ジャンルが滅びるとは
本稿では「マーダーミステリーとは」については取り上げません。
プレイヤーのなかに犯人がいる/いない、キャラクターごとに固有のミッションがある/ない、正体隠匿要素がある/ない、殺人が発生する/しない、等々……。
様々な意見がありますが、本稿では「これこれこういう条件を満たしたものがマーダーミステリーである」と定義づけることはしません。
今回は、あくまで総体として、おおきく、抽象的に捉えていきます。従って、本稿ではマーダーミステリーを自称している作品、マーダーミステリーと他称されている作品、その両方をマーダーミステリーであると、広く扱うことにします。
さて、それでは広義のマーダーミステリーが滅びるときについて考える前に、そもそも特定のジャンルが滅びるとはどういうことなのか、から始めていきましょう。
分かりやすい指針のひとつは、商業作品の新作が発表されなくなることでしょう。
商業作品はリリース後、一定の利益を得て、損益分岐点を越えうるという判断がなされなければリリースされることがありません。
損益分岐点を越えられないということは、それだけの需要がない、つまりユーザから求められていないことを意味します。需要がないところに供給されるということはなく、商業作品の新作が途絶えることになります。
とは言え、現代において、供給が完全になくなるということは考えられません。
かつてと異なり、現代では個人作家による作品発表が容易です。即売会で販売することだってできますし、ネット上で有料無料を問わず公開することが可能です。
だからこそ、ここでは単なる作品ではなく、商業作品とさせていただきました。事業として成立しうるほどに需要があるかどうか、それがジャンルが生きているかどうかの判断基準と言えます。
滅びたジャンル、蘇ったジャンル
ジャンルの滅びについて考えるとき、いつも思い出すのはハードボイルドとゲームブック、SFにミステリです。
ハードボイルドについて
固く茹でられたゆで卵を語源に持つハードボイルドは、精神的にも肉体的にも鍛え上げられた男性を主人公とした作品を総称するジャンルです。
古くはレイモンド・チャンドラーによる『大いなる眠り』のフィリップ・マーロウシリーズなどが有名で、主人公のセリフ「強くなければ生きていけない。優しくなければ生きる資格がない」は知っている方も多いことでしょう。
現代日本で有名なハードボイルド作家としては、大沢在昌、北方謙三、原尞が挙げられるでしょうか。
ハードボイルドは現在でも人気があるジャンルではありますが、往年ほどの勢いはありません。たとえばハードボイルド専門の月刊誌はありませんし、ハードボイルドを専門的に発行するレーベルもありません。書店の平台を見ても、古くから活躍している大御所の名前は見ますが、新人ハードボイルド作家によるデビュー作を見ることは少ないです。ハードボイルドが好きで、ハードボイルドだけを読んでいるという読書家にも、最近は、あまり会っていません。
ただ、大藪春彦賞によって毎年、力強い筆致を持つ骨太な作品が見出されていますし、2017年からは大藪春彦新人賞という新人発掘のために公募の賞もはじまっています。
商業としてハードボイルド一本で回していけるほどジャンルに対する需要はないけれど、供給が完全に途絶えたわけでもない。
ハードボイルドというジャンルが、このような経緯を辿った背景としておおきいのは、なんと言っても人間社会の変化でしょう。
孤独で寡黙、後ろ指をさされようとも毅然とした態度で、自らの信念を貫き通す、一本、筋の通った男。そういった固茹で卵のような男性像がカッコいいとされたのは第二次世界大戦を経て1950年代が終わるまで。1960年に入ってからは内省的で、半熟卵のような男性が活躍しはじめ、マイクル・Z・リューインなどの作品はネオハードボイルドと呼ばれることもあります。
社会の在り方が変われば、理想的な人物像も変化するもの。ハードボイルドの隆盛は、あるいは時代の変化を受けたものと言えるかもしれません。
ゲームブックについて
ゲームブックほど一世を風靡した、という表現が似合うジャンルはないでしょう。
1980年代半ば、スティーブ・ジャクソンとイアン・リビングストンによる『火吹山の魔法使い』が発売されるや否や、瞬く間にブームが訪れました。
各出版社がこぞって参入し、海外作品の翻訳作品を刊行し、国産のオリジナル作品を刊行し、多くのアニメやゲーム作品とのコラボを生み出しました。専門の雑誌が創刊され、新人賞がはじまり、どの書店にもゲームブックの棚が設けられました。
急激に作品が投入されたことで、ゲームブック市場は玉石混淆だったと言われており、中にはクリアすることができないバグが存在する作品も出版されていたそうです。
1990年代に入り、数年間の熱狂が嘘だったように、ゲームブックは急速に衰退します。各社が撤退したことで新刊が出なくなり、雑誌は休刊を迎え、書店からは姿を消しました。
2000年代以降、何度かリバイバルの波が来ましたが、残念ながらそのいずれも長続きしていません。とは言え、少数の熱意のある作家により新作の発表は継続されていますし、ファンもそれに応えているので完全に滅びたジャンルではありません。
わたし自身、ゲームブックは愛着のあるジャンルですので、なかなか遊ぶ時間は取れにくくなっていますが、購入することで支えられればと考えています。
SFについて
SF……については言及しないでおきます。
わたし自身が、それほど深く接することができていない門外漢だからです。
キーワードとしては、冬の時代、これはSFではない、浸透と拡散、などでしょうか。すこし調べていただくだけで、いかにSFの方々が、長きにわたりもがき苦しみながら考え抜いたかが推し量れるかと思います。
ミステリについて
最後に、ミステリについて。
ミステリは、わたしにとって蘇ったジャンルです。
1841年、エドガー・アラン・ポー『モルグ街の殺人』で誕生し、アガサ・クリスティやエラリー・クイーンが活躍した黄金時代を経て、日本においては1920年代からは江戸川乱歩が、1940年代からは横溝正史による本格ミステリが人気を博しました。
しかし、その後、1960年代頃から富豪の館で不可能犯罪が発生し、名探偵がトリックやアリバイなどを解き、犯人を突き止めるというパズル要素を持つ、古典的な本格ミステリは衰退し、代わりに社会的な問題に向き合う、いわゆる社会派がミステリの中心となります。その頃、駅のキオスクでは、表紙に半裸の女性が描かれた通俗的な小説が、ミステリと銘打たれて売られていたそうです。
契機となるのは、1987年に刊行された綾辻行人『十角館の殺人』でしょう。
新本格と銘打たれたムーブメントを機に、一度、衰退した本格ミステリというジャンルが蘇り、今日に至るまでおおきく成長しました。
ジャンルを滅ぼすのは人間社会
ここまで4つのジャンルを見てきましたが、ここからいくつかのことが分かります。
ひとつはジャンルの滅びに最も強く影響するのは、生活様式や社会情勢の変化など、人間社会の在り方が変わることです。
理想の男性像が変わったことで需要が失われたハードボイルドや、他に魅力的で安価なエンターテインメントが生まれたことで衰退したゲームブックなど、そのジャンルの活動や努力に関係なく、人間社会というよりおおきな波によって転覆していることが分かります。
あるいはハードボイルドは警察小説や時代小説に姿を変えて生き残っていると言えるかもしれませんし、ゲームブックは媒体を変えて、サウンドノベルやスマートフォンのゲームとして生き残っていると言えるかもしれません。
個々の作品はジャンルを滅ぼさない
もうひとつ、分かることがあります。
それは個々の作品のクォリティによって、ジャンルが滅びることはないということです。
ジャンルが成長すれば、機会を損失しないために、クォリティが低い作品が市場に投入され、玉石混淆の状況が生み出されることはあります。あるいは小ジャンルが多様化したことによって生み出された様々な作品に対して「これはSFではない」や「これは本格ではない」といった表現がされることもあります。
しかし、これらによってジャンルが滅びることはありません。
何故ならどのジャンルも、そのジャンルの代表的な作品が、そのジャンルの中央に屹立しているからです。
ハードボイルドにおける『大いなる眠り』、ゲームブックにおける『火吹山の魔法使い』、ミステリにおける『十角館の殺人』など、いつだってジャンルは駄作によって殺されるのではなく、名作によって生かされるのです。
その名作が絶版を迎えない限り、ジャンルが滅びることはありません。
ここから先は

アナログゲームマガジン
あなたの世界を広げる『アナログゲームマガジン』は月額500円(初月無料)のサブスクリプション型ウェブマガジンです。 ボードゲーム、マーダー…
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。サポートは次の記事を書くための、カフェのコーヒー代にさせていただきます。
