
犬も歩けば介護予防② 伸びの動作
介護予防の鍵となる歩行。
これを長く健常に保つには、愛犬のちょっとした変化を、なるべく早い段階で飼主が気付いてあげることが重要です。

それには起きぬけに犬が行う、伸びに注目します。この動作は犬を飼っている人にはおなじみの、見慣れた行動ではないでしょうか。
この、犬が起きたときに行う全身の伸びは、自発的なストレッチ運動です。
動作には「からだをスタートさせる」役目もあります。
①筋肉を調整する
②呼吸を深める
③循環を動かすスイッチ
④体の巡りをよくする
⑤緊張を和らげる
⑥自律神経を整える
⑦起きる時間だと脳に知らせる
これらが1日の始まりによい効果をあげます。
ところが、関節の痛みや不具合、なにか調子が悪い、冷えや身体の硬さなどを犬自身が感じると、この伸びを中途半端に行うことがあります。
犬は嫌なこと、痛いこと、動かしにくい場所があると、その部位を使わずに動かさなくなったりするためです。
そんなとき、伸びの動作にも変化が見られます。
たとえば、後ろ左足のつま先を伸ばす動作だけを省略したり、動きが緩慢になったりなど。そういった行動に目を光らせておくと、どの足をかばうのか、痛いのかなどの目安になります。
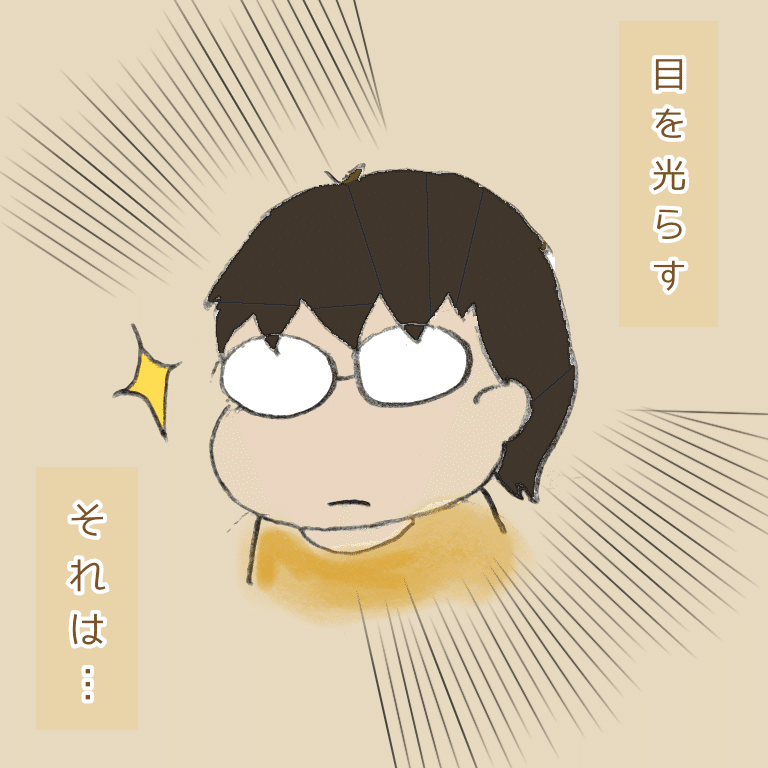
あまりに凝視したりなど気迫をつけると、犬は察して逃げたり隠したり、緊張したりします。ほどよく観察しましょう。
そして変化に気付くには常を知ることです。
愛犬が調子のよいとき、若いときに伸びの動作を動画撮影しておくなどすると、比較ができて変化が分かりやすいと思います。
痛みや身体の硬さがかなり進むと、伸び自体をしなくなることもあります。
また、シニア犬は伸びの後のブルブルをした拍子によろけたり、転倒したりすることがあり危険です。なかには転倒の際に脱臼、驚いてパニックを起こすなどする場合も。
若い犬でもすべりにくい床にする工夫は必要ですが、シニア犬ではそばに寄り添い、よろけた時は支える心づもりでいると安心です。「こんな時によくブルブルをするな」という愛犬のタイミングも覚えておくとよいと思います。
身体への効果に加え、あんなに気持ちよさそうな全身の伸び、可愛らしい仕草。何歳になっても愛犬ができるとよいですよね。
そのためにはまず、変化に気付いてあげること。
愛犬の伸びの動作を観察してみてくださいね♬

分かりやすい♬おもしろい♬役に立つ♬「愛犬おうち介護note.」をお伝えしていきます!
