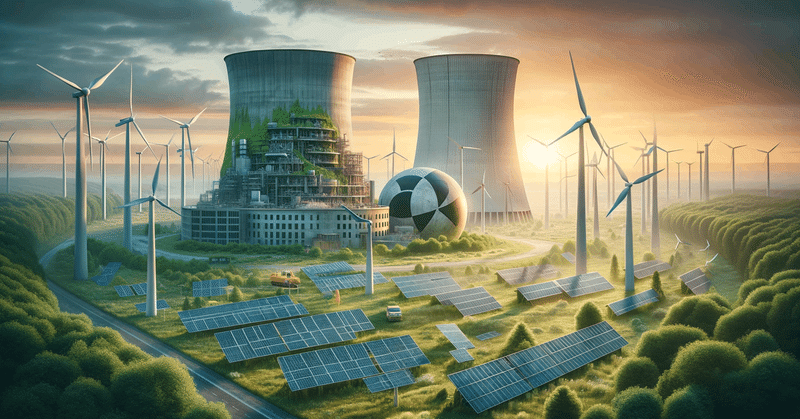
ドイツの脱原発から1年:5つの記事から見る現在地
トップ画像はChatGPTが作成しました。
脱原発1年でハベック氏が投稿した動画が話題に
ドイツ国内で最後の原子力発電所が運用を停止してから1年が経過しました。この節目に、多くのメディアが過去1年間の動向を振り返る記事を掲載しています。
この記事では、まずハベック経済大臣による脱原発1年の動画、市民の声を紹介し、5つのマスメディアによる記事を紹介します。
経済大臣の評価
経済大臣ロベルト・ハベックは、1分間の動画メッセージを通じて、原発停止後の1年間におけるドイツの主要な成果を説明しています。動画によると、この1年間で以下の4つの主要な変化があったとされています:
電力供給の安定性は保たれている。
CO2の排出が20%削減された。
電力の卸売価格が40%下がった。
電力は純輸入になったものの、これが電力コストをさらに低減させている。
この動画には賛否の声が寄せられています。
国民の意見
電力市場の比較サイトであるVerivoxが実施したアンケートによると、2023年の脱原発は間違いだったと考える人は51.6%を占めました。一方で、この決定が正しかったと回答したのは28.4%に留まっています。
このデータから、ドイツの市民の間で原発政策に関する意見が分かれているものの原発を延長すべきだったというのが市民の多数派のようです。
Tagesschau、WiWo、Zeit、NZZ、Focusの記事比較
今回は、ペイウォールのない5つの記事を紹介します。これらの記事は対照的な視点を取り上げており、どの記事が正しいかを論じるものではありません。
まずは5つの記事を紹介しましょう(要約はChatGPTも使っています)。
Tagesschau:"脱原発1年後のドイツの現状"
この記事は、最終的な脱原発から1年後のドイツの状況について、再エネの役割の増大とドイツの電力構成の変化に焦点を当てながら解説しています。
脱原発にポジティブかつ肯定的で、脱原発のメリットとCO2収支の改善、再エネの利用拡大を強調し、脱原発にもかかわらず、よりクリーンなエネルギー生産と安定供給を実現できたと述べています。
記事の構成は以下の通りでした。
電力需要・発電量が減少した。
再エネは発電量、容量ともに増加した。
安定電源(主に石炭)の容量が減少した。
純輸入と欧州市場の関係については、ドイツ内外の電源の価格差で久しぶりの純輸入に転じた。
これまでで一番クリーンな電源構成となった。
脱原発は価格に影響しなかった。
脱原発によって、使用済核燃料の総発生量が確定し、最終処分場候補地と話がしやすくなる。そのことが最終処分場探索に良い影響を与えるだろう。
NZZ: "脱原発に関する4つのエコ神話"
この記事は、ドイツ政府とハベック氏による脱原発の肯定的な表現を批判し、著者が「4つのエコ神話」と呼ぶ、供給安定性、競争力のある電力価格、CO2削減、原子力のリスク評価についてのハベック氏の見解に疑問を投げかけ、エネルギー問題の複雑さを強調しています。
脱原発に懐疑的な視点を提示し、政治的なナラティブ、特に政府による経済的・環境的な主張の正当性の解明を重視しています。
構成は以下の通りでした。
脱原発批判の論点として、ドイツが安定供給を維持していることは認めたうえで、ヨーロッパの危機時(ウクライナでの戦争と原発停止によるフランスの電力安定供給の崩壊)におけるドイツの原発の役割について強調しました。特にドイツの決定がEUでの協調に欠ける点を問題視しています。そのうえで長期の供給安定性の減少リスクについても批判しています。
電力価格の低下はこの1年の短期、かつ超高騰時からの下落の話で、長期的に見たドイツの産業用電気代はとても高いことを指摘しました。
再エネの発電コストだけでなく総コストの話をすべきで、原発が動いていれば卸価格は更に安かったとグリム教授の試算を用いて主張しています。
ドイツの電源がクリーンになったというが、ドイツよりダーティーなのはポーランドとチェコだけと主張しています。
原発は高リスクというが、kWhあたりの死者は石炭などに比べると全然少ないと主張しています。
WirtschaftsWoche: "脱原発:電気料金の高騰-ドイツに原発は不足しているのか?"
この記事は、脱原発から1年間の状況を、電力価格とエネルギー供給の安定性への影響という観点から評価しています。再エネの専門家のデータによれば、卸売価格は下落し、脱原発の影響は再エネの発展によって相殺されました。
データに基づき、実際の発電データに基づいて状況を分析しています。
構成は以下の通りです。
原子力発電から再エネへの置き換えが成功し、全体的な電力料金の引き下げが実現した。
脱原発は間違いと考える人は半数以上である。
脱原発後に卸価格は下落した。
原発の電力の減少分はkWhでみると再エネが相殺した。
電力需要減少も貢献した。
輸入電力のほうが安かった。
脱原発が原因ではないが、系統対策費用の高騰と、柔軟性の不足は深刻な問題。
再エネの専門家は全体の進捗をポジティブに見ている。
ZEIT Online: "脱原発:すべてが輝いているわけではない"
この記事は、脱原発後のドイツのエネルギー政策の長期的課題、特に再エネ拡大への資金調達とインフラ整備について考察しています。
エネルギー転換の社会的・経済的影響に焦点を当て、批判的かつ反省的です。
エネルギー転換に伴う財政的課題や政治的緊張について論じ、エネルギー転換を公平で効率的なものにする必要性を強調しています。
構成は以下の通りでした。
原発推進ロビーが警告したようなことは起きなかった。この点では原発推進ロビーの主張は正しさで1~10点の12点と完全に的外れだった(1がベスト)。
データ上はドイツはうまくやっているが、2023年の進捗を脱原発と結びつけて「脱原発は成功だ」というのは間違いである。
電気代高騰による電力需要減の影響は大きい。
国際的な文脈からドイツの脱原発を批判し、数年の延長を支持する専門家は多い。
ただCDUの求める原発復活は意味がないし非現実的である。
再エネの拡張と供給安定性確保については、例えば系統拡張は加速しているが他方で資金不足に陥っている。予算が違憲判決されたことも問題を深刻にしている。これらの課題は原発を続ける国よりも深刻である。
エネルギー転換のコストは公正に分担すべきである。転換に国の支援が欠かせないのであれば負担配分の調整を行う施策が必要だ。しかし政権は支援の拡大を躊躇している。
Focus Online:”脱原発は何を達成したのか?原発の議論においてハベックはどこが正しく、どこで我々をミスリードしているのか?”
この記事は、脱原発のさまざまな視点と効果について、特にハベック氏の動画の政治的発言と関連させて論じています。
焦点は、電気料金、CO2排出量、エネルギー供給における経済大臣の政治的主張と現実の状況との不一致です。
ハベック氏の動画と、ドイツを代表する原発推進インフルエンサーWendland氏のハベック氏の動画に対する批判を比較し、両者の意見をエネルギーの専門家が解説しています。
Wendland氏は脱原発がドイツをよりダーティーで高コストなエネルギーの未来に導いた可能性を強調する一方で、専門家は両者の意見に批判を加えました。
構成は以下の通りでした。
供給安定性は保たれているというハベック氏の主張に概ね同意し、ドイツの供給安定対策コストの高騰の原因は脱原発とするWendland氏の批判を不正確とした。
CO2削減については再エネを強調するハベック氏の主張は電力高騰による産業の電力需要減について触れておらず不十分と指摘した。
原発があればもっとCO2を減らせたとする主張には、色々な条件が折り重なっておりこれという回答は出せない。
CO2減少はガス価格の低下で、ガスが石炭を代替したことも大きいとし、ハベック氏はこの点に触れていないと批判した。しかしWendland氏のドイツの電力は今後もヨーロッパで最もダーティーであり続けるという主張にはバックアップ電源の種類とその稼働量によって決まるので確かとは言えないと批判し、主張は考えうる最悪シナリオではあるが、そうしたことは起こらないとまとめた。
コストと価格については、ハベック氏が電力価格は40%下がったと述べているがこれは脱原発の成果ではない。また下がったのは卸価格で小売価格ではないためハベック氏の主張は混乱を招くと批判した。
ドイツは脱原発のせいで小売価格が欧州で最も高いというWendland氏の主張にはドイツの高コスト体質は託送費の問題であり、脱原発は関係ないとした。
また、Wendland氏の用いている数字は原発ロビー団体傘下の研究機関の出した数字で現実よりも高く評価されていると批判しました(Wendland氏は普段再エネロビーのデータを使うべきでないと主張しています)。
Wendland氏の原発が安いといする主張にも、LCOEだけでの判断は不十分で、今後の維持費や新設コストは決して安くはないと批判した(維持費というのはドイツの最後の6基は国際的な安全基準を満たしていないので再稼働するなら相当の改修が必要だという意味と思われます)。
原発に投資する民間投資家がいない、最終処分場のコストは公的資金で賄う点もWendland氏は言及していないと述べ、Wendland氏のコスト試算は前提が不正確とした。
最後に、「多くの市場参加者は、これまでに決まっている方針を貫徹することを望んでおり、方向転換はどんなものであれ高くつく」と述べた。
ドイツの脱原発政策の評価:5つの視点
ドイツの脱原発政策に関する5つの記事の要点をまとめましょう。
共通点:
これらの記事は、ドイツの将来のエネルギー供給における再生可能エネルギーの重要な役割を認識しています。ただし、このエネルギー転換がどの程度うまく管理されるかについては意見が分かれています。
相違点:
脱原発の成功に関する見解:一部の記事(WirtschaftsWocheやTagesschauなど)は、脱原発が成功し、エネルギー供給に大きな影響を与えていないと報じています。一方、NZZやDie Zeitなどはより批判的な見方をしており、既存の問題点や潜在的な問題を強調しています。
経済的影響への焦点:各記事は脱原発の経済的影響について異なる側面に焦点を置いています。一部の記事は財政的な課題やコストについて詳細に論じているのに対し、他の記事は環境や技術的な側面に重点を置いています。
政治的発言の分析:特にFocus Onlineの記事では、ハベック氏やWendland氏の政治的発言とその妥当性を分析しています。
総括
今回紹介した5つの記事は、脱原発政策に対して異なる評価が可能なことを示しており、単純に良い変化や悪い変化を脱原発の成果や原因と結びつけることの難しさを示しています。脱原発後1年の変化はニュースとしてのバリューはあるものの、政策を検証し分析する上では、より広範な視野が求められるでしょう。
脱原発政策の影響評価
脱原発以外の要因の大きさ
脱原発後1年間の短期の変化において、原発の有無よりも、ガス価格の変動など他の要因がより大きな影響を与えたことは明らかです。
2021年のエネルギー危機開始以来、ドイツが直面している最大の課題は原発の稼働の有無ではなく、ガス供給の管理であると見る専門家も多いです。
短期的には、産業が多大な痛みを負うことでガスの需要が減少し、エネルギーだけ見ればこの1年で数字が悪化したとは言えません。例えば原発停止による卸値の上昇はガス価格の低下で相殺されています。また今年に入ってからはガス価格の低下に伴い、産業産出量も上方に転じている分野もあり、油断は禁物ですが、経済見通しが改善されているとの報道もあります。
他方で、脱原発の長期的な評価は時期尚早であると考えられます。少なくとも原子炉の停止から数年はたたないと、脱原発を軸にドイツのエネルギー政策を評価するの困難です。
また、ドイツがロシア産ガスに依存した経緯については、「ドイツは再エネのバックアップとして大量のガスを必要とした」といった、再エネ推進が直接的な要因とする見方は一面的です。
もちろんロシアを疑いもしなかった政治家の責任も大きいのですが、実際、安価なガスを求めてロシアとのノルドストリーム2に投資したのは、BASFなどの超大規模電力・ガス需要家や、エネルギー転換で遅れを取った巨大エネルギー会社だったりしたわけです。これらの企業は過去にも何度も原発回帰を訴えており、再エネの不安定さと高コストを理由にエネルギーセキュリティを考慮せず、ロシア産ガスというやすい化石燃料を求めたといえます。
その意味では、エネルギー転換が間接的な原因とは言えますが、因果プロセスの分析は慎重に行う必要があります。
エネルギー転換の移行期には多くの難しさが伴います。これまで、再エネ推進派が移行の難しさを軽視し、従来のエネルギー供給構造を重視する産業界がロシアへの依存を助長したことにより、責任の所在や動機が複雑化しています。これは日本の中東資源依存を検証する上でも重要な視点ではないかと思います。
現在のドイツ政府は系統拡張の迅速化、ガス(LNG)と将来の水素の輸入先の多様化に少しは気を配るようになっており、多少は反省が活かされると期待しています。
脱原発がなければ現状はマシだったのか?
ドイツが脱原発を行っていなければ状況はマシだったかどうかについては、マシだったという意見もありますが、今それを断言するのは困難です。多くの専門家は、脱原発が成功だとする主張にも失敗だとする主張にも慎重な姿勢を示しています。実際、数年間の原発の延長には賛成する声が多い一方で、原発回帰や維持を支持する専門家は少ないです。
ドイツの根本的な問題は、グリーンな電源の推進よりも、安価な化石燃料を求める姿勢にあったとも言えます。ロシア産ガスが安い限り、原発を維持していたとしても、ドイツが最終的にロシアに依存するガス供給の構造は変わらなかったでしょう。
ドイツにおいて、再エネを推進する人に化石燃料も推進する人はいませんが、原発を推進する人に化石燃料も推進する人は割といます。そのため、原発維持によって化石燃料消費が減り、再エネは今と変わらないくらい成長していたというのは疑問のあるストーリーで、再エネは伸びずに原発もガスもロシアに依存していた可能性こそ考えるべきだと思います。
例えばNZZ紙の記事はまとめで、「もしドイツが原発を廃止せず、再エネを同じペースで拡大していたならば、今日の気候フットプリント(CO2排出)ははるかに改善されていただろう。グリム教授のような専門家に従えば、電気代も安くなるだろう。ハベックと彼の同僚たちは、もちろん脱原発を支持し続けることはできる。しかし、それを圧倒的な成功として売り込むべきではない。」と指摘しています。ハベック氏などが脱原発を圧倒的な成功として売り込むべきではないという指摘には同意しかありませんが、ドイツが原発を廃止せず、再エネを同じペースで拡大できるという想定は楽観的すぎるでしょう。
また、グリム教授の試算は最後の3基の原発が稼働していれば(ガス価格が高騰していた当時の試算で)卸価格を8~12%下げられていたとするものだったと記憶しています。ガス価格が下がった現時点ではどれだけ大きく見積もっても卸値の抑制効果は1kWhあたり0.5セントいくかどうかで、電力小売価格への影響は大きくはなかったでしょう。
とはいえ、エネルギー集約企業にとっては産業用電気代のわずかな差が大きな違いになる可能性は十分にあります。これを過小評価するつもりはありません。産業用電気代が高いのは脱原発の影響が大きい、逆に言うと原発が動いていればドイツの産業用電気代は競争力を持つ、という意見には同意しないとしても、産業用電気代は昔も今も大きな課題であることは間違いありません。
ドイツの原発の容量の推移と電気代の推移を示しておきます。

色々なデータを見るに、大規模需要家の2024年4月の電気代は10セントを切るくらいだと思います。現在、超大規模電力需要家では産業用電気代がアメリカや中国の2倍程度で、中規模需要家ではアメリカの3倍、中国の2倍弱あたりでしょう。

最初の問に戻りますが、脱原発をしていなければドイツはマシだったか?という問いに対しては、YesもNoも現時点では言えません。
最後に、Focus Onlineに登場した専門家は託送費の高止まりは脱原発とは直接的な関係はないと述べていますが、再エネ成長が原因ではあるので、エネルギー転換移行中の資金調達と負担の配分については継続的な見直しが必要です。これはZeitの記事の指摘のとおりです。
あえて原発稼働によるリスクを挙げるなら
安全保障は保たれのか?
安全保障を考える場合、ドイツや東欧の原発は相当程度ロシアとカザフスタンに依存していました。もし脱原発していなければ、ウランや燃料の中間処理をはじめ、ドイツの原発はロシアの武器として使われていたリスクがあります。中期的にはこれらをロシアから他の同盟国へ移行できたでしょうが、短期的には解決困難な課題でした。
また、原子力の安い安定した電力が産業競争力につながるのであればフランスは欧州最強の工業国であるはずです。
ドイツは確かにベースロード電源である原発の電力を輸入しており、フランスはピーク電源をドイツなどから輸入しています。しかし現実には電力の60%を原発で賄うフランスは安定供給が確保できておらず、しばしば国政連係がないと停電してしまいます。フランスは工業化ではドイツに遅れを取っているのは事実です。
原発の推進は「建てたい、維持したいという業界の強い意志は実現されない」という現実を見据えた戦略を持つべきでしょう。ドイツにはこれを強い意志で貫徹できる政治家はいません。CDUの一部やAfDの政治家では不可能です。
CO2排出は少なかったか?
原発があればCO2排出はもっと少なかったという話も、ドイツの電力システムを考えると、そうだったかもしれないし、そうでもないかもしれない話です。例えば、原発が存在した場合、電力余剰時により多く出力抑制されていたのは褐炭ではなく再エネだった可能性が高いというシナリオも説得力があります。
要は、設定するシナリオによって結果は異なります。
経済はより多くの恩恵を受けていたか?
これも、結局どういう視点を持つかで変わります。
原発と再エネではコスト構造や経済効果が異なります。ドイツの場合、再エネのほうが地元は幅広く直接的な恩恵を受けられます。原発も経済効果は大きいですが地域も幅も再エネより限定的になりがちです。
実際、再エネに移行した地域や自治体電力(シュタットベルケ)はかなり潤っています。これが、自治体レベルでエネルギー転換が根強く支持される要因にあります。
脱原発は正しいのか否かについては意見が分かれるものの、多様なシナリオを総合的に検討すると、ドイツの脱原発は短期的な課題は大きいが、長期的には適切な方向であったと思います。
ただし、その成功を過大評価することなく、隣国との連携やエネルギー政策の持続可能性についても考慮する必要があります。このセクションではあえて原発維持のリスクやデメリットを挙げましたが、逆の指摘も正しいのは間違いありません。いずれにしても、エネルギー政策のビジョンと現実、その結果の関係については本当に慎重に見るべきです。
ドイツの例から得られる教訓は多く、これを基にした議論や研究が今後も必要です。とはいえ、少なくともドイツの失敗から不正確な教訓は導いてほしくないと願います。
再エネPPAは今後の鍵に
最後に、ではドイツの企業は電気代をどのように下げていくのかについて私の考えを述べましょう。
その回答の1つがPPAです。
2023年にドイツ国内のPPAを結んだ電源は3.6GWと2022年の0.9GWから323%アップしました。ポストFIT電源のPPA締結も増えています。
再エネPPAだけで解決するわけではありませんが、再エネPPAは1つの手段として今後もドイツで成長すると見られます。
ありがとうございます!
