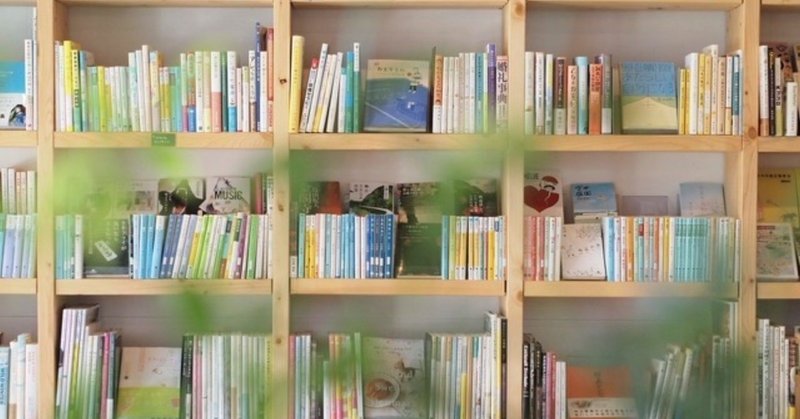
Photo by
kakukakubooks
高見順が愛した浅草|浅草文庫 #朝note
浅草の魅力を、時代時代の庶民の情報媒体であった小説・随筆・詩・俳句・絵画・浮世絵で語られるコトバで紡ぎます。私が日本食料理屋「浅草おと」を根城に運営する「浅草文庫」WEBサイトより編集。浅草をめぐる、本の旅。
高見順が愛した浅草
場面は、――綴り方の女生徒のおとッつぁんのブリキ屋の職人が、大晦日だというのに親方から金が払って貰えず、一文無しで正月を迎えねばならない。人のいいおとッつぁんは家へ帰って家族と顔を合わせると、苦痛に狂ったようになって暴れ回る。そうした場面になったが、ドタバタ騒ぎの場面にひきかえ、シーンと静まり返っている客席の雰囲気に、私は、おや?と思った。丸の内で見たときは、ここで丸の内の客たちがドッと笑ったのである。たとえば、かけ取りの苦労も経験もないサラリーマンとか、一文無しになっても寝て待っていれば親もとから金を送って貰える学生とか、江東の長屋など生れてから見たこともないにちがいない金利生活者とか、そういった丸の内の客は大晦日の悲劇を見てワッハッハと笑ったのである。さよう、かく言う私もいくらか笑ったのだが、ブリキ屋のおとッつぁんに扮した役者の狂乱的演技はいくらか喜劇的でもあったのだ、だがそのおかしさに、浅草の客は決して笑わないのであった。笑わないどころか、見ると、私の前の、何かの職人のおかみさんらしいのが、すすけた髪のほつれ毛が顔にかかるのにかまわず肩掛けで眼を拭っているのである。あちこちから啜り泣きが聞える。
(おお、浅草よ。)
私は感動に胸を締めつけられながら、浅草というものに、――その実体はわからない、漠然としたものだが、浅草というものに、手をさしのべたかった。さしのべていた。
(やっぱり浅草だ。)
思わずそう心の中でつぶやいた。何か宙に浮いたような、宙で空しくもがいているような私を救ってくれるのは、浅草だ、やはり浅草に来てよかった、そんな気がしみじみとした。私は泣きたかった。うれしいのだ。――泣いていた。だが、それは浅草の客と一緒に映画に泣いていたのだ。私は浅草というものに対して涙を流したかったのだ。
同時代に描かれた小説・随筆・詩・俳句
1939(昭和14)年から前後2年の間に語られた、浅草の魅力。
『浅草文庫』とは?
浅草について、江戸時代、戦前、戦中、戦後、高度経済成長前まで、沢山の小説家・俳人・詩人に愛され、彼らによって様々に魅力が語られています。この「当時の魅力」をかき集めて、当時の人々の口、筆によって描かれた浅草を伝えるのが『浅草文庫』です。浅草を訪れると、ふと「何か懐かしい」という感覚が呼び起されますが、それは「当時の魅力」がそこかしこに残っているからです。
毎朝出社打刻前15分のnote活動
毎朝出社後、打刻する前に15分noteを書く、を実施中。実際にやってみると、メール処理などがあって大変。。仕事激務時はお休みします。※「それならもっと早くに出社すれば良いのでは?」というお声に対しては、既にニア始発出社であることを言い訳併記。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
