
ただのXiaomi好きが「Xiaomiモノづくり研究所」に参加してきた話 体験レポート
■Xiaomiモノづくり研究所とは?開催の目的
Xiaomiモノづくり研究所はXiaomiユーザーの意見を聞き、製品開発や製品展開に活かしていこうと発足されたイベントである。2022年から始まりオフライン、オンラインともに開催されている。

■どんな方が参加していていたのか
今回の参加者は20名弱だった。ガジェット系のブログやYoutube活動をされている方、映像業界にお勤めの方、家電業界にお勤めの方などがいた。参加者の中には自分のような一般の参加者ももちろんいたが、全参加者に共通しているのは「米粉 Mi Fan」であることだ。関東圏の方が多かったが、関西圏など遠方からの参加者も見られた。
その他には取材陣としてマイナビニュースさんやケータイ Watchさんからライターの方が来られていた。そして驚くことに携帯電話研究家の山根博士が見学に来られていた。山根博士の記事はASCIIさんの方に掲載されている。
■当日のイベント内容と流れ
▫開場、名札の記入
今回のモノづくり研究所は四ツ谷にあるカフェ・アマルフィーさんを貸し切って開催された。イベント参加中は研究員として行動するので研究員用の名札に名前の記入を行った。

▫自己紹介と流れの説明
まずはイベントを主催しているXiaomi Japan プロダクトプランニング本部 本部長の安達氏から自己紹介があり、続いて参加者による自己紹介があった。自己紹介では各々が「Xiaomiへの愛」を簡単に語り、愛用しているXiaomi製品を紹介している方もいた。Twitterで募集しているということもあり、参加者の中には面識がある方やFF関係にある方も多くいたようだ。「日本未発売のXiaomiスマホを使っている人」という質問には大半の人が手を挙げ、国内のXiaomiハイエンドスマホユーザーが一挙集結しているように感じた。
その後、(各々語りたいことが多く)少し時間に押されながらも流れの説明が行われイベントが進められていった。

▫未発売製品の紹介と体験
まず最初に各製品の説明があり、その後実際に使用してみて出てきた疑問点について意見や感想を交換し合った。白物家電(生活家電)に強い人、黒物家電(娯楽家電)に強い人が割と分かれており参加者は自分の得意分野を中心に意見を出している印象だった。
住んでいる場所、生活スタイルなどにより、人によって気になる点や考えることは様々で自分では気づけなかった新しい着眼点を得られたのでとても貴重な機会であったと思う。
▫パネルディスカッション(ライブ配信)
事前に参加者が回答していたアンケートでの質問を中心に、パネルディスカッション(座談会)形式で質疑応答が行われた。
流石はMi Fanの方たち、鋭い質問が多く安達氏も答え方に慎重になっていたが、はぐらかしすぎることもなく真剣に答えられていた。

▫休憩と雑談
新製品体験やパネルディスカッションを通してだいぶ参加者同士が打ち解けあってきた頃に、休憩タイムを挟んだ。
改めて自己紹介をし合ったり、Twitterを交換したり、安達氏にライブ配信中は答えにくかった突っ込んだ質問をしている方などがいた。

▫クイズ大会
最後のプログラムとして景品をかけたクイズ大会が行われた。豪華な景品なだけあってクイズの内容も激ムズになっていた。

▫記念撮影と景品のお渡し
最後は集合写真を撮り、景品を受け取って解散した。Mi Fanにとっては写真も景品も宝物になったであろう。

■今回紹介された新製品と参加者からの意見
今回、会場に持ち込まれていたのはXiaomi Electric Scooter 4 Pro・Xiaomi TV A2 55 Inch・Xiaomi Robot Vacuum S10の3点だった。
※具体的にこの3点が国内販売されると確定したわけでないことは注意(特にTVのインチ数等)
▫Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

現在は原付バイクと同じ扱いになっている電動キックボードだが、2023年7月より「特定小型原動機付自転車」という新しい区分に位置づけられ、16歳上・免許不要で利用できるようになる。なお、今回持ち込まれたScooter 4 Proは時速25km出るモデルで、国内で販売するには時速20km制限にカスタマイズする必要がある。現状まだまだ利用者は少ないが、改正によりハードルが下がったことでどのくらい利用者が増えるのか気になろところだ。
参加者からは、「近距離の移動に便利そう」「手軽に乗れるのが魅力的」「坂道を登れるのは凄いが、下りが怖そう」「そこそこ重量がある」「一軒家でない場合どこに置いておくのが良いだろうか」などの感想が出てきた。自分含め今回の参加者の中でイベント以前に電動キックボードを利用したことがある人は少なく、なかなか生活に組み込むイメージがしにくかったのかと思う。
▫Xiaomi TV A2 55 Inch
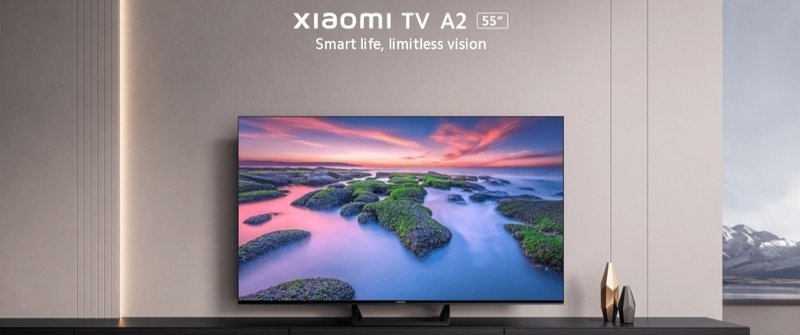
2021年にドン・キホーテが発売して話題になったチューナーレステレビ。地上波を受信するチューナーが内蔵されてなく、ネットコンテンツの視聴に特化しているのか特徴だ。チューナー非内蔵にしたことで、通常のテレビよりも安価で購入できる。発売当初こそ話題になったが、2022年にゲオ・イオンから、2023年頭にニトリから、家電量販店で大きく扱っているのはエディオンのみにとどまっている。その他、ECサイトではちらほら見かけるようにはなったがまだまだ選択肢は少ない状況だ。この文面だけ見ると開拓の余地ありの魅力的な分野に見えるが、チューナーレステレビの存在は現在のテレビの形を否定するものである。これはテレビ番組の視聴に力を入れてきた国内の家電メーカーにとってはあまり印象の良いものではなく、定期的にメーカーフェアを行う家電量販店では歓迎されないものなのかもしれない。だが若者中心にテレビ離れが進んでいるのは事実であり、チューナーレステレビの認知度と需要は徐々に増えていっているので今後どういった形で扱われるのが楽しみだ。
今回持ち込まれたXiaomi TV A2 55 InchはXiaomiのテレビの中では上位モデルでないもののリフレッシュレートが60Hzまでであること以外は、高水準に作られている。参加者からは「自宅で使っているものより動作が軽い」「リモコンのレスポンスが早い」「内蔵スピーカーにしては十分音が良い」などの感想が出た。全体的に好印象な様子で、世界シェア5位なだけのことはあるなと思った。参加者の中には既に購入を考えている方もおり販売が待ち遠しい。
Xiaomiのテレビは小さいものだと32インチ、大きいものだと80インチ以上のものまであるのでどのモデルが投入されるのかも注目したい。
▫Xiaomi Robot Vacuum S10

大きな家で掃除をするのが大変な場合に、ロボット掃除機を導入することで負担を減らすというのが今までのイメージだった。つまりは通常の掃除機を持った上での補助的な役割だ。しかし最近は一人暮らしの方が通常の掃除機を持たずに、ロボット掃除機のみで掃除を済ませるというケースも出始めている。ロボット掃除機でよく起こるトラブルに「階段から落ちる」「床の障害物で停止する」などがある。一人暮らしではシンプルな間取りで荷物も少ないことが多くロボット掃除機との相性は良いのかもしれない。
参加者の中でロボット掃除機を所持している人は多く、そのうちの一人が「最初は安いものを使っていたが性能に満足できず買い替えた」と言った。これはどの家電にも言えることだが、生活に必須でないいわゆる便利家電に位置づけられるようなものは中途半端なものだと使わなくなてしまう事が多い。ロボット掃除機は「カメラ搭載」「マッピング機能」「モップ機能」「ごみ自動収集機能」など上位モデルになればなるほど様々な機能を搭載する。必需品でないからこそ、購入の際にはちゃんとしたものを購入したいところである。
今回会場に持ち込まれたXiaomi Robot Vacuum S10はエントリーグレードながらMi Homeアプリと連携しマッピング機能に対応する。スマホ上で直感的に操作できるのはこの製品の魅力となるだろう。

■パネルディスカッションで出た質問
▫今後のPOCOの発売は?
今はまだ答えられない。まずPOCOはオンライン限定発売の端末として展開。日本の携帯販売は少し特殊で大半の方が携帯通信会社を通して購入する。コスパを考える上での傾向としてオンラインで端末価格の安い製品を求めるよりも、キャリアを介して契約の場での発生金額を抑えたいようにある(たとえそれが端末レンタルだったとしても)。この状況でのオンライン販売の開拓は難しいところがある。
▫LeicaコラボのXiaomiスマホの国内発売は?
可能性がゼロというわけではない、出したい気持ちもある。現在Xiaomi以外のLeicaコラボのスマホが国内で販売されている状況であり、Leicaの方での整理が必要になっている。
▫Xiaomiのローカライズ強化の予定は?
売上が見込めないとなかなか難しい。日本にしかない要求でいうと、FeliCaや防水性能など。カスタマイズにはコストも時間もかかる。キャリアで扱う場合にはある程度の台数が見込まれるためカスタムにも対応するが、それ以外の分に関してはコストと時間をかけるより、グローバル版と遜色ない形で早急に日本に投入する方を選択するかもしれない。
▫Redmi 12Cを投入した意図は?
廉価モデルはまだ日本で需要があるのではと思い投入した(一定数の需要があるのは事実)。大前提として思っている以上にものづくりの業界は厳しいということを理解しておかなければならない。そして同価格帯にあるRedmi Note 11が投入された時とは円相場も変わっている。その中で「求められている廉価モデルの価格」に見合う端末がRedmi 12Cしかなかった。
▫ドラム式洗濯機などの大型家電の投入予定は?
日本投入する製品には順番があると思っている。まずはスマホ、次点でスマホに近い製品から投入していく。ウェアラブル製品がそれにあたる。大型家電の投入が難しい理由として、1つ目にしっかりとしたサポート体制の準備が必要であること。2つ目に大型家電を販売する上で家電量販店での取り扱いが大事になってくること。小型家電と違い大型家電は今でも家電量販店で購入する方が多い。その中で新規参入したメーカーが戦っていくのは難しいことである。特に生活家電には一定のメーカーファンが存在している。大型家電を販売していくには認知してもらうことが大事。
■景品について
おそらくこのイベントに参加したい方の多くが気になっているのがこの景品についてだろう。
今回頂いたのは、トートバッグ・ネックピロー・ノート・ボールペン・指尖积木PLUS PLUS PLUSというおもちゃ。クイズ大会の景品はXiaomi Pad 5・Xaiomi Watch S1・Xiaomi Smart Band 7 Proが1人ずつ計3名に配られた。

■今回参加してみて
イベントに関して
面と向かって消費者と企業が話し合うイベントは中々無いので、貴重な機会に参加できて光栄でした。消費者目線で物事を見てくれているのが強く感じられてより一層Xiaomiの事が好きになれたと思います。
個人的にイベントの最中に感じてたこと
オフラインでの「モノづくり研究所」は参加条件が20歳以上ということで、(年齢が理由にはなりませんが)20歳なりたての自分にとってはレベルの高い会話が繰り広げられていました。
会話の内容だけではなく、参加者の方達の伝えたいことを簡潔に述べれる力、急な質問にも対応できる力など見習うべき点はいくつもありました。特にブロガーさんの方達は、質問しながら…メモしながら…写真撮りながら…雑談しながら…とマルチタスクの鬼だなと思いました。中の人はもう話について行くのに必死でイベント終わってからスマホの中見返してみても数行のメモと数枚の写真しか残ってなかったです…笑
この度は #Xiaomiものづくり研究所 に参加いたしました!!
— なおし@Xiaomiファン (@burasino) April 8, 2023
超有名なカステラ王子さん(@castella555)、やずさん(@F10Dfjtu)、ういおりくん( @uiori_xiaomi)含む超有名な人々が多くて驚きました(* 'ᵕ' )イイヨ!!(* 'ᵕ' )イイヨ!!@XiaomiJapan @xiaomi_aa pic.twitter.com/yapWYB2CSK
雑談の時間には初めて知り合った方Mi Fanの方や、なおしさんややずさんのように元々Twitter上で関わりがあった方とも沢山お話することが出来て楽しかったです。
年齢制限、メディア、開催場所が都内など決してハードルの低いイベントでは無いですが、その代わり参加して学べる事は多いと思うので今まで応募を悩んでいた方も是非応募してみて下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
