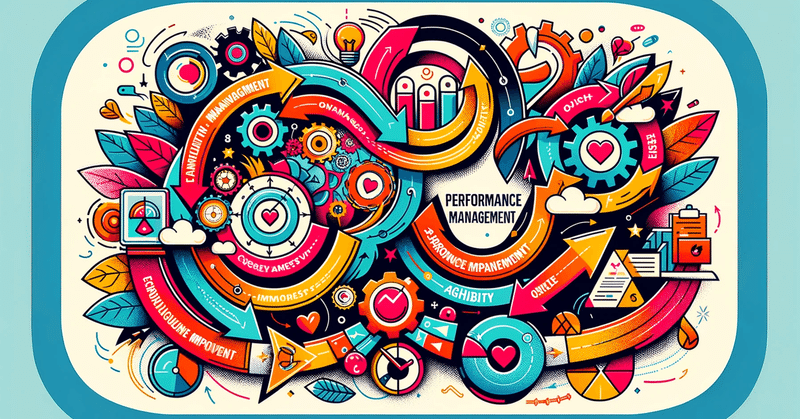
【完全理解】パフォーマンス・マネジメント
こんにちは。HR Tech企業で組織開発・人材育成をやっているうえむらです。本記事では人事用語としてのパフォーマンス・マネジメント(以下、PMと省略)について私がインプットした内容を整理します。これからPMへの理解を深める段階にある人事パーソンに役立つ記事になることを目指して書いていきます。
余談ですがタイトルの「完全理解」はご推察の通りダニング=クルーガー効果(完全に理解した曲線)を指しています。この記事を読み終える頃には絶望の谷へと向かう準備が整っているはずです。名前がかっこいい。
「『完全に理解した』曲線」こと、「ダニング=クルーガー効果」の図、各パートの名前が意外とかっこいい。 pic.twitter.com/2TMvOLebec
— 三崎律日 (@i_kaseki) October 4, 2021
学びのきっかけ
はじめになぜ私がPMを学ぼうと思ったのかを書いておこうと思います。
先日、社内のビジネス現場社員と1on1をする機会がありました。そのなかでMBOの設計・運用について話す機会があり、坪谷さん(@tsubo92)の「図解 目標管理入門」をおすすめされました。早速読んでみたところMBOだけでなくOKRやKPIを含め目標管理を広く理解することができました。
今日も現場社員と1on1していたところMBOの在り方や運用についての改善案を共有された。坪谷さん(@tsubo92)の「図解 目標管理入門」を読んで感銘を受け、人事の私と直接話したいと思ってくれたとのこと。私もポチりました。読みます。 https://t.co/F0qbLydJTf
— うえむら (@uemura_HR) January 31, 2024
読了。目標管理について体系的に理解することができる1冊。個・組織×主観・客観の4象限からMBO、OKR、KPIに落とし込む手法に深く納得した。また成長企業における実践的なアプローチやエピソードも載せられており、とても参考になった。https://t.co/9fAF4WetQi
— うえむら (@uemura_HR) February 24, 2024
特にMBOについては正式名称である「Management by Objectives and Self-control」の後半部分、つまり自律的な貢献がキーとなることを本書を通じて理解しました。
目標管理の利点は、自らの仕事を自ら管理することにある。その結果、最善を尽くすための動機がもたらされる。高い視点と広い視野がもたらされる。
そのときに、着目すべきは「貢献」です。 自らの果たすべき貢献は何かとの問いからスタートするとき、人は自由になる。責任を持つがゆえに自由になる。
自ら果たすべき貢献を定め、自らをコントロールする姿勢のことを、私は「自律的な貢献」と訳しました。
一方で企業人事としての自分に立ち返った際に果たして従業員から「自律的な貢献」を引き出せているのだろうかという点が気になりました。またMBOの主役はマネージャーにありMBOとはマネジメント哲学であるという点についても同様に、はたと立ち止まるような感覚を持ちました。
私はMBOを評価制度の一部と捉えてきました。捉えてきたというより囚われてきたという方が近いかもしれません。だからこそ自律的な貢献やマネジメント哲学という言葉を見た際に頭ではそうだなと思いつつ、何かしっくりこなかったのだと思います。
共通の目標と自律的な貢献によって、組織を使って成果をあげるというMBOの本来の目的に近づくために、私自身の囚われ、つまり評価制度と目標管理の関係性についてもう一歩理解を深めたい。そんな中でtweeeetyさんの記事をきっかけに「パフォーマンス・マネジメント」なる言葉に出会いました。
これまでの評価者 / 被評価者 経験から「評価」単体についての理解はしているつもりでしたが、本質的に「成果を最大化するには?」という視点でパフォーマンス マネジメントとして全体像を捉えていなかったなーというのが反省点でもあり気づきになりました。
上記の「全体像を捉える」という点について、私は評価制度と目標管理の関係性を包含する広い概念というイメージを持ちました。知りたかったことはまさにこれかもしれない。こうした経緯を経てPMを深掘りして学ぶことにしました。
先に結論
先行研究や実践事例を読み解くとPMの統一的な定義は存在しない代わりに、いくつかの共通点が浮かび上がってきました。ここでは先に結論としてその共通点を列挙します。
組織の長期的な成功を目指し、従業員のパフォーマンス向上に重点を置く包括的なアプローチである(業績や職務行動を査定し、処遇に反映させるという人事管理的なアプローチからの移行を含む場合が多い)
全社的な人材・組織マネジメントのフレームワークである
定期的、離散的な活動ではなく、年間を通じて随時行われていく周期的な活動である
人事をやってきた皆様であれば「イマイチ何を言ってるのかピンとこない」と思われた方も多いのではないでしょうか。少なくとも私はそう思いました。PMは一見すると理解しづらい概念と言えます。それはなぜなのでしょうか?
輪郭を捉えることが難しい理由
「パフォーマンス」という言葉の多義性
performanceという単語をGoogle翻訳にかけると、様々な和訳が返ってきます。「業績」「演奏」「実行」「出来栄え」「履行」など、他にも数多くの意味を持った言葉であることが分かります。PMにおける「パフォーマンス」の定義は近いのは「業績」になるかと思います。これはビジネス活動における成果を指すと同時に、人や組織の成長を含む概念と捉えるのが良さそうです。
またパフォーマンスを発揮する主体についても分かりづらさを助長しているかもしれません。PMは直接的には「個」にフォーカスするアプローチです。つまり、個々の従業員の成果・成長を最大化することを目的としています。その結果、組織や会社全体の成果・成長を引き出すことができるというわけです。
従来の人事機能区分に沿った整理のしづらさ
人事にとってPMを理解することが難しい理由のひとつは従来の人事管理における「目標管理」「評価」「人材育成」「キャリア開発」といった各機能が混然一体となっている点にあると考えています。
多くの大企業では人事部内での組織は機能別に編成されていますが、PMを制度企画チームから見る場合と人材育成チームから見る場合とでは景色が異なって見えるはずです。この時、それぞれの担当領域からの主張を重ねるだけでは、あるべき姿を描くことは難しいのではないでしょうか。
つまりPMについて考える際には従来の担当領域の枠にとらわれず、人事全体の視点でビジネス・人・組織の成果・成長を引き出すにはどうすれば良いかという視点で向き合うことが必要になります。
ノーレイティングと混同されがち
PMについて調べていると、ノーレイティングという言葉によく出くわします。むしろノーレイティングの方が一般的には知られているかもしれません。
ノーレイティングとはレーティング、つまり従業員の成績をS・A・B・C・Dと格付けすることで報酬決定を行うことを止めることを意味しています。一方で評価そのものを止めるという意味ではありません。多くの場合1on1や360度フィードバックなどを通じて随時のフィードバックを重ねていき、その結果を年次評価とする手法となります。
ノーレイティング自体は評価手法そのものを指していますが、目標設定やフィードバックを含めた全体像として語られることも多く、結果的にPMと同義と見なされている節があります。
ノーレイティングはPMという概念を実装する上でのベストプラクティスのひとつであると私は考えています。関係性を全力で簡略化すると以下の図となります。

ここまではPMを理解する上での難しさを中心に前提となる情報に触れてきました。以降についてはPMそのものについて私が学んだことを書き記していきます。
PMが必要とされるようになった背景
人事考課制度(Performance Appraisal/PA)の歴史
まずはPMが登場する以前の、主に米国における人事考課制度の歴史について簡単に振り返っていきます。
・1900年代初頭の科学的管理法: テイラーとその他の産業技術者により、パフォーマンス水準の定義の重要性が強調され、従業員パフォーマンス評価の基礎が築かれた。
・第一次世界大戦中の人物比較法: Scott や他の研究者が軍の事務員の評価を行い、心理学を活用した評価の仕組みが導入された。これがPAの始まりと位置づけられる。
・1920年代の研究: パフォーマンス定義と測定のための研究が行われ、評価基準の標準化に向けた努力がなされた。Patersonは図式評定尺度を紹介し、定量的評定に貢献。
・1950年代と60年代: パフォーマンス基準の開発と拡大、臨界事例法が導入され、職務関連行動基準が開発された。
・公民権運動の影響: 1950年代後半から60年代にかけて、職務関連パフォーマンス基準が重視されるようになった。1964年の公民権法とそれに続く立法が雇用実務における差別を禁止。
・1960年代と70年代: 同僚や顧客などの代替的な評価源泉に関する研究が増加。多面評価や360度フィードバックの導入。
・1990年代から2000年代: コンピテンシーベースのHRMシステムが重要になり、PAの概念がPM(パフォーマンス・マネジメント)に発展。
その他の論文を見ても、PMという概念が登場したのは1990年代から2000年代(主に2000年以降)となっており、比較的新しいものであることが分かります。
一方日本企業では、評価制度はざっくり以下のような変遷を辿ってきました。人事パーソンにとっては既知の点が多いため詳細は割愛します。
・戦後の日本企業には評価制度は存在しなかった。それは、年功序列が基本であったからである。年功主義では年齢によって処遇が一律的に決まるので、わざわざ評価を行って差をつける必要がなかった。
・1970年頃から職能資格制度が導入され、実力主義が謳われはじめた。この制度は、職能資格ごとに定義された能力基準によって評価を行うもの。
・1990年頃から成果主義の導入と共に、当時アメリカ企業で厳格なレーティングシステムが用いられていたことから日本もそうすべきだとして輸入された。これが今日の日本企業における評価制度の原型となった。
なぜPMが必要となったのか
PMが必要となった背景としては下記のような経営環境の変化が挙げられます。
グローバリゼーション: 組織は21世紀になってますますグローバル化しており、組織の意思決定者は、パフォーマンス評価を規制する法律や裁判所の決定に敏感である必要があります。これらは、各国の文化を反映しています。
文化的多様性: パフォーマンス評価の目的は文化によって異なります。たとえば、個人主義的で権力が低い文化では(例えばカナダやアメリカ)、評価は給与や昇進決定のための従業員間の差別化に使用されます。一方、集団主義的で権力が高い文化では(例えばアジアやラテンアメリカの多くの国々)、評価の発展的側面が強調され、組織へのコミットメントが増加します。
法的要件: アメリカでは、人々が自分たちの法的権利に対してますます認識を深めています。特に、1995年から1999年にかけて、差別に関する訴訟件数が100%増加しています。これらの裁判では、パフォーマンス評価に関する苦情が一般的です。アメリカの裁判所は公正性と適正手続きの証拠を重視しています。
また同時期に学術面、実務面で評価をとりまく認識が変化していったこともPMへの移行に大きく影響を及ぼしています。
学術面では心理測定学の理解浸透や評価手法に関して監督者、同僚、自己評価に焦点を当てた研究や部下からの上向きフィードバックなどの研究が行われました。
実務面では多くのマネージャーが従来の評価手法に不快感を持っていたこと、評価を受ける側の従業員も、パフォーマンス評価の決定やプロセスに対して不満を持っていたことが挙げられます。
まとめると労働環境がよりグローバルになり、文化的多様性が増加し、法的要件への対応の必要性が増していく中で、ほぼ並行して先行研究が進んでいき、現場マネージャーや従業員の不満も相まって一回限りのパフォーマンス評価から継続的なパフォーマンスマネジメントに注目が集まるようになったということが言えそうです。
PMの概念モデル群を元にした考察
PMの概念モデルについては「パフォーマンス・マネジメント概念に関する理論的考察(福井 2012)」にまとめられています。ここでは各モデルのタイトルを列挙します。
Armstrong (2000)によるパフォーマンス・マネジメント・サイクル
Den Hartog, Bosselie & Paauwe(2004) のモデル
Murphy & DeNisi(2008) のモデル
Aguinis(2009) のモデル
Cardy & Leonard(2011) のモデル
上記のモデル群を元に、PMとPA(Performance Appraisal: 人事考課制度)の関係性は下記のように結論付けられています。
以上のモデルにおいてはPAとPMは完全に異なる概念として規定されている。両者の関係を端的にいえば、PMという全体システムのなかに、PAというひとつのサブシステムが包含されているといってよい。PAとは従業員のパフォーマンスを評価する制度であり、この点は従来とは変化していない。ただし異なるところは、PAがPMに有機的に組み込まれ、同時にPAはその機能を拡充する点である。従来のPAのように年に 1、2 回の切り離された評価活動として位置づけるのではなく、全体としての PM に有機的に統合させることが強調される。
上記の結論から概念モデルを元にしたPMの全体像がぼんやりと掴めてきたのではないでしょうか。ここからはより理解を深めるべくPMの構成要素の詳細にドリルダウンしていきます。
PMの構成要素
PMには統一的な定義が存在するわけではないため、ここまでに紹介した概念モデルから共通点を抽出しつつ、PMの要点を理解することを目指して構成要素を洗い出してみます。
個人起点かつ強み重視の目標設定
PMでは目標へのコミットメントと個人のパフォーマンスとの間に強い関連があると考えられています。目標へのコミットメントを促進するためには「個人起点で目標を設定すること」や「個人の強みにフォーカスした目標であること」が必要です。その他にも以下の要素を意識することが個人のパフォーマンスを引き出すことにつながります。
具体的かつ高い目標であること
アウトカムの期待に焦点を当てること
常に見直し、更新可能であること
継続的なフィードバックとコーチング
PMにおいてフィードバックは従業員の行動に対する具体的な評価や情報を提供するのに対し、コーチングは従業員の能力開発や自己認識を促進し、継続的なサポートと挑戦を提供することに重点を置いています。
フィードバックとコーチングは、行動が発生した状況とその行動が生み出した影響を具体的に記述することで効果的に行われるとされています。つまり年間を通じてタイムリーかつ継続的に行う必要があります。フィードバックについての具体的な手法については以下を参考にしてください。
フィードバックは、コントローリング(支配的)な方法ではなく、情報提供的な方法で行われるべきです。このようなアプローチをとると、フィードバックを受けた人のその後のパフォーマンスが改善されます。
フィードバックは、個人ではなく行動に焦点を当てるべきです。これには、望ましい行動を特定し、その行動を示す方法に注目することが含まれます。
フィードバックは選択的であるべきです。つまり、フィードバックを受ける人が圧倒されないように、必要な情報に限定して提供することが重要です。
フィードバックは、具体的かつ高い目標を設定するための基盤となるべきです。このような目標設定は、行動の改善に寄与します。
コーチングは、従業員の自己認識とパフォーマンス管理を強化することに重点を置いています。コーチは、従業員が自らの能力を拡大し、望ましい目標を達成できるよう自信をもたらすべく、日々の基盤で従業員に挑戦を提供します。効果的なコーチはコミュニケーションスキルを重視し、知識や期待を他者に伝える能力に長けています。
未来志向の対話機会
PMでは経営戦略の実行、組織開発、個人のキャリア・アスピレーションなど、会社・組織・個人それぞれのレイヤーで未来志向の対話機会を持つことが重要であるとされています。これはVUCAの時代において継続的に高いパフォーマンスを発揮するために必要なプロセスです。具体的には以下のような機会が挙げられます。
人材開発会議
会社のニーズと個人のニーズを調整しながら、個人のキャリア形成を支援するための場が人材開発会議です。評価会議が過去の一定期間における社員の業績や貢献を評価するのに対して、人材開発会議では個人のキャリア開発や能力開発に関して未来志向で議論がなされます。直属のリーダーがメンバーひとり一人の人材開発シナリオを発表し、参加者で議論して昇進・昇格、ジョブアサインメント、他部署への異動可能性、研修受講、後継者候補の識別など、様々な角度からメンバーの未来をより良いものにするために話し合います。
海外では元々「タレントレビュー」という形で一部の選抜されたタレントを対象にこうした会議を実施してきましたが、その取り組みが全メンバーに広げられ「ピープルレビュー」「ピープルディスカッション」という呼び名に変わっている企業も多いようです。
キャリア開発にフォーカスした1on1
上司と部下の1on1形式で将来のキャリアプランについて対話します。事前にプランを言語化するためのキャリアシートを記載した上で対話に臨むのが一般的です。参考までに私が自社で企画・運営しているCareer Interviewという人事施策について書いた記事をシェアします。
オープンなコラボレーションを促す仕掛け
PMは個人にフォーカスして成果・成長を促す仕組みであると同時に、チームや組織の成果・成長に繋げる仕組みでもあります。その鍵となるのがオープンなコラボレーションを促す仕掛けです。チームワークの強化、職場内外との連携、知識や経験の共有などを通じて組織力の向上をもたらす方法を紹介します。
個人目標のオープン化
OKR(Objectives and Key Results)においては、個人目標をオープンにすることで個人のコミットメントが向上するだけでなく組織のパフォーマンスも向上する効果があるとされています。OKRを導入していない企業においても、隣のチームが何をしているのか、初めて話す別部署の従業員がどんな目標を立てているかを知ることがコラボレーションを促すことは想像しやすいはずです。また昨今では「ネットワークパフォーマンス」と呼ばれる他者との相互関係によって生み出される成果の比重が高まっていることもあり、目標をオープンにすることが相互貢献を促し、組織全体の成果に繋がる点にも注目されています。
360度フィードバック
1on1による上司部下間でのタイムリーなフィードバックに加え、複数の周囲の同僚から総合的にフィードバックを受け取る仕組みが360度フィードバックです。この仕組みが上手く浸透すれば組織にフィードバックカルチャーをもたらすことができ、学びに対して前向きな組織風土の醸成に繋がるとされています。
本章ではPMの構成要素について触れてきました。これらの要素を組み合わせつつマネジメントプロセス全体の在り方を変革し継続的に改善することが、PMの目的である「組織の長期的な成功を目指し、従業員のパフォーマンスを継続的に向上させること」を満たすことに繋がります。
PMの実践事例
本章では企業におけるPMの実践事例、具体的にはAdobe社の「Check-in」について見ていきます。Adobe社はこの仕組みをオープンソース化しており、概念だけでなく実施フェーズでのtoolkitについても公開されています。人事施策をここまでオープンにできるのは凄いなと思いました。
Adobeでは「Check-in」システムと呼ばれるPMを2012年に開始しました。従業員と管理者がパフォーマンスとキャリア成長についての継続的で双方向の会話を行うことを目的としています。従来の年次パフォーマンスレビューや評価制度に代わるものとして導入されました。この新しいアプローチでは、デジタル化されたプラットフォームを使用して目標設定、フィードバックの交換、キャリア成長の探求などが行われます。
AdobeのCheck-inプロセスは、従業員のニーズに対応するより効果的な方法を求める取り組みの一環として始まりました。従来の年次パフォーマンスレビューが従業員の成長とエンゲージメントを十分に促進していないと感じたため、Adobeは新しいアプローチを採用しました。この新しいシステムは、継続的なフィードバックと対話に基づくもので、従業員と管理者間のより効果的なコミュニケーションを促進することを目的としています。

AdobeのCheck-inプロセスは、以下の三つのフェーズに分けられています:
Expectations(期待):
このフェーズでは、従業員に対して年間を通じて期待される成果、行動、貢献について合意します。具体的な目標や貢献のレベルが設定され、従業員はこれらの期待を満たすために働きます。
Feedback(フィードバック):
次に、従業員がこれらの期待に対してどのように進捗しているかについて、頻繁な双方向のフィードバックが提供されます。これには、従業員の進捗状況の確認と、必要に応じてマネージャーによるサポートの方法の調整が含まれます。
Development(成長):
従業員が自分のパフォーマンスについて理解している場合、彼らは学習、キャリア、経験に関する実行可能な目標を計画することができます。このフェーズは、従業員のキャリア成長とスキルの向上に焦点を当てています。
これらのフェーズは、従業員と管理職が一緒に進行し、従業員のパフォーマンスと成長を支援するために設計されています。

上記のガイドラインの他にtoolkitでは実務で利用するワークシートについても公開されており、運用イメージについても掴むことができます。改めて同社の透明性の高さに驚かされるばかりです。
おわりに
以上、パフォーマンス・マネジメントについての調査結果でした。長くなってしまいましたが、本記事を通じてPMの全体像について理解が深まれば嬉しいです。もう少しさくっとまとめる力が欲しい。
個人的な感想としてPMは様々な要素を取り入れた高次のマネジメント・プロセスであり、企業に取り入れる際には全体像を描いた上でステップを踏みつつ徐々に浸透させていくことが良いのではないかと思いました。
本記事を通じてPMについて学んでいる方や、既にPMを実践されている人事担当者の方とつながるきっかけが生まれると嬉しいです。興味を持って頂いた方はXなどでお気軽にご連絡ください。
それでは、いざ絶望の谷へ。
うえむら(@Uemura_HR)
参考文献
パフォーマンス・マネジメント概念に関する理論的考察 (福井 2012)
ADVANCES IN THE SCIENCE OF PERFORMANCE APPRAISAL: IMPLICATIONS FOR PRACTICE (Gary P. Latham and Sara Mann 2006)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
