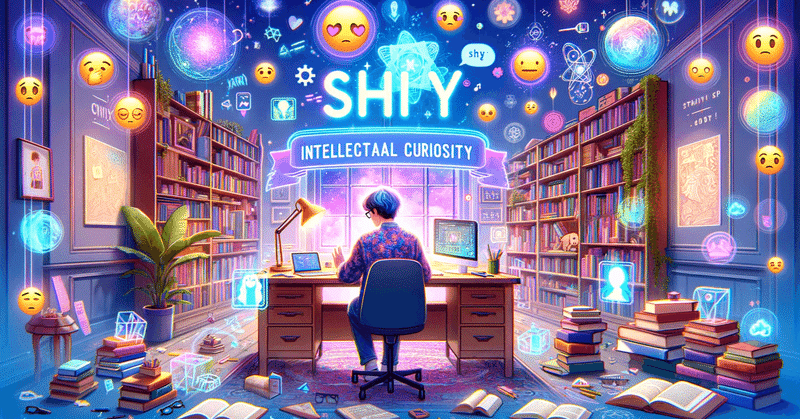
人見知りへの苦手意識と向き合う「シャイネス」についての自由研究
こんにちは。HR Tech企業で組織開発・人材育成をやっているうえむらです。本記事では私が「人見知り」について得た知識についてゆるーく書いていきます。
誰のための記事?
本記事はいつもの人事に関するトピックとはやや雰囲気が異なるため、どんな人におすすめしたいかを宣言しておきます。
初対面かつ大人数の場が苦手な人
自分のことを人見知りだと思っているが、周りからはそう見えないと言われて困惑している人
つまりは私のことです\(^o^)/ワイワイ
学びのきっかけ
いきなり余談ですが、GWということで普段と違うことをやってみようと思ったことが本記事を書くきっかけです。個人的な動機に振り切ってテーマ設定しています。言うならば大人の自由研究ですね。
「私は人見知りであるという自己認識がどこからきているか」をGW中の探求テーマに置きました。連休だからこそ、日常では優先順位が下がりがちな自分の内面と向き合ってみようかなと。
— うえむら (@uemura_HR) April 28, 2024
私はGW明けから複数のコミュニティに参加する予定です。せっかく参加するのであれば楽しみたい。しかし楽しむうえで明確な苦手意識を持っている自覚があります。これを機に「私は人見知りであるという自己認識」とうまく付き合えるようになることで、人とのつながりをより豊かにしていきたいと思っています。
人見知りを意識してしまう場面
「人見知り」という言葉から連想する場面は人によって異なる可能性があります。そこでイメージを共有するために、私が自分に対して人見知りだなーと思った場面を挙げてみます。
初対面の人が集まる勉強会において、周囲を過度に意識してしまう感覚に思考を遮られてしまう
オフィスで仕事をしている際に、誰かに見られているような感覚によって集中を妨げられてしまう
SNSで個人的なことは進んで発信するのに、一同に会する場では発言しなくなる自分に気持ち悪さを感じてしまう
上記のいずれかにピンときた方には本記事の知識が直接役立つ機会があるかもしれません。あまりピンと来なかった方については、身の回りの当てはまりそうな方を思い浮かべながら読んでもらえると嬉しいです。
人見知り=シャイネス
まずはWikipedia先生に人見知りについて聞いてみましょう。
人見知り(ひとみしり、英: Shyness)とは、従来は子供が知らない人を見て、恥ずかしがったり嫌ったりすることである。大人の場合は「内気」・「照れ屋」・「はにかみ屋」・「恥ずかしがり屋」の言葉をあてるのが標準的である。社会心理学では、社会的場面における上記のような行動傾向をシャイネスという[1]。
なるほど、「人見知り」は子どもの言動を指す言葉なんですね。知らなかったー。大人の場合は内気・照れ屋・はにかみ屋・恥ずかしがり屋とのことですが、私どれも当てはまらないんですよね。。いったん自分の中にいる子供の部分がそうさせているということにしておいて、もう少し読み進めてみます。
社会心理学者のチーク (Cheek.J.M) とバス (Buss.A.H) は、シャイネスを「他者が存在することによって生じる不快感と抑制」と位置づけている[1]。また、リアリー (Leary.M.R) はシャイネスを「他者から評価されたり、評価されると予測することによって生じる対人不安と行動の抑制によって特徴づけられる感情-行動症候群」と定義している。行動の抑制とは、口数が少なくなる、視線を合わせないなどの回避的行動や過剰な微笑や同意といった防衛的な行動を指す[1]。
これこれ、まさにこれです。私のイメージをしっかりと捉えた言葉が並んでいます。特に「対人不安」や「行動の抑制」といったワードに強い心当たりがあります。先ほどの「照れ屋」「恥ずかしがり屋」などが実際の行動に焦点を当てているのに対し、こちらは認知にも焦点が当たっていそうな点にしっくりきます。ここから先は「シャイネス」について調べていくのが良さそうです😊
状態シャイネスと特性シャイネス
シャイネスは大きく以下の2つに分類できるとされています。
状態シャイネス: 危険と判断された状況に対応するための一時的な感情状態で、ある特定の状況下で誰もが示す傾向。
特性シャイネス:ある特定の状況を超えて比較的安定して存在する一種の人格特性。
冒頭に私が挙げた「初対面の人が集まる勉強会」においては、状態シャイネスによって誰もが一定の緊張状態に置かれることになりますが、その状態をどのように認知するかは個々人が持つ特性シャイネスによって異なります。このように実際の状況下では状態シャイネスと特性シャイネスが混在しているものと予想されます。
シャイネスの3要素モデル
Cheek & Watson (1989)はシャイネスを認知・感情・行動の3側面のいずれかを伴う症候群であるとする3要素モデル(three-component-model)を提唱しました。
認知 (鋭敏な公的自己意識、自己非難的思考、他者からの否定的評価への恐れ)
感情 (情動的覚醒の自覚、動悸・発汗・赤面など特有の身体的兆候)
行動 (望ましい社会的行動の欠如)
例として、初対面かつ不特定多数の人が集まる勉強会において、グループ毎に分けられたテーブルに着席して自己紹介し合う場面を想像してみます。
認知:(他の人の自己紹介を聞いて)有名企業の人だ…きっと自分よりすごい人に違いない。もしかして自分は場違いなのではないか。
感情:自信が持てなくなり、自分の話す番が近づくにつれ不安な気持ちが強まっていく。
行動:自己紹介で思ったように発言できず、完全に自信を失ってしまう。その後も消極的になり、会が終わるとそそくさと退場してしまう。
人によってはあるあるな場面ではないでしょうか。私もこの文章を書きながら大人数の場面が脳裏をよぎり、霧のような緊張感に包まれ始めています😅
シャイネスはなぜ発生するのか
シャイネスが発生する要因については多くの研究で解明が試みられており、特に個人的要因においては自己呈示という概念の影響が大きいとされています。
自己呈示理論
自己呈示とは、他者とのコミュニケーションにおいて、自分が他者にどう見られているかを考慮し、他者からの自分に対する認知やイメージをコントロールしようとすることを指します。印象操作にも似た言葉ですが、自己呈示はあくまで自分に向けた行為となっており、自分以外の印象もコントロールする印象操作とは異なる概念とされています。
Leary(1983)は本人が期待する自己呈示が行えないことが対人不安の原因となるとする自己呈示理論を主張しました。自己呈示理論によると対人不安の大きさは、自己呈示の動機付けの高さと自己呈示に失敗する主観的確率の相乗によって規定されます。
つまり、対象となる他者に自分を印象づけたいという動機が強まるほど、また印象づけに失敗するのではないかと思うほど、対人不安は大きくなります。
分かりやすい例を挙げると、恋愛対象にあたる人や憧れの有名人との距離を縮めるために自分をアピールする場面を想像してみてください。相手への想いが強いほど、また相手との距離が遠いほど緊張感に満ちた様子が思い浮かぶのではないでしょうか。
自己呈示についてはさらに行動分類や内在化といった掘り下げポイントがあるのですが、本筋から逸れてしまいそうなのでいったん割愛します。
対人不安傾向と対人消極傾向
従来のシャイネス研究では不安傾向と消極傾向を単一次元上で取り扱うことが一般的でしたが、菅原(1998)はシャイネスの主要な構成要素を対人不安傾向と対人消極傾向に分け、各々が独立した特性であると主張しました。
対人不安傾向:否定的評価に対する過敏さからくる不安傾向
対人消極傾向:対人関係に対する無力さからくる消極傾向
しかしながら,こうした仮定に疑念を生じさせる指摘もある.人前では常に緊張し内心不安でいっぱいなのに,外見上は堂々と振る舞い,周囲からは明るい人物だと思われている人たちの存在である.
これ、まさに私です。周りからみた印象と自己認識が異なっているのはどうやらこの点に起因していそうです。周りからは対人消極傾向の小ささを見られていたのに対して自分は対人不安傾向の大きさに着目していたのです。そして2つの傾向は独立している。なるほど…そうだったのかー😳
また先に挙げた自己呈示理論をシャイネスにも適用し、最終的にシャイネスが発生する要因を「不承認への関心」「対人関係スキルの知覚された欠如」「自尊心の低さ」として整理しています。
シャイネスの対処法
シャイネスに対処する上で特に重要なのは自分の特性シャイネスをよく理解することです。特性を理解することで、場面を問わず自分について回る無意識の癖のようなものに対処する手立てを得ることができるでしょう。
私の場合、対人関係スキルの知覚や自尊心は比較的高い方だと思っていますが、一方で不承認への関心が高く、否定的評価に過敏であることを自覚しています。
日常生活でも妻からよく「私が何かを確認しようとすると、私に指摘されたと勘違いして勝手に怒りだすことが多い」と言われます。これも恐らく否定的評価への過敏さから来ているのだと思います😅
特性を理解した上での対処法としては、認知行動療法に近いアプローチを取っていくのが有効とされています。
認知行動療法では、ストレスを感じた具体的な出来事を取り上げて、その出来事が起きた時に「頭の中に浮かぶ考え(認知)」、「感じる気持ち(感情)」、「体の反応(身体)」、「振る舞い(行動)」、という4つの側面に注目します。
(中略)
一般的には、「認知」と「行動」が自分の意志でコントロールしやすいものと言われています。その反対に、「感情」や「身体」は自分の意志でコントロールすることは難しいと言われています。
(中略)
そこで認知行動療法では、この「認知」や「行動」の幅を広げたり、変えていったりすることで、気分や身体を楽にして、ストレスとうまく付き合っていけるようになることを目指します。
シャイネスの対処法としても自己教示訓練(self-instructionaltraining;SIT)という認知行動療法の有効性が研究されており、訓練を重ねることで否定的な自己陳述が弱まったり、自尊感情が高まるなどの効果が見られています。また研究の過程で認知的再体制化(認知の歪みを修正し、適応的な行動を可能にする心理技法)が有機的に結びついたことも指摘されています。
個人差はあるかと思いますが、私の場合はシャイネスの3要素を意識しながら実体験を細かく書き出すだけでも自己理解が深まりました。あるいはシャイネスを発揮した場合に備えてコーピングリストを作成しておくといった予防策も有効そうです。
こうした事前準備によってシャイネスによる苦手意識がなくなることはないかもしれません。しかし、これから参加する場に目的を持ち、自身の行動を変えることで得られる学びを増やすことはできそうです。その結果、苦手な場であっても楽しんでやろうという攻略心が勝る状態を目指していければと思います。
(※本記事はあくまで自由研究となります。本気で症状に悩んでいる方については医療機関を通じて適切な知識を得るようにしてください。)
おわりに
以上、私は人見知りであるという自己認識=シャイネスについての調査結果をお届けしました。本記事のまとめは以下になります。
シャイネスは状態シャイネス、特性シャイネスに分けることができる
シャイネスには認知・感情・行動の3要素モデルが存在する
本人が期待する自己呈示ができないことを対人不安の原因とする「自己呈示理論」がシャイネスにも影響している
人見知りに対する自己認識と他者からの印象の差分は、対人不安傾向と対人消極傾向の違いから説明できることがある
シャイネスの対処法としては認知行動療法のアプローチが研究されており、自己教示訓練や認知的再体制化の有効性が示唆されている
なお本記事では触れませんでしたが、性格特性としての外向性/内向性とシャイネスについての研究もなされているようです。私自身は内向型で、ちょうど内向型についての書籍「I型さんのための100のスキル」を読み終えたところでした。性格特性との関連性についても気が向いたときにゆるゆると調べてみたいと思います。
本記事を通じて人見知りに頭を悩ませる方に新たな発見や少しでも役立つ情報を提供できていれば幸いです。私自身も本記事で得た知識を活用しつつ、新たなコミュニティに飛び込んでいくことを楽しみたいと思います。
それでは、また。
うえむら(@Uemura_HR)
参考記事・論文
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
