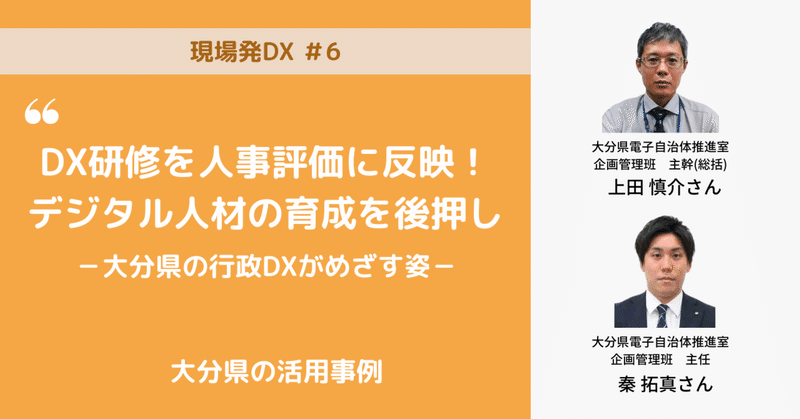
「DX研修を人事評価に反映」でデジタル人材の育成を後押し!大分県の行政DXがめざす姿
大分県では、県民目線に立った施策形成や庁内業務の改善をめざし、Udemy Business(以下、Udemy)を活用したDX人材育成を実施しています。
大分県は2023年12月に総務省から発表された「人材育成・確保基本方針策定指針」で触れられている、「人事との連動」や「県内市町村の支援」にもいち早く取り組んでいます。
取り組みの狙いや大分県ならではの工夫、今後の展望について伺いました。
【話し手】大分県電子自治体推進室 企画管理班
主幹(総括)上田 慎介さん
2001年大分県庁に入庁。工業振興課、商工労働企画課等の産業振興部門等を経て2022年から現職。
----------------------------------------------------------------------------
主任 秦 拓真さん
2015年大分県庁に入庁。ラグビーワールドカップ2019推進課、土木建築企画課等を経て2022年から現職。
自治体業務をデジタルで変革する「大分県DX推進戦略」
秦:大分県で庁内のDX人材育成を開始した背景には、2022年3月に策定した「大分県DX推進戦略」があります。
この中で、DX戦略の4つの柱を掲げています。
①県⺠をユーザーとする「暮らしのDX」
②県内事業者をユーザーとする「産業のDX」
③⾃治体⾃⾝を変⾰する「⾏政のDX」
④⼈材育成やデータ整備等 「DXの推進基盤」
中でも「行政のDX」では、コロナ禍をきっかけに行政のデジタル化の遅れが顕在化し、県・市町村ともにDXへの迅速な対応が求められています。
この取り組みを進める上で欠かせないのが、デジタル技術に精通した人材の確保・育成です。
行政サービスの電子化やキャッシュレス決済の導入はもちろん、庁内の業務効率化においてもDX化を推進するため、デジタルツールを使いこなせる職員を育成したいと考え、今回のDX人材育成を開始するに至りました。
大分県独自の「2つのコース」で若手職員を中心に150名を育成
秦:DX人材育成は、それぞれの所属の中核となる「DX推進リーダー」を3年間で集中的に育てる計画です。
ゆくゆくは、デジタルの知識を身につけたリーダーたちが各部署で中心となり、DX推進体制をさらに実効性のある形にすることをめざしています。
具体的には、DX推進リーダーのスキル習得支援として、「施策形成コース」と「業務改善コース」2つのコースを設け、集合研修とUdemyを活用したオンライン研修を実施しています。
2023年度は「施策形成コース」に30名、「業務改善コース」に120名の計150名、主に35歳くらいまでの若手職員を中心としたメンバーを募りました。

上田:「施策形成コース」では政策検討から予算要求・事業実現までできる人材になることが最終目標です。
県民目線の施策形成を行うためにデザイン思考を学んだ上で、さらにそれを活用するスキルとしてデジタルツールの使い方も学びます。
デジタル技術を活かして施策の形成に取り組む人材を育てるのが狙いです。
「業務改善コース」は、日常業務や県民の皆さんが利用する行政サービスについて、継続した改善を重ねる人材を育成します。
庁内では近年、ノーコードで業務アプリを構築できるクラウドサービスを使い、業務効率化を行っています。
実際に電子申請を実現したり、国への報告の取りまとめを一元管理したりといった実績もあることから、今後も様々なデジタルツールで業務効率化が進むことを期待します。
人事制度との連携により職員の意欲向上を図る
秦:DX推進リーダーとなる職員は、研修の実施に加えて、現場における業務改善の実践も期待することから、他の職員に比べて業務量が増える点が懸念事項でした。
そこで、少しでもモチベーション高く研修に取り組んでもらう方法として、人事課と連携した業績評価への反映、職級が上がる際の単位として今回の研修が認定される制度を設計しました。
この制度が研修を受講するインセンティブとして周知・定着するよう、今後もさらに庁内への広報活動や制度のブラッシュアップをしたいと考えています。
DX推進リーダーの孤立を生まない工夫
秦:これまで庁内の職級別の研修では、デザイン思考やマインド面の学びも何度か実施しました。
しかし、それを実業務にどう活かせばいいのかわからないという声が多数ありました。
また、デジタルスキルやツールの活用に関する研修も実績が少なく、デザイン思考などの考え方とデジタルツールを関連させて学べる内容を求めていた経緯があります。
先に大分市が職員の育成にUdemyを活用しており、その取り組みを知ったときに「様々な分野が網羅的に学べる方法として、Udemyはぴったりだ」と考えました。
上田:オンライン学習はスキマ時間に学べて便利な一方で、個人が孤立しやすい傾向があります。
研修を受けた次のステップとして「現場の業務に活かそう」と考えたとき、横のつながりが作りづらい点が課題として挙がりました。
そこで庁内では、DX推進リーダーが孤立しないように掲示板型のコミュニティを設置したり、外部のDX推進アドバイザーに相談できる体制を整えながら学びを支援しています。
「施策形成コース」では集合研修とUdemyをセットにした学びを提供していますが、今後は「業務改善コース」でも同様の形式を取り、リーダー同士が協力して取り組める仕組み作りが必要だと感じています。
市町村を巻き込み、県内全域でデジタル人材を育てたい
上田:現在、大分県では県内の市町村とともにデジタル人材の育成に取り組んでいます。
Udemyの共同利用を市町村に対して推進していくべく、まずは県でUdemyを活用した学びのモデルを構築し、その事例を情報共有して市町村でも始めやすい風土を作りたいです。
市町村を巻き込んで定期開催する「行政DX推進会議」では、行政手続きのオンライン化や基幹システムの標準化などが喫緊の課題としてあります。
デジタル人材の確保・育成の重要性は共通理解としてありますので、県と市町村が一体となって推進することが重要です。
一連の取り組みの中で、県として育成を進めるDX推進リーダーは中核となる存在です。
県内の行政DX化をますます加速するためにも、DX推進リーダーたちが学びやすい環境づくり、現場で成果を出せる仕組み作りを支援し、DX人材の確保・育成を積極的に進めたいと思います。
