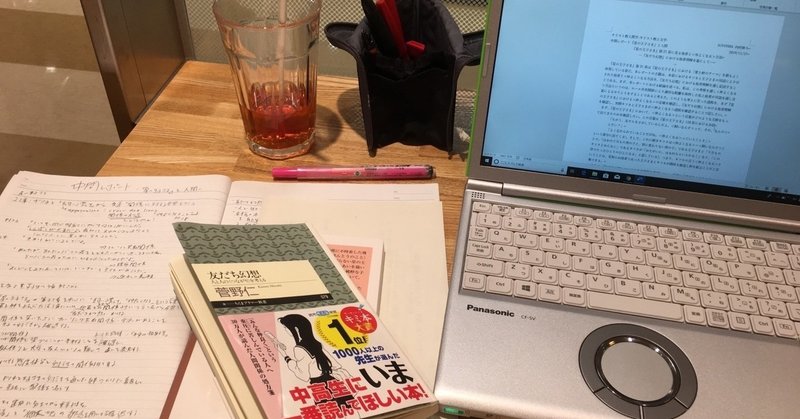
『星の王子さま』に見る他者と<仲よくなる>方法 ―『友だち幻想』における他者理解を基にして―
お久しぶりです。しゅーとです。突然ですが、実は私大学生なんです。とはいっても、まだ一回生なのですが、一回生はレポートが多いのが特徴。それなのに、そのレポートはどれも提出したらそれっきり。添削などもありません。フィードバックがなければ、文章力も上がらずモチベーションも上がらず、だんだんと冗漫で惰性的な文章になっていくのは当たり前。
そこで、せっかくなのでNoteに自分が書いたレポートをあげたいと思います。ぜひ、みなさん読んだらアドバイスやフィードバックをください!
少し前置きが長くなりましたが、今回は『キリスト教人間学ーキリスト教と文学』という授業の中間レポートである「『星の王子様』と人間」というテーマのレポートを公開したいと思います。よろしくお願い致します。
1.概要
『星の王子さま』第21章は『星の王子さま』における「愛と絆のテーマ」を最もよく体現している章だ。本レポートの主題は、本章におけるキツネと王子さまの対話により示された他者と<仲よく>なる方法を、『友だち幻想』における他者理解を通し記述することである。まず、本レポートにおける結論を述べる。私は、この考察を通し<仲よくなる>方法というのは、ルール共有関係により適切な距離を保持した私と他者が対話を通し言葉によるやりとりをすることであると考えた。このような考えに至った過程を、まず『星の王子さま』における<仲よくなる>の定義を確認し、『友だち幻想』における他者理解を確認し、実際キツネと王子さまが<仲よくなる>過程を確認することで記したい。
2.『星の王子さま』における<仲よくなる>
まず、『星の王子さま』において、<仲よくなる>という言葉がどのような文脈をもって出てきたのかを確認したい。この言葉は『星の王子さま』118頁における会話
「ちがう、友だちをさがしているんだよ。<飼いならす>って、それ、なんのこ
とだい?」
「よく忘れられていることだがね。<仲よくなる>っていうことさ」
ー『星の王子さま』サン=テクジュペリ作 内藤濯訳 118頁
という部分に出てくる 。そして、これに続きキツネは<仲よくなる>=<飼いならす>ことで、「ほかの十万もの男の子と、別に変わりない男の子」である王子さまと「十万ものキツネとおんなじ」であるキツネが「おたがいに、はなれちゃいられなく」なり、「この世でたったひとりのひとになる」と話している 。つまり、キツネの言う<仲よくなる>ということは、見知らぬ他者であった王子さまとキツネが関係を創造し絆を結ぶことだと定義できる。
3.『友だち幻想』における他者理解
ここで、『友だち幻想』における他者理解を確認したい。本書は「身近な人たちとのつながりを見つめなおし、現代社会に求められている「親しさ」とはどのようなものであるかをとらえ直すための、「見取り図」を描こうとした」本であり『星の王子さま』における思想を現実に実践するにあたり助けになる内容だと考え参考文献として採用した 。
4.他者の定義
本書において他者とは自分以外のものすべてを指し、その中に「見知らぬ他者」「身近な他者」、中でも「信頼できる他者」の三種類に分けられると指摘している 。そして、これは竹田青嗣氏の概念であるが、他者には「脅威の源泉」として他者と「エロスの源泉」としての他者という矛盾する二重の本質的な性格があると指摘している 。この二重性ゆえに、人々は他者との関係性に困難さを覚え、様々な障壁を感じる。
人間は本質的に「他者との交流」に歓びを覚える社会的生物であり、「自己実現」的な幸福のみでは虚しさを感じてしまう。そこに一人で生きられる時代でも他社との「交流」-『星の王子さま』的理解でいうところの<飼いならす>こと-が重要である理由がある。
5.「ルール関係」と「フィーリング共有関係」
また、本レポートでは他者との関係性を主題としたものだが、この「関係」にも二種類の関係性がある。それは、「ルール関係」と「フィーリング共有関係」である 。それぞれ、「ルール関係」とは他者と共存していくときに、お互いに最低限守らなければならないルールを基本に成立する関係であり、「フィーリング共有関係」とは「僕たちは同じように考えているし、同じ価値観を共有して、同じことで泣いたり笑ったりする、結びつきの強い全体だよね」というような同質性の理解のもと築かれる関係のことである。『友だち幻想』においては、日本の学校―特に高校までの学級や学校―の考え方が「フィーリング共有関係」を前景化させた理念に基づいているムラ社会的なものであると警鐘が鳴らされている。「フィーリング共有関係」が前景化するとどのような問題が生じるかといえば、これは「同質性」を前提とした関係であるために他者が根源的に持つ「異質性」を排除した考え方であり極端な同調圧力が生まれやすいことだ。これは、日本の学生間におけるやり取りの中で頻繁にみられるスケープゴート的な会話や、「連れション文化」さらには、いじめ問題にまで見られる現象だ。筆者はこのような「フィーリング共有関係」が前景化した関係を脱するためには、他者が本質的に持つ異質性を認め「ルール関係」に基づく「フィーリング共有関係」を目指すことで「親しさか、敵対か」の二者択一ではなく、態度保留という真ん中の道を選べる環境にするべきだと主張している 。
6.「かかわり」を持つためには?
しかし、態度保留で距離を置くだけでは関係性は育まれない。そこでまた、筆者は「関係の作り方のポイントとして、異質性、あるいは他者性というようなものを少しづつ意識して、それを通してある種の親しさみたいなものを味わっていくトレーニングを少しづつ心がけていくことが大切」であると述べている 。ここで、「少しづつ」という言葉が繰り返されていることに着目したい。これは、急激に関係性を持とうとすると抵抗が強いため、少しづつ相性を見計らいながら「信頼できる他者」だ、と思える人を見つけていくとこが必要であるということを示している。つまり、「ある程度辛抱強さがないと、どのみち人付き合いはうまくいかない」のである 。
7.『星の王子さま』の関係性構築プロセス
ここで、『星の王子さま』におけるキツネと王子さまの関係性のプロセスに着目したい。122頁において、キツネは「しんぼうが大事だよ。」と言った。そして、「一日一日とたってゆくうちにゃ、あんたは、だんだん近いところへきて、すわれるようになるんだ」とここでも関係性を「少しづつ」築いていくことの重要性が語られている 。
また、キツネは「いつも、おなじ時刻にやってくるほうがいいんだ。」「きまりがいるんだよ」と強調している 。これはまさに、「ルール関係」を疎かにしては「フィーリング共有関係」(交流)はないという『友だち幻想』における主張と重なる。
8.「ことば」の大切さ
しかし、『友だち幻想』と『星の王子さま』では一点において、主張が真っ向から異なる部分がある。それは、「ことば」についての部分だ。『星の王子さま』ではキツネは「あんたは、なんもいわない。それも、ことばっていうやつが、勘ちがいのもとだからだよ。」と述べている 。これが、『友だち幻想』においては、「なるべくいろいろな人の言葉に耳を傾けるということが、関係作りのバランスを鍛えるいいトレーニングになる」と言葉によるコミュニケーションの重要性を強調し、「ノリとリズムだけの親しさには、深みも味わいもありません。」と高密度な言葉を排したコミュニケーションに警鐘を鳴らし、言葉のストックを増やすことが、自分と他者とのつながり、自分と社会との関係の輪郭を掴むことになると指摘し、読書により語彙を高めることの重要性につなげている 。もちろん、『星の王子さま』における「ことば」がコミュニケーションを阻害する粗い言葉のことを指している可能性は十分に考えられる。キリスト教的概念としての「愛」をあらわすものとして「目に見えないもの」である「心」の重要性を説いているのであれば、これは「御大切」の重要性を説いているのであり他者と関係を気付くにあたり疎かにしてはならない基本的な「きまり」を指していると解釈できる。しかし、私はキツネと王子さまが<仲よく>なったのはひとえに、キツネと王子さまの間で行われた言葉による対話であると考える。言葉による対話の重要性と、その際に使う語彙への配慮についてもこれは「御大切」の概念と同じように重要なものだと考える。
9.結論
これまでの議論を通して、私が考えた他者と<仲よくなる>方法を簡潔に記し、このレポートの最後としたい。私は『友だち幻想』における他者理解を眼鏡に『星の王子さま』第21章を読むことで、他者と<仲よくなる>とは、「きまり」を踏まえた関係―つまり「ルール関係」―を前提とし、適切な距離をとった態度保留と言葉による対話のバランスにより、少しづつ対象となる他者を信頼していく作業であると定義する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
