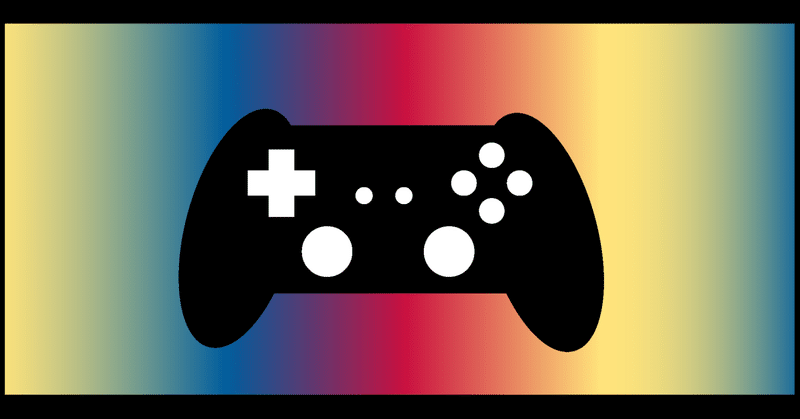
「ゲーム依存」のこと、ちゃんと知ってる?
Q. たくさんゲームしてるだけで病気?
A. 病気じゃない
本人や周囲の人に著しい支障がなければ、病気ではない。次の項目で紹介するゲーム行動症の分類基準にも当てはまらない。
ゲーム行動症に限らず、介入すべき病気として扱うには、生活に支障をきたしうるというのが前提になる。支障をきたさないのであれば介入対象ではなく、病気として扱う意味がない。
Q. ゲーム依存って本当にあるの?
A. ある
世界保健機関 (WHO) が2022年に発効した国際疾病分類第11版 (ICD-11) に、ゲーム行動症 (gaming disorder) という項目が追加されたことが話題になった。日本では「WHOがゲーム依存を病気認定した」という報道が多かった。(それだけの単純な話ではない)
2022年の発効に至るまで、この分類基準については非常に議論があったようだ。しかし「ゲーム行動症」追加反対派ですら、問題となるゲーム行動が存在することを認めている。そこは論点になってない。
Q. ゲーマーの私はゲーム依存症?
A. ほとんどの場合は違う
ICD-11では、次の3要素が12か月以上続いており、著しい支障がある場合にゲーム行動症と分類される (以下は意訳)。
管理できない : ゲームを遊ぶ時間やタイミングがコントロールできない
優先しすぎ : 他の生活よりゲームを最優先している
悪影響を無視 : ゲームしすぎで悪影響が出ているのにゲームを控えない
なお「著しい支障」の定義はない。個人の環境や社会背景によって相対的に判断される。つまり、同じ行動であっても、環境によって病気とするか判断が分かれる。
いずれにしても、生活が成り立っていればゲーム依存症ではないだろう。
Q. ゲーム依存症の人ってどういう人?
A. 大半が子ども
ゲームを問題として病院に相談する事例の大半が子どもの事例とのことだ。また、ゲームについて病院に相談される事例の多くはゲーム行動症の基準を満たさないようだ。
むしろゲームでしか満たされない環境に追い込まれていることが根本的な問題とされている。本人の性質 (発達障害など)、家庭環境、学校環境などの複合的な問題の氷山の一角として、ゲームに依存している様子が見られるのだろう。いずれにしても支援が必要な環境には違いない。
支援する医療関係者が分類基準とは関係なく「ゲーム依存症を治療した」と表現することもあるようだ。現場では、どう名付けるかよりもどう支援するかのほうが重要なのだろう。
分類基準をきちんと用いてゲーム行動症を分類する場合は、報道から受ける印象よりずっと少ないことになる。
Q. どういう根拠でゲーム依存症と言っているの?
A. 根拠はない
「ゲーム行動症」追加推進派でさえ、分類基準に科学的根拠がないことを認めている。実際に診療している医師でも病気の存在意義に戸惑うほど、曖昧な概念なのだ。
その一方で、問題になるゲーム行動が存在することは国際的にも合意されていることだ。どのように問題になり、どのように対処していくべきか、研究が必要だ。そして研究するためには、ゲーム行動症の定義が必要になる。
ICD-11にゲーム行動症の分類基準を載せるべきかの論争の主な論点として「研究を進めるために、科学的根拠がなくても、分類基準を載せるべきか?」というものがあったようだ。論点は「ゲームが有害か?」でもなく「分類基準に科学的根拠があるか?」でもない。
Q. ゲーム依存症になったらゲーム禁止?
A. 禁止はベストではないかも
最近の精神医学では、禁止するのではなく上手く付き合う方法を探していく「ハームリダクション」がトレンドのようだ。実際のところ、ゲームやインターネットを完全に断って一生過ごしていくのは現実的ではないだろう。
そのためには周囲もゲームの性質を知っておくことがある。具体的にはどのようなタイミングならキリよく終われるかについてだ。ゲームはテレビ番組のように時間で簡単に区切られるコンテンツではない。セーブポイントにたどり着く前、あるいは対戦中に強制終了されたら、人間関係に溝を深めるだけだ。さらにゲームに逃げたくなる。
(ゲーマーとしては、普段ゲームしない人や上の世代の人が「テレビゲーム」のイメージで止まっている可能性があることを知っておくと良いかもしれない。オンラインで他の人と遊んでいると思ってないし、アップデートやDLCという概念もなく時間が経てば終わると思われている、かもしれない。)
Q. ゲームが悪く言われすぎてない?
A. 日本ではゲームを悪者にしがち
日本の一般メディアでは「ゲーム行動症」という基準ができたことは報道するが、それまでに学術的に様々な論争があったことは報道してこなかった。ゲームがいよいよ危険なものだと認められたという印象しか与えないだろう。
この報道傾向は、産業団体が学術論文に基づいた声明を出す文化がないことも一因だろう。海外のゲーム産業団体がICD-11への収載に反対する中、日本の団体は声明を出すことはなかった。ゲーム擁護論がメディアに出てきにくいのだ。
まとめ
ゲームと病気にまつわる状況は、思っているよりも複雑だ。簡単に病気として線引きできるものでもないが、かといって無視することもできない。
精神疾患を研究する立場ではない我々にとっては、厳密に病気かどうか判定することは重要ではないのだとも思う。ゲームも関係する困ったことがあれば、個別に対応していくしかない。(困ってなければ病気として騒がなくてもいい)
参考にした図書
佐久間 寛之 (編), 松本 俊彦 (編), 他.『ゲーム障害再考 - 嗜癖か、発達障害か、それとも大人のいらだちか』. 日本評論社. 2023.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
