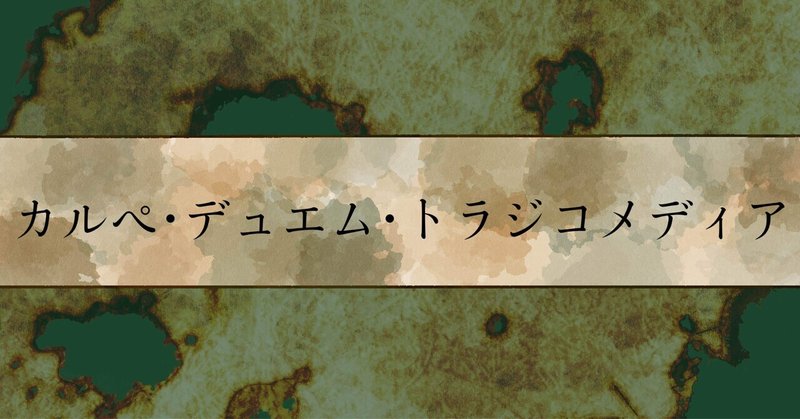
Ep4/あるバーテンダーの日常【カルペ・デュエム・トラジコメディア】
オレル・ドゥメルグは、その生まれ持った性質上、それを見逃すことができなかった。
寒空の下、路上に横たわる一人の女性。年齢は20代半ばといったところだ。薄汚い毛布の下には、ボサボサの髪とすり切れた衣服が見える。体の下に敷いた薄い茣蓙の傍らには空き缶がぽつんと寂しげに立てられていた。そう、所謂物乞いだ。エカムに限らず、このアメリカではありふれた光景の一つだ。
「レディ」
出勤途中にかかわらず、オレルは脚を止め、彼女に語りかけた。暫く待ったがぴくりとも動かない。冬の風に、枝毛まみれの栗髪が揺れるだけだ。
女の物乞いとは珍しい。この街で生業を失った女性の多くは、ギャングに買収、娼婦として働かされる。若さと多少の愛嬌さえ在れば、引く手数多だろう。考えれば考えるほど、彼女が捨て置かれる理由が分からなかった。
いつしかオレルは一つの結論に思い当たった。きっと恐らく、彼女はこのエカムの街に来たばかりなのだろう。街の仕組みを一切知らず、路上で休息を取っていた。ああ、コレならば納得ができる。早く、その旨を伝えてやらなくては。
先ほどより声を抑え、驚かせぬようにそっと囁く。
「レディ。ここは危ないぜ、少なくとも雨風をしのげる場所に、……!?」
耳元を、鋭い風が横切った。いいや、風ではない。ぎらりと曇天を映すそれは、ナイフだった。突然のことに驚いたオレルはしりもちをつき、唖然と女を見つめる。瞼から解き放たれたその視線は、爛々と得物を見つめている。
これは、ただの浮浪者ではないな。
以前客の一人が話していた内容を思い出す。ここ数日、男の死体が大通りに転がる事件が多発していた。被害者は共通して首に傷があり、明らかな他殺であるという。薬や菓子、野犬の類いではないこと、被害者が皆男性であることからちょっとした話題として賑やかされていた。
ああ、この女か。
確信したときには既に遅く、振り上げられた凶器が首元に向けられる。万事休す。死を覚悟した瞬間だった。
「なーにやっているんですかぁ、てんちょ」
軽薄な笑い声とともに、女の断末魔が上がった。恐る恐る目を開けると、血まみれの女が仰向けに倒れており、その横にバルトの姿があった。綺麗な顔に弾けた赤い斑点が妙に鮮やかで、暫しの間言葉を失う。
「バルト……どうして」
「たまたま通りかかったんで見てみたらアラアラ吃驚。うちの店長が襲われている!助けなければ!死んで仕舞ってはお給金の支払いが伸びて仕舞うからね」
血濡れたナイフを得意げに回すバルトは、動かなくなった女を見下ろし、あ!と声を上げた。
「コイツ、前に寝たギャングの情婦じゃん。ははーん、分かった。親玉に言われて強盗殺人やってた訳かぁ。何者か気になってたんだよなぁ」
すっきりした!とバルトは女を足蹴にしてにこやかに笑う。
「お前、本当に殺しに躊躇がないんだな」
オレルの質問に、バルトはああ、とさも当たり前のように答える。
「まあ、感覚としては同衾と一緒サ。でもこちらの方が、さくっと気持ちよくなれる」
「狂ってやがる」
「普段はやらないよ?身の危険を感じたときだけ。僕としては、初心な初客を口説き落とすのと大差ない。ほら、」
赤く染まった右手を差し出される。立つのを手伝ってやろう、ということなのだろうか。無意識のままいぶかしげに眉をひそめると、本人の性格とは比べものにならない繊細な手をとった。そのまま、細身からは信じられない力で立たされる。
「あ、以外にも素直に触れてくれるなぁ」
「親切心を無下にできるほど、俺の心は腐ってないぜ」
「あはははは!たった今殺されそうになっていた男が言う台詞かい?可笑しい」
バルトの目が細まった。笑っていないのは明白だ。
「もし、僕の手に致死の毒が塗られた針が仕込まれていたら?そのまま引き寄せられ、喉を食い破られたら?どうやら、ほんの爪の先ほども考えなかったようだね」
「……」
意地の悪い問いだ。オレルは数年間の付き合いで、この男の性質についていくらか理解している。そう、今この性悪自称音楽家のバルトは、自身を嬲って楽しんでいるのだ。答えなど求めていない。脇腹を突くような質問を投げかけて、困惑している様子を見てほくそ笑んでいるだけだ。
「ほんと、危機感がない。さっきのこの女だって、もしかしたら……みたいな下心でもあったとか?あ、もしかして昔の女と似て、」
「別に、お前だったし」
「は?」
わざと放った脈絡のない答えに、バルトは硬直した。一泡吹かせてやったときのような、浅ましい優越感に陥る。
「なんで手をとったのかって答えだよ。お前は俺に嫌がる言葉をかけはするが、危害を加える真似はしないだろ……なんだ、不満でもあるのか」
「……っは、ほんと馬鹿だなぁ!優しさとお人好しをはき違えていらっしゃる。そのおめでたい頭、早く治さないと、路上でおッ死んでも知らないぞぉ!」
「はいはい、わかった。礼に一杯ご馳走してやるから黙れ、喧しい」
ご馳走、と言う言葉を耳にしたバルトは、不満げな表情からみるみるうちにニヤけ顔になっていく。
「おやぁ?言質はとったぞ?最高級のリキュールを頼んでも文句は言わないねぇ」
「その最高級がうちにあるか、だなんて愚かな回答をさせるつもりか」
「ちっ」
悔しげに、彼は持っていたナイフを放り投げる。からりと煉瓦道に転がるそれに目をやると、見覚えを感じた。あれ、うちの食器じゃないか。一つ文句を言ってやろうと思ったが、命を助けて貰った手前、文句を言えなかった。
一人先に歩くバルトの背をため息つきつつ、追うことにした。
・・・
開店前のトラジコメディアは、営業中とはまた違う静寂に支配されている。そんな中響くシェイカーの音は、待機中の従業員の視線を一手に集めた。
「何しているか……なんて、聞くのすら馬鹿馬鹿しい。店長、よりにもよってこの男に始業前の飲酒を許すんですか」
「今日は例外なんだよウルリカちゃん。大目に見てくれないか」
例外?
入り口前に待機するウルリカが、いぶかしげに眉をひそめた。
「そうだ、たった今さっき、この僕が彼の命を救ったんだ。これがその礼というわけ。ところで、なんて名だいこれは」
ああ、と生返事を返したオレルは、細身のグラスにシェイカーの中身を移した。ふわりと檸檬の甘酸っぱい香りが広がる。縁に輪切りにした檸檬を差し込み、バルトの前に置いた。
「ジンベースのショートカクテル、ビーズニーズのアレンジだ。仕事前の従業員に度数の高い酒を飲ませるわけにはいかないからな」
低度数と知ったバルトは一瞬嫌そうな顔をするが、出された贈り物を無下にする男では無かったらしい。静かにグラスに口をつけた。
「どうだ」
「んん。仕事前の一杯にしては悪くない。シェイカーを振るう腕も、正直なようだ!」
「どうも」
機嫌よさげにグラスを呷ると、さァて!と大声を上げ、バルトはステージに向かった。
そっと、ウルリカがカウンターに寄り、小声で囁く。
「使っていたリキュール。母国から取り寄せた良い品だったんじゃない?あんな奴に飲ませてよかったの」
「ああ。例え値段をつけておいても、客はみんな安い酒ばっかり飲む。と言っても価格を下げて安売りする気もおきないからな。どうせなら気心知れた奴に飲んで貰った方が嬉しいよ。君も飲むか」
ウルリカは少し考えた後言った。
「店じまいの後、店長の目が冴えていたら」
「心得ておくよ」
ふと、軽やかなピアノの音が鳴り響いた。ゆらゆらと殻を左右に揺らしながら、バルトは鍵盤の上で繊細な指を踊らせる。
「胎児の干物。こりゃご機嫌だ」
「いつ聞いても風変わりなメロディーね」
二人は椅子に腰かけ、嫌みったらしさのない軽やかな旋律に身を預けた。イヴァンを起こす、ギリギリの時間まで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
