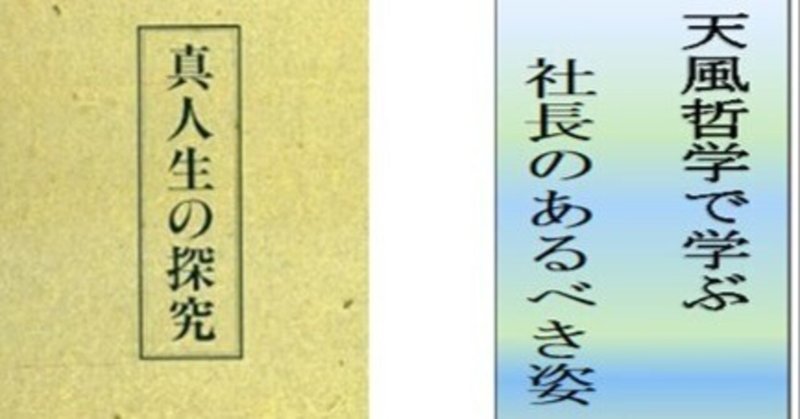
天風哲学で学ぶ社長のあるべき姿 6-1
社長、その考え方で大丈夫ですか(6-1)
小規模企業に組織は必要か、その前に組織とは何かを考えてみたい。組織とは、企業などにおいて二人以上が共通の目的を遂げようとする場合に必要な「分業」と「調整」の仕組みといえる。
社内での部門や役職の相互関係、また指揮系統や予算の配分、役割や権限を明確にすることといえる。また、組織図の作成目的は、組織管理のために役立たせ機能をスムーズにするためともいえる。
しかし、小規模企業でも社長に就くと、社屋の有無、従業員数や売上規模、さらに自らの肩書など対外的なことが気になり、まずは組織図づくりに取りかかろうとする。自らの会社の役割や責任を明確にすることは重要であるが、自社の経営基盤の強化などよりも対外的なことを気にして着手する例も見受けられる。
下図は一般的な組織図であり、その目的は部門間の相互関係、指揮系統の一本化などの管理機能を発揮するために作られたものである。トップに社長が、その下に経営陣や管理職、そして一般従業員という形で配置されている。

当然、それぞれの機能を果たす人たちの人数はピラミッド型のように底辺は複数人となり、上にいくほど少なくなりトップは1人の社長となる。中堅企業や大企業であれば、ゼネラリストやスペシャリストなど多くの従業員によって形成されているのでこのような組織形態を採らざるを得ない。また、分業体制や適材適所などの配置による効率化が可能となっている。
では、小規模企業でも全く同様に考えてもよいのだろうか。多くの小規模企業からの経営相談を受けているが、問題点の原因を探っていくと必ずといってもいいほど社長にたどり着くのである。
例えば営業成績が悪い会社の場合、その原因を社長に聞くと営業部長が責任を果たさないとか能力が低いとかの言い訳をする。でも、その営業部長は誰が任命したのかといえば、社長自身ではないか。資金繰りでも、製造部門の非効率でも・・・社内おけるすべての諸問題の根源は一体どこに、誰にあるのかを問いたい。
小規模企業になればなるほど、社長の役割や権限等は重要となってくる。いちいち社員各人の意見を聞いて、調整して方向性を決めていては非効率的であり、多数決の決め事となってしまう。
ある程度の意見を聞くことは重要であるが、最終的な意思決定は社長自ら判断しなくてはならない。そこに社長の人間性や経営能力が必要となってくるのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
