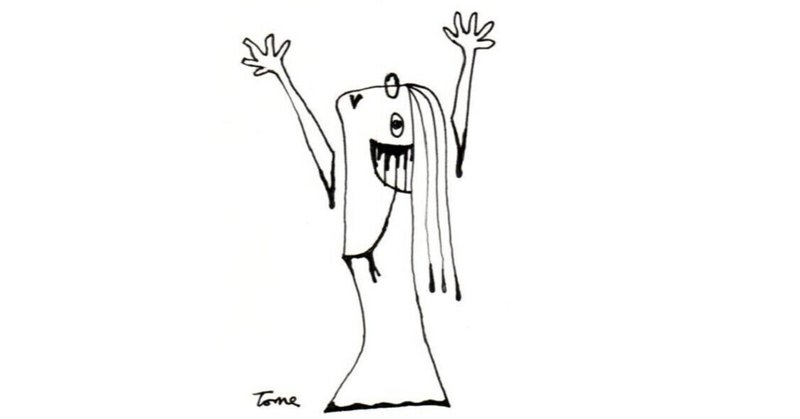
連作小説ショートショート➁:「とある僕と彼女の幾何学的科学実験について」
その炎は、中学の時に美術室で見た「ゲルニカ」を思い出させた。
絵画「ゲルニカ」とは、一九三七年、四月二十六日にドイツ空軍のコンドル軍団がスペイン・ビスカヤ県・ゲルニカに対して行った都市無差別爆撃(ゲルニカ空爆)をモチーフにピカソが描いたものである。
どうして今になって「ゲルニカ」を思い出したのか。
それは、僕の脳内に広がる混沌とした思考のせいである。その結果、脳内の細胞という抽斗を無造作に開き、何処にしまったか分からない「ゲルニカ」の記憶を呼び起こしたのだ。でももしかしたら、僕はその「ゲルニカ」の記憶を想起するために、脳内の細胞を無造作に開く必要があったのかもしれない。目の前に広がる炎を見ていると不思議とそう思った。それは、僕が初めて「ゲルニカ」を見た時に覚えたある種の恐怖とよく似ていたからだ。
「ゲルニカ」は先程も述べた通り、ゲルニカ空爆をモチーフに描かれている。その絵は非常に異質で、幾何学的に形取られた人間、馬、牛が空爆から逃げ惑う様子が描かれている。また、その絵に色味はなく、白と黒の二色にグラデーションを用いるという、何処か水墨画を思わせる作りになっている。まるで戦火により焼け落ちた街や生物を思わせるかのように。
そして、僕が「ゲルニカ」に興味を持ったのは、絵そのものが持ち合わせる奇妙さにある。しかし、根本的な意味で僕を引き付けたのは、何なのだろうか。当時、僕にはそれが分からなかった。だから、僕は「ゲルニカ」について調べた。自身が何故「ゲルニカ」に興味を抱いたのかを知るために。調べていく上で、僕はその理由をはっきりと理解することが出来た。それは、単なる恐怖心だったのだ。「ゲルニカ」に対する、いや、戦争に対する、純粋な恐怖だったのだ。政治的意味合いで命を差し出す人々、引き裂かれる家族、壊れる街並み、得るものと失うものが比例していない戦争という人類の汚点は、僕の心を酷く痛めつけた。そして傷付いた心の内側で、僕は確実に「ゲルニカ」を保管していた。「反戦メッセージを持つ絵画」として、僕は心の深い部分で展示していたのだ。
そんなことは長い間忘れていたのだが、どうして今になって心の中に展示した「ゲルニカ」を見に行こうと思ったのか。それは、僕の目の前に広がる炎が戦火によく似ていたからである。人々は声を荒げ、助けを求む。しかし、多くの人はその圧倒的恐怖に恐れ、佇むことしか出来ない。そして僕は、圧倒的に後者である。
「ちょっと、何ぼーっと立ってんのよ。早く火を消すのを手伝って!」
僕は彼女の怒声のおかげて、ようやく「ゲルニカ」から目を逸らすことが出来た。
「ねえ、ちょっと、いつまで突っ立ってんの!手に持ってるペットボトルのお茶を早くかけて!」
僕は彼女に言われるがまま、手に持ったペットボトルのお茶を火にかける。大体二百㎖程度しか残っていなかったから、あまり火消しの役には立たない。
彼女はバックを漁り、ペットボトルを二本取り出した。一本はコカ・コーラ。もう一本はただの水だった。彼女はその二本を思い切り火にかけた。しゅうう、と情けない音を立てて、火は鎮火した。
「はあ、良かった」
彼女はその場に力なくへたり込んだ。心なしか、瞳には涙が浮かんで見えた。
「良かった」僕も無意識に声を出していた。
「ありがとう。えっと、確か駒野、だったわね。同じクラスの」
僕はゆっくりと頷いた。
「ねえ、一個お願いがあるんだけど、このことは黙っててくれない?」
「このことって?」
「このことはこのことよ。ボヤ騒ぎになったこと。それと」
「煙草」と僕は先回りして言葉を告げる。
「正解。こんなこと学校にばれたら、バスケどころじゃなくなっちゃうのよ。こんなだけど、バスケだけはわりと本気なの」と彼女は言った。そして、ゆっくりと黒縁の丸眼鏡を外した。
「ねえ、飲み物奢るからさ。お願い」
彼女は両手を合わせて、いたずらな笑みを浮かべた。
僕らは燃えた公園の花壇を後にして、少し離れたコンビニ前のベンチに腰を掛けた。彼女は約束通りコンビニで飲み物を買ってくれた。僕はお茶を、彼女はコカ・コーラを購入した。僕はペットボトルのお茶に口を付けながら、先ほどの光景を思い出していた。
あの時、僕は学校からそのまま家に帰ろうとしていた。そしていつも通り下校途中にある公園をショートカット目的で横切っている最中、黒縁の丸眼鏡をかけた彼女と目が合った。彼女は公園の奥にある花壇の前で煙草を吸っていて、僕と顔を合わせると驚いたように目を見開いた。そして、手に持った煙草をぽとりと落とした。それだけならこんなことにはならなかったのだが、運悪く彼女が煙草を落とした真下には捨てられた新聞紙があったのだ。そのため落ちたと同時に煙草の火は新聞紙に着火し、先ほどのボヤ騒ぎに至ったわけだ。
「その顔は、まさか私が煙草を吸ってるなんて思ってもなかったって顔だね」
彼女はコカ・コーラを一口飲んで言った。
「思ってもなかったよ」と僕は答えた。
僕が彼女に抱いていた印象と言えば、黒縁の丸眼鏡が良く似合っていて、髪は黒く艶やかで重たい。顔立ちは整っていて、両の目は大きく二重。そして、見かけによらずバスケットボールに熱を入れる活発な女子生徒である、ということだ。確か「上野」という苗字だただろうか。
「上野さんはさ」僕が一口お茶を飲んでから口を開くと、「愛子でいいよ」と上野さんは言った。
「じゃあ、愛子さんはさ」
「だから、愛子でいいって言ってるでしょ。苗字で呼ばれるとか、さん付けされるとか、気持ち悪いのよ。今までずっと呼び捨てで呼ばれてたから」
愛子さんは大きな二重を薄く細めて僕を睨んだ。その視線は、僕が愛子さんに覚えていた何処か素朴な印象とは全くの別物だった。僕は愛子さんから視線を逸らし、ゆっくりとお茶を傾けた。僕の逃げた視線の先には、柔らかそうな雲が二つ青空の海を優雅に泳いでいた。
「えっと、じゃあ、あい、こ」
何の保護着もなしに彼女の名前を口にすると、先ほど潤したはずの口腔内は一気に乾燥した。僕はまたお茶を傾けた。今までの人生において、僕は女子を呼び捨てにしたことがなかった。
「そんなに声を震わせなくてもいいのに」と愛子は笑った。
「あんまり人を呼び捨てにしたことがないんだよ」
「なんかそんな感じがするよ」
僕らがそんな会話を繰り広げていると、目の前の駐車場に一台の車が停まった。白色の軽自動車だった。中から出て来たのは四十代くらいのくたびれた表情をした女性だった。女性がコンビニに入ると、中から「いらっしゃいませ」と大きな声が聞こえた。
「ねえ」愛子は一口コカ・コーラを飲むと、僕に目を向けた。
「ずっと煙草のことが気になってるんでしょ」
僕は頷いた。何故なら、僕の印象の中の愛子は煙草を吸うような不良少女ではないからだ。
「いつから、吸ってるの?」
僕が訊くと、愛子は当たり前なことをいうように「中学二年の時からかな」と言った。そして、「ほら、駒野も吸う?」とバックからマールボロのケースを取り出して僕に見せた。
「え、いらないよ」僕が咄嗟に首を横に振ると、愛子は笑ってマールボロをまたバックにしまった。
「そんなに焦らなくてもいいじゃん」と言い、愛子は足を汲んだ。
「いや。急に出すから」僕は律儀に両足を下ろしていた。
「私が煙草を吸い始めたのは、周りが吸い始めたってのもあるけど、一番両親への反抗かな。私の家は母子家庭なんだけど、当時お母さんが新しいお父さんを連れてきてね。私は元のお父さんが好きだったから、とても反抗したの。だって、嫌じゃない?全くもって知らない人と急に暮らせなんて言われたら」
「嫌だ」と僕は言った。
「それでね、反抗するために、私は煙草を吸って、髪を金髪に染めたの。派手なカラコンを入れたりしてね。でも当然、そんなの学校では受け入れてもらえないから、何度も親を学校に呼ばれたわ。当時もバスケは頑張っていたんだけど、髪を染めている子は部活に参加させられないって言われて、数か月バスケを休んだの。その数か月ちゃんと部活が出来ていれば、私のチームは全国に行けたと思う。なにせ、私がエースだったんだから。で、私が中三になるくらいで、お母さんと新しいお父さんが別れてね。これは私云々じゃなくて、二人があまり上手く行かなかったって言ってるけど、よく分かんない。私のことを考えて別れてくれたのかもしれないしね。それをきっかけに私は髪を黒に戻して、普通の中学生に戻ったってわけ。結局煙草は辞められなかったんだけどね」
話終えた彼女は掛けていた黒縁の丸眼鏡を外して、レンズを指先でとんとんと叩いた。
「本当はね、私は眼鏡なんていらないの。これは伊達眼鏡。でも、こうして少しでも真面目に見せていた方が印象いいかと思ってね。過去の教訓を生かしたの。不良少女を演じてた時は、先生の風当たりを強かったから」
「でも、その眼鏡も似合ってるよ」
「当たり前じゃない。私は美人なんだから」
僕は何と答えていいか分からず、意味もなくお茶を飲んだ。
「ねえ、駒野には私の煙草を学校にチクる権利があるけど、どうする?」
愛子は空に目を向けながら、無表情な声色で言った。
「言わないよ」
「じゃあ、もしも誰かに私と二人でいるところを見られていて、運悪く一緒になってボヤ騒ぎを起こしたと疑われたら?」
愛子の声はとても緊張感のある声だった。僕の返答によっては、愛子の高校生活が終わってしまうのだ。それは同時に、愛子のバスケットボールへの情熱を失うことを意味していた。
「もしそう言われたら、一緒にピカソの『ゲルニカ』をモチーフにした幾何学的科学実験をしていました。運悪く失敗してまるで「ゲルニカ」のような戦火を模してしまいましたが、って答えるよ」
「何それ」彼女は可笑しそうに噴き出した。
「ねえ駒野。あんたってもしかして、頭おかしいの?」
「場合によってはね」
愛子は顔を斜めに上げて、声を出して笑った。しばらく笑った後、愛子は「ありがとう」と言った。
「ねえ、ちなみにだけど、ピカソの『ゲルニカ』って知ってる?」
愛子は「知らない」と言う。
「そっか」と僕は答えた。
僕ら高校生の多くは、「ゲルニカ」について知らない。場合によっては、それは「戦争」を知らないことと同意義なのだ。それはとても危険なことだ。
そして、僕らは他人の心の奥で起きている「戦争」について知らない。例えそれが同じ教室内にいるクラスメイトであろうとも、知らないものは知らない。
それは現実に起きている「戦争」と同様に、とても危険なことなのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
