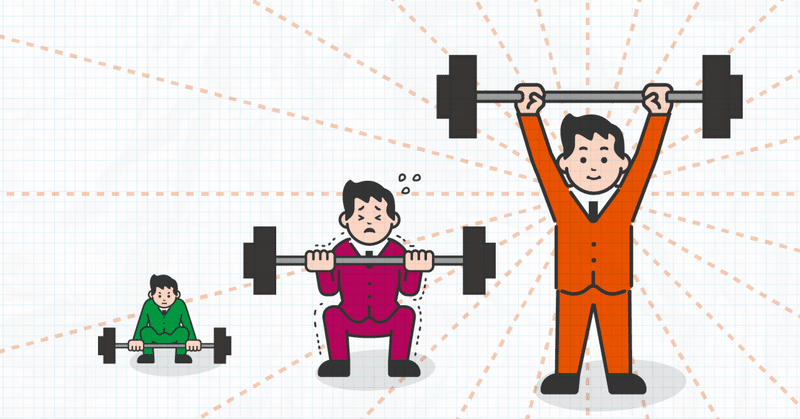
【2023→2024】CSがUIUXデザインを学んだら仕事がどう変わったかをダイアグラムにしてみた
2024年最初のnoteは2023年の振り返りから行っていこうと思います。
昨年はUXデザイナー(UXディレクター?)になるために日夜勉学に励む毎日でした。
(ようやく買えたPS5もかれこれ1年くらい封印している)
もちろん、勉強したことを実務で活かすために、CS業務を終えたら、
それ以外の業務時間で「ユーザーの体験を良くするにはどうすればよいか?」という問いに対する調査と改善、検証に取り組んでいました。
そんな2023年を過ごして、CS時代から現在の自分の仕事領域がどのように広がったかをお伝えしようと思います。
【2022年(CSのみ)まで】
2022年までの仕事の取り組み方はこんな感じでした。

元々「VoC起点でサービスをより良くしたい」思いの強いカスタマーサポートだったので、お問い合わせ内容やアンケートのフリーコメント欄を目視でカテゴライズして、見つけた課題を各チームに改善依頼はしていました。
CSはあくまでCSとしての仕事を、という圧力と見えない線引きを勝手に感じていたため、課題を見つけて報告したら「あとは担当者に任せた!」という感じで、基本的には顧客応対(コミュニケーション)の改善や応対顧客満足度の向上、CS業務効率化企画がメインの仕事で、サービス改善に深く携われている感覚はありませんでした。
ですが、その感じていた圧力や線引きは、後々勉強とチャレンジを続けていく中で、周りの環境のせいではなく、自分自身の知識の少なさ、経験のなさ(自信のなさ)によって作られた、思い込みによる諦念感であったことを知ることになります。
(ろくに勉強もしてないのに、やる前から「いくら自分がテスト勉強頑張ったって上には上がいるしきっと無駄。どうせ細かい部分を間違えて、合格なんてできない」と拗ねているような感じ)
UXライティングは、CSが担当する風習が職場に元々あったので、以前から独学で勉強していたことや、昔学んだ映像字幕翻訳(一画面に入る十数文字で場面を理解させるノウハウ)の知識が応用できたので、それを活かしてガイドラインを作成したり、FAQを修正したり、マイクロコピー作成の相談に乗ったりと、色々やってました。
単語の使い方で、ぱっと見たときの見やすさ(視認性)、テキストの読みやすさ(可読性)や文章の意味の分かりやすさ(判読性)が変わるのは、とても面白く、こだわりがいのある業務でした。
とくに漢字は象形文字なので、文字でデザインを描いているような感覚でした。
【2023年(UIUXデザイン学習開始後)から】
2023年にUIUXの勉強を始めて、覚えたことを実務で実践していたら、いつの間にか自分の仕事領域はこうなりました。

ユーザーの声(定性)や、サイト数値(定量)の両面から、課題を見つけては、自分でアイデアを出して、自ら改善を推進していく何でも屋になりつつあります。
2023年の間にあった変化は主に以下の通りです。
GA4でサイトのアクセスデータから課題を発見できるようになった
└ 7回くらいGA4のテスト落ちて、8回目でやっと合格しました。GA4でアクセス数やコンバージョン率をみて、課題のあるページの大まかな当たりをつけられるようになりました。
検証が必要な仮説に対し、自分でUXリサーチを実施できるようになった
└ お問い合わせやアンケートで分からないなら、直接聞いてしまおう、というスタンスになり、ユーザビリティテストやインタビューの企画から実査まで行うようになりました。
リサーチ結果を分析し、フレームワークを使って、改善案を提出できるようになった
└ リサーチした内容をKJ法や狩野モデルなどのフレームワークで分析し、
改善案の報告を受ける他のメンバーにも理解しやすいフォーマットで提案できるようになりました。
頭の引き出しを増やすため、毎朝1フレームワークをノートに書き写して頭に叩き込む作業を習慣化しました。朝からペンで文字や図、イラストを描くと、なんか頭がスッキリする感じがあって好きです。
デザインプロトタイプをFigmaで作成し、アウトプットイメージを共有しながら他チームに提案できるようになった
└ リサーチ結果によって、導き出された改善案がデザイン改善であった場合、自らFigmaでリデザイン案を作成し、ビジュアル付の改善案を提出できるようになりました(BONOで学んだUIデザインが活きています)
開発会社とリソース・コスト・スケジュールをしっかり確認しながら、サイト機能改善のディレクションができるようになった
└ これは本当にCS時代から、できる人にずっと憧れて勉強を続けていたので、うまくいったとき本当に嬉しかったです。ガントチャートや定期的なコミュニケーションで課題感を共有しながら、期日に間に合うよう、ばっちり開発会社さんやデザイナーさんに依頼できるようになりました。
顧客応対(CS)で、お問い合わせ内容の捉え方がこれまでと大きく変わった
└ これまでお問い合わせ内容は「インスタントに解決策を伝えなければならない困りごと」「誰かに改善してもらうためのレポート対象」といった感じだったのですが、いまでは「ユーザーにとってのよい体験を生み出すためのインサイト発掘の種」「リサーチ対象となる課題」「インタビューの話題」「自ら根本的な改善策を考える必要がある困りごと」という観点で見るようになりました。VoCを見る視点の深みが増しました。
常に4つの改善軸で課題の解決策を考えるようになった
└ これまでは漠然と解決策を提案してきたのですが、自分が行おうとしている改善はどういう課題に関する改善なのかを4つに分けて明確に意識することで、ブレずに集中して取り組みやすくなりました。他チームにも課題カテゴリと合わせて伝えることで、どのような課題に対する改善策なのかの解像度を高めることができています。
以下の4つに分類した課題への改善案として共有しています。
①コミュニケーション課題
└ CSの案内方法、回答スクリプトやテンプレートなど、ユーザー接客時のコミュニケーション方法に関する改善で解決できそうなもの
②コンテンツ課題
└ ニュースレターやLP記事、FAQなど、ユーザーが受け取るコンテンツ内容(テキスト)に対する改善で解決できそうなもの
③サービスデザイン課題
└ サイトデザインや、資材デザイン、UIライティング、サービスフローに関する改善で解決できそうなもの
④プロダクト機能課題
└ サイト機能や、商品の品質に関する改善で解決できそうなもの
上記で分けたものを、さらに2種類の改善軸に分類しています。
・コスト改善
└ コストを下げるための改善(ツール効率化など)
・プロフィット改善
└ 満足度や利益を上げるための改善(コンバージョン率UPや新規顧客獲得など)
マーケティングチームの取り組みを補完するために発想する感覚が身に付いた
└ 売り上げやコストに重きを置くビジネスサイドの人間の考えと、ユーザーの満足に重きをおくサービスサイドの人間の考えは、水と油になりがちですが、本来はその両軸のどちらもが大切であり、どちらかの考えに大きく偏りすぎると、そのサービスはいずれ顧客離反かリソース枯渇により継続していくことができなくなるかと思っています。
CS時代はあくまでサービスサイドを代表して物申すスタンスだったのですが、学習とディレクションを行っていく中で、お互いが協力体制を築き、互いに利益を循環させられる関係になることが大事であるという考えに至りました。現在ではマーケティングの取り組みがより成功する方法を考えつつ、さらにユーザーにも満足してもらえる方法は何か?という2軸思考が強くなりました。
直近だと1to1マーケティングがしたいマーケティング部と、パーソナライズ対応したいCSの双方のニーズがマッチしたので、それを叶えるためにCRMツールの導入を推進しました(どういった機能要件が必要かは何度もすり合わせを行いました)
【身に付いたことの代償】
着々と勉強の成果が出ているのですが、朝から晩までPCのモニターを凝視しているので、代わりに視力が1年でとても悪くなりました。新調したメガネの度数が前より0.2度分くらい上がった。目の下のクマもすごい。。。
なので今年はホットアイマスクで目を癒したり、森林浴など、ちゃんとケアの時間も取り入れようと思います。。。カラダ大事。
【まとめ】
去年1年間、UIUXの勉強は8月から始めたので、約4カ月で自分の仕事の領域をここまで広げることができました。
2024年になり、ひと月が経とうとしていますが、今年も引き続き広がった領域で勉強を続けながら、実践を積んでいます。
できる仕事が増えると、視野が広がり、視座が高くなって、これまでは考えられなかった発想もできるようになることを身をもって知りました。
つらいこともあったけど、しっかり自分を見つめ直して、やりたいことをとことん棚卸しして、UIUXデザインを見つけられて本当によかった。
現状に満足せず、初心を忘れず、今年もがんばるぞ💪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
