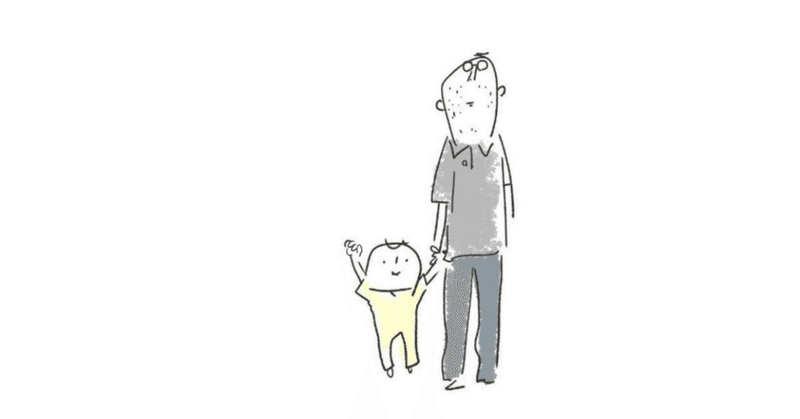
共同注意について
お久しぶりです。
月1更新と言っていたのにもう3月になってしまいましたね。
今回のテーマは「共同注意」です。
共同注意と言われる行動の例としては、お子さんが大人の視線や指差しを追って対象に注意を向けたり、お子さんから指差しや物を見せるなどして大人の注意をひく行動です。
子どもの発達において共同注意は、他者から学ぶための土台となるスキルと言えます。ある研究では、乳児期の共同注意の量や質がその後の言語発達を予測すると言われています。言語発達だけでなく、コミュニケーション全般の発達を促進するスキルと言えます。
早期発達支援プログラムであるJASPERでは、共同注意をこう定義しています。
共同注意とは、共有することを目的として、物や人の間で注意を共有することです。共同注意は単なる1つのスキルではなく、子どもが自分の経験について他人とコミュニケーションをとるのを助ける一連のスキルです。
つまり共同注意とは、物や活動を得ることを目的ではなく、他者と共有することを目的とした行動と言えます。
要求≠共同注意
「要求と共同注意は違う」
ここに注目することが共同注意を理解するための手がかりになるのかなと思います。
「要求」とは文字通り、物(食べ物、玩具など)や活動(お出かけ、ゲームなど)を要求し、手に入れることを目的としています。
「共同注意」は、他者に見てほしい、他者が見ている物を見たいなど他者の注意を目的とした行動です。
要求と共同注意は目的が異なるという点が大きな違いです。同じ指差しでも、棚にある食べ物が欲しいための指差し(要求)なのか、お空の上の飛行機をお母さんにも見てほしいから指差し(共同注意)なのかでは大きく違います。
それでは、次に共同注意はどういった形で発達していくのか見ていきましょう。
共同注意の発達
生まれてすぐの乳児まだ視力も弱く、意図的に自分の体を動かすこともおぼつかないため、共同注意ができないのは当たり前の話しですね。
運動発達的にも首がすわっていない状態では、頭を動かして注意をあちこちに向けることも難しいです。以下に共同注意が発達するまでのおおまかな段階について記載します。
◆2〜4ヶ月(2項関係)
大人とのアイコンタクト
◆6〜9ヶ月(2項関係)
子どもの注意を大人が追うようになる
◆9〜18ヶ月(3項関係・共同注意の獲得)
他者の注意がどこに向いているのか視線や指差しを追うようになる。
自分が関心を持っている物を指差しなどの身振りを用いて伝える。
◆18ヶ月〜
言葉を獲得し、言葉でのコミュニケーションが増える
典型的な発達では、こういった流れで共同注意が発達してきます。
生まれてからの数ヶ月は、自分ー物、自分ー他者という2つの関係性の中で関わりを構築していきます。赤ちゃんが玩具を手にし、夢中でなめたり振ったりしているときには玩具へのみ注意を向けます。反対に大人に抱っこされているときには大人へのみ注意を向けます。3項関係と比べると2項関係のときには、注意の調整が限定的であると言えます。
共同注意が成立しはじめる9ヶ月以降になると、玩具で遊びながらも大人の視線を確認したり、大人が指さした先にある物を追うなど、自分ー物ー大人の3項関係が成立したと言えます。
発達心理学者のトマセロはこの共同注意の成立を「9ヶ月革命」と名付けています。それほど、発達にインパクトのあるスキルを獲得したと言えますね。
今回は「共同注意」をテーマに書いてみましたがいかがだったでしょうか。感想も募集中です笑
「共同注意」はなんとなく分かったけど、じゃあ自閉症のあるお子さんなど社会性に特性があり、共同注意が成立しづらいお子さんに対してはどうしていけば良いのか?という疑問もあるかと思います。
いずれ、その点についてもまとめて書きたいかなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
