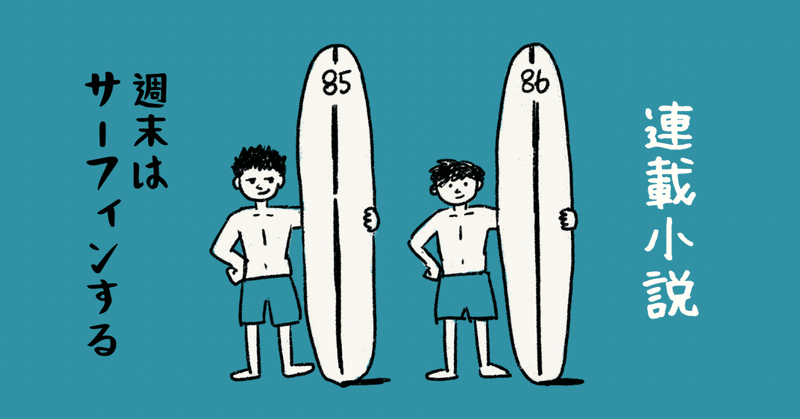
連載小説 | 週末はサーフィンする #7
《あらすじ》
システム会社に勤めて7年目の鹿島友紀。
会社にはなんの不満もないが、自分の人生はこのままでいいのかと考え始めていた矢先、上司から鎌倉・七里ヶ浜へ出張しないかと声をかけられる。
七里ヶ浜のゲーム会社の社長、南田さんはとても魅力的な人物で、趣味のサーフィンを一緒にしないか、と誘われる。
即断即決の南田さんに促されるように、鹿島は毎週末、サーフィンを習いに行くことになる……。
▼前回の話
ひさしぶりに江ノ電に揺られていた。
9月初旬。江ノ電の窓から見える海面はまだ、目一杯の光を浴びてキラキラしている。
ここはやはり懐かしい場所だな、と思った。
昨日まであんなに仕事のことで頭がいっぱいだったのに、あんなに焦って仕方なかったのに、海を見たら全部吹っ飛んだ。
早く、早く。この海と風を体で感じたいと心が踊っている。
七里ヶ浜駅の改札を降りて、駆け足で海岸へ向かった。横断歩道を渡り、階段を降り、砂浜に降り立つと、海が眼前に広がった。
波がきらきらと反射し、波に乗ったサーファーたちは光の中に消えていく。おれは息を大きく吸い込んで、目を瞑った。太陽の暖かさと、爽やかな潮風がおれを快く迎えてくれた。
「おかえり。待ってたよ」
目を開けると、片手にサーフボードを持った誰かが逆光の中で立っていた。よく見ると、相変わらず肌の黒くて爽やかな南田さんが白い歯でニカっと笑っていた。
「南田さん!」
「目立ってたよ。スーツ姿で立ってるから」
「えっ」
周りのサーファーたちの視線に気づく。確かにおれは場違いな格好であると気付いた。
「まぁ今日は仕事ですから……」
「そうそう、忙しいところよく来てくれたね! 助かったよ〜」
先日の電話は南田さんからだった。
システム障害が起こったから助けてほしい、というヘルプの電話だった。
本来なら、引き継いだ後輩の仕事だったが、『任せるには少し不安があるため自分が行きたい』と課長に申し出たのだった。
「鹿島くんが来てくれてよかったな〜」
ボードを乗せた自転車を押しながら、南田さんが笑う。
本当は、たぶんおれじゃなくてもよかった。でも、南田さんが作ってくれたきっかけを無駄にしたくなかった。
「呼んでくれてありがとうございます。おれ、たぶんこんな事がなきゃ一生会社から出れませんでした」
「そうなの? 仕事が楽しくて忘れられたかと思ってたよ〜」
南田さんがからかうように言う。
「んな訳ないでしょう! ボードだって買ってからまだ一度も使ってないのに……」
「ああ、そうだったね」
はぁ……とため息をつくおれに、南田さんは肩を叩いた。
「大丈夫、波は逃げないから」
「……そうですね」
そう、おれが仕事を早く終えて、余裕を作れればいつでも来れるのだ。
「おれ、もっと頑張ります……!」
そう見上げると、南田さんは俺の顔を見て複雑そうな顔をしていた。
「……?」
『キキッ!』
自転車のブレーキ音が響く。南田さんが急に停まった。まだ会社には着いていないのに。
「どうしました……?」
「俺、腹減っちゃってさ! 早いけど先に昼休憩しない?」
「え、ああ! 全然いいですよ、おれも朝飯抜いてきちゃったので」
「よかった!」
南田さんはニカっと笑った。
「わっ! すごい!」
潮風にさらされた木造の階段を登ると、視界一面が海になった。
「ね、いいでしょう」
後ろから登ってきた南田さんが自慢げに話す。
南田さんの行きつけのバーガー屋「BIG BURGERS」は134号線を挟んだ海沿いに建ち、二階全面がテラス席になっている開放感溢れる場所だった。木造のカウンターテーブルに座ると、もう目の前は海しか見えない。高いところからこうやって海を眺めるのも、なんだか新鮮な気分だ。
間もなくハンバーガーが運ばれてきた。大きな皿の半分は山盛りのポテト、店名の通り、ハンバーガーはかぶりつけるのか不安になるほどのBIGな大きさだ。肉厚なパティに溢れるアボカド、とろけるオレンジのチェダーチーズ。
「いただきまーす」
嬉しそうにバーガーを両手に持ち、南田さんは一思いにかぶりついた。口いっぱい頬張りながら、満足そうに「うん、うん」と頷いている。
「いただきます!」
おれも続いてかぶりついた。
うまぁ……!
肉汁が口の中に流れ出し、スモークの効いた牛肉の旨みがガツンと口いっぱいに広がってくる。アボカドのクリーミーさとBBQソースが良いハーモニーを作りだしている。
「うまいでしょ」
「うますぎて幸せです!」
「そりゃよかった」
南田さんは満足そうにそう答えた。
「最近、休みはどうしてたの?」
一瞬ドキンとした。
「……そうですね、ひきこもってゲームばかりやってました……」
ああ、なんだか言葉にすると罪悪感が出るものだな。
「へぇ! 鹿島くん、ゲーム好きなんだ?」
「ええ、昔からよくやってますね」
「どんなのやるの?」
「えーと、好きなのはFFS9とか、RPGが多いです」
「FFS9いいよねぇ、おれも好き」
「いいですよね! 特に海のシーンのグラフィックが幻想的で好きで! ゲームやってると、自分を異世界に連れてってくれる感じがして、なんだか癒されるんですよねぇ」
いわゆる現実逃避かもしれないが、外に出るのが億劫だった自分にとってはありがたい癒しになっていたのだなと感じる。
「うんうん、おれもFFS影響でRPG好きになって、それでかな。昔うちで作ってたのはRPGが多かったな」
「スマホのアプリゲームですよね。おれあまり詳しくないんですけど、どんなの作ってたんですか?」
「一番力入れてたのは『海釣りキング』ってゲームだね」
「えっ!」
おれは一瞬、耳を疑った。
「『海釣りキング』はさすがに知ってますよ! 大学生の時、友達みんなやってましたもん!」
「嬉しいなぁ。頑張って作ったからね」
「ええ、まじで南田さんが作ったんですか……? まじか……すげぇ……」
「ははは、ありがと〜」
「船で世界を旅しながら魚を集めるって、めっちゃワクワクしましたもん!おれだいぶ集めましたよ、レアフィッシュ!」
「そうなんだ。……楽しんでくれてたのに、ごめんね」
南田さんの笑顔が少し曇った。
「あ……いや……」
しまった。
そうだった、『海釣りキング』は人気に火がついて2年も経たず、急にサービスを終了してしまったのだ。人気のスマホゲームは5年〜10年プレイし続けるプレイヤーはたくさんいて、ロングセラーになるのが普通だと聞いたことがある。
それが急に終わったものだから、せっかく頑張って集めたレアフィッシュたちが全部消えてしまって、嘆き悲しむ友人や子供たちがたくさんいた。おれもその一人だ。
《1回この会社潰れてるんですよ、渋谷にあった時ですね。……社長と仲良いから聞いているかと思いました》
木本さんが言っていたことはこのことか。
「あの……すみません……」
「いや、いいんだ。今日はこの話をしようと思ったんだ」
南田さんはそう言って、にこっと笑った。
「え?」
いつも南田さんの考えていることは読みきれないが、今回は特にわからなかった。
「海っていいよね。おれも元々海が好きでさ」
南田さんの目線の先には、波を待つサーファーたちが一列に並んでいる。一人一人が小さな人形のように小粒に見える。今日の波はとても穏やかだけど、たまに大きな波が出来る。水平線からやってくるその波は、1つのきれいで真っ直ぐな線となって、サーファーたちへ向かっていく。
「小さい頃、よく親父に海釣りに連れて行ってもらってた。テトラポットに登って、上から釣竿投げて、目の前の水平線をじっと見ながら何が釣れるかわくわく待ってた。だから思いついたんだろうね、釣りのRPGなんて」
押し寄せた大きな波に数人が果敢にトライする。
次々と失敗し、波の中へ飲まれていく中、乗ることに成功したたった1人のサーファーは気持ちよさそうにライディングしている。
「『海釣りキング』は確かに成功したんだ。小さな会社だったけど、創業時のメンバーはみんな優秀で、みんな努力家で。絶対日本一のゲーム作るぞってでかい夢を掲げて、全力で走ってた。だから、『海釣りキング』のダウンロード数が日本でNo.1になった時は、嬉しくてみんなでビールかけあってバカ騒ぎしたりしてね」
南田さんは青春時代を懐かしむように、遠くを見て優しい目をしていた。
「でもそこがピークだった」
波は徐々に小さくなり、推進力を失ったサーファーはやがて海に身を投げ出した。
「おれは次はもっと凄いゲームを作りたくなった。それこそFFSのような、グラフィックがきれいで、クオリティの高いものをね。だから、『海釣りキング』の売り上げはほとんど全部、次のゲームの開発に投入した。社員も一気に増やして、会社も渋谷に移転して、でかくなった。傍目からは順調そうに見えたと思う。おれもそう思ってた。でも、みんなは違ったんだ」
南田さんの顔から笑顔が消えた。
「みんな、『海釣りキング』が売れた時点で燃え尽きてたんだと思う。そのことに当時のおれは気付かなかった。急に売れた『海釣りキング』の対応に追われながら、新入社員の教育をしつつ、新しいゲームの開発や新技術の勉強会。おれは毎日わくわくして、疲れ知らずだったから、そのペースにみんなを付き合わせてしまった。特に古株のメンバーへの負担が凄かったんだと思う。当たり前のように、残業して終電で帰って、休日も返上して対応してくれてた。みんな努力家で真面目だったから……」
努力家で真面目……。たぶんおれもそうだ。それにみんな南田さんに信頼して着いてきているんだ。おれがもし社員だったら、南田さんが頑張ってるんだから、おれも、って同じように頑張っていた気がする。
「最初に辞めたのは副社長だった。一緒に創業したパートナーで、一番頼りにしてたんだ。だから一番キツかったんだろうね。相談もなく、ある日突然、辞表を出されたんだ。『会社だけじゃなく、子供の成長も見守りたい』って。当たり前だよね、みんな家族がいたり、プライベートもあるんだ。そこから創業時のメンバーは次々にいなくなって、最後はおれ一人になった」
南田さんは話を続ける。
「それでもなんとかやって行こうと思った、けど今度はおれが倒れてしまってね。みんなが去ってしまったことがショックで、精神的に来てしまったみたい。結局ドクターストップがかかって、会社はそこで解散することになった」
「……そうだったんですね」
一生懸命努力した事業が成功して、さぁこれからというところで、仲間に去られてしまい、会社がなくなってしまった時の南田さんの気持ちは、おれにも想像もつかないが、さぞ辛かったことだろう。でも……、
「でも、なんでもう一度会社をやろうと思えたんですか?」
おれだったら、きっと立ち直れない。また同じ轍を踏むのが怖いから。
「それはね、サーフィンがきっかけなんだ」
「サーフィン?」
「うん。おれ、会社が潰れてから、ずっと引きこもってたんだ。みんなを不幸にしてしまった、って自分を責めてしまってね。おれがもっと頑張ってたら会社は潰れなかったのに、って。こうすればよかった、ああすればよかった、って後悔しか浮かんでこなくてね。そしたら、だんだん何も気力が湧かなくなって、家から出れなくなっちゃった。そういう日々が1年くらい続いてね」
南田さんにも引きこもった経験があったんだ。
普段の南田さんからはとても信じられないけど。
「それで、ある時、古い友人が電話かけてきてくれて。ふわふわってした声で、『暇してんなら、サーフィンしよ〜ぜ〜』って誘ってくれたんだ。徳ちゃんっていうんだけど」
「徳ちゃん……って。あ! まぐろ丼の徳次郎さんですか?」
「そうそう。あまりにふわふわ〜って言うもんだから、こっちも気持ちが軽くなってね。重い腰あげて湘南に出掛けたんだ。学生ぶりに海に来て、徳ちゃんのボード借りて初めてサーフィンやってみたら、見事に下手くそで」
「え! そうなんですか? めちゃ上手いのに……」
「いやいや、小さい波なのに、全然立てないで、何度もひっくり返ってたよ。頭から海に落っこちて、巻かれて、めっちゃ疲れるんだけどさ。なんか悔しくって何度も挑戦してた。で、海から上がった後は全身疲労マックス。そしたら、徳ちゃんが飯ごちそうしてくれるってんで、ご実家でまぐろ丼作ってくれてさ。それがめちゃくちゃ旨かったんだよね」
確かに、徳次郎さんのまぐろ丼はめちゃめちゃ美味かった。
でもそれはまぐろ丼が旨いのもあるけど……。
「徳ちゃんが言うんだよ。『サーフィンして旨い飯食ったら、辛いこと全部忘れるくらい幸せになれる』って。俺、気付いたらまぐろ丼食べながら泣いてたの。旨すぎて泣くのって初めてだったよ」
そうだ、旨いものって人を幸せにしてくれる。それはおれも徳次郎さんのまぐろを食べて感じたことだ。それが辛い時なら、なおさら。
「そこから毎週サーフィンに通うようになったの。だんだんとね、おれ海好きだったなって思い出して。それで引っ越してきちゃった」
「なるほど。その時に会社も立ち上げようと思ったんですか?」
「それは、きっかけは木本くんかな」
「木本さん?」
あのそっけないメガネの木本さん……?
「木本くん、その時はまだ入社したての新人だったんだけどね。解散する時に言ってくれたんだ。『また立ち上げる時は声かけてください。自分は南田さんの作るゲームのファンなので、待ってます』って」
「へぇ……」
木本さんと南田さんの間には見えない信頼関係があるんだな。
それってすごく素敵なことだ。
「ああ、待ってくれる人がいるんだ、って。それで、いつかまたやらなきゃいけないってずっと思ってた」
「怖くなかったですか? また会社を立ち上げること……」
「おれ学んだんだよね。一番大事にすべきは周りの人たちなんだなって。創業メンバーたちと一緒に夢を追いかけられたこと、徳ちゃんに励まされて復活できたこと、木本くんが信用して待っててくれたこと。今のおれがいるのは、すべて周りの人のおかげだった。おれはずっと『凄いゲームを作ること』が大事だと思ってた。もちろん目標は必要だけど、それによって、周りの人が苦しくなってしまうのは、間違いだったんだ。この年になってその事にようやく気付けた」
おれは黙って聞いていた。
いまの南田さんがあるのは過去に出会った大事な人たちのおかげで、おれもきっとそうなのだろう。
「それにね、一番は自分を大事にしなきゃいけない。周りの人と同じようにね。おれは仕事ばっかしてたせいで、視野が狭くなっちゃって、いま自分が辛いのか、幸せなのか、どうしたいのかわからなくなってた。おれには、ゆっくり自分を見つめる時間が必要だった。それができると思って、おれはここに会社を構えたんだ」
「そうだったんですね……」
ふと思った。
おれはどうだろう? いま自分を大事にできてるだろうか?
「だからね、おれは今の鹿島くんが心配なの」
「おれ……? ですか?」
「うん。今の鹿島くんは、前のおれとおんなじ顔してるんだよね」
「え……」
「おれね、こっちに住んでから人との縁を大事にするようになったんだ。一人一人、その人とおれが出会った意味を考える。インスタントな関係じゃなくてね、きっとあるって前提で接するんだ。そうすると、その人の事がよく見えるようになる」
「……じゃあ、おれと南田さんが出会った意味も、あるんでしょうか」
「あると思うよ。だからサーフィンに誘ったんだ」
南田さんと初めて会った時のことから、今までのことを思い返した。
「……おれ、海が好きだったなって思い出しました。新しいことにわくわくする自分や、もっと自由でありたいって思う自分とか、今まで知らなかった自分をここに来て知れた気がします。それはたぶん南田さんと出会ったから……」
「うん、それなら良かった」
「でも……今、また戻りつつあって。なんか閉じていく感じがするんです。せっかく南田さんに会って、サーフィンが好きになって、幸せな日々だったのに、それって夢だったんじゃないかなって。現実に引き戻されるんです。それは、社会人だから仕方がないのかなって、思ってしまうんです」
「そうなんだ」
「はい……」
南田さんは「はははっ」と笑った。
「真面目だな〜、鹿島くんは」
「真面目、なんですかね……」
「どうせ真面目になるならさ、真面目に人生楽しんだらいいんじゃない?」
「……真面目に人生楽しむ?」
「そう。鹿島くんはどうやったら、自分の人生楽しめるかなって、真面目に考えた事ある?」
思わぬ問いに、空を見つめて数秒考えてみたが……
「……ない……かも」
南田さんニカッと笑った。
「それなら一度、ゆっくり考えてみることをおすすめするよ」
そう言って、残ったバーガーを口に放り込み、満足そうに微笑んだ。
《つづく》
お読みいただきありがとうございます。
▼最終話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
