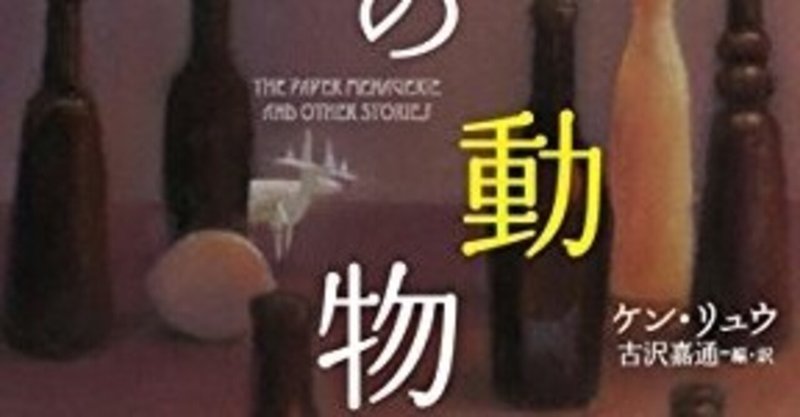
ケン・リュウ『紙の動物園』-多作なテッド・チャン-
『折りたたみ北京』『三体』以来、僕には中国SFを見かけるたびにポチっておく習性がついているようだ。特異な世界観、奇抜な着眼点、奇想天外な展開がギュッと濃縮された短編SFの愉しみは、長編小説とは違った面白さがあって、定期的にハマってしまう。学生の頃は阿部公房やフィリップ・K・ディックあたりを虫食い的に読んでいたが、ここ半年くらいは中国、日本の短編SFアンソロジーを目についたものから読み漁っている。ちなみに僕は、あの超大作『三体』シリーズも、中身は様々なアイデアが詰まった短編小説の見事な融合体だと思っている。VRから異星人から宇宙旅行から脳科学から未来世界から、あらゆるSFジャンルが楽しめる欲張りセットだ。
そんな『三体』の英訳者でもあるケン・リュウの短編アンソロジーが『紙の動物園』。中国文化、東洋文化(日本含む)、アメリカ文化が時に混じりあい、時に反発するような世界観を下敷きにした読み応えのある作品ばかりで、時々テッド・チャンの作品に似た情感を感じさせる作品集だった。
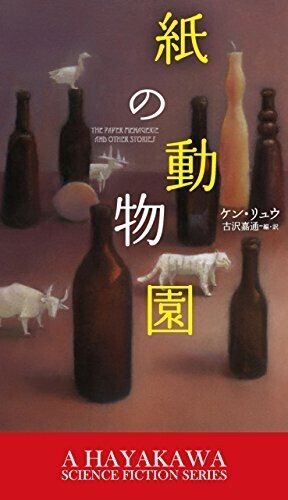
紙の動物園
アメリカ人の父と、結婚斡旋業者によって出会った(買われた)中国人の母の間に生まれた主人公の、アイデンティティの微妙な揺れ動きと家族、特に母親とのすれ違いと和解を描いた作品。主人公が幼いころ、母親が紙を折って作った動物たちを通して、中国人の母親の人生と息子への愛が明らかになっていくクライマックスの展開は物悲しくも美しい。
もののあはれ
人類滅亡の危機に瀕した地球から脱出したアメリカ製宇宙船で生活する日本人の青年の物語。ストーリー展開自体はハリウッド映画的でそこまで目新しいものはないのだが、「もののあはれ」をはじめとする日本語の解釈や囲碁を巡るエピソードなどが物語に深みを与えている。この短編集の中では一番原語の英語版で読んでみたい作品かもしれない。
月へ
善悪二元論的正義感の強い見習い弁護士が、中国からアメリカに亡命した家族の難民申請を担当し、家族から中国で受けた迫害のエピソードを聞かされるが・・・という話。それと並行して月人を巡るファンタジックな寓話が挿入される。
結縄
複雑に絡み合う縄の結び目を用いた文字体系を用いる少数民族の持つ、世界の認識体系を、これまた複雑に絡み合った遺伝子情報を解きほぐす製薬業界のイノベーションに活用するという、突飛なアイデアが光る作品。一方で、非西洋世界における伝統技術や知恵を西洋世界が自身の発展のために搾取していく構図も皮肉に描かれているビターな読後感でかなり好みの作品。
太平洋横断海底トンネル小史
もし第二次世界大戦後に太平洋横断海底トンネルという世界的な大事業が行われていたら、というIFストーリー。光の届かない海底トンネル内の駅における人間模様が描かれるのかと思いきや、闇に葬られたトンネル工事中の真実が明らかになっていく。中国現代史の闇が見え隠れする作品。
潮汐
どんどん月が地球に近づいていて、潮汐の力が次第に大きくなっている世界で、月-地球の関係と父-娘の関係が並列的に描かれる超短編。ストーリーや世界観は良く分からないが、勢いで読ませる作品。
選抜宇宙種族の本づくり習性
様々な宇宙種族の、本に関する習性(言語体系、読書の仕方、読書のスケール等々)を百科事典的に書き連ねた作品。ストーリーはほとんどないようなものだが、空想科学読本のような想像力の面白さが際立つ作品。
心智五行
人間の思考は実は人間の体内に無数に存在する細菌、バクテリアによってコントロールされているかもしれない、というアイデアは伊藤計劃/円城塔の『屍者の帝国』にも似たようなものがあった。現実世界でも腸は第二の脳みたいな話はされるし、人間の性格なんて精神に作用する薬ひとつで一発で変わってしまうものなので、この作品で書かれている話は割と真実味が高いのかもしれない。ストーリー展開は未開文化への接触と搾取、という上の「結縄」に似た構造を宇宙スケールに拡張したもので、なんだかざわざわする読後感。
どこかまったく別な場所でトナカイの大群が
多くの人間が身体を捨てて電脳空間におけるバーチャルで不死の存在になった世界における、完全にバーチャル化した娘と、いまだ自分の身体を持ち続けて「死」という確実な未来を待つ母のロードムービー的な作品。この次の「円弧」「波」もそうだが、「不老不死」というモチーフに対して、必ずしも否定的ではないノスタルジックな筆致を感じるのは、中国文化という下敷きがなせる業なのだろうか。
円弧
これも「不老不死」系の作品。10代で妊娠・出産し、子供を捨てて男と当てのない旅に出て、死体を永遠に残るモノとして加工するデザイナーとなったのち、開発された不老不死技術を自らに適用して若さを保ったまま生き続ける主人公の半生を描いた物語。波乱万丈な人生と比べて凪のように静かな筆致で語られる不老不死という生き方は、生まれてから死ぬまでという円弧=人生の姿を鮮やかに描き出す。
波
合間合間であらゆる古代世界における創世記の物語を挿入しつつ、宇宙船という閉鎖空間と移住先の惑星における不老不死の在り方(成長固定、機械化、電子化)と文化・価値観の伝承及び革新を描く。宇宙船という閉鎖空間×不老不死という魅力的な新技術⇒血で血を洗う争いの勃発、とハリウッド的展開に毒された僕などは安直に考えてしまうが、そうはならないのが本作の面白いところ。
1ビットのエラー
テッド・チャンの作品に似たような話があったよなー、と読みながら思っていたが、著者付記にてケン・リュウ自ら、テッド・チャンの「地獄とは神の不在なり」という作品にインスパイアされたと書いている。テッド・チャンの方は、射程圏内の人間に奇跡をもたらす一方で、その周辺の人間に死を含む災厄をも同時にもたらす「天使」を巡る信仰の物語だったが、本作は天使のもたらす奇跡と災厄にSF的な設定を加えつつも、信仰譚としても成立させており、これはこれでとても面白い作品。
愛のアルゴリズム
人間が機械を機械として判別できるか?というチューリング・テストを下敷きにした、機械人形を巡る物語。これはわりとベタなストーリーかな、と思った。
文字占い師
中国や台湾の現代史をほとんど知らないので、どうしてもこのあたりの背景をちゃんと理解できないことがもどかしい(エドワード・ヤンとかホウ・シャオシェンの映画を観るときもそう)。漢字や英語を用いた文字占いというギミックを用いた老人と少女の交流譚かと思いきや、めちゃくちゃ重たくて非道な話に展開していく。誰も救われない拷問の場面は読み進めるのが苦しいほどのおぞましさ。
良い狩りを
妖狐と人間の触れ合いを中国・香港の急速な近代化・脱魔術化を背景に描く物語。何とも微笑ましい妖狐との交流は、日本のライトノベルやアニメ感もあって親近感の沸く筆致だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
