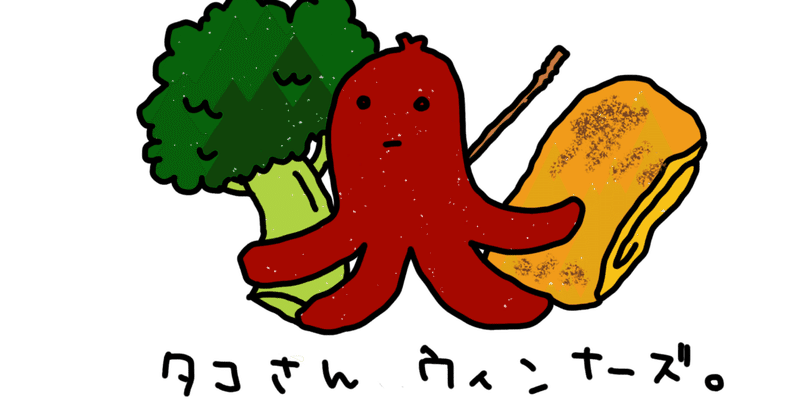
サンドイッチとウィンナー 2
惜しい試合を落としてもっとガッカリするかと思ったのに、頼子はいたって元気だった。みんなが慰めても「なんのなんの。高校行って国体出るから」なんて叫んでる。相変わらず素振りと腕立ては欠かさないようだ。受験のことはまだ頼子には黙っていた。自分の心は決まったが、夏休みが終わって胸を張って勉強したぞと言えるまで、秘密にしておくことにした。
「うちは中高一貫だが、高校入学はひとつのけじめとして考えてほしい。この夏休みはしっかりと勉強するように。休み明けには五教科の到達度テストするぞ」
矢ガモの言葉に、みんな一様にエーっと声を上げる。でも本気色は薄かった。私はまた自分だけ違う世界にいるように感じた。受験組ももしかしたらいるのだろうが、みんなと合わせて反応しているのだろう。私とはキャリアが違う。
帰り道、頼子が夏休みの予定を訊いてくる。
「ねっ。どっか行く?」
「どこも。勉強する」
「勉強!? だって試験終わったじゃん」
「到達度あるし」
「そんなん夏休みに遊びほうけさせないためのホーベンだって。知ってるでしょ。うそもホーベン」
「知ってる」
「まあ、あんた勉強に目覚めたみたいだから、それはそれでいいけど、あんま頑張りすぎっと後でガタくるよ」
私は笑った。でも、その問には答えなかった。
お父さんからは夏期講習の話も出た。受けたいんなら受けてもいいぞとも言ってくれた。でも、断った。受験は自分だけの力でやりたかった。それが自分のけじめのような気がしたから。
夏休みから私は図書館に通った。二階の隅の机で必死に辞書のページをめくった。
「おっ。勉強してんじゃん」
私に言われてるとは思わなかった。向かいの椅子が引かれる音で顔をあげた。いつかの男の子が私を見ている。
「ねえ、どこの学校?」
ナンパか。私は無視した。
「相変わらずオッカネーな」
鞄から勉強道具を出して机に並べ始める。チラ見したとき、英語の辞書が同じなのに気づいた。前の時は分からなかった。同じ辞書でも、男の子のは、端の方がめくれてすり切れてすっかり貫禄がある。私の視線に気づいて男の子が言った。
「あっ、これカッコイイでしょ。いかにも勉強してますみたいで。これツバつけて何回もペラめくりしたんだぜ。へっ、無駄な情熱ね」
一人で話してる。そのうち私の辞書にも気づいた。
「あれ、もしかしてオソロ?」
「ウルサイよ。みんな静かにしてんだから黙ってなよ」
相変わらずデリカシーのないやつだ。
男の子はまた「オーコワ」をやって勉強をはじめた。
暫くして、また男の子が話しかけてきた。
「あのさ、アドバイスしていい?」
「なによ」
「おまえさ、考えすぎ」
「なにが」
「ひとつの問題で考えすぎ」
「どういうこと」
「数学なんてパターンなんだからさ、わかんなかったらそんな考えてないで素直に解答見んのよ。そんで、日を置いて、も一回やるの。その方がノーリツ的だぜ」
言われると確かにその通りかもしれなかった。悔しいような気もしたが、そういう考えもあるのかと納得する気持ちの方が強かった。
「ドモね。やってみる」なるべくそっけなく答える。
男の子は嬉しそうにウンウン頷いて、また勉強を始めた。
午前中いっぱい私たちは無言だった。前のときは男の子の出すかすかな音を聞いてずっとすごしていたが、今日は私の動かす鉛筆の音も聞こえた。男の子の鉛筆の音と自分の音と重なって、二人で協力して同じ作業をしているような錯覚がした。図書室のクーラーは絞ってあって、少し汗ばむ。私は時々ハンカチを額に当てた。
十二時になったとき、不思議なことに二人同時に鉛筆を置いた。目があって、私は自然に笑えた。
「ジュースのみに行こうか」私の口から勝手に言葉が漏れる。
「今日もコーヒー?」ずっと友達だったように男の子がそう言った。
「うん。今日もコーヒー」
休憩室で、男の子は関口隆司と名乗った。私も自分の名前を教えた。男の子はまたサンドイッチを持ってきていて、ひとつもらった。キュウリのサンドイッチはおいしかった。
「もしかして中三?」
「そう」
「俺も。じゃ、お互い受験生なわけだ」
「うん」
「夏季講とか行かないわけ?」
「いかないわけ。いろいろあってね、自力勝負で受験したいの」
「へえ、いろいろね」
「関口くんは?」
「俺ん家は金がないから必然的に自力勝負なわけ」
「ふうん」
「いまどき珍しくもないけど、母子家庭だからさ」
「そうなんだ」今時珍しくもないって、うちの学校ではどうだろう。いまどきだから、母子家庭もあるにはあるんだろうけど、私立入れるくらいだから経済的に難しい家はないんだろうな。だから母子家庭とか表面に出てこないんだろう。そういえば小学校の時、学年が上がると同時に名字が変わる子がいたっけ。
「でも夏季講行けんのに行かないなんて、もったいないねえ。俺なんてソッチョクそう思っちゃうけど」
「まあ、そこんとこは人それぞれってことで」
「で、どこ受けんの?」
「都立」
「まあ俺も都立だけど、どこよ」
口ごもった。都立とは決めてるけど、どこって具体的な学校までは決めてない。
「まだ決めてないの」正直に言った。
「うそ」関口君は信じられないって顔をした。
「ほんと」
「イイナってのもないの」
「ないの。どの都立がどのくらいのレベルかも知らないの」
「信じられない。そんなんでよく勉強できんな」
「悪い?」
「別に悪かあないけど」
「ねえ、図書館、毎日来る?」
「まあ、ここははかどるかんな」
「じゃお願いがあるんだけど。お昼とか休憩してるときに、そのへんの情報教えてくれない」
「いいけど。へえ、ホントなんも知らないんだな」
だって、うちの学校にいたらそんな情報なんか入ってくるわけない。そのまま高へ行くのが当たり前だし、他学受験する人はその辺の情報は塾で入って来るだろうし、どだいそういう人は都立なんか受けないし。実際クラスでだって、大学どこ行きたいとかの話は聞くが、他の高校のレベルがどのくらいなんて話、聞いたこともない。
私はお弁当を広げた。サンドイッチのお礼におかずでも少しあげようかと思った。
「ウインナー、食べる?」
「えっ。いいのサンキュ」
関口君は指で摘んで、パクっと口に放り込む。鯉がえさを食べるみたいで可笑しかった。
「うまい。自分で作るの」
「まあね。料理するのは割と好きなの」
ほんとはお母さんだけど、ちょっと見栄を張りたかった。
「へえ、すげえな。卵焼きもウマソ?」
「いいよ」
「ほんと。あんがと」
関口君はまた鯉になった。
「お弁当、つくってきてあげようか」
えっ。見栄はるにもほどがあるだろ。
「いや、そこまでは悪ィよ」
「一つも二つもいっしょだよ」
おいおい。
「でも、金払えないし」
「お金なんかいらないよ」
「でも、そこまでは」
「あ。じゃ、こうしよ。勉強の仕方、教えて」
ずうずうしいのはどっちだ。馬鹿。関口君の勉強する時間が減るだろ。
「あ。それでいいの。いいよ。俺の方が勉強進んでそうだから。俺のやり方でいいんなら」
「ありがと。あんまし迷惑かけないようにするね」
それから関口君に私の問題集を見てもらった。学校で使ってる現代文法のワークを見て関口君の顔が曇る。
「おまえ、こんなんやってんの」
「学校で使ってるワーク」
「お前の学校ってレベル高けえな」
「でも、私ぜんぜんできないんだ。オチコボレなの」
「へえ、これで」
「だから、基本問題んとこしかできないんだって」
「充分じゃん」
「え?」
「おまえさ、都立の問題見たことあるの」
「ないけど」
「かー。言いようないね」
「なに」
「都立で文法の問題なんて一問でるかどうかなのよ。五点だけ。それも基本的なとこ。こんな突っ込んで勉強してどうすんのよ。俺から言わせりゃ、おまえさ、時間の無駄」
「そうなんだ」
驚いた。そうか闇雲にやってても駄目なんだ。続いて関口君は漢字のワークを広げた。
「これもダメ。信じられないよ。なにやってんのって感じ」
「そうなの」
「おまえ、都立志望だろ」
「そうだけど」
「都立の書き問題なんてな、いっちゃん出るのは、中一・中ニレベルだって知ってた?」
「え」衝撃だった。私が勉強してた漢字、で、出ないの?
「し、しらない」
自分がやってることは試験に出ない。言葉が出ない。
「おまえ、受験のイロハのなんも分かってないでしょ。ただ闇雲にやってんでしょ?」
それから関口君は漢字のワークをパラパラめくって、
「俺の感じだと漢字とか文法とかもういいんじゃない」
「じゃ、なにやればいい? 国語って正直なにやっていいかわかんないんだけど」
「国語はさ、長文読解」
「あのさ、ショウジキ言って言っていい?。長文読解ってショウジキなにが力になってるか不安なのよね。例えば歴史とか1867年、イヤムナシ大政奉還とか、ひとつ憶えると確実にひとつ合格に近づけるとか、そういう感覚があるんだけど、でも国語の長文読解ってなんか、やってもショウジキこんなの出るのかなって、文章変わったら全然役にたたないんじゃないかって、なんか、なんて言うか、確実性がないっていうかーー」
「わかるよ」
いともあっさり関口君は私に同意した。
「今うちの学校だって、国語の長文なんて意味無いって全然やんないヤツいるよ。それより英単語とか歴史の年号とか憶えた方がいいって、国語の授業なのにそっちやってるヤツいるけど、俺考えるに、それダメだな」
「ダメなんだ」
「だって、そんなんじゃ国語の現代文の力なんて、いつまでたってもつかないじゃない」
「そうだけど。でも、じゃ、どうすればいいの」
「文章読む。問題に当たる。国語だって解答のパターンっていうか、解くためのヒントがあんだよ」
「ヒントって何?」
中学受験でやったはずなのに、いや、やったかもしれない問題の解き方とか、三年ぶりに思い出した。ああ、もしかして、そういうことやったかもしれない。
「あのさーー」
「私、文章読むの苦手なの」言われそうなこと、機先を制して、言った。
「ああ、やっぱね」
「どうすればいいんでしょうか」
「ハハ。殊勝だね。なんか、ホント読むこと、嫌そうだね」
「はっきりいって」
「本なんか読む?」
「どっちかって言うと、なんて言うか、その」
「しょうがねえなあ。じゃ、まず字を読むことに慣れたら」
「て、言うと?」
「読書」
「ダメかも。本、読むの苦手だし」
「そんな贅沢言ってらんないしょ?」
「まあ、そうですが」
「じゃ、本読めよ」
「本?」
「そう。勉強の息抜きにもなるしさ」
「本読んでたら、勉強できなくなんない?」
「だから息抜きだって。根詰めて一時間も読めなんて言ってないよ。空いてる時間、十五分でいいんだ、テレビ観るみたいにさ」
「なに読むの」
「そうだな」
「ミステリーとか」
「いや、それもいいけど。でもミステリーって受験に出ないだろ?」
「それは、ーーそうね」
「近代文学かな」
「キンダイブンガクって。あのナツメソーセキとか」
「そう」
「それで読解力つくの」
「いや、そうじゃなくて、読むことの抵抗なくすために、読むの」
「だからミステリーとか」
「じゃなくって、近代文学。ミステリーっていいもんもあるけど、文章練ってないものもあるじゃない。だから、近代文学を読むの。ゆっくり」
「ゆっくり?」
「そう。ゆっくりね」
関口君もゆっくり言った。
「なに読めばいい?」
「そうだな。そうね、芥川とかどう?」
「アクタガワって、竜之介?」
「そう。読んだことある?」
「なんか国語の時間にやったな」
「『トロッコ』でしょ」
「そうそう。『トロッコ』やった」
「どうだった?」
「なんか泣いて帰るってやつでしょ」
「そう」
「やったけど、あんま面白くなかったけど」
「じゃ、今度『トロッコ』の話しよう。読んだら教えて」
「いいけど、あんなんすぐ読めるよ」
「ゆっくり何回も読むんだよ」
「何回も?」
「そう何回も。ゆっくり」
「筋、知ってても」
「そう」
とても嬉しそうに関口君は言った。ゆっくり。何回も。それで何がわかるのか関口君は言ってくれなかった。ほんとに何かそれで分かるのか。まあ、『トロッコ』は短いから、言われるまま読んでみようか。一年生の教科書にあったな。ゆっくり、何回もね。
それから英語と社会の勉強法も教えてもらった。数学の問題集も関口君にならって揃えることにした。それなりにまんべんなく勉強が出来そうだったが、関口君は国語が一番好きだと言った。なんで国語? まあ今度じっくり聞いてみよう。一時間くらい休憩室で話して、午後は五時まで勉強した。時々、関口君がポイントを教えてくれる。午前中は向かいの席だったが、午後は並んで勉強した。
図書館の前で別れて、なんだかウキウキしている自分に気がついた。自転車を漕ぎながら吹き出る汗さえ気持ちよかった。そうだ、と途中で本屋に寄る。料理本のコーナーでお弁当のレシピ本を見る。私にも作れそうな一番安い本を選ぶ。卵焼きとウィンナーさえあれば関口君は満足しそうだったが、なんか勉強以外のこともしてみたい気持ちもあって、いい気分転換になるかな、と思って買った。レジに向かう途中、あっ、『トロッコ』と思い出した。別に中一の教科書に出てるから買わなくてもいいようなもんだが、関口君と話をするのに文庫本があるといいかな、と思った。
帰ってから、早速読んだ。言われたまま丁寧にゆっくり読んだので、筋はよくわかった。それなりに主人公の気持ちも理解できた。まあ、面白かったが、そんな何回も読んでどうすんだっていうのが、素直な気持ちでもあった。
勉強は家でもした。日本史は一問一答式の問題集で知識を整理してから、本格的な問題集に取り組むことにした。理科の一分野は、これは関口君も苦手そうだったが、分野ごとに仕上げる日にちを決めて、ひとつひとつ理解していく。というか暗記していく。
「いいかい。何だって一息にはできないんだ。難しいと感じたら、丁寧に地道にやることだね。もちろん無駄な遠回りはすることない。さっきも言ったけど、解答なんてどんどん見ていい。その時、解説をしっかり読むことね。で、地道にやる。バスとかが来なくて長い道のり歩いたことない? あとマラソン大会とか? 歩くのとか走るのとか嫌になっちゃうとき、俺はこう考えるんだ。まあ、こうして進んでりゃいつかは着くさって。進んでりゃいいさ。まだ時間はあるんだから、進んでりゃ絶対目的地にはつくって」
関口君の言葉が浮かぶ。弱くなりそうな気持ちの時、進め進め進んでりゃいつかは着くさ、と心の中で呪文をかけて、自分を励ました。
お母さんとは、あれからも何回かぶつかった。でも今は、受験に関してはもう何も言わなくなっていた。お父さんが私の気持ちに賛成してくれたからだろうか。昇は近くの水泳クラブに入って練習しているらしい。そこで十分疲れるのか以前みたいに部屋で大暴れすることは少なくなった。図書館が休館の月曜日なんかは、お母さんが気を使って連れ出してもくれる。お母さんも、消極的とはいえ、私の勉強に協力してくれているんだ。
受験のこと以外はお母さんともよく話す。特にお弁当のこと。はじめこっそり二人分作っていたが、すぐにバレた。
「それで友達に交代で家庭教師してもらってて、そのお礼」と嘘を言った。さすがに男の子の分とは言いづらかった。お母さんは、私の言うことを疑わずに信じている。それ以上に、朝、いっしょにお弁当を作るのが楽しみなようだった。私。関口君。お父さん。朝六時に起きて、お母さんと三つのお弁当を作る。いろんな料理を教えてもらった。いろんな手抜きの仕方も教えてもらった。夏休みはどんどん過ぎていった。私の十五分間読書も続いていて、今は『こころ』を読んでいる。関口君とは休憩時間いろんな話をした。でも印象に残っているのはやっぱり本の話だった。『トロッコ』を読んで、そのことを関口君に言ったとき、こんな話をしてくれた。
「どう。何か分かった?」
「主人公の気持ちの変化とか?」
「それも大事だけど、ゆっくり読むと見えてくるものなかった?」
「見えてくるもの?」
「たとえばさ、トロッコを押してて、初めは楽しかったけどだんだん不安になってくとこ、あるじゃない」
関口君は私の文庫本を広げて、こっからここまでと指さした。ニページくらいしかない。
「ここってね、一枚の紙を二つ折りにしたみたいに、ぴったり重なるんだ」
「どういうこと?」
「最初は工事現場にいるじゃない」とノートを広げる「工事現場は広いでしょ。次はミカン畑。視界は広い? 狭い?」
「シカイ?」
「見えるとこ」
「そりゃ畑の中をつっきてるンだから」と私は想像する。「みかんの木が迫り出してて、狭い、かな」
「うん。じゃ、竹藪は?」
「狭い」
「海」
「広い」関口君、何言ってんだろう。
「次。『日を受けた黄色い実』ってどんな感じに思う?」
「それみかんでしょ。どう思うって」
「明るい? 暗い?」
「まあ、みかんだから明るいかな」
「湿ってる」
「湿ってはいない」
「雑木林の落ち葉は?」
「うんと、雑木林で日は差さないから湿ってる、か」
「これ二月のお話なんだ。もう葉が落ちて時間がたってるよね」
「きっと、汚いよね」
「そうそう」言いながら、メモをとったノートを見せてくれる。
ノートの真ん中に一本まっすぐ線が引いてある。その線に「止」の字。そこを中心にして右と左に山状の線が引いてある。
右側に
「工事現場(広)」
「日を受けたみかん(明美乾)」
「みかん畑(狭)」
左側に
「竹藪・雑木林(狭)」
「ぬれ落ち葉(暗汚湿)」
「海(広)」
と書いてある。
ね。トロッコが止まったとこを真ん中に左右対称でしょ。対比的だし」
「ほんとだ。これ芥川考えて書いたのかな」
「わかんないけど、考えてたんじゃないかな」
「どうして」
「小説家だから。考えてなくても、自然とそう書けたんだよ、きっと」
「へえ、すごいねえ小説家って。ね、でも関口君はどうしてこんなことわかるの?」
「ゆっくり何度も読むからさ」
「ふうん」
「筋だけ追わないで、周りの景色とかも考えながら読むんだ。君も今、そう読んだじゃない」
「まあ、言われてみるとそうだけど」
「俺ってさ、出かけるとかで本持って行くとき、別に新しいんじゃなくてもいいんだ。古い何度でも読んだヤツでいい。でも読めば必ず見つかるんだ」
「なにが?」
「何かが。だから本を読むって面白い」
すごい。関口君の読書は攻撃的だ。私のは受け身。すごいなあ。私は勢いづいて訊いた。
「あのさ、『トロッコ』って最後のとこが、私、よくわかんないんだけど」
「どこ」
「あの塵労がどうとかってとこ」
「ああ、あれね。あそこは、他人なんか優しくもなんともないんだってことさ」
なぜかその時だけ突き放すような、白々とした言い方をした。だから私は、それ以上訊けなくなってしまった。
夏休みの最後の日も、いつもと同じに五時まで勉強した。日曜日はまたいっしょに勉強しようということになったが、週に一日しか会えないなんて、なんだか嫌だった。メールしようにも関口君は携帯を持ってなかった。家電するとか言ったけど、いいよ、また日曜ってそっけなかった。家も知らなかった。どこの学校で、どんな友達がいるかも知らなかった。何も知らなかった。夏休みに毎日会っていて、いろんな話をしたけど、結局関口君のことは何も分かっていなかった。私は昇のこととかお母さんこととかお父さんのことをいっぱい話した。へえ、イカれてて面白れぇ父ちゃんじゃん、なんて言ってくれたが、自分のことは何も教えてくれなかった。母子家庭だってこと以外。
でも、私も教えなかったことがある。学校の名前。訊かれてもごまかした。そのうち私が嫌がってることがわかったんだろう、関口君も訊かなくなった。自分のこと何も言わないのは、そのせいなんだろうか。自分の学校、教えてくれなかったのもそのせいかな。
自転車のペダルはいつもより重かった。いつのまにか蝉の声がミンミンゼミからツクツクホウシに変わっている。ちょっとイライラしながら私は家に急いだ。体育館の横を通ったとき、昇を見つけた。街路樹を見上げている。自転車を隣に止めても、まだ上を向いていた。
「なにしてんの」
「あ。ねえちゃん」
それでも顔を動かさない。
「何見てンの」
私も見上げる。放射状に広がった枝にはびっしりと濃い緑の葉が茂っている。その葉々の隙間にキラキラ光が漏れている。
「あれ」と昇が指さす。
蝉の幼虫が、少し背伸びすれば届きそうな高さに止まっている。まだ、背中が割れてないから、土から出たばかりなんだろう。
「日のあるうちに出てくるなんて珍しいねえ」
「ねえちゃん。あれ、なに」
「蝉の幼虫」
きっと見たことはあるに違いないだろうけど、中身詰まって動いているのを見て、改めて興味が湧いたらしい。
「さっき、うごいたよ」
「そら生きてりゃ動くだろ」
「ねえちゃん。とってよ」
「やだよ」
蝉の幼虫なんて触るのだって汚らわしい。怖気がふるう。
「じゃ、みてて。おとうさん、よんでくる!」
「えっ、ちょっと待って」
昇は待たない。水着の入った袋を抱えて駆けていく。マンションはすぐそこだ。仕方なく私は待つことにした。文庫本を広げる。『こころ』。もう一回読んだ。ゆっくり。ていねいに。そう思って読んでいく。関口君のようにいろんなことは見えてこない。でも、二度目は、本の中の世界と自分がぴったりあっているようで、それが快かった。
暫くすると、半ズボンにランニングシャツのお父さんが、虫取り網をかついで駆けてきた。後から昇が虫かごを持って続く。二人とも真剣な顔だ。「いやだ」思わず私は笑った。
夜の九時に羽化は始まった。虫かごの上にへばりついた蝉の幼虫は、背中の固い殻に細い筋を入れた。時間がたつにつれ、その筋は細い切れ目になって、中に真っ白な体がうごめいている。昇はもう気が気でない。三十一日で宿題は待ったなしで、やっぱり全部は終わらなくて、今、お父さんと夏休みの自由工作を作っている。大きなロボットだ。こんなんどうやって学校持っていくんだみたいなロボットを昇は作っている。お父さんはそばに控えて、セロテープとか長さに合わせて切っていく。
「いいか、昇。お前の宿題だから俺は手伝わん」
とか言いながら十分手伝ってんじゃん。と思いはするが、お父さんはそんな意識なんて全然なくて、昇がこれくらいと言えば色紙を切るし、昇がこれくらいと言えば、箱も切る。昇はそれをセロテープでくっつけるだけで、でも、なんだかすごいロボットがだんだん出来てくる。
「宿題って、お父さん、半分作ってんじゃん」
我慢しきれず笑いながら私が言うと、お父さんは青筋を立てて、
「違うぞ。俺は昇の指示通りに切ってるだけだ」
と言う。そんなん作ってるのといっしょじゃんと思いはするが、お父さんを追いつめたくないので黙っておく。それにしても昇には腹が立つ。お父さんが手伝うのが、さも当然だと言うように、あれやれこれやれ、とどんどん命令する。絶対後で殴る。そう心に決めて、でも今はとにかく作品完成が最大の目標なんで黙ってはいる。昇、後で憶えとけ。
昇は工作の合間に虫かごを見る。大丈夫だって、まださっきと変わらないって。そういっても昇は納得しない。五分ごとに我慢しきれなくなって、虫かごを見る。宿題と寝る時間のタイムリミットに追われながら、昇の行動はあっちにいったりこっちに行ったり、誠に落ち着きがない。結局私が、蝉の羽化の実況中継係にされてしまった。自分の勉強もあるけど、今日は関口くんと週に一回なんだというショックもあって、勉強できる気分にもならないから、まあ仕方ないかと、私も引き受けた。
蝉は背中を割って、それからエビぞりして、固い甲羅からゆっくりと抜け出した。それから自分の殻に捕まって、羽を「んーー」と伸ばしていく。それは「んーー」という表現がぴったりみたいな、なんか体のつま先まで力の入った作業だった。蝉につま先があるかは大問題だが、まあ、あるとして、うちの蝉は頑張った。真っ白な体を「んーー」を伸ばして、羽をぐうっと、しかもゆうくりと伸ばしていった。私は夜店で、吹き込むとしゅるしゅる伸びる笛を思った。ただし、この笛は空気が入るまでにえらく時間がかかる。私の実況中継を聞き聞き、ロボットはできあがっていく。昇は時々虫かごの中を見て、奇声を上げる。お父さんは、同じ長さにセロテープを切るのに余念がない。やがて、ロボットが完成した頃、真っ白な蝉は無事に羽化を終え、虫かごの中に女王様のように佇んでいた。
「おかあーーさーーん」
昇は叫んだが、もうお母さんは夢のなかだった。お父さんは、なんか知らんがテンション上がってて、のべつまくなし喋ってる。実況中継の私は、「もういいでしょ」と不機嫌ながら、内心蝉の羽化の美しさに見ほれるのであった。
「昇。明日起きたら、蝉逃がしてやれよ」と私は言った。
「え。なんで。しろいせみ、がっこうもってって、せんせいにみせる」
「バカ。明日になったら黒くなってんだよ」と私は言った。
「ちがうよ。なんないよ」と昇はお父さんに助けを求める。精も根も尽き果てたといった体のお父さんは、でも昇の機嫌をとるために嘘を言うようなことはなくて、「昇。この蝉が白いのは今夜だけなんだぞ」とか必死で言っている。いい加減なお父さんなのに、本気になるとこ分かんないんだよ。でも、そんなお父さん、嫌いではないけど。
結局、先に寝てたお母さんの「あんたたち! いつまで起きてんのよ!」という一喝で全ては終わって、、みんな床についた。翌朝、白い蝉は予想通り真っ黒で、昇はお母さんに言い含められて、ベランダから蝉を放した。私もお父さんもそれを見た。たった一晩のつきあいだったけど、青空をギュウーンと飛んでいく蝉を見るのはステキだった。「げんきでねえー」と昇は声を上げている。涙もためている。普段生意気で大嫌いな昇だけど、こういうとこはなんかピュアでいいんだよな、と私もちょっとグッときた。
夏休み、結局頼子とはいっぺんも会わなかった。頼子は地元のママさんソフトチームに夏休みだけ入れてもらって、それはそれなりに充実してたらしい。
「ママさんって、侮っちゃいかんぞ。知子」
別に侮ってなんかいないが、一応話を合わせとく。
「すげえぞ。ホントなら社会人に行ったっていいような人が、いるんだ、ホントに。国体に行った人だっていたんだから」と国体に妙にこだわる。
授業はもう高校一年生の内容に入っていたけれど、確認の意味もあって到達度テストの範囲は中学校の内容だった。思ったより解けた。夏休み頑張ったことは、無駄じゃなかったと実感した。そうは言っても、以前とくらべればというだけで、受験生としてはまだまだだった。関口君の志望校は尾山台高校で、その実力からいったらもったいないくらいだ。どうしてこの高校?って訊いたら、「まあね」とか言って言葉を濁す。お家の事情で都立一本だから失敗は許されない。きっとそんな思いで安全圏の高校に決めたんだろう。私は自分の実力がどのくらいか分からない。会場テスト受けたらって関口君は言ってくれた。
「金がかかるから俺は受けないけど、都内の受験生がいっぱい受けっから自分の位置も分かるし、高校の合格可能性の判定も出るよ、ABCとかで」
「関口君はどうやって自分の実力図ってんの」
「俺はね、クラスでさあ、だいたい自分と同じくらいのレベルのやついるだろ。そいつの会テ見せてもらって、だいたいこの辺くらいかなってね。それから学校でも実力テストやるし」
「へえ、いいなあ」
「お前んとこもやるっしょ」
「やるけど到達度とかいって、受験とリンクしてないし」
「そうなんだ」
うすうす私が私立だってことは関口君も気づいているんだろう。でも、それ以上詮索してこなかった。ありがたかった。私も、訊きたかったけど、そういう事情で関口君の学校は訊けなかった。
到達度が終わって、次の日の学活から体育祭の選手決めが始まった。全員が参加してクラス対抗で行う種目なんかはなくて、100M、80MH、長距離、高跳びとか、どちらかっていうと記録会めいたものだった。かろうじて団体競技っぽいものは学級対抗リレーくらいなものだ。一年、二年のときは応援団をかってでてポンポンなんか振ったりした。でも、今年は立候補しなかった。誰かいませんかあ、と学級委員の声がして、みんな私を見たりしたが、無視した。それどころじゃない、と思った。推薦ということになって、私の名前もあがったけど、かたくなに断った。最後は私以外で推された人が「じゃ、あたしやろっか」と言ってくれてやっと決まった。頼子も「アレッ?」みたいな顔をしていた。学活が終わって「どうした?」って訊かれた。
「なにが」
「オーエン団。一、二年のときあんなハリキッてたのにさ」
「なんだか疲れちゃって」
「そらうちの体育祭は盛り上がりには欠けるけどさ、でもそれはそれなりに楽しめばいいんと違う?」
頼子はリレーの選手に立候補した。やる気マンマンらしかった。
「なんだか知子が応援してくれんと力はいらんな」
「応援はするよ。ただ団に入んないだけ」
「ちょっと最近醒めてない?」
「醒めてないよ。大丈夫だって」
実際醒めてるんだろう。私は勉強のことで頭がいっぱいになりつつあった。
体育祭の朝は晴だった。去年のようなウキウキした気分はまるでなかった。できれば休みたかった。うちの体育祭は中高合同で街のホールを貸し切ってやる。晴れだろうが雨だろうが関係ない。私は100Mに出た。何位だったかも憶えてない。興味なかった。頼子がリレーのアンカーで、最初にテープを切ったことは憶えている。でも去年ほど嬉しくなかった。なんかみんな遠くの出来事のように思えた。頼子に声援を送る自分が、演技しているようで、終わってからひどく疲れた。記念写真を撮ろうよ、とクラスで集まったときも一番後ろにいた。できあがった写真には作り笑いをした私が、後ろの方に立っていた。
「絶対変だ。なんか隠してる!」とうとう頼子は爆発した。「二学期になってから、知子変だもん。なんかあったでしょ。言いなさいよ!」
実を言うと、頼子の存在にさえ、最近うっとうしさを感じはじめていた。ほっといて欲しい。好きにさせて欲しい。勉強したいんだ。頼子には関係ないんだ。そんな気持ちが頭の中で渦巻いた。でも、言えなかった。「なんでもないから」と頼子から離れた。ひとり机について勉強する私を、みんな触れたくないように、遠巻きにするようになった。それがかえってありがたかった。ひとりになりたい。ひとりでいいんだ。私には関口君さえいればいい。
運動会翌日の月曜日は代休だった。いつもは早めに家を出るから、朝の騒動を初めて見た。昇が起きてこない。お母さんが何度も声をかけて、果ては手を引っ張ったり、お尻を叩いたりしても、ゴム人形みたいにグニャグニャして、目を開かない。
「まったくもう、お姉ちゃんも手伝ってよ」
台所で朝食の支度をするお母さんに代わって、昇を揺する。何の反応もない。
「あんたねェ」と声を荒げて、でも昇が力一杯目を固くつぶっていることに気が付いた。背中を揺すっていた手を止めて、頭に触れる。
「昇。どうした?」
昇はなにも言わない。
「学校、始まちゃうよ」
昇は何も反応しない。
「お母さん。昇、変だよ」
火を止めて、お母さんがやってくる。
「そうなのよ。ここんとこずっとそう」
「ずっと? 毎朝、こんなふうなの?」
「そう。困っちゃって」
「何かあったの?」
「わからないのよ」
私はもう一度、昇の手を軽く引っ張ってみる。力をなくした昇は、なすがままにされている。ただ、目だけを固く閉じて。
「お母さん。これ、何かあるよ。学校ではどうなの?」
「何回か休んだとき、担任の先生に言ったんだけど、学校では特に心当たりがないって」
お母さんは、本当に困った顔でため息をついた。
「ね。正確にはいつから?」
「学校が始まって一週間くらいしてから」
「じゃ、ここ十日ってとこ」
「毎日」お母さんはそばに座り込んだ。「今日、休ませようか」
私もそれに賛成だった。
学校を休むと決まって、昇はズルズルと起きてきた。朝食を食べて、暫くして、いつもの昇になった。「姉ちゃん、タタカイしよ」と甘えてくる。少しつきあってやると、ほんとに楽しそうにコロコロと笑った。
「公園、行こっか」
「いく」
すぐに昇はグローブとボールをバックに詰めて、出かける用意をする。
「学校休んで、公園で遊んでいいの?」
とお母さんはトゲトゲしいことを言ったが、構わず出かけた。私自身、休日に体を動かすのは久しぶりだった。
小学校一年生にしては、昇はいいボールを投げる。でも飛んでくるボールは怖くて、グローブをなるべく体から離して捕ろうとする。女の私から見てもヘッピリ腰だ。
「昇。投げるのは100点」
昇はうれしくて、ぴょんぴょん跳ねる。
「でも捕るのは30点」
それでも昇はぴょんぴょん跳ねる。
「くおらあ。しっかりトレー言うとんのじゃ!」
私の心も、いつのまにか軽くなった。こうして姉弟で遊ぶのなんて、いつ以来だろう。昇は本当に嬉しそうだった。三十分くらい遊んで、ベンチに座って、ふたりでジュースを飲んだ。
「ねえ、昇」と話しかけてみる。「どーして学校イヤなの?」
「イヤじゃないよ」
「だって起きないじゃない」
「おきられないんだよ」
「どーして」
「ねむいの」
「うそ」
昇は手に持ったジュースを見つめる。肩が固くなりはじめている。私は、その肩を抱いてやり、なるべく優しく話しかけた。
「アヒル」と昇が小さな声で言う。
「アヒル?」何? 見当もつかない。「アヒルがどうかした?」
「ぼく、アヒルっていわれるんだ」
「ああ、あだ名。イヤなの?」
うなづく。
「アヒルくらいなによ。姉ちゃんなんか、小学校の時、ブスとかゴリラとか男子に言われたけど、負けんかったぞ」
「ゴリラ!」昇は笑った。
「ゴリラって言われてたの」
「そう」今度はふたりで笑った。「アヒルがイヤで学校行かないの」
「だけじゃない」
「なに」
「ヨウくんが、シャーペンでさすんだ」
ちょっと驚いた。
「どこ」
「おしりとか、せなかとか」
「なんで」
「ヨウくんは、ぼくのこときらいなんだ。ヨウくんだけじゃなくて、マツモトアツキくんも、サチコちゃんも」
「そう」
私は昇の頭を抱いた。腕の中で昇の頭がぐらぐら揺れる。
「そうだったの。先生に言った?」
首を振る。
「お母さんには?」
また首を振る。
「でも、言わなきゃダメだよ。姉ちゃんが言ってやろうか」
首を振る。
「じゃ、自分で言いな。いい、帰ったら言うんだぞ」
首が縦にコクンと振れる。それから昇は泣き始めた。私は昇の頭を抱いて、しばらくじっと座っていた。
お母さんの行動は早かった。すぐに担任と連絡をとって、学校に乗り込んでいった。
「そんなのモンスターペアレンツって言うのよ」
と私は言ったが、
「それくらいに思われなきゃ、学校なんて動いてくれないのよ」
と目をつり上げていた。
昇のお尻には、確かに赤いポツポツがあった。シャーペンで刺された痕だった。お母さんはカメラでそれも撮った。
「見せるの?」
「見せるわよ」
「よく写ってないし」
プリントアウトした写真をしげしげ眺める。それを取り上げて、お母さんは言う。
「こういうのは、あるってことが大事なのよ。四の五の言うようだったら、昇本人のお尻だって見せるわよ」
学校に行って、二時間くらいお母さんは帰ってこなかった。夕方に電話があって、夜、ヨウ君がお母さんといっしょに謝りに来た。もじもじと部屋から出ようとしない昇を、お母さんは引っ張ってきて、二人に会わせた。ヨウ君の「ごめんね」という声がする。昇も「ごめんね」と言っている。それからヨウ君のお母さんが詫びて、うちのお母さんが、何か言ってた。二人が帰ってから、「あんたが謝ることないのよ」とか昇に言っていた。昇はなんだか少し安心した顔をしていた。
次の日、学校から帰って「どうだった?」と訊いた。お母さんは首を振った。今日も起きなかったらしい。私は昇を見た。一人で怪獣の絵を描いている。
「困ったわね」とお母さんが言った。
「そりゃ、おメェ、嫌われてることには変わりねえんだから、行かねえだろ」
出張から帰ってきて事情を聞いたお父さんは、そう言った。
「だって、謝ったよ」
「謝ったって、嫌いは嫌いさ。シャーペンで突っつくことをしなくなるだけで、孤立してることには変わりねえだろ」
「そういわれると、そうだねえ」
珍しくお母さんが話しに加わる。昇はもう寝ていた。
「昇、不登校にでもなったら、どうしようかねえ」お母さんが言う。「やっぱり小学校から私立にしとけばよかったかしら」
「そういう問題じゃねえんじゃねえか。どこ行ったって、イジメられるときはイジメられるさ」
「アヒルだって」と私。「あだ名」
「へっ。アヒルね。どーしてだ」
「そりゃ、ひとりでガーガーうるさいからじゃない?」
「そりゃ、カモな」とウヒャウヒャ笑う。
「真剣に考えてください!」とお母さん。
「あいつは小学校入っても、まだ幼稚園みたいなトコがあるしな」
「怪獣の絵ばっかり描いてるしね」
「水泳はどうなった?」
「水泳にも行かないの。だから、ひと月お休みにしてもらって」とお母さん。
「重症だな」
解決策は見つからなかった。結局昇の問題だから、外野であーだこーだ言ったって、本当の解決にはならないのだった。
少し話を続けてから部屋にもどる。戻りかけにお父さんが、「どうだ」と声をかけてくれる。
「まあ、ぼちぼちね」
「お前も友達、大切にしろよ」
思いがけないことを言われた。昇のことがあってお父さんは何気なく言ったんだろう。ベッドに寝っ転がって考えた。「受験の王様」って言葉が浮かんだ。
中学受験の時、お父さんから言われた言葉だった。お母さんにお使いを頼まれて、勉強があるからって断った。そういうことは、その頃何度もあった。でもその時はお父さんが聞いていて、すごく怒られたんだった。
「勉強勉強って、おまえ何様だ。そんな受験ならやめちまえ! おめえみたいのを『受験の王様』って言うんだよ!」
お父さんが怒ると容赦ない。いつもはへらへらしてるけど、その時はほんとに怖かった。怖くて涙も出なかった。受験の王様、か。
昇は友達に受け入れてもらいったくって、それがうまくいかないんで学校に行けない。私は受験のことで頭がいっぱいで、友達なんかわずらわしいって思ってる。真逆だ。でも、それでいいのか。私は裏返しの昇じゃないか。孤独なのはいっしょだ。それでいいのか。関口君のことを思った。自分は関口君にすがりすぎているのかもしれない。今までの友達全部の重さを、私は関口君に預けようとしている。友達なんていらないなんて、うそだ。頼子に受験のことを言おうと思った。
「話ってなによ」
ずっと私がヨソヨソしかったから、頼子はちょっと怒っていた。放課後の教室で、私は頼子に受験のことを話した。全部話した。関口君のことも、全部、包み隠さず話した。目を丸くして聞いていた頼子は「ソーナンダ」と言った。
「そうなの」
「それでテンパってたんだ」
「そうかもしれない」
「それが、どういうご心境の変化で?」
まだ怒ってるぽかった。
「昇。知ってるでしょ、うちの弟」
「知ってる」
「小学校でイジメられてるのよ」
「え。そうなの」
「ちょっと深刻なの」
「ふうん」
「友達からハブにされてるらしくて、学校行きたがらないのよ」
「そら心配だ」
「うん」
ちょっと間を置く。
「昇のことがあって、私、頼子のことを考えたんだ」
「あたしの?」
「そう。私、変だった。受験するんで、自分だけ特別だなんて思っちゃってた。変だった。頼子、友達なのに、何も言わないで」
「ソーカ」
頼子は伸びをして、両頬をぴしゃぴしゃ叩く。
「ソーカソーカ。でも、いいんじゃない、受験。応援するよ」
「ごめん」
「だって、決めたんだろ」
「うん」
「じゃガンバレよ。いくら友達だから、仲いいからって、進路も何も全部いっしょじゃ気持ち悪りいじゃん」
「うん」
「知子は知子の道を行きなよ」
「うん」
「でも、ずっと友達だよ」
「ありがとう」
「ところでところで」と頼子は身を乗り出して顔を近づける。
「なによ?」
「関口君ってどんな人? もっと詳しく聞かせろよ」
「やだ。お前なんかにモッタイナイ」
「なにィー。こら。知子。許さんぞ」
教室で追っかけごっこをした。あっ、戻ってきたと思った。今ここに、戻ってきたって自分で思った。
昇の様子は一進一退で、起きて学校に行くこともある。妙にはしゃいで、周りにもう大丈夫かなって思わせといて、また休む。ゴム人形になってしまう。私にはなにもできない。お母さんも何も出来ない。担任の先生が迎えに来てくれたり、お友達が気をつかって遊びに来てくれたりしたが、それも最初のうちで、だんだん間遠になっていった。私は自分の勉強にも忙しかったが、昇となるべく遊んでやるようにした。でもそうすると、もっともっとと際限がない。じゃ、姉ちゃん勉強するからと言うと、とたんに暗い顔をする。お母さんも遊んでやるが、端々に心配顔が出るのだろう、二人になったときは、もっぱら昇は絵を描いた。白い紙を二つ折りにして、いくつも重ねてパンチで穴を開ける。それにひもを通してマンガを描く。カイケツゴンザエモンとか適当な名前をつけて。その数がどんどん増えていく。それが一種の逃避行動だってことは言われなくてもみんな分かってる。でも、誰も止められなかった。
昇のマンガの一番の愛読者はお父さんだった。昇はお父さんが帰ってくるまで寝ないで、玄関で「ただいま」の声がすると、すっ飛んでいってマンガを渡す。
「おっ、できたかマチカネたぞ」
なんて言いながら、日本酒をチビリチビリやりながらそれを読む。お父さんはテレビを見なくなった。マンガを読みながらゲラゲラ笑う。昇はそれを見ながら満足そうににこにこしてる。これはこれで安定しているが、やっぱりこれではいけないと思う。朝お父さんが早く出て、私が出て、お母さんは毎日ゴム人形と戦わなくてはならない。お母さんは相当参ってきたみたいだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

