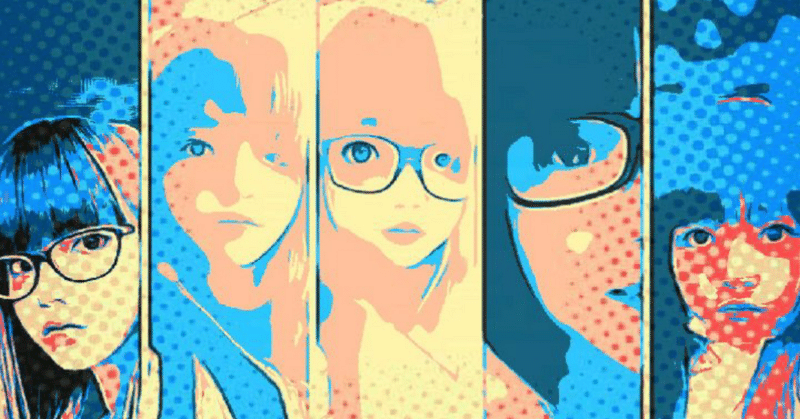
捜査員青柳美香の黒歴史Ⅱ
家に帰ると、ドアの前に、昨日の婦人警官が立っていた。警察が何の用だ。僕は勝手に行動する。そう言ったはずだ。無視して玄関のドアノブに手をかけると、婦人警官が突然歌い出した。正直ギョッとした。
お月さまいくつ
十三ななつ
まだ年や若いな
あの子を産んで
この子を産んで
だアれに抱かしょ
お万に抱かしょ
お万はどこ往た
油買いに茶買いに
油屋の縁で
氷が張って
油一升こぼした
太郎どんの犬と
次郎どんの犬と
みんな嘗めてしまった
その犬どうした
あっちのほうでもどんどんどん
こっちのほうでもどんどんどん
「お粗末様でした」と頭を下げる。いや、なかなかいい声だった。拍手してもいいくらいだった。
「東京バージョンです」と付け加える。どうやら二通目の手紙のこともお見通しらしい。
「見たんですか」
そう問うてみた。いえいえと顔をふりふりして婦人警官が言う。断っておくが、婦人警官といっても制服は着ていない。二十代半ばの娘さんらしいイデタチだ。白いふかふかのセーターに真っ赤なベレー帽。しかもこの寒いのにミニスカートで生足だ。これ以上、女性のファッションを形容する言葉を残念ながら僕は持たない。
「見ませんよ。ただ、お宅を監視させてはいただきました」
「誰が封書を投函したかわかってるんですね」
「はい」
「なんで、すぐ拘束しないんですか」
「だから、犯罪行為じゃないんですって」
「どこのどいつかは、わかってるんですね」
「はい」
「任意でなんか聞かないんですか」
婦人警官は、両手を広げ首をすくめる。なんの動作だ。
「まあ、投函した女性はなんにも知らないでしょうけど」
「どうして、そんなこと言えるんですか」
「だって。彼女は奥泉からまっすぐ此処に来て、しかもスマホを見い見い、たぶん初めて来たんでしょうね、ごそごそバックから封筒を取り出して、郵便受けに入れました。そのときのホッとした顔といったら、まあ、彼女は完全な伝書鳩ですね」
「あなた、手紙の内容知ってましたね」
「ええ、毎度同じパターンなんで」
「て、ことは、僕以外にも、同じ被害にあってる人がいるってことですか」
「そこは、まあ。ご想像におまかせします」
「いい声ですね」
なんでそんなことを言ったのか分からない。でも、確かにいい声だった。透き通るような、聞いているとうっとりするよな声だった。いかんいかん心が弱ってる。こんなメンタリティでは、僕の存在などたちまちのうちに国家権力にからめ取られるに違いない。
「ありがとうございます」
婦人警官は恥じらいを見せつつ頭を下げる。
「歌はちょっとだけ自信があるんです」
と、余計なことも言う。なんだコイツ。と思いながらも、冷静に見れば、まあ、そこそこ美形では、ある。ええい、と心の中で邪心をふりふりし僕は言った。
「ねえ、言いましたよね。僕は僕の好きなように行動するって」
「はい。聞いてました」
「なら、なんであなたは僕の前にいるんです?」
ふむふむと考える素振りを見せながら、その実、それがポーズであるのが丸わかりの動作をしつつ婦人警官が答える。
「わたしをあなたの助手にしていただけませんか」
なんと。意外な提案だった。
「助手ってなんですか。僕を監視しようっていうんですか」
「まあ、平たく言えば、そうですが」
「断る。冗談じゃない」
と怒ってみせるが、相手には全く通じない。
「でも、あなたは監視対象なんですよ」
「わかった。君がするんだな」
「ご名答です」
「じゃ、勝手にすればいいじゃないか」
「そうなんですけど」とうつむき加減で、肩までの伸びた髪をくるくるする。「あたし、尾行とか、そんなうまくないんですよね」
「僕を尾行するのか」
「はい。仕事ですから。でも、あたし、上手じゃないんです。すぐ分かっちゃうんです。下手なんです」
「それは、そっちの問題でしょ」
「でねでね、考えたんです」と目を輝かせて言う。「尾行するから駄目なんだって。それなら堂々と、その、なんですか助手として、くっついてればいいって。ね。名案でしょ」
「そんなこと、僕には関係ない。尾行したかったら、尾行すればいい。勝手にしろ」
「それがですね、簡単に見失っちゃうんですよね。こないだもちょっとトイレいった隙に逃げられちゃって」
「トイレなんか行くからだろ」
「だって、トイレは生理現象じゃないですか。仕方ないじゃないですか。部長だって、そりゃ仕方ないって言ってくれましたよ」
「そんなの知らない。だってほら尾行とか、そういうの二人一組でやるんじゃないの。なんかで聞いたぞ」
「まあ、警視庁とか人が余ってるとこならねえ。所轄じゃ、ちょっとそこまで人員割けませんしねえ。それにまだ犯罪行為じゃありませんし」
「犯罪じゃないんなら、尾行なんかしなきゃいいだろ」
「だ、か、ら、まだって言ってるんじゃないですか」
むう、と少し考えた。どのみちくっついてくる気だ。ほっとけば、いいようなものだが、いや、まてよと考え直した。
「条件がある」
「わあ、了解してくれるんですね」
両手を胸の所に組んで、ぴょんぴょん跳ねる。こいつホントに警察官か。
「だから、条件がある」
「なんですか」と小首を傾げる。
「君の持っている情報がほしい」
いやいやいやと片手を振られた。
「そんな、捜査上の秘密はお教えできません。あたしの首がとびます」
「だから、捜査上のことはいい。一般的なことでいい」
「一般的なことなら自分で調べりゃいいじゃないですか」
いちいちカチンとくる。
「自分で調べてもいいが、時間がかかるだろう。僕は一刻も早く奥泉に行きたいんだよ」
ああ、ああなるほどという顔をする。「なーるほど」と口にまで出す。「そうですねえ、そうだなあ、どうしようっかなあ」
無視してドアノブに手をかけると、慌ててその手を押さえて「はいはい、わかりましたよ」とキレ気味に言われた。なんでキレられなきゃならんのだ。
「で、何が聞きたいんです」
泥でも付いたように手をはたく。いちいちカチンとする奴だ。
「そうだな、まずは憑神教について」
「ほほう、いきなり核心を突いてきますな」
「いいから、話せ」
「どのくらい知ってるんですか」
「なんで」
「だって、わたしウッカリさんだから、言わなくていいことまで言っちゃいそうで、まあ、あなたの間違った知識を正すぐらいなら、ご協力いたしてもよろしいかと。あらあらかしこ」
物言いが、いちいちイライラさせる。でも、これは使わない手はないだろう。
「じゃ、言うから、間違ってたら訂正してくれ」
「はいはーい」
「憑神教。宗教法人としての認可は昭和四十五年。すでに教祖は死去。今は二代目の山田昇が宗派を継いでいる」
「正解」
「踊る宗教として有名」
「今は踊ってないですけどね」
「じゃ、何してんだ」
「黙秘します」
睨みつけるも、涼しい顔だ。
「踊るって、みんな踊ってたのか」
「黙秘します」
「わかった。失格だ。もう用はない」
ドアに近寄る。
「わーわーわー。分かりましたよ。じゃ、ちょこっとだけですよ」と渋々続ける。「踊るのは教祖さまだけだったようです。踊って、なんていうんですか、その、わけわかんなくなってーー」
「トランス状態」
「そう、そのトランス、トランスになって、神様のお告げを言ってたみたいですね」
「占いか」
「まあ、そんなもんです。それが当たるって評判になって」
「じゃ、代替わりしたら駄目じゃないか。その山田昇もお告げ言うのか」
「山田昇はしないみたいですよ」
「じゃ、何目当てでみんな集まってくるんだ」
「さあ」
目を細めて睨んでやる。
「そんな疑り深い目で見ないでください。まあ、行きゃあわかるでしょ」
「まあ、それもそうだな。続けるぞ」
「はい、どうぞ」
「信者一千人。でも、これは水増しされた数字だと睨んでる。実際は数百人規模だろう」
「ぶー」
「なんだよ。信者数なんてたいがい水増しだろ」
「ねえねえ、警察で防犯カメラの映像見たんでしょ」
「あっ」
「あんな電車に人数乗ってたんだから、数百人ってことはないでしょう」
「まあ、そうだな」
こんな小娘にやりこめられて、なんだか悔しい。
「まあ、薄い信者も含めたら四、五千人くらいいるんじゃないでしょうかねえ」と鼻をヒクヒクさせる。「で?続けてください」
「……」
「あれ、もうないんですか」
「ちょっと待て、手紙持ってくる」
動こうとすると、その前に通せんぼうされた。
「ここまでです。どうですか助手の件?」
「どうせついてくるんだろ」
「はいー!」
「じゃ、助手にしてやるよ」
「ありあたんしたーあ」
と大声をあげた。
三時間後、助手と僕は新幹線に乗っていた。それまでに話したことは以下の通り。
「それでは、まず、自己紹介から。えへんえへん。あたくし、婦人警官の青柳美香と申します。年は二十六歳。所属部署は故あって申せませんが、ただいま憑神教の捜査に専従いたしております。特技は空手を少々。小娘だと思って舐めた真似しでかすと痛い目を見ますわよ。おほほほほ。星座は乙女座。学生時代のあだ名は、あだ名はついてませんが、みんなミカリンって呼んでくれてました。よろしかったら、以後、ミカリンでーー」
「断る」
「そうですか。それは残念です。出身は修羅の国、福岡。好きな食べものはバナナ。性格はそうですね、こう見えても、ちょっぴり恥ずかしがり屋のオマセさん。趣味は音楽鑑賞で好きな歌手はーー」
「もういい」
「えー、もういいんですかあ。じゃ、先生どうぞ」
「お前の先生じゃない」
「どうぞ」
「えー、そのなんだ、名前は大石司。妻の名は静恵。娘はアカリ。義母は江田紀子」
「はい、知ってます。年齢は五十一歳。中学校教師。担当は国語科。現在中学校三年生担任。休職中。奥様は司さんと同学年。アカリさんはこの春女子大を卒業する予定で、就職情報誌の営業に内定。お義母様は、五年前に旦那様を亡くされ、現在一人暮らし。以上」
「なんだ、じゃ、話すことないな」
「えー、趣味とか星座とか、まだ聞いてないんですけど」
「断る」
「もう。蔵サンって恥ずかしがり屋さんなんだから」
「蔵サン? 蔵サンってだれだ」
「いやだ、先生に決まってるじゃないですか」
「俺は司だ!」
「だって大石でしょ。憑神教に乗り込むとか、赤穂浪士の討ち入りみたいじゃないですか。大石内蔵助。で、蔵さん」
「司だ」
「いやだぁ。蔵サンとミカリン。うまくやって行けそうだわ」
「お前をミカリンなんて呼ばん」
「あっ、ミカリンって覚えてくれたんですね。早速お使いいただき、ありがとうございます」
「うるさい。青柳!」
「えー、呼び捨てですかあ。呼び捨てなら、せめて下の名前で」
「うるさい。青柳!」
そんなすったもんだがあって、青柳は今、隣でグーグー眠っている。ウナギ弁当とカツサンドとアイスを食って満足したらしい。静かなうちに、と僕は鞄から一通目の手紙のコピーと二通目の封書を取り出す。
差しだし人はいずれも「十四夜」。
確かに三人が伊勢参りに出かけたのは、一月十四日。二通目の手紙が届いたのが昨日、二月十四日。
日にちはあってる。でも「日」じゃなくて、「夜」とわざわざ書いてあるのはどうしてか。
十四夜。十五夜なら満月、お月見。十六夜なら、いざよい。十四夜はなんだろう。なんと呼ぶのか。スマホで調べてみた。
小望月。
ああ、なるほどね。十五夜は満月、望月だから、その前で小望月。こもちづき。他に「幾望、きぼう」とも言うらしい。「幾」は「近い」の意味。望月に近いということなんだろう。幾。「いくつ」とも読むな。
お月さんいくつ
十三ひとつ
昨日、来た「紀伊バージョン」の手紙にはこうあった。
お月さんいくつ
十三ななつ
今日、青柳が歌った「東京バージョン」ではこうだった。「十三ひとつ」と「十三ななつ」。「ななつ」の方が一般的なんだろう。なぜ、「ひとつ」なんだろう。そうか、もしかして足すのか。十三足すひとつは十四。十三足すななつは二十。「十四夜」なら「ひとつ」か。でも、それが何なのだろう。言葉遊びか。それとも、謎かけか。
「十三」でスマホをググってみる。男は十五で「元服」、女は十三で「成女式」とある。なるほど、昔は十三で大人の女性になったのか。早いな昔は。恐らく初潮の時期にあわせたんだろう。
「十三ひとつ」は、結婚してもいい年頃ということか。時代が下って、適齢期が「十三ななつ」、二十歳ごろに変化したのか。
一通目のコピーを見る。
みなかみに こと夜のしもは ふらねども 七日七日の 月といわれじ
「十四」で繋がる。この歌も「結婚」が関係するのだろうか。「みなかみ」って地名だろうか。「水上」か。水上温泉か。検索をかけても、手がかりになるようなことはなかった。ただ「月夜野」という地名があった。今は水上町に合併されているらしいが。
「憑く・神」を検索する。だいたい動物霊に憑依されるようなことが書いてある。憑神教の御神体は狐か狸かはたまた山犬か。
似た言葉で「月読命」というのもある。「ツクヨミ」「ツキヨミ」と読むようで、天照大御神とか須佐之男命と一緒に生まれたらしい。だが、記紀神話の中で「月読命」の存在は極めて薄い。どれも関係なさそうで関係ありそうでわからない。
まあ、行くしかないな。諦めて手紙をしまい目を閉じた。
駅を降りて驚いた。結構観光地化されている。グーグル・アース・ストリートビューの死角の位置で、饅頭や煎餅を売っている店もある。のれん、手ぬぐい、扇子、団扇、饅頭の名前、煎餅の名前、どれにもこれにも「胎内巡り」の文字が踊る。「日本随一」「神秘の体験」「生まれ変わり」「生き直し」などなどあおり文句も勇ましい。
「青柳、ここは観光地か」
「へえ、温泉も出ますんで」
「なんだ、けっこう開けてんな。人はおらんが」
「一月十四日が大祭で、その前後は大勢集まったんで、その反動ですかな」
したり顔に解説する。
「ちょっと、覗いてみるか」
近くの店に入ってみる。
奥でテレビを見ていた婆さんが「いらっしゃーい」と言う。でも、動かない。
「おばちゃん、憑神さんに行くのは、この道まっすぐでいいんですか」
「いーよ。饅頭安いよー」
「胎内巡りってなんですか」
「行ってみなー。行きゃあわかるよー。煎餅おいしーよー」
「そうですか。ありがとう」
「なんも買わんのかー」
「あ、じゃ、お饅頭二つください」
「まいどー」
饅頭を買ったら、奥泉観光マップをもらった。これはありがたい。
「観光饅頭って、どううしてどこもかしこも同じ味なんですかねえ」
食いながら青柳が言う。言う割にうまそうに食う。
「観光地だからじゃないか」
適当に言うと、「ああ、そうですね」と素直に納得した。
二百メートルくらい歩くと、石段が見えてきた。この上らしい。背後は鬱蒼とした山々がせり出している。
「雰囲気あるでしょ」
とスキップでも踏むように、青柳は石段を軽快に登ってゆく。こっちは青息吐息で登り切る。途中、十人くらいの人とすれ違った。
上がりきると巨大な輪っかがある。藁で編まれて紐で張られて垂直に立っている。それが奥にもある。数えると六つある。さらに後ろに本殿。背後には山。
「なんだ。これ」
「マップマップ」と青柳の催促。見ると、名前が書いてある。
天人道輪
修羅道輪
人間道輪
畜生道輪
餓鬼道輪
地獄道輪
「六道遊行だな。憑神教って仏教系か」
「さあ」ととぼける。
「おまえな、こんなのは一般常識だからな、とぼけるな」
「へえ、一般常識だとも思えませんが、では解説をどうぞ」
「六道は、生まれ変わりの世界だ。命ある者は、死ぬと何処かの世界に必ず生まれ変わる。次は餓鬼道に落ちるかもしれんし、地獄に行くかもしれない。永遠に輪廻転生し続ける。どの世界に行っても病老死の三つの苦しみがある」
一つ目の輪をくぐる。
「天人さんもですか」
「そう、天人五衰といって、やがて衰えて死ぬ。まあ、寿命は長いがな」
「なかなか死なないのもなあ。やっぱ人間がいいかな」
「仏教ではな、病老死は三苦といって、まあ生きることは最終的に苦しみである、と」
「ずっと苦しむわけか。なんか悲観的だなあ」
二つ目の輪をくぐる。
「そのころのインドは、とてつもなく貧しかったろうから、まあ、今の日本の感覚とは違うわな」
「そっかあ。でもさあ、南無阿弥陀仏とか唱えたら天国いけるんじゃないの」
「極楽浄土な。天国はキリスト教。キリスト教の方で言えば、全員行ける訳じゃない。最後の審判ってえのがあって、そんとき、キリストが天国から帰ってくる。そんで、今まで死んでた人もむくむく起きあがって、キリストの審判を受ける訳だな。それでキリストがおまえ天国、おまえ地獄とか振り分けるわけ」
三つ目の輪をくぐる。
「へえ、すげえ。キリスト最強!」
「だから、復活しなきゃなんないんで、キリスト教圏は基本土葬。体がないと復活できんからな」
「ああ、だからゾンビ映画とかあるわけだ」
「そう。で、仏教の極楽だけど、あれは如来さんの持ちもんなわけよ。よく聞く阿弥陀如来さんの持ってるのは西方浄土。奈良の大仏はなんだっけかな、薬師如来は東方浄土か。釈迦もなんか浄土を持ってる。今、そこにいるんじゃないかな。信仰すれば、死んだらそこに連れっててくれるんだな」
四つ目の輪をくぐる。
「阿弥陀さんとか、あれ人間?」
「じゃないな。人間で最初の如来はお釈迦さんだね」
「手塚治虫で読んだ。ブッダでしょ」
「そう目覚めた人って意味なのかな。でもまあ釈迦は浄土浄土とか、あんま言ってないけどな」
「じゃ、お釈迦さまは何したの」
五つ目の輪をくぐる。
「六道から逃れる方法を会得した」
「へえ、すげえ。つーか意味わかんないけど」
「六道から超越したわけだ。それを称して、<悟る>と言う」
「ふうん、じゃ、なんで、悟った後も死ぬまで人間やってんの」
「悟る方法を教えるために、だな。その教えが仏教。教えるために、あえて人間世界にとどまったんだな。悟れば、三苦だけじゃなく、すべての苦しみから解放されるのさ」
「そんなことできるんかなあ。あっ、六道通った」
六つ目の輪っかを通過した。
「これで六道遊行したわけだから、どこぞの浄土へでも連れってくれるのかな」
目の前は本殿である。賽銭箱はないが、寺の形をしている。けっこう大きい。だが、本殿の板の間の奥、本来御本尊がある場所にぽっかり穴が空いている。洞穴か。洞窟か。どう違うんだ。どっちにしてもそこだけ岩がむき出しになっていて、人ひとり通れるくらいの天然の穴が黒々と口を開けている。上の木板に「胎内巡り」とあった。
「これか」
「そうみたいですね」
青柳はそばの立て札の方を見ている。
境遇を失うことを恐れる者
常に怒りある者
欲望に負ける者
働くことだけが人生の者
貧しく飢えたる者
罪にさいなまれる者
生き直せ生き直せ生き直せ
「これ何。六道のこと」
「ふむ、なんかそうみたいだなあ。人間として生きながら、ある人は地獄道に落ち、ある人は天道におり、ある人は修羅道で怒りに満ち、とか言う意味かな」
「その通りである!」
突然の大声。声の方を見ると、白装束の若い男が立っていた。神主というより山伏に近いようないでたちだ。
「こりゃまた、変なのが出てきましたよお」と青柳が呟く。
こらこらと制して、声をかける。
「ええと、神主さんでいいんでしょうか」
「信者である」
「ああ、普通に信者さん。あの、胎内巡りなんですが」
「ご所望か」
「なんだか時代劇みたいですね」とまた余計なことを言う。
「入れるんですか」
「入窟だけか」
「入るほかになんかあるんですか」
「沐浴もできる」
「この寒いのに、やだあ」と身をくねらせる青柳
「いや、温泉である」と信者さんは。なにやらパンフレットを差し出した。
生き直し
入窟 500円
沐浴 3000円
装束一式貸与1000円
※装束にはバスタオルつきます。
「金、とるんだ」
「布施である」
「四千五百円は高いなあ」
青柳は金にこだわる。
「布施である」
信者さんは頑なだ。
「で、御利益は」
「生き直し生き直し」
「生き直しって、生まれ変わることですか」
「そう」
「そうって」
「自らの生き方を振り返ってみよ。人間道にありながら社畜と化し、畜生道に落ちる者もあろう。また、生きながらーー」
「そこのくだり済んでますから、その洞穴に入った後、どうなるんです」
「新たな命が輝く」
「そんな突然変われますかねえ。ねえ」
青柳は、やはり四千五百円が惜しいらしく懐疑的である。
「まあ、心の持ちようじゃないか。信仰とはそういううもんだろう」
「はあはあ、なるほど、持ちようね」
「いかがする。入窟するか。沐浴するか」
「どっしよかなー」
と青柳が思案中、洞窟から人が出てきた。うら若い女性三人連れである。白いじんべえみたいのをお揃いで着て、バスタオルを持って上気した顔をしている。なにやら言葉を交わしながら、ホッとしたように本殿の右奥に入っていく。
「あっちが脱衣所なのか」青柳が言うと、「男の方は左側です」と信者さん。
どうする。そういえば、土産物屋の婆さんも行けばわかるさーって言ってたな。入るか。
「お前、風呂代経費で落ちないの」
すかさず、沐浴である、と信者さんの訂正がはいる。
「あっ、そうっすね。経費か。落ちるかな。まあ、いいや、じゃ、入りまーす」
「では、左右に分かれて、手水場でお着替えくだされ」
「手水場?」
「お社では、脱衣場をそう呼んでおる」
「はあ、手水場ねえ。で、お金はどこで」
「行けば、カウンターがあって、お布施を出せば、ロッカーキーと装束一式がもらえる。キーはくれぐれもなくさぬようにな。なくすと鍵代をお布施していただくことになる。鍵を閉め忘れた場合の盗難については、責任を負いかねる故、ご承知のほどを」
「はあはあ、ご丁寧にどうも」
ということで、青柳と洞穴の前で落ち合うことを約束して分かれる。手水場は、まあ温泉宿の脱衣場と同じである。
カウンターでお金と引き替えに、白いじんべえ、もとい白装束を渡される。テレビで見た滝行の様子を思い出し、このまま湯に浸かるのか、係りのおばちゃんに聞いてみる。
「沐浴でございます」
と、早速訂正が入る。
「ああ。失礼。その沐浴は」
「いえ。次の間で裸になっていただき、装束をまとってください。装束は死に装束。死出の旅に参ります」
「はあ」
「ご本窟に入っていただくと、中は漆黒の闇でございます。私語は厳禁。左手に魔道冥界に誘う麻紐が渡してございます。それを伝いながら、中へ中へとお進みください。やがて仄かな灯りがご覧になれます。灯りに照らされるは、ご本尊の子泣き岩にございます。入窟のみの方は、子泣き岩をぐるり回って生き直し。そのまま麻紐を伝ってお帰りください」
「はあ」
「沐浴ご所望なる方は、子泣き岩をぐるり回って、その先に、新たな窟がございます。麻紐は在りませぬ。左手で壁を伝って伝ってさらに奥までお進みください。私語厳禁でございます」
「大祭のときは、混んで大変なんじゃないですか」
「本来完全予約制でございます。本日は行の予約が入っておりませんので、お声かけさせていただきました。また、大祭の折りは、ご本窟でお祭りが執り行われるため、入窟はできかねます。代わりに、お社そばの支窟にお入りいただきます。こちらは平服、土足でかまいませぬ。ご予約はいりません。御利益は同じにございます。五百円にございます」
「はあ。で、進むと、どうなります」
「中は漆黒の闇でございます。私語厳禁でございます」
「はい。で、どうなります」
「やがて、足が湯に浸かることと思います。そこで装束全てお脱ぎになって、畳んで湯の掛からぬ隅にお寄せください。後でまとめて取りに行きます。全裸になりましたら、奥へ奥へと参ります。やがて、くるぶしまでに湯が満ちて、それが膝、そして腰、胸、肩まで、参ります。心の内で、生き直し、生き直し、生き直し と三度唱えて、頭まで湯にお浸かりください。三度、繰り返し、胎内巡りは終了にございます。そのまま左手で壁を伝ってお歩きください。やがて湯から上がることができましょう」
「バスタオルはいつ支給されるんですか」
「湯から上がれば、バスタオルと白装束のご用意があります。よく拭いてお召し替えください。後はまた麻紐をつたってお帰りください。バスタオルはお持ち帰りください」
「はあ。じゃ」と次の間に向かう。
「入窟なさいましたら、私語厳禁にねがいます。声を上げた時点で、行は終わりにございます。本懐遂げることはかないませぬ。ああ、生き直し生き直し」
着替えながら、流れるような説明だったな、と思う。きっと一日何十回も同じことを言ってるんだろう。着替えて、本殿にでる。寒い。青柳はなぜか私服のままで立っている。
「あれ、お前入らないの」
「いや、入りますけど、子泣き岩までにしました。ちょっと嫁入り前ですから混浴はねえ。それに蔵さんといっしょでしょ」
「あ、俺がなんかするとでも思ってるのか」
「だって、声あげちゃいけないんでしょ。事故ないのか訊いたんですよ。カウンターの人に。そしたらもぐもぐしちゃって、きっとなんかあったんですよ。だから、子泣き岩までお供します」
「勝手にしろ」
と、洞穴に向かう。
「こっから喋っちゃいけないんですよね」
「ああ、無言の行なんだろ。お前、ひっ! とか声あげるなよ」
「無礼ですね、武道家ですよ。心の鍛錬は蔵さんよりは積んでます」
どうだか、と思いつつ、僕が先なってご本窟へ入り込む。
幅は三メートルくらい、高さも三メートルと少しくらいか。両側に麻紐が渡してある。帰りはあっちになるのか。左側通行と言うことなんだな。目の前は全くの闇。振り向くと青柳がうなずく。
足を踏み出す。
ひと足ひと足進むにつれて闇が濃くなる。穴は少しずつ左に曲がり、数分も歩くと、入り口の明かりも、もう届かない。目を閉じて、また開けてみる。闇の深さは同じだった。また、少し歩く。
お前は誰か
ギクリとして足を止める。闇の中から声がする。声を上げそうになるが、かろうじて堪えた。
お前は誰か
また同じことを訊く。中年男の野太い声。後ろからつっつかれて、また歩を進める。
お前は誰か何者か
なにゆえ窟に入るのか
お前は誰か何者か
なにを求めて窟に入るのか
黙って歩いた。やがて声はしなくなった。と--。
応
応
応
と、数名の、併せた男の声がする。三つ唱えて杖で岩を打つ音、同時にジャンと鎖の音がする。それが何度も続いていく。その声は三人、いや五人、もしかするなら十数人。理由のない恐怖が襲ってくる。まさか、何もしやしないだろうが、しかし真っ暗な何も見えない場所で、恐怖は募る。
お前は誰か何者か
また声がする。
何を思うて生きておるのか
悔いはあらぬか
間違うてはおらぬか
生きて毎日楽しいか
どうじゃ
どうじゃ
どうじゃ
何か責められているようで、汗がにじむ。気がつくとすっかり寒さは収まっていた。かすかに硫黄のにおいがしてくる。
お前は真から笑うておるか
お前は真から怒っておるか
お前は真から泣いておるか
お前は真から楽しんでおるか
誠か誠か誠にそうか
笑わさられておるのでないか
怒らされておるのでないか
泣かされておるのでないか
楽しまされておるのでないか
どうじゃ
どうじゃ
どうじゃ
お前はお前を生きておるのか
お前はお前を生きておるのか
ああ
生き直し
生き直し
生き直し
強さを誇っておらぬかえ
弱さを誇っておらぬかえ
人を侮り生きておらぬかえ
自分を侮り生きておらぬかえ
どうじゃ
どうじゃ
どうじゃ
恐怖の後には、なぜか悲しみが襲ってくる。そんな責めないでくれ、と心に思う。誰だって少しずつ自分を騙しながら生きている。そんな坊主みたいな生き方なんてできない。世俗にまみえるのが人間じゃないか。違うか。
今度は怒りの気持ちが沸く。応、応、応の声に心の中で否、否、否とこたえ続ける。なんだお前は、と逆に問うてみたくなる。
ひときわ大きくジャンが鳴る。そして、声はしなくなった。
さらに歩くと、天井から一筋光が射すのに気がつく。地にある岩を照らしている。これが子泣き岩か。なんとなく母が子を抱いているようにも見える。ああ確かに人間は泣きながら生まれてくるなあ、などと思い、手にふれる。シンと冷たい感触がする。ぐるりと回ると、わずかな明かりの中へ青柳が顔を突っ込み二、三度うなずく。そして軽く手を振り、対面の闇の中へ消えてゆく。なにか、魚が深い海に潜っていくようだなと思った。
子泣き岩から手を離し、左の壁に戻る。麻紐は途中で切れていて、それからは壁伝いに奥へいく。硫黄のにおいが、それとはっきり分かるまでになる。
やがて足に湯が触れる。白装束を脱ぎ裸になる。無防備な、なにかむき出しの不安感のようなものに包まれる。奥に進む。じんわりと暖かい。湯に包まれることで、徐々に不安感が消えていく。ゆっくり進む。奥へ奥へ。肩まで浸かったところで、生き直し生き直し生き直し、と三度唱え、頭まで湯に浸かる。不意に妻の顔が浮かぶ。二度目、それがアカリになる。そして三度目、義母を思い浮かべ、行を終えた。壁を探し、左手づたいに湯から上がった。踏んだ感触でタオルが分かる。手探りに白装束も探しだし、体をふいて、身にまとう。しばらく壁を伝うと麻紐にあたった。少し進むと右に子泣き岩が見え、逆戻りしていないことが分かる。もう声はしない。ゆっくりと歩き、洞窟を出た。
出ると、青柳が初老の小男と話している。男は、さっきの信者と同じ格好をしている。近づくと男の方から声をかけてきた。
「行のほうはいかがでしたか」
青柳が、こちら山田昇さん、と言う。
「初めまして。なかなか貴重な体験をさせていただきました」
少し警戒しながら答える。三人を拉致したのはコイツかもしれないのだ。
「ほうほう、生き直せましたかな」
と山田昇はにこにこ顔だ。
「さあ、どうですか。煩悩の塊みたいな人間なんで」
「ほうほうほう。まあ、そのうち御利益があらわれましょう」と頷き、続ける。「ところで、こちらのお嬢さんから、ご家族の話を伺いました。お社にこられて行方知れずとか」
「はい。奥泉の駅を降りたのは確実で」
「それが一月の十五日。大祭の日の翌日でございますなあ」
「そうなんです。で、なにかわからないかと」
「ほうほう。そうですかそうですか。じゃ、まあお着替えいただいて事務所のほうへ」
「はい。恐れ入ります」
いそいで着替えた。なにか分かるかもしれない。事務所の位置をカウンターのおばさんに訊いて走る。
ドアを開けると、青柳と山田昇が、テーブルを挟んで向かいに座り、お茶を飲んでいた。青柳の隣に僕も座る。
「おーい、お茶をもうひとつ」
と山田昇は声をかけ、さて、と座り直した。
とりあえず名刺の交換から始めた。
憑神教 神職 山田昇
とある。
「ほうほうほう。中学校の先生ございますか。今は、ほれ、学校の先生も大変な時代でございますなあ」
などと言いながら、窓の外を見る。
「それでは本題に。今はほれ、こう落ち着いておりますが、大祭の翌日は結構な人出で、お三人様と言われましても、ちょっと記憶にないというのが正直なところでして」
言葉をそのまま信用する訳にはいかない。何か隠しているかもしれないし。
「写真を見てください」
と差し出してはみるのだが、
「これは、私より係りの者に見せた方がよろしいでしょう。おーい」
と言うばかり。よく見もしないで、お茶を出した信者を呼んで、これをみんなに回して確かめてもらいなさい、大祭の翌日いらしたそうだ、と写真を渡す。
「あの、いいですか」
と遠慮がちに青柳が割り込む。
「はい、なんでございましょう」
「大祭は一月十四日だそうですが、十五日も大祭ですか」
「と言いますと」
「お祭りが終わった翌日に人出が多いっていうのがわからなくって」
「ああ、そうでございますな。ご説明いたしましょう。憑神教のご神体は子泣き岩でございます」
「はい、先ほど拝見いたしました」
「別名、子持ち岩とも申しまして、お触れいただけば子が産まれるという言い伝えでございまして」
「はあ、子持ち岩。それがなぜ子泣き岩と」
「子は産まれたときに泣きますな。この世に泣いて生まれます。人間道という穢土の世に、産まれて子は泣くのであります」
「はい」
「つまり、十四日に子が宿り、十五日には子が産まれる、と。もちろんのこと、宿らねば産まれませんからなあ」
「まあ、ものの道理ですね」
「したがいまして、子の欲しい方は十四日にお参りしたい」
「はいはい。それがなぜ十五日?」
「十四日と申しましても、子宿りの霊験があらたかになるのは、月が出てからでございます」
「月」
「はい、十四日の夜月が出て、十五日の夜月が出るまで、この期間が最も霊験あらたかな時といえましょうか」
「十五日の夜は」
「旧暦では満月、望月でございますな。子は欠けたるところなく産まれております」
「でも、太陽暦と太陰暦じゃ、月の満ち欠けがずれてるんじゃないですか」
「そこで、大祭でございます。今年は一月の朔日が新月とぴったりあっておるのでございます。このような年に限り大祭と称します。普段の年の一月十四日はお祭りとだけ申します」
「なるほど、で、あんな人出だったんだ。でも、なんで十四日なんですか」
わかった。十四夜。小望月。
「旧暦では、十四夜のことを<こもちづき>と申します。十五夜の望月の前夜ということですな」
「ああ、なるほどねえ。語呂合わせじゃん」
「これはしたり。子持ち岩が先にあり、小望月という言葉が後から産まれたのかもしれませんぞ」
「あっ、逆かもってことか」
「月の満ち欠けは女性の月経の巡りとほぼ同じと申します。どちらが先というわけでなく、自然とそういう流れで納得されていったのではありますまいか」
どうやら、便せんの「十四夜」の差出人は、憑神教由来と見て間違いなさそうだ。
「じゃ、生まれ変わりは?」
「そうですな。子が産まれるというところから、産まれ直しの信仰がうまれ、いつしか胎内巡りが定着していったようですな」
「はあはあ、なるほどなるほど」
青柳は納得しているようだが、あとひとつ気になることがある。
「少し僕の方からもいいですか」
「はい、なんでもどうぞ」
「憑神教って新しい宗教法人ですよね」
「はい」
「今、お伺いしてますと、随分古くからのもののように思えるんですが」
「はい。本教が宗教法人として認可されたのは昭和四十五年。まあ、新しい宗教といえばそうですな。ご説明いたしましょう。当初、子持ち岩の言い伝えは、民間信仰のようなもので特に信者さんというくくりはございませんでした。このお社も昔はお寺であったようなのですが、跡継ぎもなく、本山から派遣された坊さまは、まあ余り素行がよろしくなく、借金をこさえて仏具までも売る始末。ある時、ご本尊の阿弥陀様もなくなったことに気づいた村人に追い出されたようでございます。それから新しい坊さまを本山にお願いするも来てはなく、まあ、ご本尊もないのではねえ、やがて廃寺となりました」
「お寺の造りも独特なものですが」
「はあ、まあ子持ち岩の民間信仰を檀家を増やす手だてと考えたのかもしれませんな。今は分からぬことですが」
「なるほど。で、教祖さまはいつ頃、ここに」
「来られたのではございませぬ。教祖様のもとをただせば奥泉村の百姓でございます」
「名は」
「堤田トメ、と」
「つつみだ」
「はい。名字からしてお分かりと思いますが、戦前は小作人、戦後の農地改革で田圃はもらえたが、亭主が博打好きで、ほどなく手放さざるをえなかった、と」
「苦労されたんですね」
「子はなく、亭主の面倒ばかりで、五十を迎えたそうにございます」
「はい」
「五十を越えて、この先、老いてどうなるかと不安に思い、老後の手だてはないものか、と。神頼みするにも神社はなく、寺はなく、仕方のなしに子持ち岩に参ったそうにございます」
「そうですか」
「はい。もう首でもくくろうかと思いあまって最後に参ったのが子持ち岩。一月十四日の小望月の夜のことと申します」
「なるほど、つながりますね」
「明けて十五日の暁にーー」
「子が宿ったのですね」
「はい。堤田トメに神が降りたのでございます。神に憑かれた、憑神教の始めにございます」
「子供ではないのですか」
「子が宿り、その腹の子が申したそうにございます。我は子持ちの宿神であると。勿論、腹の子の声は出ませぬ。トメさまが腹の子の声を、きりきり口伝えに言うたそうにございます。十月十日、神懸かりとなられ、様々のご信託を下されました」
「踊る宗教というのは」
「神懸かりになられた時は、手も踊る、足も頭も踊り出す、かような様を見た村人が、踊る神だと」
「ご神託は、当たったのですか」
「はいはい。それはもう。天変地異から、天気まで。作付けの豊作不作もたちどころに。加えて胎内巡りをすれば病も治る、それで徐々に信者が増えてーー」
「旦那さんはどうなりました」
「不思議に思った旦那殿も胎内巡りをしたそうな。生まれ変わりかありがたや、人が変わったように働きものに。神懸かりのトメ様に代わって、うちのこともなにもかも全て旦那さまがやっておったそうにございます。やがて信者さんたちの中から、宗教法人としての認可をもらえまいかと私に相談がありまして、微力ながら尽力した次第です」
「山田さんの、元のご職業は」
「はい。弁護士でした」
「それがなぜ、トメさんの後を次いで二代目に」
「それは、トメ様夫妻が、おられなくなったからでございます」
「おられなくなった? 亡くなられたということですか」
「いいえ。消えてしまわれたのです」
「消えた?」
「はい。宿神さまと、トメ様と、旦那様もお消えになりました」
「それは、いなくなったということですか」
「はい」
「トメ様は十月十日の後にめでたく宿神様をお産みになりました。けれど、とたんにトメ様の神懸かりはやんでしまい、普通の母御とおなりになられて」
「神通力がなくなったんですね」
「はい。けれども信者さんは、お構いなしにご神託を求めに参ります。参られますが、トメ様にもうそのお力はない。宿神様はまだ赤子で、言葉もしゃべれぬ。心労に、トメ様の髪は真っ白になられた、と」
「で、トメさんは」
「その心労に耐えきれず、……ありていにいえば、……赤子を捨てたのでございます」
「えっ! 宿神様を捨てたのですか。どこへ」
「わかりませぬな。ある時、京都へゆくとお三人で旅立たれーー」
「なぜ、捨てたと」
「トメ様の書き置きに。信者から責められたトメ様夫婦は、書き置きを残して奥泉から消えてしまわれた。そこには、子を捨てる、と。それから、歌が一首」
「歌」
山田昇は立ち上がって、一枚の紙を持ってきた。そこには、こうあった。
みなかみに もも夜の霜は ふらばふれ 七日七日の月と言われじ
「これは……」
慌てて、鞄から一通目のコピーを取りだそうとすると、青柳がさりげなくそれを肘で邪魔する。見ると、軽くウィンクして、「私も、も少しいいですか」と言う。
鞄にかけた手を降ろしたところで、写真を持って行った信者さんが帰ってくる。
「誰も知らないということでした」
申し訳ありませんな、と山田昇が写真を返す。
「あの、トメさんがいなくなってからの教団は、どのような活動を」
「まあ、見ての通り、お参りの方に、子泣き岩をお巡りいただき生き直していただいております」
「お祭りのときは、どのようなことをなさるのですか」
「それは部外者の方には、ちょっと」
「はあ、そうですね」
「では、この辺で。ありがとうございました」
と、いきなり話を終わらせる。
「いやいや、お役にたちませんで」
「あの、支窟の方も見学していいですか」
「どうぞ。五百円になりますが」
なんだ、また金とるんかい、と思いつつ立ち上がる。
「お時間を取らせました」
事務所から出て、支窟に向かう。
「どうして、手紙を見せるのをとめたんだ」
と訊いてみた。青柳はそれには答えず、別の話を始めた。
「イエスの箱舟事件って、聞いたことがありますか」
「ああ、あるよ。千石イエスとかいうおっさんが若い女性を集めてハーレムつくったってやつだろ」
「まあ、そうですね」
「テレビのワイドショーとかでやってたのを覚えてるけど、最後、捕まったんじゃなかったっけ」
「ええ。でも、裁判では無罪になったんですよ」
「えっ、そうなのか」
「自分の娘たちが新興宗教に拉致された、洗脳されたって親たちは騒いだけど、こういうの難しいんです」
「なんだ、俺のこと言ってるのか」
「いえ、そうじゃなく一般論です。成人した人間の自由意志を制限するのは難しいって」
「やってることが無駄だっていいたいのか」
「いえ、そうじゃなくて、あたしは、というか警察は危惧してんです。イエスの箱舟事件があって、そういう判決が出て、その後、新興宗教を捜査するってことのハードルがあがったんです。オウム真理教の事件だって、もっと早くから捜査しとけばって、あのとき散々いわれたようですが、そういう経緯があって、警察は二の足を踏んだんです」
「じゃ、ほっとけって言うのか」
「違います。二の足踏んで、あんな大事件が起こってしまったんで、より迅速に、そして深く内定捜査をしなければいけない、と」
「青柳、おまえ憑神教の専従とか言ってたよな」
「はい」
「もしかして公安?」
「ノーコメントで。それより、お持ちのコピーですが、潜入捜査員が書いたものと思われます」
「え、じゃ三人と関係ないのか」
「関係はあります」
みなかみに こと夜のしもは ふらねども 七日七日の 月と言われじ
「こうでしたね」
「そう、さっき見せられたものと上の句が違う」
「暗号です」
「なんで、そんな七面倒なことするんだ」
「内容を知られたくないからです。誰かに見られたときに、いいわけできるように」
「さっきから、随分断定的だなあ。この歌の意味が分かってるのか」
「はい」
「知ってるんなら、なぜもっと早く」
「言ったはずです。捜査上の秘密は申せませんから」
「じゃ、なぜ今話す」
「蔵さんに利用価値を認めたからです。なかなか有能です」
「バカにしてんのか」
「いいえ、山田昇と蔵さんの会話で、随分事情が整理されました」
「で、歌の意味がわかるのか」
「はい。憑神教が求めていることも」
「教えてくれるのか」
「勿論です。ただし捜査への協力者としてですから」
「分かってる」
「その前に、ちょっとショッキングな話かもしれませんが」
「なんだ」
「娘さんの、アカリさんのお腹には赤ちゃんが宿っていると考えられます」
頭の中が白くなった。
「どういうことだ。そんなこと……信じられない」
「まあ、父親には内緒だったんでしょう」
「そんな、大事なことを、ほんとうか」
「まあ、まず間違いはないと思います」
「どうしてそんなことが言える」
「目下の憑神教の最大の関心は、二代目の教祖を誰にするか、です」
「それがなんだ」
「まあ、聞いてください。山田昇は、自分ではないって言ってました。トメの書き置きを信じるなら、赤ん坊は捨てられました。赤ん坊イコール子泣き岩の宿神ですから。トメも子供もいなくなった憑神教は、今、大変危機的な状況が続いていると言えます」
「でも、大祭の時は盛況だったそうじゃないか」
「民間信仰として考えるならね。観光寺なら問題ないでしょう。ただ宗教として考えたとき、その中心になる人物がいないと、それは宗教としては衰退する。さっきの話じゃ、たいした教義もないみたいだし、占いができないまでも、みんなが納得するような人間が教祖に収まらないと、早晩崩壊します。でも、誰だっていい訳じゃない。資格がいる」
「どんな」
「トメさんのことを考えると、妊娠してること。神託ができること。そして、……」
「もしかして、それがアカリだと言ってるのか」
「たぶん」
「そんな馬鹿な。アカリは神懸かりになんかなったことはない」
「まあ、おいおい分かることですが。あと一つ、どうも納得のいかないことがあるんですが……と、着きましたかね」
支窟は、本殿の向かって左側、お守りなどを売っている社務所奥にあった。こちらは洞窟がそのままむき出しで、穴の大きさは本窟とさほど変わりない。近づくと、もぎりの爺さんが寄ってきた。
「あ~、穴にお入りなさるかね」
「はい。お願いします」
「おひとり、五百円のお布施になるが」
「はいはい」
お爺さんが首から下げている箱にお金を入れる。お布施なんで、きっとお釣りは出ないのだろう。
「じゃ、お入んなさい。お洞の中は私語厳禁。ずっと奥まで参れば子無し岩がござる。それに触れて戻ってこられよ。生き直し生き直し。ありがたやありがたや」
行こうとすると、青柳が来ない。振り返ると、爺さんと話している。
「奥まで入ると、何があるんですか」
「今言うたろう、子無し岩がござそうろう。それに触れて戻ってーー」
「もう一度」
「なんじゃ、子無し岩」
「子泣き岩じゃないんですか」
あっと、爺さんは自分の額を打つ。
「しもうた。子泣き岩じゃ。いつもの受付の女の子が休みで、わしはアルバイトなんじゃ。間違うた。すまんすまん」
「お爺さん、本当は子無し岩なんでしょう?」
「こちらの窟は子無し岩、あちらの窟は子持ち岩。昔から、そう言い伝えられておる」
「さっき、山田さんとお話したら、あちらの窟は子泣き岩、別名子持ち岩、と」
「ああ、宣伝宣伝。山田さんは商売人じゃからなあ、まあ宣伝よ。子無しじゃイメージ悪かろう。じゃ、いっそのこと二つとも子泣きにしようと。まあ、あの人は地元の人でもないからの。こだわりはないんじゃろ。じゃが、わしは代々奥泉よ。昔から、子無し岩、子持ち岩と決まっておる」
「対なんですね」
「そうじゃ。本来は、両方参るものなんじゃが、山田さんが湯の出る方を高うしたんで、あっちにはあんまり人が行かん。で、あっちもこっちも御利益はいっしょということにして、両方まとめて子泣き岩。まあ客集めよ」
「こっちには湯は出ないんですか」
「赤子がおらねば産湯はいるまい」
「ああ、なるほどね。で、こちらを参れば子宝に恵まれる、と」
「まあ、そうじゃな。子がない悲しみを子無しの神さんはよう分かっていらっしゃる。それで、自分の子を人に授けるのじゃぞ。そやから、いつも子が無いばかりじゃ」
「ああ、なるほどね。じゃ、こっちにお参りしてからあっちに行くんだ」
「まあ、そうじゃ」
「私たち、もう子持ち岩にお参りしたんですが、これだと逆参りになりますね」
と、爺さんの顔が曇った。
「つかぬことを訊くが、あんたのお腹に子はおるか」
「そんな、いませんよお」
と青柳はクネクネする。爺さんは、ホッと息を吐いて、営業スマイルに戻る。
「まあ、今はどちらも子泣き、二つ入ればご利益二倍じゃ」
青柳は顔を近づけて真顔で訊く。
「ほんとに二倍なんでしょうねえ」
負けじと爺さんも、悪い顔をする。
「二倍じゃぞ」
「子無しに、子持ちに、子泣きねえ。ししゃもみてえだな。だけど、お前、呼び名に変にこだわるんだな」
「し。ここからは私語厳禁ですよ」
支窟の道行きは、本窟とほぼ同じだった。ただ、あのオドロオドロした声は聞こえない。真っ暗闇をずっと行き、やはり一筋の明かりに照らされた子無し岩を撫で戻ってくるばかりだ。子無し岩というだけあって、ただ女がうつむき加減で座っているだけのように見えた。
窟から出ると、爺さんはいない。見回すと、社務所の中のお守り売り場所に座っている。自然、足がそちらに向かう。
結構な量のお守りだ。懐妊祈願。安産祈願。学業成就。交通安全。家内安全。昇進栄達。金運招来。健康祈願。恋愛成就。お守りの横に、パンフレットも置いてある。さっきの事務所にも大量にあった。それをつまみながら、
「なんでもありだな」と青柳に言う。
「ひとつ無いですけどね」
パンフレットを鞄にしまいながら青柳が言う。
「なにが」
「欣求浄土」
「死んだ後の世界か。でもそんなお守り、普通みたことないぞ」
「みんな死んでからのことなんか、興味ないんでしょうねえ」
爺さんと目が合う。
「これなぞどうか」
と差し出されたお守りには、「待人到来」とある。爺さんの目を見る。
「待ち人にあえますかね」
「御信心御信心」
四百円だして、そのお守りを買った。
社務所の隣に道があって、「関係者以外立入禁止」とある。
「奥は何ですか」
「宿坊」と爺さん。
「泊まれるんですか」
「今は、憑神さんの道場でしてな、一般の方は泊まれません」
「実は、人をさがしてまして、中に入れてもらう訳にはいきませんか」
「それはご遠慮くださいませ。信者さんだけです」
「なんとか、なりませんか」
「案内してさしあげよう!」
と大音声。本窟に誘ってくれたあの若い信者が出てきた。
「あ、先ほどはどうも」
「身内の方が行方知れずなのですな。お写真、拝見いたしました。それから、そう、あなたは疑っておられる、当憑神教を」
と僕をのぞき込む。
「ちがいますかな」
「どうでしょう」
破顔一笑。信者はカカと笑う。
「まあ、よろしい。ついてきなされ」
「入場料はいいのですか」
「これはお手厳しい。まあ何事もお社あってのことでな。いろいろと金がかかるのだ」
道の奥までたどり宿坊についた。戸を開けると、信者たちが作務衣姿で、正座し頭を垂れ、瞑想していた。四、五人のグループがだった。下は二十くらいから上は七十くらいの老女もいる。
「みんな女性なんですね」
「この講はそうですな。同じ罪人ごとに部屋に集まり祈っておるのだ」
「罪? ここはどんな罪なんですか」
「子無し。子殺し。子捨てを悔いて、生き直ししている方々です」
「えっ、子供ができないのは罪ではないでしょう」
「罪とはなんですか。法律ですか。我々が司るのは心の問題ですからな。自分で罪人と思えば罪人です。それから逃れるには、生き直ししかありますまい」
「男にだって罪はあるでしょうに」
「勿論。数は少ないが、例えば、私もこの講の罪人のひとりです」
「と、いうことは」
「子を捨てました」
「捨てた」
「里子に出しました。今はどこでどうしているやら。後で悔いても詮無いこと。けれど、詮無い詮無いで人生を過ごしては、やはりいけませぬな。いけませぬ、というのが憑神教の教えです」
「ここにいる方々は、自分の子供を……」
「私のようなものもおります。また、子を病で亡くした方も。自ら手をかけた方までも」
「救われますか」
「それは、わかりません。心の問題ですから」
「救われる人はいますか」
「それは、おります。自分を見つめ、自分の罪を見つめ、生き直すことに道を見つけたものは、人の世に戻ってゆきます」
「戻れない人もいるのですね」
「はい。迷いにある方は、この道場で祈ります。自分で生き直しできないものは、宿神様に尋ねます。自分の罪を、生き方を」
「答えてくれるのですか」
「御神託が心に降りたものは救われます」
「誰かが、それを言うのではないのですね、そのトメさんのように」
「教祖様のような方は今はおりません。ですが、この道場で祈れば、心に神が宿ります」
「ひとりひとりに神が憑く、と」
「憑神教の教えにございます」
「他にはどんな罪が?」
「そうですな、例えば、欲に溺れたもの、怒りに満ちたもの、貧しく飢え世に恨みをもつもの、自らの地位に得々とし他人を欺こうとしたもの、などなど」
「まさに六道の苦しみですね」
「さようさよう。それぞれの罪ごとに祈りを捧げる」
「ここは子供に対する罪人というわけですか」
「さようさよう」
見渡して、妻やアカリ、義母の顔はない。当たり前だ、見える場所にいるはずはない。祈りを捧げる女の中に、ふと、薄目を開けて、それとなくこちらを見たものがいる。青柳が、自分の頬を自然な感じで二度叩く。あの女が潜入捜査員なのかもしれないと思った。
「信者さんに話しかけてもいいんですか」
「はい。どうぞ。ですが、あまりプライベートなことはご遠慮ください」
と余裕である。青柳は近場の老女に話しかける。
「すいません。お話、よろしいですか」
「はい、なんでしょう」
「もう、入信されて長いのですか」
「まだ半年でございます」
「祈って、何か変わられましたか」
「はい。気持ちが癒えるような気持ちがします」
「宿神さまは憑きましたか」
「それが、まだなのでございます」
老女は少し悲しそうな顔をした。
青柳は何人かに同じような質問をして、あの女に質問した。
「出身はどちらですか」
「京都です」
「ここの暮らしはどうですか」
「心の湯治と思っております」
「そうですか」
青柳は若い信者に向き直って訊く。
「この方たちの出入りは自由なのですか」
「勿論勿論。夕飯の買い出しにも参らねばなりませんしな。お参りにきた方のお世話も大切な仕事です」
それから部屋を六つほど見て回ったが、それぞれの四、五人のグループの中に、やはり三人はいなかった。
「よろしいかな」
「有り難うございます」
「誤解は解けましたかな」
お社の石段を下りながら青柳が言った。
「どう思いましたか」
「いや、怪しいに決まってる。状況証拠は何から何まで憑神教だ」
「きっと、どっかに匿われているんでしょうね」
「決まってる。ただしつこい所を見せすぎると、二度と接触できなくなるから、押さえてたんだ」
「はあ、なるほどね。蔵さん、考えてますねえ」
「そりゃそうさ。で、山田昇との話だが、なんで急に打ち止めにしたんだ」
「えー、そうでしたかあ」
「そうだろ! たくさん話させて尻尾をつかもうと思ってたんだぞ」
「そりゃ、どうもすいません」
「なんか魂胆があったんだろ、言え」
「そんな、別にです」
「言え」
「困ったなあ」
「言え」
「まあ、そんなとんがらなくっても。和歌が暗号なのは言いましたよね」
「そうだ、暗号の意味を言え」
「そりゃ、私には分かりません。国語の先生なんだから、蔵さんの方が詳しいんじゃないですか」
また、痛い所を突いてくる。
「わかんないから訊いてんだ」
「いや、あたしが言いたいのは、そこじゃないんです」
「じゃ、どこだ」
「山田昇の話によると、堤田トメは無学なお百姓さんということでしたね」
「ああ」
「和歌なんて、作れるでしょうか」
「なるほど」
「あっ、そうだ。山田昇が出してきた方の和歌、スマホで検索してください」
「そんな、忘れちまったぞ」
「ご安心あれ、ちゃんとこっそりメモってます」
「さすが公安」
「ちょっと、蔵さん、それは言わない約束でしょ」
「そうだっけ」
スマホで検索しても、やはりない。
「どうする。八方塞がりだぞ。これから、何をすればいい」
「今、何時ですか」
「そうだな、そろそろ五時か」
「どうりで暗くなってきた。じゃ、ここで一泊しますか。明日は京都です」
「えっ、なんで京都」
「潜入捜査員が言ってたじゃないですか。京都って、それにトメが向かった先も京都でしょ」
「そら、京都はわかるが、京都ったって広いぞ。どこ行けばいいんだ」
「あれ聞かなかったんですか。トウジだって」
「湯治って、心当たりあるのか湯治場の」
「湯治場じゃありませんよ。トウジ。京都でトウジと言ったら、決まってるじゃありませんか」
「あっ、東寺」
「トメさん夫婦は京都へ逃げた。京と言えばお寺でしょう。まして、心の助けを求めるのなら尚更です。子を捨てるにしても、誰かに拾われることが前提なら、やはりお寺。違いますかね。あと、あの歌も」
お月さんいくつ
十三ひとつ
まだ年ゃ若い
七折着せて
おんどきょへのぼしょ
おんどきょの道で
尾のない鳥と
尾のある鳥と
けいちゃいや あら
きいようようと鳴いたとさ
「きょへのぼしょ」は「京にいこう」と言ってるんじゃないですか。
「ああ、なるほど。そう言われれば、おんどきょ。今度京か。そう読めるな」
「尾のない鳥と尾のある鳥は女と男、トメ夫婦とあいますし」
「そうか、そうだな」
「ちょ、お布団、近くないですか」
駅前の旅館に泊まることにして、別部屋を頼んだのだが、断られた。なぜだか、わからない。で、ひとつ部屋になったのだが、敷かれた布団が近いと青柳が文句を言っているのだ。
「ずっと、向こうの壁際まで引っ張っててくださいね」と言いつつ、自分の布団も逆側の壁に引きずっていく。それから、真ん中の空いたスペースに座卓を横にして立てかける。
「いいですか。あたし空手の有段者ですから、襲ってきたら痛い目みますよ」
「何にもするもんか」
「ああ、それからあたし警察官ですから、くれぐれも」
「わかったって。もう寝ろ」
「それから、小さい電気はつけといてください」
「何にもしないって言ってるだろ」
「いえ、少し明るくないと眠れないんです。お化けでそうで」
「全く」
警戒してるとか言った癖に、ものの四、五分で、青柳は寝入った。今日のことを反芻しつつ、僕は長く眠れなかった。
お月さんの年はいくつ
十四(で子持ち)
まだ年若なのに(子持ちかえ)
七折(子に)着せ
今度京に上りましょ
今度京行く道で
女と男が(子を捨てて)
(子が)「帰っちゃいやだ
戻ってきてよ」と泣いたとさ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

