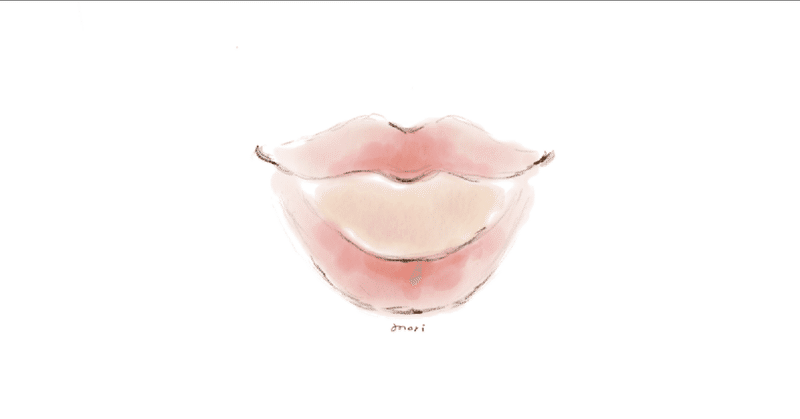
捜査員青柳美香の黒歴史Ⅲ
翌朝は、早めに京都に立った。昼前には京都について、駅ビルで腹ごしらえした後、東寺を尋ねる。警察手帳の効果は絶大で、すぐに寺務所に通され、事務方の人と、年輩のお坊さまとで対応してくれた。
ひと通り話してみても、あまりよい反応はなかった。随分昔の話ではあるし、しかし、捨て子があったことが事実なら、覚えている者もいるはずだ。山田昇が見せた和歌も見てもらった。お坊さまは、すこし拝借してもよろしいか、と奥に消え、代わってご老体のお坊様が出て来られる。座につくや、メモ書きを私に返し、捨て子も歌も存じております、と言う。
「よかった」
と青柳と目を合わせて喜ぶ。
「お話いたしましょう」とお坊様は語り始めた。
「ーーその歌は和泉式部のものと存じます。さて、お二方はその和泉式部をご存じですかな。王朝時代に歌の上手と言われたお人じゃ。その和泉式部と東寺には、深いゆかりの伝説がありますのじゃ。
和泉式部は宮仕えの折り懐妊し、公に遣える身ながら子を産む。それを恥じた和泉式部は、その子を、ここ東寺の門前に捨てましたのじゃ。
そこに子のない夫婦が清水寺に参ったのち、東寺を訪れ、捨て子を拾うたという。捨て子の横には、和歌が一首。
みなかみに もも夜のしもは ふらばふれ 七日七日の 月と言われじ
時は流れ、行く末に不安を抱く歳になった式部は、捨て子を探す旅に出る。巡り巡りて、ある山里にたどり着き、一夜の宿りを請うたところ、老夫婦に似合わぬ娘がいる。聞けば、東寺の捨て子と言う。歳も合う。そこで我が子と式部が言うが、証しがないと翁に言われ、それこの歌に覚えがないか、とさきの歌を歌うたそうじゃ。
まさにその歌と、親子はめでたく再会した、と。その娘は後に小式部と名乗ったそうな」
「なるほど。歌は同じです。意味はなんでしょう」
「歌の意味か」
「はい」
「髪の白くなるのなら、いっそ白髪になればよい、それでも、人に子持ちと笑われまいよ、くらいの意味かの。七日七日は十四夜。十四夜は小望月、子を持つ月であるからな」
「なるほど、みなかみは、皆髪。総髪のことか。そして、しもは白髪のことだ」
「和泉式部の髪は白かったんですか」
「さあのう。しかし、こういう歌がある以上、子を持つには、いくらか歳をとっておったのかも知れぬな」
「そういえば、山田昇はトメさんがいなくなったとき、その髪は真っ白だったって言ってましたね」
「さて、捨て子のほうでございますが、もう五十年も過ぎた昔でござるかのう」
「昭和四十年前後か」と僕が呟くと、
「よくわかりますね」と青柳。
「俺の歳が五十一だからな」
「ああ、なるほど」
「さよう、昭和で言えば四十年くらいの頃であったか。東寺の門前に捨て子があった。寺で預かる訳にもゆかず、警察へ届けて、その後、どこぞの里子に出されたということじゃ。まあ、東寺の門前であったのも何かの縁、もしや母御が後々名乗り出ぬとも限るまいと。これが証拠にと、東寺の住職が、和泉式部にちなんで、和歌を子に添えたと言うことじゃ。それがお持ちのその歌じゃ」
「で、母親は現れたのですか」
「いや、総白髪の婆様が門前をしきりに通ったと伝え聞くが、赤子の母にしては、年が開いておったというが」
「トメさんだ」
「で、そのおばあさんは?」
「何か事情を知っておるかと、問うてみたがな。さすれば、先の日に、赤子を門前で見たという。どうなっておるかと心配で、などと言うので、これこれこういう事情で里子に出した。赤子は無事じゃと言うたそうな」
「その時、和歌を」
「ほっとする婆の様子は尋常ではなかったし、飯もろくろく食うておらん様子であった。聞けば、和歌山辺りの村から来たという。何か、知っておるに違いないと思うたが、無理に口を割らせる訳にもゆかぬ。ただ、手がかりとして、この婆に先の和歌を告げたと言うことじゃ」
「その和歌がーー」
「憑神に伝わった」
「もう五十年も昔のこと、あの婆様はとうに亡くなっておろう。その歌を知っておるとすれば、あのときの赤子か、育てた母か。それが、つい一月前のことーー」
育てた母か。老僧の言葉に、はっとした。知っているとすれば、育ての母。五十年くらい前のこと。妻宛の手紙。もしかしてーー。
「ーー訪ねて参ったのじゃよ。その捨て子と育ての母御が。あの和歌を持ってなあ」
そうだ。妻は、静恵は義母江田紀子の養女であった。
だから、あの和歌は妻宛だったのだ。堤田トメの娘は、堤田トメの捨てた子は、妻だったのだ。東寺に捨てられたことを義母は知っていて、それで訪ねた。しかし、なぜに今頃。
頭の中がぐるぐる回る。なるほど妻は、霊的なものに興味があった。日本の霊場巡りを趣味としていた。いや、それは趣味ではなく、自分探しの旅だったのか。
義母は東寺のことを知っていたのだ。しかし、なぜ、今。
「アカリさんのお腹には赤ちゃんがいます」
青柳の言葉が甦る。それが、それが、きっかけか……一通目のあの和歌。
みなかみの こと夜のしもは ふらねども 七日七日の月といわれじ
白髪のない若い身であるけれど 子持ち女と笑われまいよ
それはアカリのことなのか。
「ひと月前、二人が訪ねたときのことを教えてください。あ、まず写真を、写真を見てください」
一目見て、老僧は、そうこの方々じゃ、と頷く。
「育ての母と捨て子であったお子と、さらにそのお子と三人で参られましたの。どう言おう、婆様と母御と娘御と言うことにしようかの」
と老僧はお茶を飲む。喉を潤してか咳をひとつして話を続けた。
「まず、お三方がなぜ東寺を訪ねに参ったかそれからお話いたしましょう。母御の話されたところによると、娘御にお子が宿ったとのことじゃった」
やはりか。予期はしていても、はっきりそうと知らされて、僕は少なからずショックを受けた。
「娘御は、お腹のお子を堕ろす算段。母御はお子を生かす算段。父御に言うこともできず、婆様に頼ったそうな。まあ、男親には言いにくいことであったのじゃろうな」
そんな、なぜ相談してくれない。親じゃないか。心配かけまいと思ったのか。そうじゃない、何か困りごとがあるのなら、相談してくれてたじゃないか。今まで、きっとそうだったじゃないか。何か、ひとり、取り残されたような気がした。そうして、ここで一人だけ、別の場所にいて、三人の後を追い回している。僕はいったい何なんだ。寂しさと、空しさと、砂を浴びたような莫とした情けなさと、様々な思いが頭を駆けめぐった。
「まあ、そこをお責めなさるな。父御思いの故のこと。そうお思いあれ」
そう思わねば、やりきれない。気がつくと、僕は頭を下げ、写真を強く握りしめていた。
「御坊様、お続けください」青柳が言う。
「お腹のお子の父親は、まあ無理筋ということじゃった。自分のことのみ考えおって、結婚なぞは興味がないそうな。その若者が堕ろせと言うて、言われてそのままそうするつもりで、じゃが、その日、娘御は迷うたそうな。その余りの憔悴ぶりに、母御が問うて、ことが知れたと。驚きあきれ、ここで普通の母御なら、やはり堕ろす算段をとったであろうか。世の母御のほとんどが、愚僧思うに、堕ろす算段をとったであろう。娘御は、春から職に就きなさる、とな。昨日まで親御がかりで育てられ、ようよう羽ばたくその時に、子を宿し、子を産み落とし、飛べようか。しかも一羽で。飛べはせぬと、堕ろすはやむえぬ。そう思うが親心。けれどもな、この母御は違うたな。何故ならば、母御は捨て子じゃ。我が身を思うて、お腹のお子が不憫に思えた。それに相違なかろう。世の常ならば堕ろす算段。生まれの筋で思うたならば、これは、やはりの、生かす算段。迷うて、迷うて、答えがわからぬ。そこで婆様に、育ての親に問うたのじゃろうよ。婆様は、そこは育ての親である。子は生かせよ、と言うたろう。我が娘御とその孫と、命を粗末に扱うな、そう言い聞かせ言い聞かせ、さては東寺に参ろうと、二人に約し、三人そろうて参られたとな。それがここに参られた理由であると」
「自分がどうして、今あるか、おばあさんはアカリさんに、それを教えたかったのね、たぶん」
青柳が言う。僕はなぜだか泣いていた。その苦しみの中に、なぜ自分を入れてくれなかったのかと、ただ悔しかったのだ。
「お坊様と話されて、心は決まったように見えましたか」
「たぶんのう。わしも知るかぎりのことは話した。産むか生かすかどちらかは、それは聞かなんだがの」
「ほかに、三人は何か言ってましたか」
「これから、和歌山のどこぞの村を訪ねると。どこかは忘れたが」
「奥泉か。だが、どうしてトメさんが奥泉村出身だとわかったんだろうか」
「奥さんは、パワースポット巡りが趣味だとか、言ってましたよね。和歌山で探せば、憑神教に行き当たるのは、そんな無理筋じゃない。お社に、あの和歌が残ってるなら尚更でしょう」
「なぜ、和歌が残っていると、わかる」
「もう、蔵サン。憑神教のパンフレット見てないんですか。お社の観光PRに、あの歌、堂々と載っかてますよ」
青柳はコートの内ポケットからパンフレットを取り出した。
「社務所にたんと置いてありましたよ。お守り買ったところにも」
見ると、確かに書いてある。お社全景の写真。子泣きの由来。トメの御神託。生き直し。六道の説明。それから、入窟料一覧。勤行と言うのもある。二泊三日。ここだけ料金がない。応相談、とだけ。それから、あの和歌。なるほど、商売好きな山田昇のやりそうなことだ。
丁重に老僧にお礼を言い、東寺を辞去した。三人は憑神教のあの建物のどこかにいる。すぐにでも、とって返して山田昇に詰め寄りたいところだったが、青柳は、もう一日、明日まで待てという。
「なぜだ」
「だって、今日は、もう遅いし」
「そういう問題じゃない。一刻を争うんだ」
「今日も明日もいっしょでしょう」
「いっしょじゃない! 何言ってんだ。俺は一人でもいくぞ」
「ちょ、ちょっと。ちょっと待って」
と袖を引かれ、振り向くと、
「ああ、しょうがないなあ」と青柳が天を仰ぐ。
「わかりましたって。言いますよ、明日まで待たなきゃならない理由」
「なんだ」
「明日、潜入捜査員と会う約束なんですよ」
「道場にいたあの女か」
青柳と目配せした女のことを思い出した。
「そうですよ。いま、勤行やってて、あの日から二日後に会う約束です」
「そんな約束いつしたんだ」
「見てなかったんですか。こうやって二回ほっぺた触ったでしょ、あたし」
「ああ、確かに」
「だから、待ってくださいよ。今、山田昇に会いに行ったって、シラを切られたらいっしょじゃないですか。どこかに監禁されてるにしても、どうやって探すんですか、令状もないのに」
「俺には、そんなもの必要ない」
「あたしには、必要です。まあ、待ってくださいよ」
「潜入捜査っていっても、なにやってんだ」
「お腹へりました。あそこの食堂入って、食べながらでいいですか」
今風の若い女性の身なりの癖に、大衆食堂と思われる小汚い店にすたすた入っていく。
「どしたんですか。こういう店の方がおいしいんですよ」
席について、僕の分まで勝手にカツ丼を頼む。それで、出てきたカツ丼をばくばく食う。
「ね、おいしいでしょ」
食欲はない。つきあい程度に箸を運び、言えよ、と言った。
「何調べてるんだ」
「詐欺」
「憑神教は詐欺やってるのか」
「まあ、そう」
「だまされたって、宗教では難しいだろ。心の問題だし。信じて金払っても、それが罪になるのか」
「宗教ならね」
「憑神教は宗教法人だろ」
「でも、教祖はいない。でしょ」
「ああ、いないな」
「教祖様のご神託を有り難いと思って、信者はお金を払うわけでしょ」
「お布施っていってたな」
「そう。どっちにしてもお金を払う」
「でも、それは詐欺にはならないだろ。今、教祖がいなくても、教えが続いているなら、それを信じて金払うなら罪じゃないだろ。教祖がいなくて宗教じゃないんなら、キリスト教だって仏教だって、同じじゃないか」
「でも、キリスト教には聖書があるし、仏教にはお経があるし、神父や牧師やお坊さんが、勝手にご神託したりしない。教えに従って信者を導くわけでしょ」
「でも、時々いないか、神の声が聞こえたとかいう奴」
「それは、いいのよ。本物だもの」
「本物?」
「その人は、本当に神のお告げが聞こえたと信じてるんだろうし、信者さんもそれを本当に信じている。宗教性はあるわ」
「憑神は?」
「山田昇は神の声を伝えない。宗教者じゃない。自分でも、そうだって言ってる。トメさんの教えを伝えるだけの役割だって」
「まあ、そんなこと言ってたな」
「でも、今、憑神教の教えは、たぶんトメさんの言ってたこととは違う。六道うんぬんだって怪しいものよ。あの本窟で聞いた声、あんな声、テープで流してるだけでしょ、おかしいと思わない?」
「あ、まあ、そうだな」
本窟で聞いた声に、自分がまともに答えようとしたことは、言えなかった。そうか、あの時、自分はまるめこまれようとしていたのか。
「まあ、でも五百円、五千円の程度なら、私らだって動かなかったかもしれないけど」
「もっと払わされるのか」
「問題は勤行なのよ。パンフレットにあったでしょ。応相談って」
「いくらぐらいなんだ」
「二百万」
驚いた。たいした額だ。
「そんな、でも、普通に考えて、そんな額、払うわけないだろう。二泊三日で」
「普通の状態ならね」
「普通じゃないのか」
「私たちが訪ねたのは、たぶん初日。だから道場の中まで案内してくれたのよ。勤行が始まるのはこれから」
「なにが始まるんだ」
「最初に順繰りに懺悔させて、人それぞれの罪をみんなの罪として共有させる。最初は、ののしるみたいね。お前は罪人だ。みんな罪人だ。人非人だ。人の皮を被った化け物だ。人殺しだ。生きる価値もないとか」
「ひでえな」
「それから、瞑想に入って、自分の罪を見つめる。あたしたちが行ったのは、その頃かしらね、やがて、あのテープが大音量で流される。それでますます精神的に追いつめる。それを勤行する者は聞き続けなければならない。電気は煌々と照らされる。夜は寝かさないし、あの状況では眠れない。互いが互いを監視して、グループから抜けられない状況になる。食事だって、まともに与えられてない。そんな中で懺悔、懺悔、懺悔。絶望させて、希望をなくさせて、最後に、生き直しできるのは憑神教だけだって、教える。すがるものはこの世に、他にない。生きながら、生まれ変われるのは子持ち子無しの宿神様だけだとね。おすがりなさい、おすがりなさい。最後はそれの大合唱よ」
「逃げるのは自由だって言ってたが」
「自由よ。でも、あそこに来る人は、自分のことを罪人だと思ってる。なんとかそれから免れたい、生き直したいと考えてる。憑神教に救いを求めてる。はじめから、そういう暗示にかかりやすい人たちなのよ」
子無し。子捨て。子殺し。あの若い信者は、勤行する人の前で、わざとそう言った。自分の犯した罪を自覚させ、そうして暗示をかけるのか。
「しかし、二泊三日でかかるのか」
「睡眠不足と情報の洪水。ほかのことは一切考えさせない集団催眠。自分をひたすら罪人だと思う人間に、二泊三日は長いくらいよ。正常な判断を失わせておいて、寄進を募る。二百万。払えば救われる。絶対他力。欲を持つな。生き直し。産まれたとき、人は何も持ってないはずだ。財産がお前の罪を作るんだ。欲が生き直しを阻むんだ、てね」
「それで、支払いの判を押しちまうのか」
「押します。一度だけでは飽きたらず、何度も財産を寄進する者もいる。全てを寄進して、憑神教の下部になる者もね、あの若い信者さんみたいに。でも中には、押して、しばらくたって、暗示が解ける人もいる。でも、それから、金を返せといっても、いったん寄進したものは返らない。それで、訴訟に」
「勝てる?」
「勝てない。宗教ならばね。だけど、憑神は、今は宗教じゃないってのが、警察の見解なのよ。その尻尾を捕まえるための潜入捜査。どうですか、その捜査結果を聞いてからでも、遅くないんじゃないでしょうか」
なるほど。山田昇と対決するにしても、あくまで宗教法人として対されたら、厄介かもしれない。三人は、憑神を信じて、自分の意志で、ここにいる。そう言われると、確かにやっかいだ。それなら、少しでもこちら有利なものがあるほうがいい。宗教であること自体を否定できれば、だが、どうやって。
「わかったよ」
アカリの妊娠の話で混乱していた頭が、ようやく正常に働きはじめたらしい。比較的、冷静に青柳の話を受け止められた。そうだ、しっかり準備をして、それで山田昇と対決して、三人を必ず取り戻す。
僕は冷めたカツ丼をかきこんだ。あれだけ喋っていた青柳は、もうカツ丼を食べ終えて、二杯目の茶を飲んでいた。
その日は京都に部屋別で泊まり、翌日、あの駅前旅館に戻ってきた。旅館の亭主は、前と同じ部屋を用意した。
「二部屋ないの」
と訊いてみたが、それがちょっと申し訳ございません、と言うばかり。
部屋に向かう途中、青柳が文句言う。
「蔵さん。思い詰めすぎ。死にそうなんだもん。だから、一人にしたくないんで、同部屋なのよ、きっと」
そうか、と思った。廊下の鏡に自分を映すと、確かに憔悴している。疲れ切った顔をした男が、そこに映っていた。
部屋でくつろいでいると、電話が鳴る。フロントから、お客様です、の声。
「どうぞ、通してください」
と言いおいて、ほんの二、三分後、土気色した顔でふらふらになった捜査員が、部屋の中に倒れ込んできた。
「オカリン! 大丈夫? ミカリンだよ、わかる」
助け起こしながら、青柳が「布団、布団」と大声で叫ぶ。
心配してついてきた宿の主人に、「あと一人、泊まりで。もう一組、布団用意してくださあい」と言って追い出し、押入から布団を引っ張り出して潜入捜査員オカリンを寝かしつける。
「これじゃ、当分、だめね」
青柳が両手を広げ、パアのゼスチャーをする。仕方ない。事情を聞くのは、明日になるか。
翌日の昼過ぎまで捜査員オカリンは爆睡し、起きて飯を三杯食べた。
「はい。一通目の手紙は、私が出しました。大祭の日、なんとかアルバイトでお守り売場に潜り込めたとき、あの三人が来たんですよね。山田昇さんに会うにはどうしたらいいかって。まあ、とりあえず住所と氏名を書いてもらって、それでその場の責任者みたいな人に取り次いでもらったんです。まあ、捜査員の性といいますか、山田昇に関係ありそうなものはメモしとくんで、それで送れたわけです。三人は、なんか偉いさんに連れてかれて、その後、戻ってこないんですよね。なんか心配になっちゃって、顔色も悪かったし、なんか深刻そうだったし、それで大事にならなきゃいいなと、とりあえずその住所に手紙をだした訳です。身分は明かせませんが、まあ消印で場所はわかるか、と。あの和歌ですか、まあ、みなさん白髪じゃなかったんで、変えてみようか、と。一応、国文の出なもんで」
「二通目は」
「探っていって、でも何もわからず、そんなとき、あのお月さんの歌が、道場から聞こえてきたんです。なんか初めて聞いたような、どこかで聞いたような。とりあえず書きとめて、捜査資料として署に送った次第です」
「しかし、署でも、なんだかわからず、とりあえず蔵さんに送ってみて、反応を見ようということになりまして。それで、あたしが」
「二通目をいれたのは、お前か」
てへ、と青柳が頭をかく。
「でも、蔵さん、何にも知らなかったんですよねえ。歌まで歌ってあげたのに」
「お前ら、まわりくどいんだよ!」
「だって、身分は明かせませんし、三人は心配だし、捜査内容は漏らしちゃならないし。大変なんですよ、ねえ、オカリン」
「ミカリンの言う通りなんです」
「頭、痛くなってきた。でも、まあ。これで手紙の謎がとけたな。あと、他にわかったことは」
「それは、ちょっと」
「ここまできて、まだ隠すのか」
「どうする、ミカリン」
「ちょっとだけならね。もうだいぶ分かっちゃってるから」
「じゃ、ちょっとだけ。山田昇って大金持ちなんです。でっかい家に住んでて、車もごっついのに乗ってます」
「ていうことは、教団のお金を私(わたくし)してるってことか」
「そうでしょうね。あと、独身です。あの広い家にひとりだけ。あ、犬がいるか。それだけ。よく住めますよね。寂しくないんですかね。あたしなんて、ごろっと寝返り打って壁が手に触れないと、落ち着いて眠れないのに」
「関係ないよ」
「ああ、そうでした。これで情報ストップです」
「しかしオカリン、よく二百万払わずに返ってこれたね」
うんうん頷きながら、青柳が茶を注ぐ。うまそうにひとくち飲んで、捜査員はフウっとため息をつく。
「そうなのよ。死ぬかと思ったわよ。みんなポンポン判ついて、あれ完全な洗脳ね」
「まあ、宗教は洗脳ちゃあ洗脳だからねえ」
「宗教と違うって。だって、あの洞窟で聞こえる声とか、山田昇が勝手に考えてんのよ。会議で他の人に意見きいたりするってよ」
「ほんと。じゃ、神の声ってトメさんと関係ないじゃない。やった、でかした。よく探り当てた。憑神教は、やっぱ詐欺だ。で、証拠はあるの」
「はいよ、会議の内容、ばっちりボイスレコーダーに録音してあります。これ録るの大変だったんだから」
「ちょっと。やるじゃんオカリン。神の声みたいなのを会議で決めて金巻き上げてるって分かったら、これはもうダマシに断定。お手柄ね」
「でしょ。でもね、最後の仕上げの勤行はきつかったあ~」
「眠れないんでしょ」
「もともと不眠症だから、まあ、それは」
「あんな爆睡してたくせに。まあ、いいや、で、テープがガンガンするんでしょ」
「それは耳栓しといたから」
「懺悔は」
「うそっぱちだから。あたし、子供いないし。適当に言ってた」
「でも、なんというか、その場の雰囲気によく呑まれなかったねえ」
「そうなのよ、聞いてくれる。私ね、ずっと、神木くんとお話してたの。それで乗り切れたの。神木くんってやっぱり神ーー」
「だれだ、神木って」
「神木龍之介よ。テレビで見たことないんですか。最近は声優としても有名!」
「芸能人か。その芸能人がいたのか」
「いるわけないじゃない。だから、頭の中の神木くんとずうとおしゃべりしてたわけ。神木くんとなら一週間だってしゃべれるわ」
「お前も違う意味で特殊だな」
「オカリン。やっとその特殊能力が発揮できる時がきたのね」
「そうなのよ、ミカリン。これで私も部長にほめてもらえるう~」
オカリンとミカリンはひしと抱き合い、感激の涙を流す。もうやっとられんわ。
夕方、僕は憑神教の社(やしろ)に向かう。潜入捜査員オカリンは、情報を伝えるべく東京に戻る。
「警察が令状持ってきて、家宅捜索するまで待てっ言っても、蔵さん、行くつもりでしょ」
青柳が言う。
「ああ」
「しょうがないなあ。じゃ、つきあってあげます、か」
おっこらしょ、と立ち上がった青柳はなぜだかとても頼もしく思えた。
夕焼けの光線が石段を赤く照らしている。枯れ葉が風に舞う。気温がだいぶ下がってきて、空気の冷たさに頬が痛む。
「お前、そんな格好で寒くないの」
相変わらずのミニスカート。今日は全体緑系でまとめている。
「大丈夫です。鍛えてますから」
「虫みてえだな」
「相変わらずデリカシーゼロですね」
「いくぞ」
「はい」
石段に足をかける。三人はこの上のお社のどこかにいる。いや、もしかしたら、山田昇の家かもしれない。どこにいようと、必ず、必ず見つけてやる。
知らず拳を固く握っていた。悪い予感が頭をよぎる。相手には二泊三日で人間を洗脳してしまうノウハウがある。三人は捕らわれて、もうひと月になる。普通に考えれば、何も起こっていないと考える方がおかしい。すっかり暗示をかけられ洗脳された三人を、自分は正気に戻せるだろうか。
石段をずんずん上る。一足一足が覚悟の時間だ。大丈夫。自分に言い聞かせながら上る。アカリの顔が、妻の顔が、義母の顔が、浮かんで消える。あの日の笑顔を、僕は取り戻せるだろうか。
取り戻せるさ。取り戻せるに決まってる。赤ちゃんができたって。なんだメデタいことじゃないか。俺が育ててやる。そうさ。家族みんなで育ててやるさ。何を恥じることがある。命の尊さ。それを共有できれば、勝てる!
石段を上がりきって、社を見る。その間にある六つの輪。ずんずん歩いた。
天人道
修羅道
人間道
畜生道
餓鬼道
地獄道
全てくぐって、社に向かう。社は夕闇に紛れ、黒々と僕たちの前に、あった。
あの若い信者が駆けてくる。
「もう、本窟、支窟のお参りはなりませぬぞ。よろしいか」
「山田昇に会いたい」
僕はそう言った。
「山田、昇」
言い方に剣があったのか、若い信者は警戒の表情を見せた。
「ここにいるのか、いないのか」
「失礼では、ありませんか、そのものの言いようは。お引き取りください。取り次ぐわけにはいきません」
「大石と伝えなさい。あなたの判断でなく、山田昇に伝えなさい。大石が来たと。東寺に参って、一部始終を聞いてきた、と」
若い信者はは怪訝な顔をした。そして更に、今日は御引き取りください、と尚も言ったとき、青柳が進み出て、警察手帳を鼻先に突きつけた。
「四の五の言ってるんじゃないよ。国家権力が、山田昇に会いた言ってんだよ。黙ってサッサと取り次ぎな! 痛い目みたいか。公務執行妨害でしょっぴかれたいかい!」
若い信者は瞬時に青い顔になり、しばしお待ちを、と言い置いて社務所に走る。
「ミカリン。本気か?」
「蔵さん。討ち入り二人ですまないね」
「なんの、百人力さ。俺は必ず三人を取り戻す」
「微力ながら、あたしもご助力いたします」
「武張ったことがおきたらーー」
「お任せあれ、伊達に空手はやっておりません。ああ、東京オリンピックに空手が採用されるなら、公安なんて行くんじゃなかった」
「やっと認めたな」
「知ってた癖に」
覚悟は決まった。胸の息を全部吐く。
そうさ。やってやろうじゃないの。中学教師を舐めんなよ!
薄暗い本殿、本窟を背後にした板の間が急に明るくなる。信者たちが出てきて、篝火を焚く。やがて、山田昇が歩いて出てきて、板の間の真ん中に立つ。その横に信者が二人ずつ。全員が山伏のような白装束で、庭にいる僕たちを見下ろした。山田昇が進み出て口を開いた。
「またのお越しでございますかな」
「三人を返してもらう」
「三人?」
「妻と娘と義母だ。ここに来ているのは分かっている」
「ああ、東寺の坊さんが申されたか」
「どこにいる」
「お三人様はおられますが、お返しすることはかないませぬな」
「ここにいる娘さんは、警察の人だ。三人が拉致されたことも知っている。数日の内に家宅捜索が入る」
青柳は大きく頷き、一歩前に出る。
「おい、このおっさんの言うとおりだぞ」
青柳は再び警察手帳を掲げ、よおく見せてからポケットにしまい、一歩下がった。その様子を見て、左右四人の信者が笑う。山田昇も表情をくずし、宗教弾圧ですか、と言う。
「宗教。笑わせるな。憑神教は宗教なんてもんじゃない」
「いいえ、憑神教は宗教ですとも。教祖様が長く不在ではありましたが、トメ様のお子さまもお孫様も、育ての母様も。先日お帰りになられました。まことに目出度いことです。これで安泰です」
「その三人を連れて帰る」
「叶いませぬなあ。そういうわけにはいかんのです。三人様は、この地で骨を埋める覚悟ですので」
「洗脳したな」
一気に体中の血が煮え立つように感じた。一歩前に踏み出す。
「おやおや、手荒なことはご勘弁を。老体の身ですからな。静恵様に二代目を継いでいただいたら、私は引退する覚悟です」
「逃げる気ね」青柳がいきりたつ。
「ほう、逃げる? 何から」
「だから、警察が介入するって言ってんだろ。お前等の集団は詐欺なんだよ」
「詐欺? これは異なことを申されるな」
ここで、山田昇は表情を引き締め、大音声を響かせた。
「ならば、問いましょうか。宗教とはなんぞや!」
青柳は突然の大声に気圧されたように身を引く。伊達や酔狂で何十年も代表を続けてたわけじゃないだろう。はったりはお手のものか。
「宗教論を戦わせに来たんじゃない。いいか、三人を連れ帰る」
社の板の間に続く木の階段に足をかける。
「無礼な。土足であるぞ!」
山田昇の右側にいた信者が駆け寄り、階段の最上部に立ちはだかる。あと、二、三段を挟んで睨みあう。見上げる僕と見下ろす男。
「まあまあ、こちらも手荒いことはしとうはない」
男を左手で横にどかし、山田昇がしゃがみ込む。目線の高さが同じになる。四、五十センチの距離で対峙した。
「ここを上ぼりたいんなら靴をお脱ぎ。三人に会いたいんなら、会わせんでもない。じゃが、会っても無駄じゃ。まじめに宗教のことを考えられぬ人間に、三人は会わぬよ」
どうやら宗教問答が三人に会う条件らしい。
「蔵さん。だめよ。相手の口車に乗っちゃあ。蔵さんに勝てっこない!」
そうだろう。勝ってこない。というか、山田昇には、負けの選択肢は端からない。どう言ったって駄目だろう。だが、僕は山田昇の提案に、のる。山田昇に喋るんじゃない。山田昇を言い負かすためじゃない。山田昇に勝とうってわけじゃない。山田昇なんて、どうでもいい。僕は、きっと、必ず、どこかで僕の声を聞いている、アカリに、妻に、義母に、僕の思いを届けたい。それだけだ。
「わかった。靴を脱ごう」
僕は言った。
板の間の上手と下手に丸い籐の座布団が敷かれ、山田昇と僕が対面して座る。僕の後ろに青柳が、山田昇の後ろに四人の信者が控えた。
「用意は調いました。お三方に会わせる資格があるのか、お伺いしても、よろしいか」
まるきり理不尽な問いかけだが、そこは我慢して、頷く。
「そもそも信心というものを、どうお考えか」
「神や仏にすがることだろう」
「そうですな。憑神教では、子泣きの宿神さまにお願いして子を宿す。宿ると信じて参られる。お布施は自由じゃ。なにか問題があるのかな」
後ろから、青柳が叫ぶ。
「子宿しだけじゃなくて、今は何でも屋じゃないか」
「さようさよう」と山田昇は嬉しげに笑う。「宿神さまのお力は、子宿しだけにとどまらず、悩める者みな救うてくださる。まことに有り難いことじゃ」
「それが捏造なんだよ。なんでもかんでも救えるもんか」
「はあはは。これは元気な娘さんでありますなあ。救われるか救われぬかは、心の問題。救われたと思うた者は、救われた。救われなんだと思うたものは救われぬ。救われたと思うた者だけが憑神教を信心する。どこに問題がありますかな」
「救われたと思わせて金を巻き上げるのが魂胆だろう。お前たちが、寄ってたかって神の声とかを勝手に造って、信者をだまくらかしてんのは、わかってんだ。会議の様子も録音してある」
「いけませぬなあ。こっそり録音とは。言うてくだされば、導き言葉なぞ、存分にご披露いたしましたのに。それから、宿神様の声など、我らは代弁してはおりませぬ。宿神様の声が聞こえるのは、あくまで信心される方々、ご自身でございます。我らがやっておりますのは、そのお声が聞けるよう、導きの道筋を作るまででございます」
「なんだ導き言葉って。それが神様の声なんだろ。信者たちには、そう聞こえたんだよ」
「それは、考え違いというもの。ほれ、前にお越しいただいたときに、申しませなんだかな。私は教祖ではございません。代を継いで、二代目教祖になってもおりません。そんな、恐れ多いことは出来ようはずもございません。ない知恵を絞り、あるいはここに控える信者様たちと話し合い、導きの言葉を考え考えしたまでのことにございます」
話が堂々巡りになりそうなので、手で合図して青柳を黙らせた。
「こっちからも訊きたい」
「なんなりと」
「救われるってどういうことだ」
「救われるとは、心の平穏が保たれること。生の苦しみから逃れられること」
「人は罪人か」
「罪を犯した者は罪人でしょう。人が全て罪を負うているとは思いませぬな。私は宗教家ではないので、そうは思いませぬ。しかし、罪を犯した者は、一生を罪に苦しむ。その苦しみから救うてやるのが教えでしょうな」
「三人にはどんな罪がある」
「お三人様は決まっております。子無し。子捨て。子殺しの三罪」
「お前、まさか、そう言ったのか。そう言って追いつめたのか!」
思わず腰が浮く。すかさず山田昇の後ろの男たちが身構える。まあまあ、と今度は山田昇が信者をとどめ、僕もゆっくり腰を落とす。今は、今は喋るんだ。
「事実でありましょうが」山田昇は涼しい顔で言う。「育ての親御様には、子がおらなんだ。哀れに思うて宿神様がトメ殿のお子を授けた。よくぞ育てて、救われた。そのお子静恵さまは、真の母御から捨てられた。その業故に、宿神様が離れてしもうた。神はここへお帰りじゃ。じゃがの、よくぞ捜し当てたの、よう来たの。たどり着いたで、救われた。さて、最後のひとりじゃアカリ殿。喜ばれぬ子を身ごもって、殺す算段おそろしや。ここへ参って、思いとどまり救われた。宿神様は、お三人とも救われた。違いますかの」
「違う。お前らなんかに救ってもらわなくても、僕が三人を必ず救えた」
「おや、ではどうしてお三人は、ここへ来なすったのかの」
「それは、これが自分たちの出自を確かめる旅だからだ。旅が終われば、それが確かめられれば、三人は僕の所へ帰るつもりだったんだ。必ずそうしたはずなんだ」
ーーこっちは、ひどい雪です。名古屋で乗り換えるときは吹雪になって、電車が動くか心配しました。
あの日、にアカリからもらったメールが甦った。メールの終わりはこう結んであった。
ーーお母さんは、張り切ってます。明日の朝、伊勢神宮でお払いしてもらいます。夕方には帰ります。
そうさ、三人は、アカリは必ず帰るつもりでいたんだ。あの日、帰るつもりでメールを打ったんだ。
「おやおや、それならば、なぜ三人はお戻りにならぬのですか。宿神様より、あなたにこそ救われたいなら、なぜ帰らぬのですか。誓って言いましょう。お三人は、このお社から、出ようと思えばいつでも出られる。最初、あなたが来られたときに、黙っていよとはお三人様の意志なのですよ」
ヘックショイィーー!
青柳が突然、大きなくしゃみをする。驚いて、山田昇の言葉が止まる。
「気に入らないなあ、気に入らないなあ」鼻をぐずぐずさせながら、青柳が言う。「救われた救われたって、どう救われたっていうんだよ」
それから盛大にまた二回くしゃみをして、ティッシュを取り出しながら言う。
「お前の言う救われたなんか、誤魔化しじゃないか」そう言ってちーんと鼻をかむ。「お前、何言ってんだかわかんねえんだよ」
「おやおや、風邪を召しましたかな。この寒いのに、おみ足まるだしでは寒かろうて」
後ろの信者どもが笑う。
「なんで子供の無いのが罪なんだ。捨てられた子のほうに罪があるってなんだ。子供を堕ろすのは犯罪か! 今の日本じゃ、どれもこれも罪なんかじゃねえんだよ!」
「法律のことを申しておるのではありませんな。心の問題。それをお助けするのが我々ですから」
「罪を犯した者を救うのが仕事とか抜かしたな」
「その通りです。罪なき者に、憑神は、いえ宗教というそのもの全ては、必要ございませぬな。罪人の心をお救いするのがーー」
「そんなん。全然救われてないんだよ!」
青柳が立ち上がる。四人の信者も立ち上がって身構える。山田昇は座ったままだ。穏やかに青柳の顔を眺めている。青柳は山田昇を指さして、声のトーンを一段とあげた。
「そんなん。逃げてるだけだろう! いいか、罪人は自分の罪を忘れちゃいけねえんだよ。苦しまなくっちゃいけないの。それを神様にあずけて、私救われましたなんか、許しちゃなんないの。一生背負って生きてくんだよ」
「そこで、生き直しでございます。人間は弱いものです。その罪を一生背負える者もおりましょう。けれど、背負えぬ者もおりまする。では、その背負えぬ者は救われぬのか。いえいえ、自分を悔い、罪を悔い、そればかりあるならば、宿神様を信心なされて、生き直し生き直し、ああ、ありがたや、ありがたや」
しまいの「ありがたや」は信者四人も声をそろえる。青柳は怒りに声が震えながら、尚も続ける。
「そんなのマヤカシだ! 盗んだ者は救われるのか」
「救われます」
「騙した者は救われるのか」
「救われます」
「人を、人を殺して救われるのか」
「救われます。憑神教を信じなさい。宿神様を信仰しなさい。ああ、ありがたや、ありがたや」
再び五人が唱和する。
言葉が通じない。そう思った。こいつらは、僕らと違う価値観の中にいる。これ以上、言葉を継いでゆく意味があるのか。言葉を継いで、その意味が伝わることは、きっと、永遠に、それはない。
「話は尽きましたかな。では、お帰りくださいますか」
「帰れませんね。僕はまだあなたとしか話していない。三人があなたと同じ考えだとは到底思えない」
「弱りましたなあ。こうまでご説明申し上げても、御納得いただけませぬか」
「納得は、できない」
「よろしい。それでは、お三人様に会わせましょう。ただし、約束していただきたい」
「何を」
「お三人様の意に反して、連れ帰るようなことはなさらぬと」
「三人がここへ残るのなら、それを尊重しろって言うんだな」
「そうです。無理に連れて戻られても、必ず三人様はお戻りになられるでしょう。なぜなら、それが三人様のお気持ちだからです」
イエスの箱舟事件のことが頭をよぎる。家族が無理に連れ戻しても、結局女たちは千石イエスの元に戻った。成人した女性が自分の意志で行動することに警察は介入できない。警察署での部長さんの言葉が甦る。いや、三人のは信仰じゃない。彼女たちは確実に洗脳されているんだ。じゃあ、その洗脳が、この短い時間で解けるのか。やってみるしかないだろう。
信者が二人、本窟の中に入っていく。やがて信者たちと同じ白装束を着た三人が現れた。静恵。アカリ。お義母さん。懐かしい三人は、しかし、おぼつかない足取りで、山田昇の隣に立つ。
名前を呼んだ。けれど、三人に反応はない。帰ろう、と続けた。やはり、三人は、ただ僕を見つめるばかりだった。
「お父様です」山田昇が言う。「はるばる東京からおいでです」
三人が頷く。
「お連れになりたいそうです」
静恵の眉根に皺がよる。アカリは目を泳がせ、静恵を見る。義母はなにか、言いたげで、でも途中でよして、やはり静恵を見る。どうやら、二人の意志は静恵にあるらしい。責めさいなまれて、自分の心のより所を二人は静恵に預けたらしいのだ。静恵さえ、こちらに引き戻せれば、あるいは何とかなるかもしれない。
「静恵」
ともう一度呼びかける。
「迎えにきた。戻ろう」
静恵は何も言わない。
「アカリのお腹の子のことは知っている。悪かった。何も気づいてやれなくて」
アカリが小さく首を振り、また母を見る。
「僕も一緒に考えさせてくれ。アカリが産みたいのなら、いいじゃないか、僕とお前とアカリで育てよう。お義母さんだって手伝ってくれるから。な。そうしよう。こんな所になんかいなくて、新しい家族をみんなで作ればいいじゃないか。お義母さん。それで、いいですよね」
義母は頷きそうになって目をそらし、それからやおら静恵を見る。
風が吹き込み、静恵の髪を揺らす。静恵は眉間に皺を寄せたまま、怖いような顔をして僕を見る。これが、この女が何十年も連れ添った妻なのか。何十年の重みが、ほんのひと月の洗脳で消えてしまうのか。
「頼んでも」静恵の口が開く。「頼んでも、駄目です。私にはもう、宿神様が憑いている」
いつの間にか、信者四人と山田昇は、静恵の方に向き直り、深々と頭を下げていた。
「お前は宿神なんかじゃないだろう。お前は大石静恵だ。僕の妻だ」
「そうだったのかもしれない。でも、今はそうではない」
「箱根に旅行も行ったろう。アカリの受験の時は大変だったな。お義父さんのお葬式の時、みんなで語り明かしたな。思い出してくれ。俺たちは何十年も夫婦だったんだ」
静恵は黙ったままだった。やがて、きびすを返して本窟の方に歩み出す。義母もそれに従い、アカリは一度だけこちらをちらりと見たが、やはり静恵に従う。
これまでか。やはり、無理なのか。
「お分かりかな。お帰りなさいませ。何度通われても同じこと。お三人様は、もうあなたのもとへお戻りにはなりませぬ」
山田昇がそう言った。
青柳が僕の隣から飛び出した。気づいた信者が前を塞いで、たちまち青柳は跳ね飛ばされる。ひっくり返って頭を打った。どうみても、運動神経が良さそうには見えない。あれ?
「蔵さん。行っちゃうよ。止めなきゃ!」
はっと我に返り、僕も三人に追いすがる。でも、やはり同じに突き飛ばされ、青柳の隣に倒れ込む。
「蔵さん。弱ッ!」
「お前だって。空手の有段者だろ」
「エッ、あれ嘘だよお。蔵さんに襲われるかもしれないから、予防線」
この緊迫した場面で脱力させる。
「申し上げましたよ。お三人様の意に反して、お返しはできぬと」
勝ち誇ったように山田昇が言う。どうなる。どうすればいい。
「静恵さぁーん!」青柳が馬鹿でっかい声を出す。瞬間、静恵が振り返る。「いいんだね。ほんとに行っていいんだね。後悔ないね」
「後悔などーー」と言い掛けたとき、青柳は跳ね起き、僕の頭を横抱きにした。えっ。な、なにをーー。
いきなり青柳は僕の口に、チューをした。
静恵の位置からは、青柳の頭しかみえない。でも、僕の顔は確実に静恵に見えている。僕も青柳にチューされながら、静恵の目を見る。静恵が僕の目を見る。
一回離して、青柳は大声上げる。
「静恵さん。蔵さん、もろうた。あっち行けーー!」
それで再びチューをする。口と口だ。思わず、後ずさりする。だけど、青柳は僕の頭を離さない。じりじり僕ににじりより、距離を必ず詰めてくる。こ、これは。混乱した。いや、僕とて男だ。二十代の、うら若き女性と、いや、だが、もう、諦めていたというか、なんと言うか、いいのか、いや、それで、いや。これで。
山田昇が、信者の四人が、目を丸くして、硬直して、僕らを見ている。いや、その位置からだと、青柳のパンツ丸見えだろ。いや、そんな、こんな、いや、もっちょと、いやいや、深刻であるべきで、ああ。
「なっ」
誰の声だ。いや、なんか、もう、誰だって。
「なっ、何やってんだ。このウスラ馬鹿!」
ああ、聞き慣れた、っ、聞き慣れた? なに、誰? 全力疾走で、静恵が駆けてくる。たちまちにうちに青柳を引きはがし、呆然と、にやにや顔の僕の頬に、思い切り、渾身の力で、グーパンで、殴りつける。
グーで? と僕は思った。グーはないだろ。右頬の、中の奥歯が浮くようだ。確実にやられた。
山田昇と信者たちは、どうしていいやら、わらわらしている、静恵に、近づいていいやら、離れていいやら、足を差しだし、足を止め、顔を見合わせ、あまりのことに、体自体が動かない。
ぷ。と声がした。胸ぐら捕まれて、更に制裁のビンタを食らう僕を見て、あ、アカリが笑う。堪えきれずに、アカリが笑う。義母も。義母も笑う。その間に、なぜか、僕は殴られ続ける。なぜ。なぜ。殴られながら、ああ、静恵は、笑っている、笑ってそして泣いている。とうとうしまいに、いや、それは、静恵は僕にちゅーをして、お、息が、鼻までかぶすな、ちゅうーをして、それから、大声で笑い出す。
「司さん。お家に、帰る!」
静恵のその言葉を聞いたとき、山田一味は膝から崩れた。青柳は、青柳は僕ら二人の周りを、なにか、わけのわからぬ踊りを踊って、何周も、何周も、駆けていた。
「静恵、連れて帰るぞ」
両頬の痛みを感じつつそう言うと、今年五十一の静恵は言った。
「はい。必ず来てくださると、信じて信じて、私は待っておりました」
って、ほんとかね。
「ああ、とうとう入ったなあ」
テレビを見ながら署長が言う。憑神教の社務所に、今まさに十数人の捜査員が入っていくところだ。道場をはじめとした他の建物にも別働隊が入っている。
「青柳、今回はご苦労だったな」
「はっ。署長とお別れするのは、辛うございます」
直立不動の青柳がそう答える。
「また、心にもないことを。古巣に帰ったら、なんだっけ、潜入捜査員の岡本くんにもよろしく伝えてくれ」
「は。かしこまりました」
制服姿の青柳は、返事と同時に敬礼する。
「でもなんだ、あの奥さん以外はかかってなかったんだって、洗脳?」
「深くは。アカリさんは、最初山田昇に会ったとき、逆参りしろと言われたらしいです」
「逆参り」
「普通は、子無し岩、子持ち岩と巡るのですが、悩みを告げたとき、山田昇は、子持ち岩、子無し岩の順に逆参りしろと言ったそうです」
「へえ、逆参りね」
「逆参りすれば子は堕ちる、と。脅しです。できないことを見越して、そう言ったと思われます。それをきっかけに三人を追いつめていったようです」
「そうか。ひでえ奴だな。で、山田昇はあげられそうなのか」
「山田昇は、自分は憑神教の顧問弁護士だ。いわば憑神教教団に雇われている。雇用関係の中で、報酬をもらっているだけだ、と供述しています」
「馬鹿か、今更」
「馬鹿です。弁護士のくせに」
「意見が合うな」
「恐縮です。山田昇は早晩起訴は免れないと推察します」
「まあ、そうだろうな。ところで、大石一家は、その後どうなんだ」
「は。大石静恵をはじめ失踪した三人は、無事、大石司と暮らしてます」
「アカリさんは」
「残念ながら、雑誌社の内定は辞退したようですが、子供は産む決意です。代わりに子供の父親の青年が、改心して今は地道に働いているということです」
「ほう、よかったじゃないか。それで、お前がチューした大石司は?」
「は。復職して、先日、無事卒業生を送り出したとのことです」
「担任だったんだろ。生徒も大変だったろうな」
「いえ、副担任の若い魅力的な女性の先生が全てうまく仕切ったようです。生徒からは、卒業式の呼名を、大石先生ではなく、その若い魅力的な女性の先生にお願いしたいと署名運動まで起こったと仄聞しております」
「まあ、若い魅力的な女性の先生なら、そっちの方が生徒もいいだろうな」
「は。自分もそう思いますが、大石司は、その役を絶対譲らず、生徒、保護者双方から大いに顰蹙を買いながら呼名を行いました。見上げた馬鹿です」
「あ、そうなの。よくわからんけど。ハハ。まあ、それぞれの鞘に、それぞれ収まって、よかったってことでいいのかな」
「は。自分もそう思います」
「で、お前、そのチューした大石司と、あの後、会ったの」
「いいえ。自分としては、それは一刻も早く忘れてしまいたい黒歴史です。あの日以来、一度も会っておりませんし、連絡もとっておりません」
「そうなの。随分世話になったから、向こうもお礼なんか言いたいんじゃないの」
「いえ。私はあくまで職務として大石司に接触しました。事件が解決した以上、これ以上の接触は無用と考えます」
「へえ、公安って固いんだんなあ」
「署長! それは言わない約束です」
了
参考文献
1、北原白秋「お月様いくつ」
2、奈良絵本「小しきふ(小式部)」解題 https://www1.gifu-u.ac.jp/~gulib/koshiki/kaidsi.html
小しきふ・下 https://www1.gifu-u.ac.jp/~gulib/koshiki/koshige.html
岐阜大学図書館
3、泉鏡花 「蛇くひ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

