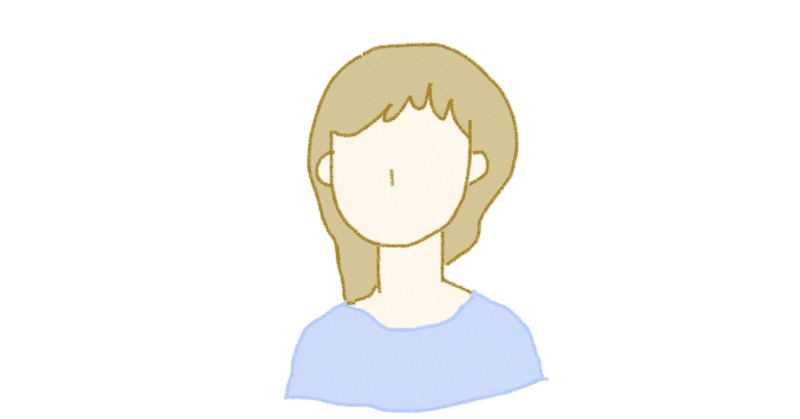
村上春樹「夏帆」
ある女性が、友人の紹介で会った男に、君のような醜い女性に会うのは初めてだ、と言われる話である。
村上春樹は、悪意が現れる様を、よく小説に書く。初期は、デートした女の子を逆の電車に乗せてしまったとか、身内にひどい不幸があって注文したケーキのことをすっかり失念するとかいった、偶然の、想定外に犯してしまった悪意を書いた。それは悪意とも呼べない、普通に考えれば過失といった類のものだ。そしてその過失を起こすのはきまって主人公の側だ。人生にそうした過失は起こりうるもので、それもまた人生だみたいな話が多かった。喪失感を抱えながらも、基本的に春樹は人間を信じており、性善説の側にいた。
それがサリンを経験し、東日本大震災を経験し、海外に住みよりリアルにテロや戦争を経験して、春樹は変わっていく。この世界には悪意が確かに存在する、と確信するようになる。それは自分のそばに確かにいる、と。
今、経験と書いた。勿論これらは作家が直接体験したことではない。が、体験したと同じくらいに作家の心を揺さぶったはずだ。
地下鉄サリン事件で、例え車両に乗っていなくても、作家はサリンを体験した。同様に、作家は大地震を体験し、今、現に戦争を体験している。そういうことだ。
手に負えない不可避の、いつ突然に現れるかも知れない悪意と、すぐ隣り合わせで作家は生きている。勿論私たちも。それがリアルな現実だ。悪意は日常の中にも潜んでおり、不意に襲いかかってくる。作家はそう言っている。
小説の後半で、醜いと言われた女性は絵本をかく。少女が自分の顔を探しにいく話だ。
村上春樹という作家は、よく寓意を使う。羊男だったりリトルピープルだったり。読者はそれがなんのメタファーか考える。では、自分の顔を探す少女はなんのメタファーか。それは人が悪意に対抗し、それを打ち負かす方法を示唆するものなのか。
この小説は考えることを求めてくる。私の出した答えは、ごく単純な、シンプルなものだ。その答えで世界にある悪意に対抗できるのか。それはわからないが、何も考えないよりずっとマシだということだけは確かだと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
