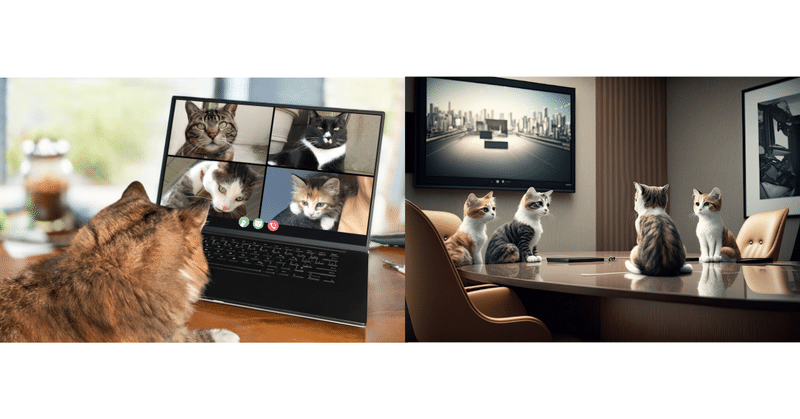
ハイブリッドワーク時代の組織文化継承のヒント
私にはここ3年くらい考えてるけどハッキリと答えが出ない大喜利のお題があります。それはハイブリッドワークと組織文化の継承についてです。
出張で使うものだったリモートアクセスのシステムが、東京五輪を前に公共交通機関の混雑緩和の一策として政府の呼びかけ(?)で在宅ワーク(テレワーク)のツールとして進化して、職場以外で働くことが一般的になりました。
そして、2020年春からのコロナ禍によってリモートワークは世界中で一気に広がり、新しい働き方としてハイブリッドワークが一般的になっているのはご承知の通りです。
ただし、ハイブリッドワークではメンバー全員が職場に集まらないため、組織の文化や同僚との信頼関係に基づいたうまい仕事の進め方などのノウハウや暗黙知は、どのように継承されていくのかが、今後の課題になると思っています。
今回の電脳随想録では、ハイブリッドワークにおける組織文化の醸成や継承という観点で答えを見つけるための4つのヒントを書きたいと思います。
はじめに
テレワークは、働く個人や企業にとって利点が多いです。しかし、ハイブリッドワークという働き方では、複数年にわたって人々が作り出す「組織の文化」を作り、継承することができるのか、という疑問がまだ解決していません。
リモートワークを牽引していたGAFAMなどの大手企業がオフィス回帰の方針を打出して1年以上立ちましたが、「個人のしあわせ」と「組織の発展」をどのようにバランスさせるのかに一つの正解はなく、現在は日本でも各社各様のハイブリッドワークが行われています。
文化とは「民族や社会の風習・伝統・思考方法・価値観などの総称で、世代を通じて伝承されていくもの」と辞書に書いてあります。私なりに言い換えると「同じ場所で暮らす人々の知識と知恵の集まり」と言えると思います。
組織の文化が「同じ場所で働く人々が作り出すもの」だとすれば、「仕事」と「仕事場」を切り離して考えざるを得ない現在、どのように作れば良いのでしょうか。また同じ場所にいなくても組織文化を醸成し継承することは可能なのでしょうか。
4つのヒント
①絆が生まれる条件は、所属なのか? 一緒に過ごした時間なのか?
私の好きな映画監督に是枝裕和という人がいます。彼はさまざまな作品を作っていますが、一貫して伝えているメッセージは「家族や友達との絆は、血のつながりや制度ではなく、一緒に過ごした時間の長さによって作られるもの」と私は理解しています。
これを会社に当てはめると、部署やグループに所属しているだけでは素晴らしい関係を築くことはできない、となります。実際に一緒に協力して仕事をした時間や、業務内外で過ごした時間が、人々の関係性に大きな影響を与えると言えます。
最近は、組織内での協力や意見交換には「心理的安全性」という言葉が使われます。これは、人々が良好な関係を築いて初めて実現できると言えます。また、一緒に過ごした時間も重要だと思います。
悩みのポイントは、この「一緒」が物理的な場所に関係するのかどうかです。
②メンバーと会話する: コミュニケーションとカンバセーションの違い
コミュニケーションは目的を持って会話することを指します。一方で、カンバセーションは会話すること自体が意味を持つと言われています。
コミュニケーションでは目的に応じた結果(質問への答えや合意など)が得られます。一方、カンバセーションの後に得られるものは相互理解やセレンディピティ(偶然に出会う幸福のこと)であると言えます。
「リモート環境でもコミュニケーションできていますか」というアンケートで、「問題なく取れている」という回答が見られます。オンライン会議では目的のある会話が行われているため、問題なくコミュニケーションができているのは当然だと思います。
一方で、これが「リモート環境でもカンバセーションできていますか」という問いだとどうでしょうか。
例えば、職場で何気なく聞こえてきた会話に入って雑談した経験は誰にでもあるかと思います。同じような経験をハイブリッド環境で実現する手段はデバイスの「常時オン」かなと思いますが、全く同じ環境を再現するのはまだ難しいと思います。
「テレコミュニケーション」ではなく、ハイブリッドでも遠隔の同僚とスムーズな会話が可能な「テレカンバセーション」を提供できる最適なデバイスとかサービスはどのようなものがあるか、考えてみる価値はあるのかも知れません。
③リアルで会わないと仕事の信頼関係は築けないのか?
①と②ではリアルもしくはリアルタイムで共働するメリットについてのヒントを見ましたが、人は非リアル、且つ非同期だと信頼関係を築いたり大きな仕事を成し遂げられないのでしょうか。
世の中には、世界中の会ったことのない人たちとリモートワークだけで素晴らしいプロダクトを作り上げる事例がいくつかあります。例えばオープンソースソフトウエア(OSS)のプロジェクトです。
では成功しているOSSにはどのような背景や仕組みがあるのか見てみましょう。
OSSの世界にはBDFLという言葉があります。それは開発プロジェクトのリーダーに与えられる称号で、BDFL (Benevolent Dictator For Life)は「慈悲深い終身独裁者」と訳されます。
元々は、Pythonプロジェクトを開始したGuido van Rossum氏を指す言葉として作られたそうですが、一般的にはコミュニティ内で論議・論争が発生した際に最終的な仲裁を行う権利を持つ人のことで、プロジェクト創設者であることが多いようです。
Guido van Rossum: Python
Linus Tobals: Linux
Andy Rubin: Android
Yukihiro Matsumoto: Ruby
Matthew Mallenweg: WordPress
etc...
共通しているのは、リーダー本人が圧倒的な技術力とビジョンを持ち、それに共感・共鳴したエンジニアたちが自分の時間と能力でビジョンの実現に貢献し、そのエンジニア達とリーダーとの間で意思決定していく仕組みが出来ているということですね。
これをリモートワークの意味付けやベストプラクティスとして一般企業に当てはめると、リーダー本人にエンジニアが共感し敬服する技術力やビジョンがあるか?ということが問われることになりなかなか厳しいものがあります。
ただし、それはテック系の新興企業などでは普通のことかも知れませんし、リーダーの立ち振る舞いによってはハイブリッド環境、フルリモート環境でも信頼関係を築き、大きな仕事を成し遂げることは実現可能であると思います。
④ヒトが生物界の頂点に君臨できたのはナゼか?
私は「ユヴァル・ノア・ハラリ著:サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」という有名な本を読んで、地球上でホモ・サピエンスが支配者となった2つの大きな理由が分かりました。
まず、ホモ・サピエンスは①共通の言葉と文字を発明し、思考を共有することができるようになりました。また、②ホモ・サピエンスはフィクションを信じる能力も発達しました。
この進化によってサピエンスは「血縁関係のない他人と協力して集団で目的を達成することが可能になった」ということなのだそうです。
動物は集団で狩りをすることがありますが、獲物が見つかりそうな場所へ行くためには「明日、丘の向こうに行こう」という意思伝達ができるのはヒトだけです。
言い換えると、他人と協力できるかどうかは、みんなが同じ理解を持ち、共通の言葉や目標(ビジョン)を信じることができるかどうかにかかっています。
だから、リーダーの役割が非常に重要です。
しかし、この力を使っても、現在組織にいる人々にとっては良いですが、会社では常に人員が入れ替わります。長年にわたって共有し、受け継いだ共通の言葉やビジョン、経験や知恵を維持するためには、日々の記録や成果物を共有し、情報を検索できる仕組みが必要です。
このような「知識と知恵を共有・継承できる仕組み」が整備されて初めて、組織文化の継承が可能になると考えます。
今後この仕組みを実現するためには、ICTをどう役立てるかというところがポイントだと思います。しかしながらGAFAMという、計算機とソフトウエア、そしてネットワークの利活用では世界を席巻する企業がオフィス回帰を表明しています。
彼らの業態では、リモートワークもしくはハイブリッドワークのデメリットが見えているということかと思いますので、良く分析する価値があると思います。
おわりに
新しい働き方時代に組織文化を作り、継承するために必要なことを4つのヒントから考えてみました。
「関わった時間の長さと相互理解によって人々の関係性は強いものになるが、リーダーがメンバーを率いてビジョンを実現するためには共通理解のための用語の定義が必要であり、その経験や知識を組織や世代を超えて継承するには共有するための仕組みも必要である。」
というのが現時点での私なりのまとめですが、だからオフィスワークが良いとかテレワークが良いとか、ハイブリッドワークならこうすればよいというところまで結論できていないのが現実です。
おそらく、世界中でハイブリッドワークの形態が永続的に続くと思われます。企業の文化や良い点を引き継ぎ、組織の維持と発展を促進する試みは続けられるでしょう。
その中で、様々な人やグループに関するベストプラクティスを共有する仕組み、このnoteを含むプラットフォームでの情報共有の重要性が高まっていくと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
