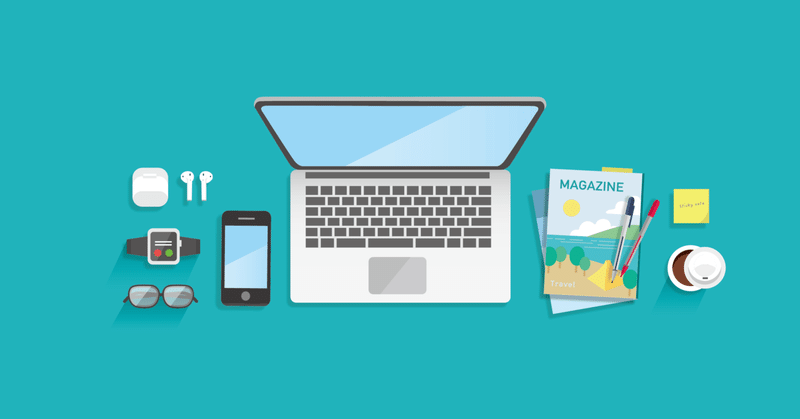
J-PlatPatを使った特許調査
誰でも無料で使うことができるJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を用いて特許調査を行う方法を解説します。
1.特許・実用新案検索を選択
まず、J-PlatPatにアクセスして、特許・実用新案検索を選択しましょう。

なお、J-PlatPatのパンフレット・マニュアル・講習会テキスト等はこちらで提供されていますので適宜参照してください。
2.キーワードで予備検索
調査の対象は、「CRISPR/Cas9を利用して生体内(in vivo)でゲノム編集を行う技術」とします。
まずは、キーワードを用いて予備検索を行いましょう。
検索項目は「特許請求の範囲」を選択して、キーワードは「CRISPR」と「vivo」を入力して検索ボタンをクリックしましょう。
この検索では、特許請求の範囲に「CRISPR」及び「vivo」の両方が記載された文献がヒットします。

予備検索の結果、約140件がヒットしました(※2023/10/20時点)。
キーワードで「CRISPR」と「vivo」を含むものを検索しましたので、特許請求の範囲に「CRISPR」と記載がないものはヒットしません。

3.特許分類の調べ方
どうしたら、「CRISPR/Casを用いてゲノム編集を行う技術」を適切かつ効率的に検索することができるのでしょうか。
このような場合に有効であるのが特許分類(FI)を用いた調査です。
特許分類は、発明の内容に対して付与される記号で、特許文献を検索することを目的として技術毎に細分化されています。
以下に、特許分類の調べ方をいくつか紹介します。
特許分類の調べ方はこちらの記事も参照してください。
(1)パテントマップガイダンス
パテントマップガイダンス(PMGS)で特許分類を調べてみましょう。
以下のように、キーワード検索を選択、検索対象は「FI/ファセット」、キーワードとして「CRISPR」を入力して、検索をクリックします。

検索の結果を以下に示しますが、C12N15/09,110というFIが「・・・CRISPR/Casを用いるもの」に関する特許分類であることがわかります。

特許分類には階層構造があるため、C12N15/09,110をクリックして、上位の特許分類を確認します。
1つ上の階層である・・(ツードット)のC12N15/09,100が「・・ゲノム編集技術,例.TALEN,ジンクフィンガーヌクレアーゼを用いるもの」であること、
2つ上の階層である・(ワンドット)のC12N15/09が「・組換えDNA技術」であることがかわります。
つまり、C12N15/09,110は「・組換えDNA技術において、・・ゲノム編集技術に関し、・・・CRISPR/Casを用いるもの」となりますので、今回の調査対象の特許分類として適切であることがわかります。
(2)J-GLOBAL
また、J-GLOBALで特許分類(IPC, FI, Fターム)のランキング表示することもできます。

「CRISPR」と入力して、検索対象として「特許」を選択して検索を実行しましょう。
検索の結果、CRISPRに関する特許の一覧が表示されます。
「フィルタで絞り込み」の欄を選択すると、出願年や、出願人などと並んで、FIやFタームなどの特許分類についてもランキング形式で表示させることができます。

上位のFIから順番にパテントマップガイダンス(PMGS)の「コード照会」で調べることで、適切な特許分類を見つけることができます。
(3)ChatGPT
特許分類を調べるためにChatGPTを用いることも有効です。
例えば、以下のように質問をすると、関連するIPC(国際特許分類)として「C12N15/09」などが提示されます。
提示された特許分類について、パテントマップガイダンスの「コード照会」で下位の階層を含め確認することで、適切な特許分類を見つけることもできます。

4.特許分類を用いた検索
(1)特許分類(FI)×キーワード
次に、「CRISPR/Cas」に関する特許分類(FI)である「C12N15/09,110」を用いて、検索を行いましょう。
予備検索では、検索項目として「請求の範囲」を選択していました。
本検索では、検索項目として「FI」を選択して、キーワードの欄に「C12N15/09,110」を入力して検索を行いましょう。

キーワード同士の掛け合わせ(AND演算)を行った場合と比較して、ヒット件数が約20件増えて、請求の範囲に「CRISPR」の記載のない文献もヒットしていることがわかります。
このように、キーワードのみを用いた場合よりも、特許分類を用いて検索を行うことで、調査対象の技術を適切かつ効率的に調査することが可能です。
(2)キーワードの同義語もカバー
次に、同義語もカバーすることで、より網羅性(再現率)を高くしましょう。
「vivo」について、同義語を調べて、「生体 体内 生物内 生物中」というキーワードを追加して調査を行った結果を示します。
同義語の調べ方はこちらの記事を参照してください。

調査の結果、同義語を増やす前よりもヒット件数が約200件増えて網羅性がより高い検索となりました。
5.まとめ
以上のように、キーワード同士の予備検索から初めて、特許分類(FI)とキーワードを併用した本検索により、目的とする技術を適切かつ効率的に検索することができます。
皆さんも自分の探したい技術について、特許分類を調べて、効率よく目的とする技術を見つけてみて下さい。
論理式入力を用いた本格的な調査については、こちらの記事で説明していますので、興味がある方はご参照ください。
特許調査に関する情報発信も行っており、執筆や講演もnoteにまとめておりますのでご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
