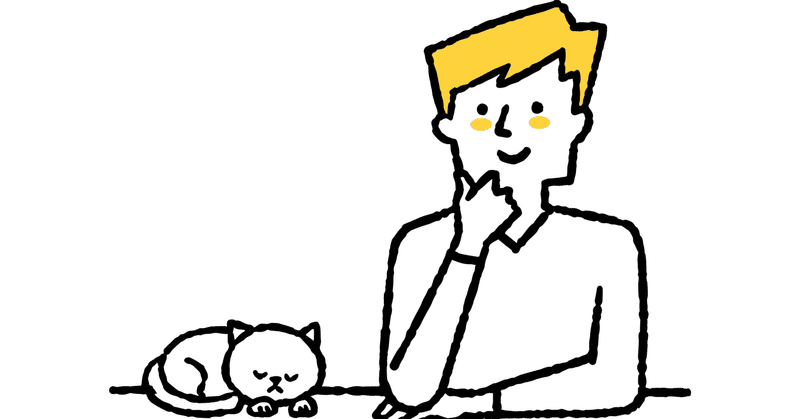
「ほうれんそう」という言葉は、
ビジネスパーソンの常識になっているのではないかと思います。
「報告」「連絡」「相談」のそれぞれの頭の文字をとって
「報連相(ほうれんそう)」というわけです。
1982年頃、当時の山種証券(現・SMBCフレンド証券)の
山崎富治社長が発案し、社内で「ほうれんそう運動」を始めたのが
キッカケだということです。
「ほうれんそう」が有名になったのは、山崎富治社長が
『ほうれんそうが会社を強くする』という本を書いて、
ベストセラーになったことが一因です。
「報告」とは、上長から出される指示に対して、
社員や部下がそれに取り組みながら、その途中経過などを
報告すること。
「連絡」とは、そのことに関係する人たちに自分の意見や憶測を含まず、
ファクトの状況を知らせること。

「相談」とは、その遂行途中で自分だけで判断することが難しいときに、
社長や上司に相談してその考えや意見を聞くことです。
「ほうれんそう」は部下を育てる、あるいは大きな間違いを
しないように指導するという観点からすれば、
きめ細かい「ほうれんそう」は捨てがたい意味を持っています。
一方、「ほうれんそうは不要」という考え方もあります。
どこそこの会社を回りました、パンフレットを置いてきました、
という日報のようなことを連絡したり、されたりするのは時間的にも無駄である。
「結果」を報告することは必要だがいちいち「プロセス」についてまで
「ほうれんそう」をする必要はないということのようです。
確かに「ほうれんそうをする時間があればもう1件、
お客さんのところを回ったほうがいい」
「営業報告を行うためだけに会社に戻るのはナンセンス」
という考え方は、一見、理にかなっています。

しかし、この「ほうれんそう」は、組織の上下をつなぐ重要な意味を
持っています。社員や部下は「社長は私のことをわかってくれない」
「上司はオレの働きをちっとも理解していない」と不満を持ちがちです。
しかし、社長も上司もすべてを見ているわけではありません。
たくさんの課題を抱えて取り組んでいるため、
すべてに時間を取れるはずがないのです。
現場で働いている社員がどういう仕事ぶりなのか、
どれほどの実力があるのかがわからなくなってくるのです。
そのようなことを前提にすれば、実は「ほうれんそう」は、
社員や部下が自分の能力や実力を社長や上司にアピールする
「絶好の機会」なのです。
「指示された課題にいまここまで取り組みこれだけの結果を
出しています」「こういう考えで取り組んでいます」ということを
きちんと伝えれば、自分の能力・実力を社長や上司にアピールできるのです。
もちろん良いことだけを報告するわけではない。
プロジェクトがうまく進まないときには早めに相談すればいい。
相談すれば、社長も上司もこうすればいいのではないか、
こういうやり方に変えたらどうかと助言してくれるはずです。
こういう場合には、社長も上司も「よく相談にきてくれた!」と思うものです。
もし、結果至上主義でプロセスの報告も連絡も相談も不要となって
しまえばどうなるでしょうか。
人材が育たなくなるのです。
教える必要などない、欧米ではそういうやり方を
しているという声が聞こえてきそうですが、ここは日本です。
業種にもよりますが欧米の多くの大企業では職場で人材を
育成するという発想がほとんどない。
言い換えれば、最初から「出来上がった人材」「完成品」を
採用する経営なのです。日本とは違います。
とはいえ、確かに困ったときに「相談」ばかりということになれば、
いわゆる「指示待ち人間ばかり」になる可能性がなきにしもあらずです。
自分で究極まで考えずにちょっと困ると上司に「相談」ということでは、
逆に「人材育成」にはなりません。
やはり「自分で考えて実行する人間」に育てなければなりません。
そう考えると「ほうれんそう」も考えものです。

動いた分、新しい自分になる!
就労移行支援事業所 JoBridge飯田橋
~うつ病・発達障害など専門の就労移行支援~
~自分らしい生き方、働き方を見つける場所~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
