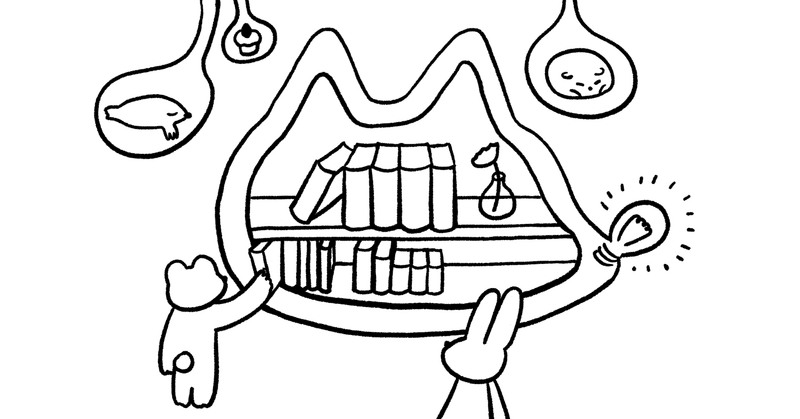
最近読んだ本[ASD/複雑性PTSD]
*amazonアソシエイトに参加しています
日頃の怒りとか
外出先の飲食店で「一緒に働いている人が発達なんだけどさ、仕事に響くから嫌なんだよねー」と女の人が男の人と話しているのが聞こえた。
最近会社などで「あの人発達障害みたいだから」と単純に好き嫌いや社内政治の都合のためか、発達障害かもしれないからというのを言い訳にして、気に食わない人を排除するような風潮があるということを知った。
問題なのは本当に発達障害なのか、障害があるのか見分けられないような人たちが勝手に憶測でジャッジしているという点だ。
ただの虐めのようになっているだけなのに、彼らにはその自覚もなさそうだ。
医師でもないのになんとなくの印象で発達障害と決めつけている人たちがいるのだ。医師でも発達障害の診断を下すのは慎重になるし、時間もかかるそうだ。
私は妹に重度の知的障害(診断の仕方に疑問があるので本当に重度かなと思っている。性格との兼ね合いもあるのだ。)があり、迂闊にこのことを会社に伝えると、私の頭も怪しいと疑られる可能性が高いことと様々な誤解を招くため、会社に教えたことは一度もない。言葉で説明することが難しく、健常者有利の社会から真っ当な理解を得られるとは思えないからだ。
この経験があるため、私はその人に知的障害がありそうかどうか大体だけれど見分けられる。または少しのことくらいなら気にならない。こういう人なんだなあと思って終わり。みんな少し自分と違うからって気にしすぎなんじゃない?というのと自分達はまともで正常と思える自信があるという考えが異様に思えてしまった……
健常者に囲まれて暮らしてきた人たちの中には、少し人と違っていると思っただけで嫌悪感が増して線引きしたがる人たちがいるらしい。自分達は何も悪くはなく、人のせいにするために発達障害を引き合いに出しているように私には思える。私はむしろ一部健常者のそういう卑怯さに前々から嫌悪感とはらわたが煮えくり返る思いだ。
発達障害は凹凸の差が平均的な人と比べて目立つ人のことだから、余程のことがない限り発達障害にはならないのではないかと思う。多少の凹凸は誰でも持っているものではないのだろうか。むしろ健常者と同じ扱いをされ、なんでできないのと責められ困っていることの方が多かったのではないか。「みんな同じ」が間違った使われ方をされているのだ。
読んだ本1
自閉症スペクトラムの精神病理-星をつぐ人たちのために 2015年
発達障害の精神病理 1 2018年
ある日、臨床心理士さんに「ASD気味だしな…」って言ってるの聞こえてるんですけど…ということがあって、ASDってどういう人なのか気になった。(確定でない診断名を当人の面前で迂闊に言わない方がいいと思う…)
先天的にASDの傾向がある人は、明らかに通常の人と異なり、人の顔が覚えられないとか、人の気持ちが直観的にわからないとかが顕著に現れるそうで、知的障害を併せ持っていたりそうでなかったりする。ASD=知的障害というわけではない。
知能が高くてもASDの人もいる。工夫してカバーしているから他人から気づかれにくいらしい。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴
・発達障害は統合失調症と誤診されやすい
・人の顔を覚えることが困難
→パーツごとに認識している傾向があり、全体を捉えることが困難。それが家族にも及ぶ。
人の顔の認識の仕方が健常と異なるので、ASDは人と目を合わさないとよく言われている。
・連続性を認識することが困難
→昔の自分の写真を見ると、亡くなった人の写真として認識している。
・人の心を理解するのが困難
→ASDの人は、人の心を自分に置き換えて自分ならどのような行動を取るか推論する⇒信念や欲求といった思考性を他者に帰属させることによって他者の行為を推論する⇒定型者が他者の行動を理解するときはこのような不器用な方法はとらない
→アレキシサイミア。
エコラリア(オウム返しなどの鏡のように相手と同じ反応を返すこと)になる
・見えないものを想像することが困難
→直感的な感覚に依らないものを他者や鏡による媒介を通して受け入れることも困難
・asdの基本障害は想像力の障害とされていたが、受容されにくいことのようでアメリカでの診断基準から外された
・直感でわかることを推論で代償しなければならない。→暗黙のルールがわからない。言語行為として感じられるから。本能的に身につけるべき自明性を知性でカバーしなければならない。
健常者もルールが何であるかなど知らない。知っているかのように振る舞っているだけ。文脈は依然としてわからず、過敏にはなっている。
・情緒的な関心の共有ができない
→分析して記憶する高い認知能力を動員している。
・影響されやすい。
例えば校則を破ってる友人の影響を受けて勉強をするのをやめる→高校卒業間際にそれは間違っていたと気づく→浪人して大学に入る
・体系的な物事を理解するときに細部から認識して積み上げる(トップダウン型にならずボトムアップ型になる)ような理解の仕方をする。木を見て森を見ず。
・発達障害者に対しては、コツコツより一発勝負がおすすめ
→時間の区切りがないと選択して佇んでいたり、細部に引っかかったままでいる。
目標志向性がはっきりしてくるとやるべきことが決まり、場が構造化され、やらざる終えなくなる。何をやるべきかが決まる。一発勝負と書かれてあったのは、そのくらい短い期間に設定しないと脱線しやすいということなのかもしれない。
・定型者から見るとASDの行動は唐突で不意打ち
のように見える。唐突に見えるのは心を介在させないから。物理的な、思っても見ないような計算ずくの理由は見出されるかもしれない。→ボトムアップ型の思考
・疲労感がわからない場合がある
・感覚過敏に気づいて照明を暗くしたりして環境調整を行う。
・自分の気持ちを言葉に乗せるのが難しい。
・痛みに鈍感
・手先を動かしたり運動が苦手
→人によっては経験を積むことで改善することも
・ASDではなくASと呼ばれることもある
→ Autism Spectrum DisorderのDisorderが障害という意味のため、配慮してASとしている。
ASDの人は上記の特徴が全てある人、というわけではなく、グラデーションになっており、若い頃は体力や高い知性で凹凸をカバーできていたけれど、ある程度年齢を重ねた時点で疲労感が溜まり、適応しづらくなり精神科を受診し、診断に至る人もいる。
感想
多分、小さい頃からいろんな他人とコミュニケーションを取っていないと、あいつはASDなんじゃないか、と言われてしまう。というのが本を読んでみた個人的な感想。きょうだい児(障害がある兄弟がいる人。健常者とコミュニケーションを取る機会が少なくなりやすい。)に多そう。
私は一応人の顔を絵に描けるほどに認識できる人なので、もしそうだったとしても気にしなくていい程度だと思っている…。家族の顔は流石に覚えられる。。。
でも細部が気になって全体が掴みにくいというのは学生の頃何となくそういう部分があって、単純に思い込みが強くて頭が悪いからって思っていた…デッサンの練習をしてある程度昔よりマシになったと思う。デッサンは木も見て森も見ないと描くことが難しい。物事の細部が気になりすぎて引いて見ることが出来ない自覚がある人で、絵を描くことに抵抗がない人はデッサンを描くことをおすすめする。何かを作るときは、細部も大事なんだけど、まず全体がとても大事。。。
ロゴをつくる課題で書体を決める時、本当は満遍なくいろんな書体をピックアップしなければならないのに、いろんなゴシック体に絞っていたところ、先生に「自閉症か…?」と言われたことがあった…🥹(頭の中で「ローマン体はないな」ってイメージして決めつけてしまった結果なんだけど…ASDの人もそういう感じなのかな…)
マルチタスクも全くできないわけではないし、自閉症と誤解されやすいんだと思う😢
読んだ本2
身体はトラウマを記録する-脳・心・体のつながりと回復のための手法 2016年
複雑性PTSDのことが書かれてある本。
・PTSDは震災や戦争などによる一時的なトラウマ体験によるもの。
・複雑性PTSDは、幼少期の虐待や、性被害などの慢性的なトラウマ体験によるもの。
・脳の働きがトラウマ体験によって停止してしまう。(今を生きることができない)
・避逃不能ショック
危機感が身に起きても逃げることができない。
マウスを使用した実験では、温かい巣で育ったマウスはやかましい環境にするとすぐ巣に戻り、騒がしい巣で育ったマウスは好ましい環境に移っても騒がしい巣に戻ろうとする。虐待や性被害を受けた人も同じような行動を取る。
・トラウマを負った犬は通常より多くのストレスホルモンを分泌する
・虐待や性被害を受けた人が何度も同じような出来事を繰り返してしまうのは、反復強迫と呼ばれるもの。
最初は苦痛や不快感がある。
マラソンやパラシュートなどと似ており、恐れと嫌悪が喜びに変わる。
離脱症状の苦痛で頭がいっぱいになり、繰り返し体験してしまう。薬物依存と似ている。
自身の苦労した経験を何度も話してしまうことも反復強迫という。
・大脳皮質が生存のための闘いにはまりこんでいる動物脳から主体性を取り戻したい
壁を殴ったりする→ますますコントロールできてないと思い、自信が取り戻せない
・人から嫌がられるような態度を取る人が実は親から虐待を受けているような人だったりする。
・アレキシサイミアの人は感情が言葉ではなく身体的な症状になって現れることが多い。お腹が痛いとか頭が痛いとか。拒食症や過食症になって現れる。
・復讐してやるという主体性でptsdにならない人もいる。
・人間から慰めを得られないときは他の哺乳類との関係が役立つことがある
犬と馬が患者の治療によく用いられている
・手一杯になっているシングルマザーは子どもを慰めたり安心させることはできなかった。敵対的な押し付けがましい親は身体的虐待や暴力を受けている場合が多く、内向的で依存心のつよい母親は性的虐待、親を亡くしている場合が多い。
・記憶に大きな欠落があり、頻繁に自己破壊行動をとる。
これらは自然災害サバイバーでは稀
→他に特定不能の極度のストレス障害を複雑性PTSDと言う
・トラウマのきっかけとなる記憶がなくなっていたり、断片的になっていたりする。人に触られたりすることで記憶が蘇り解離したり情動が抑えられなくなる。トラウマ時の記憶を話せないため、診断することが困難になる。虐待や裏切り、ネグレクトの影響に対処している人々の診断をうつ病、境界性パーソナリティ障害、双極性障害、パニック障害などと診断せざるおえない。
・虐待を受けている貧困層の子どもを大人しくさせるために、薬を処方することがアメリカではあるそうだ。
・逆境的児童期体験研究(ACE研究)
→児童期と少年期にトラウマ体験をする人は、予想よりはるかに多いことがわかった。中流階級の白人男性でも。児童期の逆境体験をしなかったと答えた人は全体の三分の一
→児童虐待を減らすことができれば、肺がんやアルコール依存症などを減らすことができる。
ACE研究にはまだそのような効力はない。
向精神薬によって彼らは扱いやすくなるが、喜びや好奇心を感じたり、情緒的、知的に成長したり、有用な社会の成員になる機会を奪われる
・虐待は脳の発達に影響を与える。人が「乗り越える」ようなものではない
・虐待されたりネグレクトされてる患者より、そのような背景を持たない患者の方が抗うつ薬がよく効く
感想
何が困るのかというと、ASDと同様他の診断と間違えやすく、うつ病の薬を処方されたとしても効果が表れなかったりすることなのかな。医療機関は慎重に選ばないといけないけれど、自分に合ったところに巡り合うまでに相当渡り歩かなければならない気がするし、実際そういう人も多いと思う。渡り歩いている間に心身がけづられていくし、誰かの心無い一言で傷ついてしまうこともあると思う。
カウンセリングを受けてもなかなか改善されずに困ってる人をXでよく見かける。。。お金もかかるし大変すぎる。。。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
