
やりたかったことが、ようやく分かった
(約 4,600文字の記事です。)
今日、今後の創作活動の大きな方針が決まった。とりあえず書き流し形式の日記です。詳細は3DCG関連なので具体的に決まり次第ブログのほうに書く予定。
やりたいことに合わせて柔軟にブログサイトの構成を変更できるように、急ピッチで「はてなブログ」からWordPressに移行したわけです😊
また今回はテストとしてnoteの新エディタを試すことにした。というのもWordPressに移行してからいやがおうにも「ブロックエディタ」に慣れる必要があり、いじっているうちに「悪くないな」と思えたので「noteの新エディタももしかしたらブロックエディタスタイルなのかな?」と思い、今試している次第。
うん、まるっきりブロックエディタスタイルね(笑)慣れれば快適。
特に番号付き箇条書が使えるのがいいね。
話を戻そう。
更新履歴
2022/10/15
基本的にnoteの記事は更新しないで書き流すスタイルなのですが、今回はメインとなるDCCツールをMayaから3dsMaxに変更することにしたので内容を一部書き換えしました。
3DCGの各ツールの使い分けが決まった

今まで色んなツールを試して色々と考えたり悩んだりしていたが、今日、ついに方針を決定した。具体的にはこんな感じ。
モデリングはZbrush+Blender
リギングとアニメーションは3dsMax
レンダリングはPSOFT Pencil+ 4 for 3dsMax (有料プラグイン)
背景はAI画像(Stable Diffusionなどを予定)
コンポジットはPhotoshopまたはAfter Effects
なんでこういう結論に至ったか。
やりたいことは「最初から」セル画表現だった

TOP絵は以下のチュートリアルサイトからの抜粋です。
実はここ数ヶ月間、ずっと悩んでいた。自分はなぜ3DCGをやっているのか?と。もちろん生業として「お金を稼ぐ手段」として割り切ることはできるのだけれど、そういうことではなくて、もっと本質的に「なぜ3DCG?」ということを考えていた。
たまたまZbrushから3DCGに入ったために、Zbrushの使いにくさをプラグインで補おうとしてプラグイン開発に入り現在に至るわけだが、そのゴールも見えてきた気がするのだ。
私に必要なのは「次のステップ」だったのだ。
初心に戻って「自分が本当にやりたいことは何だったのか?」を、ずっと考えていた。考え出すと、アウトプットが急激に鈍る。実際にブログもnoteも、某仮想空間おしゃべりツールの一件以来、ピタリと筆が止まった。
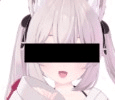
そもそも某仮想空間おしゃべりツールの模索にしても、上記の悩みを抱えつつ、とりあえずはマネタイズという側面で将来性を探ろうとしていた背景がある。なので別に某ツールそのものについて何か惹かれるものがあったとか思い入れがあったとか、そういうものは一切ない。何となく「話題になっているから調査してみよう」その程度だ。だからヘビーユーザーと私との熱量の差は、当然ながらある。(そして色んな後悔 - regret - も残ったが。)
今も某仮想空間おしゃべりツールに関わることが苦手だ😱 当時感じた課題や問題点は何も変わっていないので。
人生の残り時間と「やりたいこと、やり残したこと、後悔の可能性」
割と深いテーマだ。自分が本当にやりたかったことを考えたとき、ふと思った。逆に「もしこれから先、自分の人生がいよいよ終わるそのとき」に「やり残したこと、後悔する(した)こと、特にクリエイト関連について」を考えていた。
人生はいつか必ず終わる。
それは緩やかかも知れないし、ある日突然、何の予告もなしに、かも知れない。「看取ることすらできなかった」という経験があれば、色々考えることだろう。
人生には、必ず終焉が訪れる。
そんなとき、ふと、自分が後悔するクリエイトって、なんだろうな?と考えていた。そしてそこでポップアップしてきた想い、多分それが「正解、やるべきこと、やりたいこと、本当にやろうと思っていたこと」なのだと理解した。
元々は絵を描きたかった。これが原点だった。

ここに戻ろうと思う。
もっと言えば、油絵でも水彩画でもなく、セルルック調の、セル画調の、そう、アニメのワンシーンのような1枚絵。これでよかった。これは3DCGではセルルックとかトゥーンシェーダーとかセルシェーダーとか、色々な呼び方がある。これは物理演算よりもハードルが高い。影と影以外の部分のしきい値の問題があるから、結構面倒くさい。だから「やりたくてもやれずにいた」。
だが今回色々と調べてみると「業界標準の枯れた手法が1年くらい前に確立されていた」ことを知る。あとはお金を出して有料プラグインを使えば、あっさりと「今の、枯れた手法で自己実現ができる」ことを知ったのだ。
セル画調の絵を3DCGで作れるようになれば、無彩色を使えば当然ながら漫画調の絵も作れる。モノトーンは配色センスが不要で、しかも読者の想像にお任せできるメリットもある。そして線画+トーン表現で1枚絵を完結させられるメリットもある。3DCGで漫画を描くというテーマにもつながるだろう。私はあまり興味はないが、そこに惹かれる人もたくさんいると思う。特に現役の漫画家は。
そういう意味ではこの取り組みに関する情報発信についてマネタイズの可能性はあるのかも知れない。
Zbrushとの付き合い方。マネタイズと自分にできること・できないこと

ここも結構悩んでいた。というのも日本国内のZbrushユーザー様の場合、私のお付き合いする範囲ではかなりの人がフィギュア関連のお仕事をしている。ところが自分はフィギュア方面にはあまり興味がない。もともと立体データはデジタルデータとしての扱いのほうがアナログよりも利便性が高いと思っているので、敢えてアナログ立体造形について何かを考えるという発想がなかった。
今でこそ3Dプリンタが個人でも扱えるようになったが、そこまでして立体物を「物質として」手に入れたい、という思いが私にはあまりない。
もちろん、平面表現だったアニメキャラが平面ではなくて現物の立体としてそこに存在させられることには価値があると思う。立体造形のセンス、○○らしさの表現は、簡単じゃない。そこは造形師の皆様を尊敬している。平面を立体化するのはとても大変だ。とくに「らしさ」を生み出すことは、並大抵じゃない。愛情が必要だ。
そう、愛なのである。これは間違いない。
そこを「ツールの使いこなしや作業の効率化」という観点でZbrushクリエーターを支援したいと思っている。
これが今の私にとってZbrushプラグインの開発&メンテをし続けるモチベーションだ。
でも個人的には、日本のフィギュアの枯れた造型については1点、ずっと引っかかるところがあって、それは「アニメ頭」の立体的な存在の不自然さ、違和感だ。これはお絵描きを始めた当初から感じていたことだ。特に人体を解剖学的に捉えると、アニメの頭の大きさ、眼球の大きさ、それを実現させるための頭蓋骨の不自然さ、それは幼児のそれに相当する、など色々考察したことがあった😊 あと鼻の個性がなくなることも、ちょっと気になる。
だいぶ古い記事だ。WordPress前、はてなブログ前の、ライブドアブログ時代の記録だ(笑)
脱線したので話を戻そう。
フィギュアの原型を作るためにZbrushを活用している人はたくさんいる。そして自分にはZbrushプラグインを開発できる能力がある。これをお金に変換して、他者に便利な価値(効率化)を提供しながらその価値をお金に変換しつつ、せっかくだから自分も積極的にモデリングツールとしてZbrushを使っていこうと思っている。
そもそも自分が使わないツールの開発をし続けることなど、不可能だ。ここも実は悩んでいた部分で、もしかしたらZbrushから離脱すべき?と結構の間悩んでいた。幸い、復帰できそうなのでプラグイン開発やメンテに戻ってきたわけですが😊
とはいえ、フィギュアの原型師様のように「微細な(肉感的な)表現の、繊細な表現のためのブラッシング」という使い方は、今の私にはできそうもない。私としてはもっとラフに、直感的に形を出すためにZbrushを使うと思う。そしてBlenderでリトポして表面の荒れを抑える、という使い方になる予定。
なので今後もしばらくはZbrushプラグイン開発やメンテは細く長く継続予定です😊
Maya+Pencilで運用?(3dsMaxに変更)

Mayaについては、モデリング自体は「とってもやりづらい」と感じた。本当にMayaを学ぶべきか悩んだが、今回、トゥーンシェーダーとしてPencilというプラグインを知り、しかもそれがMaya版も出ていたことを知ったので、Mayaをレンダラーとして利用することにした。
だが残念なことにMaya 2023にPencilは非対応。今後のことも考えてまずは3dsMaxを優先することにした。
Pencilプラグインは元々は3dsMaxで登場し、3DCGアニメーションでは鉄板のプラグインになっているようだ。だが2018年にはついにMaya版も登場したことで、多勢のMayaを使うメリットがさらに高まった。今敢えて3dsMaxに行く理由が見当たらなかった。だが二転三転して3dsMaxに戻る。
Mayaはモデリングはしづらい。3dsMaxのほうがやりやすいらしいが、そもそも静的メッシュを組み上げるならばどんなソフトを使っても同じだ。リギングから先になるとソフト縛りが付くが、モーション付けは3dsMaxよりもMayaのほうが扱いやすいらしいので、リギング、アニメーション、Pencilレンダリングの環境としてMayaを採用することにした。これでついにMayaを学ぶべき決定的なモチベーションが自分に生まれた😍
でも諸事情により最終的に3dsMaxに変更した。
それだけMayaのモデリングはしづらかった。Blenderのモディファイアによる可逆なポリゴンモデリングや、Zbrushの自由で直感的なスカルプトを知ってからMayaのモデリング手法を学ぶと、Mayaはちょっと古臭い感じがした。
なんだかとりとめがなくなってきたので今夜はこの辺で打ち切ります。
ま、要するに、ようやくやりたいことが固まってきた。そういう日記でした。
noteのブロックエディタも、慣れないと何だか歯がゆい。イライラするw
今回の創作活動は約1時間30分(累積 約2,920時間)
(805回目のnote更新)
筆者はAmazonアソシエイト・プログラムに参加しています。(AmazonアソシエイトとはAmazon.co.jpの商品を宣伝し所定の条件を満たすことで紹介料をAmazon様から頂けるという大変ありがたい仕組みのこと。)
以下のリンクを経由してAmazonでお買物をするとその購入額の1~3%ほどのお小遣いが私に寄付されます(笑)以下のリンクを経由して頂ければ紹介商品以外のご購入でもOKですよ~。
読んでくれてありがとう。気長にマイペースに書いてます。この出会いに感謝😊
