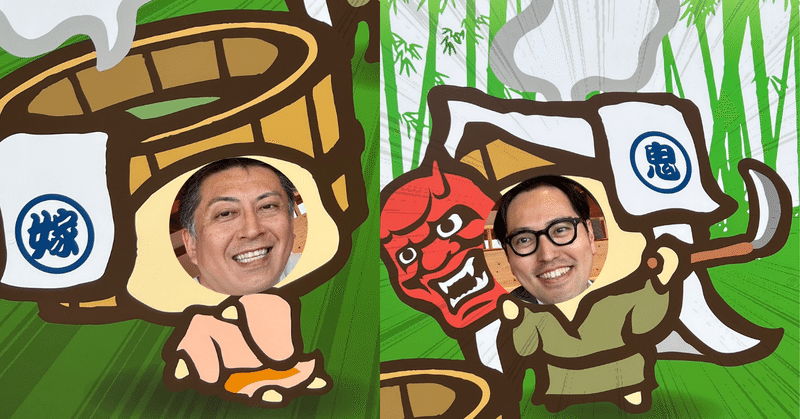
LDLバディ対談(前編)in あわら
LDL(Locally Driven Labs)とは、『まちづくり幻想』『地元がヤバいと思ったら読む凡人のための地域再生入門』『福岡市が地方最強の都市になった理由』『地方創生大全』『稼ぐまちが地方を変える』などの著者で、約20年にわたって全国各地で経営とまちづくりに取組んでいる木下斉さんが所長として立ち上げたラボです。
LDLの恒例企画であるバディ対談にて今回は船田幸夫さんとの対談を実施しました。LDLの中でも圧倒的な存在感を持つ船田さんですが、メインで手掛けている事業は、神社仏閣における各広報業務(公式サイト・SNS 等)の企画・運営で、他には日本国内および台湾における旅行及び研修会、講習会、各種イベントの企画・催行などを行われております。詳しくは船田さんのホームページをご参照ください。
今回の対談はオンライン対談ではなく、直接お会いして対談したいと思い、福井県にお呼びしました。急な申出にもかかわらず、快く受け入れてくださり、今回の1泊2日の宿泊対談企画が実現したのであります。
このフットワークの軽さが本当に素晴らしいなと思います。
船田さんと対談したかった理由は大きく2つあります。
1つ目は、船田さんは日本国内だけでなく台湾、中国、中東などなど、かなり旅をしていらっしゃいます。そんな旅慣れしている方に、当ホテルの取り組み、そして私が考えるローカル生存戦略の可能性をどのように感じて頂けるのかを第3者視点で体感して頂きたかった事です。
2つ目は、福井県のインバウンド訪問客が劇的に少ないため、船田さんの専門的知見を聞いて今後の展開に活かしたかった事です。
船田さんが来られると決まってからはどのようにアテンドしようかなと色々考えていたのですが、船田さんが現在手掛けている発酵ツーリズムの視察もかねてお越しになられると事前にご連絡を頂いたので非常に企画が立てやすかったですね。
北陸は発酵が盛んな地域で、福井県では昨年小倉ヒラクさんと発酵ツーリズムほくりくという企画を行っており、書籍にもなっています。
普通の観光地巡りでは面白くないですから、私が可能性を感じる場所へアテンドしたいと思い、超主観的な内容にしました。行程内容はこんな感じ
■1泊目
JR芦原温泉駅着→ホテル八木にて打合せ→あわら温泉街散策→昼食
→道の駅蓮如の里あわら→願慶寺→ex cafe(イクスカフェ) 吉崎鳳凰閣
→ホテル八木着→夕食→対談→入浴・サウナ
■2泊目
朝食→チェックアウト→天たつ→青木蘭麝堂→一乗谷朝倉氏遺跡→一乗谷朝倉氏遺跡博物館
天気が良ければ駅から歩いてホテルまで来られる予定だったようですが、あいにくの雨模様でしたので、JR芦原温泉駅までお迎えに行きました。
JR芦原温泉駅といえば、来年の新幹線延伸に向けて3月に新設されたばかりですが、色々と突っ込みどころ満載の箇所があり、本当はこの駅もゆっくり解説しながらご案内したかったのですが、私自身が福井県観光連盟の方と打合せが入っていたため、急遽船田さんにも打合せに合流して頂くという流れになりました(笑)
インバウンドという抽象的な言葉だけが独り歩きしますが、明確なターゲット層の話や、どこにプロモーションすべきか等、話される情報の鮮度が違いましたね。また、ご自身が手掛られたヘリツーリズムの話題になると立て板に水のごとく話はじめ、観光連盟の方も興味津々でした。
後日談になりますが、この打合せから具体的な進展があり、福井県でのヘリ遊覧デモが実現しそうです。こういった思いもがけぬ出会いがあったのは、現地にお越し頂けたからこその副産物ですね。
したがいまして、対談したかった2つ目の理由がこの副産物の出会いにより叶ってしまったのです。
これは船田さんが持っている強運なのでしょうか。そんなことを感じさせられました。
打合せの後はあわら温泉街を歩いて散策。現在、紹興酒にも興味をお持ちの船田さん。そんな紹興酒発祥の地である紹興市とあわら市は友好都市でもあり、友好都市記念に設立された藤野源九郎記念館を訪れました。
館内は小さいですが、文化財の建物を間近で体感することができます。魯迅は中国で人気があるので、この記念館は日本人より中国人観光客がよく訪れるようです。
藤野源九郎記念館とは、昭和58年芦原町と中国の浙江省紹興市との間で締結された友好都市を記念して、藤野家遺族から三国町宿第35号14番地にあった旧宅を寄贈されたもので、芦原温泉開湯100周年記年祭の昭和59年7月に「藤野厳九郎記念館」としてあわら市文化会館横に移築されました。
さらに、平成23年には、同年整備された、あわら温泉湯のまち広場に移築されました。
藤野厳九郎は、解剖学教授として周樹人(魯迅)と師弟の交わりのあった仙台医学専門学校(現東北大学医学部)を辞して以来、主として生まれ故郷である本荘村(現あわら市)下番に住み、医師として診療に当たりましたが、昭和8(1933)年から逝去した昭和20(1945)年までの12年間は、文夫人と三国のこの家で暮らしました。
記念館内の資料室に展示してある書籍、医療器具、 書簡など多くの遺品は、藤野厳九郎の人柄を知る上で、たいへん貴重なものです。
「藤野厳九郎記念館」は登録有形文化財(建造物)に登録されています。







その後、温泉街ぶらぶらと歩いて昼食をとってから車で移動し、あわら市北部に位置する吉崎地区にお連れしました。
こちらは2023年4月23日にオープンしたばかりの道の駅と京都で人気の和スイーツのお店が北陸初上陸で話題のeXcafe(イクスカフェ)吉崎鳳凰閣によりエリア価値がかなりいい方向に変化しそうな可能性がある地域です。その辺りを書いたレポートがありますので、併せて読んでいただければありがたいです。
そしてその記事を書く際に見つけた吉崎地区に伝承される嫁脅し伝説。今回船田さんと一緒にその伝説を聞くべく訪れたのは願慶寺(がんけいじ)です。
以前訪れたことのある知人から、住職の話がめちゃくちゃ面白いからとすすめられていたのです。
※今回のサムネもこの嫁脅し伝説の顔はめパネルを使用しています笑 道の駅の入り口にありますのでお越しの際は是非記念写真にどうぞ(^^)
かくいう私も願慶寺を訪れるのは初めてだったのですが、嫁威し伝説の話は本当に面白かったですね~。今回はもう一つの嫁脅し伝説がある吉崎寺(よしざきじ)には訪れることができませんでしたが、後日必ず行ってみようと思いました。
願慶寺の住職の和田重厚(わだしげあつ)氏が仰られるには、この嫁脅し伝説は江戸時代には落語の演目として扱われていたとの事で、実際に聞いてみるとなるほど、これはまさにエンターテインメントだと思いましたね。
なんだか話が深いというか人情味あるというか、まるで落語を聞いているような感覚。嫁姑問題はインバウンドに受けるかどうかはわかりませんが、少なくとも日本ではいつの時代も変わらぬ普遍的な話題なんでしょうな。



神社仏閣が専門なので当然と言えば当然なのですが、ここでは船田さんが持っている歴史・宗教文化に関する知識の豊富さに驚愕しましたね~。
私は宗派の違いはほとんどわかりませんが、船田さんには住職の話に出てくる登場人物等ほとんどわかっているようでした。
あまり真面目過ぎる解説よりもこのようなエンタメ性があって身近に感じれる方がハードルが低いですし、より興味を持ちやすいように思いました。
浄土真宗寺院では御朱印が頂けないことを最近になって初めて知りましたが、この願慶寺では御朱印が頂けるようです。
私は集めませんが、御朱印帳を集めるのも人気がありますよね。
嫁威し伝説を楽しんだ後は話題のex cafe(イクスカフェ) 吉崎鳳凰閣へ。願慶寺の余韻に浸りながらアイスグリーンティーでほっこりと。今までこのちょっと休憩して佇む場所がなかったんですよね~。こんなゆったり佇めるカフェが出来たのは地元民としては本当にありがたいのです。平日の15時過ぎで、しかも雨にも関わらず若い客層が結構いましたね。
その後ホテルへ移動し、チェックイン。
私が夜に予定があり、船田さんと一緒に夕食は食べることができなかったので、夕食は船田さんお1人で堪能して頂くことにしました。
夕食後にロビーにて合流し、じっくり対談させて頂きました。1日を振り返りながら、ホテルの取組みや現在の課題、今後の展開などで盛り上がり、その後一緒に温泉とサウナに入って初日が終了。
1日を振り返って感じたのは、船田さんの感想が自分にはない目線でとらえていた事です。自分ない観点からの意見が出ることで、今まで行ったことのある場所でも新しい発見や価値の再認識ができた事は自分にとっても非常によい学びとなりました。
今回の対談記事は内容が盛りだくさんなので、2日目の内容は後編に続けたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

