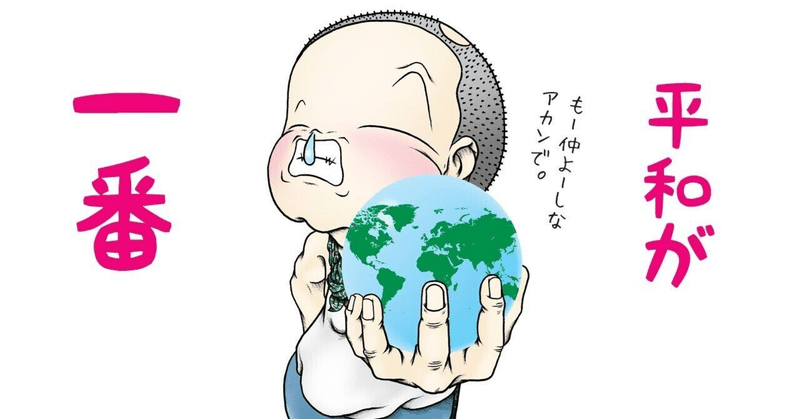
政治講座ⅴ895「終わりなき米・ロ・中の戦い」
地球上の生物で一番危険で凶暴な生物は破壊兵器とその科学知識を以て凶暴な利己的な人間であろう。毒を持った植物は自分の身を守るための生きる手段として進化してきた。他の生物を殺す目的でなく自分を守るためである。動物でも同様である。翻って人間社会はどうであろうか。好戦的な面をいつも内在している。一度究極の破壊まで行きつかないと辞めないのであろうか。核兵器で、人類が死滅するのが運命であろうか。今回は人類の破滅を示唆する報道記事を紹介する。
皇紀2683年3月4日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
アメリカとソ連が備えた「互いを破滅させる」ための「ヤバすぎる最終兵器」の全容
玉置 悟 によるストーリー •
なぜ世界各地で戦争や紛争は続くのか。世界経済はなぜ不安定なのか。
実は、現代という時代が今のようになったのは「アメリカとロシアの闘い=冷戦」が多大な影響を及ぼしている。もともと欧米とロシアとの闘いは、100年以上も前から続いており、地政学の大家・マッキンダーもこの闘いを「グレートゲーム」として考察していた。つまり、ここ100年の世界の歴史は「地政学」と「冷戦」という2つのファクターから眺めると、とてもクリアに理解が広がるのである。
いまウクライナで起こっている戦争も、中東やアフガニスタンで紛争が絶えないのも、この「地政学」+「冷戦」の視点からみていくと、従来の新聞やテレビの報道とはまた違った側面が見えてくる。まさに、それこそが「THE TRUE HISTORY」なのだ。発売前から一部で大きな話題になっている、「地政学と冷戦で読み解く戦後世界史」から、とくに重要な記述をこれからご紹介していくことにする。
“最終兵器”と核戦争の恐怖の時代
初期のICBMは、TNT換算でメガトン(100万トン)級の破壊力を持つ核弾頭を搭載していた。その理由は、初期のICBMは命中精度が低かったため、目標から離れた場所に着弾しても確実に目標を破壊できるようにするためだった。そこで米ソは大破壊力を持つ熱核爆弾(水爆)を開発した。ICBMは撃墜が不可能であるために、核搭載ICBMは“最終兵器”と呼ばれた。
比較のために例をあげれば、広島に投下された原爆の爆発時の出力エネルギーはTNT換算でおよそ15キロトン(1万5000トン)だったが、初期のアメリカのICBMに搭載されていた水爆の破壊力はおよそ1・4〜3・75メガトン(140万〜375万トン)、最大のもので9メガトン(900万トン)もあった。最も多かった3・75メガトンの核弾頭1発の破壊力は、単純計算で広島型原爆250発分もの破壊力に相当する。9メガトンなら600倍だ。
このように巨大な破壊力を持つ兵器を米ソとも所有するようになったことから、両国が戦争をすればともに全滅してしまうことは明らかとなり、そのような全面戦争を避けることが絶対に必要になった。偶発戦争を避けるため、キューバ危機の後、両国の間にホットラインが引かれた。
相手を全滅させる報復能力を持つことで、敵が攻撃を仕掛けてくる事態を防ぐ。これが、この章のはじめに述べたアイゼンハワーの「大量報復戦略」のコンセプトだった。核戦争を防止するために核を禁止するのではなく大量に持つというのだから、一見矛盾する理論だが、人間にはそれ以上の知恵がない。
だがアイゼンハワーの「大量報復戦略」の理論は、「アメリカは先制攻撃をしない」ことが前提になっている。ソ連はそのようなことを信用するほどお人好しではなかった。すでに何度か述べたように、米英は常にソ連を攻撃することを考えており、ソ連の最優先事項は米英の攻撃から国を守ることだった。後に、1964年にソ連でフルシチョフが引退し、強硬派のブレジネフ政権が誕生すると、「アメリカと交渉するには、同等の軍事力を持っていなければならない」との考えにより、ソ連も猛烈な勢いで軍備増強を開始することになる。

米ソ(米露)間でICBMが発射された場合、目標にはおよそ30分で到達する。アメリカはアイゼンハワーの時代に、アラスカからカナダ北部を通りグリーンランドに至る長距離防空レーダー網を建設した。もしソ連がICBMを発射したら、上昇中の15分間に長距離レーダーで探知し、落下してくるまでの15分間に大量のICBMを発射して報復攻撃を行うというのだ。そうすれば、ソ連はアメリカを攻撃すれば自分も報復攻撃で全滅するので、先制攻撃ができなくなるという理屈だった。
だがアメリカが極地に建設したレーダー網は、航空機の侵入を探知するには有効だったが、ICBMの攻撃に対して報復攻撃を行うには意味がなかった。なぜなら、そのころのICBMは液体酸素と液体燃料を使う巨大なロケットで、液体酸素は発射直前に燃料タンクに注入しなければならなかったからだ。液体酸素はマイナス183度で気化してしまうため、ロケットの燃料タンクに入れたままにしておくことができない。注入には数時間かかり、報復攻撃に間に合うようにICBMを発射するのは不可能だった。地上の施設でさえ液体酸素の保管は難しく、爆発事故も起きている。
報復核攻撃を可能にする方法は別にあった。米ソとも、ミサイルの命中精度が100パーセントではない以上、先制攻撃で相手のすべての核を破壊できる保証はない。たとえ90パーセントが破壊されても、生き残った核ミサイルで報復攻撃をすることにより、相手の首都その他の大都市や司令部や基地などを全滅させられればよい。これが、相手を何回も全滅させられるほどの数の核兵器を持つ理由とされた。
しばらくして、液体酸素を使わない貯蔵可能な液体燃料ロケットのICBMが開発され、これら第2世代のICBMは、敵の先制攻撃で破壊されるのを防ぐため、地下に縦穴式に作られた「サイロ」と呼ばれる発射施設に保管された。だがサイロの地表の開口部は強固な蓋で閉じられているものの、至近距離で敵の核ミサイルが爆発すればやはり破壊をまぬがれない。
また、サイロからミサイルを発射すればロケットの噴射でサイロが破壊されてしまうので、サイロが使えるのは1回だけだ。ICBMを発射するのは最終戦争の時だけなので、2回以上使えるようにする必要がないのである。アメリカはソ連のICBMの攻撃で北米航空宇宙防衛司令部が破壊されるのを防ぐため、コロラド州の山中に同司令部の巨大な地下指令センターを建設した。だがメガトン級の水爆が直撃すれば、それすら山もろとも跡形もなく蒸発してしまっただろう。この司令センターは今では使われていない。
ソ連はアメリカの先制攻撃でICBMが破壊されるのを防ぐため、鉄道で移動する発射台から発射する方法を研究した。アメリカでもその方法は研究されたが実用には至らなかった。
1960年代になると、固体燃料を使う弾道ミサイルが登場した。固体燃料ロケットは長期間保管できる上、いつでも発射できるので、兵器としてはるかに実用的だ。これは原子力潜水艦(原潜)と組み合わせて使うことを念頭に開発された。潜水艦から発射するミサイルは、取り扱いの安全性のためにも固体燃料ロケットでなければならない。まもなく、地上配備のICBMも固体燃料を使う新しいタイプに入れ替わっていった。これら第3世代の長距離弾道ミサイルは、液体燃料を使った初期のミサイルよりずっと小型で、弾頭も小さくなった。命中精度が向上したために、初期のもののように巨大な破壊力を必要としなくなったのだ。
こうしてアメリカの戦略核戦力は、ICBM(地上のサイロから発射)とSLBM(潜水艦に搭載し水中から発射)の2つにB─52戦略爆撃機を加えた3つの柱によって成り立つようになった。まもなく対空ミサイルの性能が向上したため、戦略爆撃機によるソ連領土内への爆撃は現実性を失い、B─52は空中発射型の巡航ミサイル(水平飛行する有翼ミサイル)を搭載するように改造された。
B─52は1950年代末から1960年代はじめにかけて生産された古い飛行機だが、今日でも現役として使われている。1980年代に生産されたB─1超音速爆撃機が遠からず引退する予定であるのに対し、B─52は今後も30年くらい使われると言われている。もしそうなれば、驚くなかれ、B─52はデビュー以来なんと100年間も使われることになる。
一方ソ連は、前述のように戦略爆撃機によるアメリカ本土攻撃は考えていなかったが、ICBMとSLBMによりアメリカの主要都市や基地を破壊しうる能力を向上させた。地上配備のICBMは相手の攻撃にさらされやすいが、原潜は長期間潜行したまま移動できるので位置を知られにくく、核戦争で生き残る確率がずっと高い。そのため原潜と核搭載SLBMを組み合わせたシステムは、米ソともに冷戦時代の究極の兵器となった。
なぜ世界はここまで「崩壊」したのか…「アメリカ」と「ロシア」の戦いから見る「ヤバすぎる現代史」
なぜ世界各地で戦争や紛争は続くのか。世界経済はなぜ不安定なのか。
実は、現代という時代が今のようになったのは「アメリカとロシアの闘い=冷戦」が多大な影響を及ぼしている。もともと欧米とロシアとの闘いは、100年以上も前から続いており、地政学の大家・マッキンダーもこの闘いを「グレートゲーム」として考察していた。つまり、ここ100年の世界の歴史は「地政学」と「冷戦」という2つのファクターから眺めると、とてもクリアに理解が広がるのである。
いまウクライナで起こっている戦争も、中東やアフガニスタンで紛争が絶えないのも、この「地政学」+「冷戦」の視点からみていくと、従来の新聞やテレビの報道とはまた違った側面が見えてくる。
米英の傀儡だった? エリツィン
ゴルバチョフの改革はソ連を解体に導く結果となったが、本人は開かれた社会主義による新しい連邦国家を作っていると大真面目で信じていた。彼はなぜあのように無謀なスピードで改革を急いだのか。
ゴルバチョフを知る人によれば、彼は虚栄心の強い人間だったという。西欧の文化に憧れていた彼の誤りは、米英のおだてに乗り、自分の国を西欧のように作り替えようとしたことにあった。ロシアはユーラシアの多民族国家であり、西欧とは本質的に違うということを彼は理解しなかった。
ゴルバチョフは今でも西側では好意的に語られているが、それはソ連を崩壊させた功労者だからである。ロシアの愛国者から見れば彼はA級戦犯であり、評価されることはない。彼が2022年8月に亡くなった時、プーチン大統領は葬儀に出席しなかった。
ゴルバチョフが能力を超えることをやろうとしたドン・キホーテだったとするならば、エリツィンは米英の傀儡だった。華々しくロシア共和国を分離独立させてソ連を分解させたまではよかったが、彼は1年も経たないうちにヒーローの座から転落し、最後は哀れな傀儡の道をたどった。
エリツィンが進めた民営化により、旧ソ連の重要な事業が次々に彼と個人的に関係のある者たちの手に渡り、しかも彼らはアメリカやイギリスとつながっていた。彼らはロシアの国富を吸い上げて急速に巨大化し、オリガルヒと呼ばれる新興財閥に成長した。日本の財閥は企業だが、欧米のオリガルヒはすべてを個人が握っている。彼らは突出した億万長者であり、私兵を抱え、国の政治経済を支配している。ロシアのオリガルヒは事業を通じて国富を欧米に流出させ始めた。
またエリツィンはアメリカのウォール街が主導する市場経済への移行プログラムを実行し、ロシアをソ連時代の末期よりはるかにひどい状態に突き落とした。ハイパーインフレが襲い、労働者の蓄えが消失し、欧米から流入する製品が産業を破壊し、ロシアの大衆は貧困と飢餓に陥った。
エリツィンが進めた民営化により、旧ソ連の重要な事業が次々に彼と個人的に関係のある者たちの手に渡り、しかも彼らはアメリカやイギリスとつながっていた。彼らはロシアの国富を吸い上げて急速に巨大化し、オリガルヒと呼ばれる新興財閥に成長した。日本の財閥は企業だが、欧米のオリガルヒはすべてを個人が握っている。彼らは突出した億万長者であり、私兵を抱え、国の政治経済を支配している。ロシアのオリガルヒは事業を通じて国富を欧米に流出させ始めた。
またエリツィンはアメリカのウォール街が主導する市場経済への移行プログラムを実行し、ロシアをソ連時代の末期よりはるかにひどい状態に突き落とした。ハイパーインフレが襲い、労働者の蓄えが消失し、欧米から流入する製品が産業を破壊し、ロシアの大衆は貧困と飢餓に陥った。ボリス・エリツィン/PHOTO by Gettyimages
エリツィンが進めた民営化により、旧ソ連の重要な事業が次々に彼と個人的に関係のある者たちの手に渡り、しかも彼らはアメリカやイギリスとつながっていた。彼らはロシアの国富を吸い上げて急速に巨大化し、オリガルヒと呼ばれる新興財閥に成長した。日本の財閥は企業だが、欧米のオリガルヒはすべてを個人が握っている。彼らは突出した億万長者であり、私兵を抱え、国の政治経済を支配している。ロシアのオリガルヒは事業を通じて国富を欧米に流出させ始めた。
またエリツィンはアメリカのウォール街が主導する市場経済への移行プログラムを実行し、ロシアをソ連時代の末期よりはるかにひどい状態に突き落とした。ハイパーインフレが襲い、労働者の蓄えが消失し、欧米から流入する製品が産業を破壊し、ロシアの大衆は貧困と飢餓に陥った。
ソ連崩壊後にロシアが味わった地獄
1991年の分離独立後、平均的なロシア国民の消費はわずか1年で40パーセントも減少した。1998年までにロシアの農業のおよそ80パーセントが破産し、7万ヵ所の工場の操業が止まり、トラクターの生産が88パーセント、洗濯機の生産は77パーセント、綿の布地の生産も77パーセント、テレビの生産は78パーセントも減少した。ロシアのGDP(国内総生産)は分離独立後の最初の数年間に50パーセントも低下し、通貨は紙切れ同然になった。
だがそれまで資本主義経済を一度も経験したことがなかったロシアの大衆は、なぜそうなるのかがわからなかった。共産主義から突然アメリカの新自由主義による自由市場システムに変更され、オリガルヒに金融、産業、経済を牛耳られたロシアは、壊滅的な打撃を受けて崩壊した。
世界銀行の統計によれば、ロシアでは1989年に200万人だった貧困レベル(1日の生活費が4ドル以下)で暮らす人の数が、1990年代半ばまでに37倍の7400万人に急増し、1996年の統計ではロシア人の4人に1人が「極貧」レベルの状態に陥った。アルコール中毒者が急増し、自殺率が2倍に跳ね上がり、暴力犯罪が増えて殺人が横行し、癌、心臓病、結核などの病気にかかる人の率が工業国で最大になった。男性の平均寿命は57歳にまで下がり、ロシア人全体の死亡率は60パーセントも上昇した。西側とロシアの人口統計学者は、1992年から2000年までの間にロシアでは500万〜600万人の超過死(それまでの統計にあてはまらない過剰な死)があったという意見で一致している。これはロシアの人口の3・4〜4パーセントに相当する。
だがエリツィンの時代のこの悲惨さは、西側にはほとんど伝わってこなかった。ニュースになったのは、最高会議の議員たちから批判されたエリツィンが軍を出動させ、戦車で議会ビルを砲撃して反対者たちを押さえつけたことくらいだ(この事件では数百人の死傷者を出した)。彼はカネと支配欲に目がくらんだ独裁者だった。
エリツィンは1989年9月にアメリカのNASA(航空宇宙局)を視察に訪れた時に、テキサス州ヒューストンの大型食料品店を訪れてアメリカの物質的な豊かさに衝撃を受けた。モスクワに戻る飛行機のなかで、彼は「いかにロシア国民の生活レベルが低いか、共産党がやってきたことがどれほど間違っていたかを知った」と側近に語っている。だがアメリカや西欧がそのように豊かになった理由こそ、共産主義が生まれた原因ではなかったのか。
エリツィンは建築以外、政治も経済もヨーロッパの歴史も学んだことがなかったに違いない。ウラル地方の寒村の農家に生まれ育ち、ブレジネフの引きでモスクワの共産党中央委員会に移った彼は、ゴルバチョフに劣らず「ぽっと出の政治家」だった。そのうえ派手な政治パフォーマンスを好み、すぐキレる過激な自由化論者だったこの男が、米英情報機関のリクルートのターゲットになったとしても不思議はない。科学技術、軍事力、芸術、音楽、文学などで世界のトップレベルにあったロシアが、暴政を振るう途上国の独裁者並みの1人の男のために崩壊したという事実には驚くほかはない。
1996年の大統領選挙では、国民の支持率がほぼゼロ近くにまで下がったエリツィンを勝たせるためにオリガルヒたちが全面的に動き、アメリカのクリントン政権が選挙キャンペーンのプロやスタッフを送り込んだ。エリツィンが当選して2期目が始まるとIMFが400億ドルものカネを貸し付けたが、その多くは彼の政権の腐敗の中に消えて行った。
そして月日とともに、エリツィンは鬱屈した日々を送るようになっていく。国の崩壊を目の当たりにして自責の念もわいたのだろうか。もともと大酒飲みで奇行が知られた彼は酒の量が増え、アルコール依存症も悪化した。議会のたび重なる大統領弾劾の動きに加え、右派からも左派からも激しく突き上げられてストレスも増したのだろう。飲酒が原因で健康が衰え、持病の心臓病が悪化したエリツィンは、1999年末、ようやく大統領を辞任した。後継者に指名されたのはウラジーミル・プーチンだった。
金儲けに邁進したクリントン時代のアメリカ
一方アメリカでは1992年の大統領選挙で番狂わせがあり、ブッシュ(父)が敗れてビル・クリントンが当選した。クリントン時代のアメリカは、ブッシュの時代のような地政学的な世界支配にではなく、金儲けに邁進した。もちろんそれもアメリカが単独の超大国となったからこそできたことだが、新自由主義と自由市場がますます唱道され、ハイテク時代の訪れも相まってファンドが巨大化し、アメリカの大手金融機関による世界の金融支配が進んだ。
日本もそのあおりを受けて1990年代後半になると金融機関の統合・再編成が進み、大手証券会社が廃業するなどの大変動が起きた。ドルはウォール街が富を増すための武器として使われ、南米、東南アジア、ロシアなどでアメリカの金融機関が大規模な空売りを仕掛けた結果、それらの国の通貨が暴落して金融危機が発生した。
その反面、アメリカの軍需産業はクリントン時代に冷や飯を食わされ、兵器メーカーの受注はレーガン時代の約半分にまで落ち込んだ。軍用機やミサイルを開発していた技術者の多くが仕事を失い、自宅の裏でコーヒーのテイクアウトの店を営んでいるなどという記事が新聞に載るようになった。イギリスでもMI5やMI6が縮小され、諜報員の仕事がなくなったと言われた。この時代に米英とも軍産の再編が進み、中小兵器メーカーが大手に吸収合併され、いくつかの巨大軍需企業が誕生した。
「21世紀は戦争の世紀になる」
ここで特筆すべきは、クリントン時代の末期から次のブッシュ(子)政権にかけてアメリカは東欧諸国を次々にNATOに加えていったということだ。アメリカの戦闘機メーカーは、そうなることを見越して、クリントン時代の中期に戦闘機やミサイルを東欧諸国に売り込んだ。
東欧の国がNATOに加盟すれば、それまで所有していた旧ソ連製の兵器を徐々に他のNATO加盟国と同じアメリカの兵器システムに入れ替えていく必要がある。そのためNATOの東方拡大には軍産ビジネスが相乗りしていた。アメリカの戦闘機メーカーはルーマニア、ポーランド、ハンガリー、チェコなどで頻繁にセミナーを開き、CEOや重役たちが自ら乗り込んで売り込みを行った。
またクリントン時代にアメリカは石油や天然ガスが豊富な中央アジア諸国に進出し、石油メジャー(国際石油資本)がカザフスタンを中心にパイプラインの建設を開始した。これもソ連が消滅してはじめて可能になったことだった。いよいよマッキンダーの言うところの「世界島」(ユーラシア)の中心部への進出が始まったのだ。
2001年にブッシュ(子)政権が誕生すると、アメリカは再び軍事的な世界支配への道を進み始める。ブッシュ(子)は大統領に就任してまもなく、「21世紀は戦争の世紀になる」と宣言した。この時代になると兵器のハイテク化が進み、軍産がシリコンバレーのベンチャー企業を次々と吸収して、安全保障ビジネスはより広い領域をカバーするようになった。
アメリカ一極支配の時代になったと信じたブッシュ(子)政権は、2001年に起きた同時多発テロをきっかけに「テロとの戦争」を始めてアフガニスタンに出兵し、クリントン時代に冷や飯を食わされていた安全保障関係の企業に青天井の天文学的な額の予算が与えられた。ブッシュ(子)は「テロリストだけでなく、テロリストをかくまう国も攻撃する」と宣言し、「あなたの国は我々とともにいるのか、それとも彼らとともにいるのか」として「味方でないなら敵」という中間を認めない二元論で踏み絵を迫った。ハイテクを駆使した監視システムが世界中で大ビジネスとなり、怪しげな民間軍事会社が急成長したのもこの時期だ。
だがブッシュ(子)政権は2003年にイラク戦争を開始したが、まもなくイラクでもアフガニスタンでも目算が外れて壁に突き当たる。イラクでは皮肉にもブッシュ(子)が勝利宣言をした直後から米軍へのゲリラ攻撃が急増し、米兵の死者も増え始めた。2005年頃になると、イラクはベトナムの再現になるとまで言われるようになった。
冷戦が終わり、世界で左翼政権が後退した
日本では1980年代に西欧諸国と同じく左翼が後退を始め、1990年頃から自民党を出た政治家による新党ができては消え、自民党政権も総理大臣が短期間で次々と交代するという政治の混乱の季節が到来した。これも冷戦の終了によって世界各地に生じた症候群の一つだ。アメリカという親亀が体を揺すれば、背中に乗っている子亀はみな振り落とされる。
南米の親米右翼独裁政権や、韓国や台湾の軍事政権が1980年代末に次々と崩壊していったのも、冷戦の終了と関係していた。共産主義が衰退すれば、防波堤として機能していたそれらの独裁政権や軍事政権は必要なくなる。それらの国々に民主的な政権が誕生したのは、おもにアメリカの金融界の意向だった。南米の多くの国は独裁政権時代にアメリカの銀行から多額の融資を受けて国家インフラを建設していたため、1990年代に金融危機が訪れると次々と財政が破綻し、債務不能に陥る国が連鎖反応的に広がっていった。
西ヨーロッパでは1993年にEUが誕生し、2002年には共通の通貨であるユーロの流通が始まった。だがEUは国力に大きな差がある複数の国家を人為的に束ねたものであり、とくにすべての加盟国が使用する共通の通貨を欧州中央銀行が発行する金融システムは、はじめから矛盾を内包していた。EUを確立してNATOとEUを西欧の両輪にしようという、イギリスとアメリカの一部の勢力が進めてきた計画は次第にトラブルが表面化し、イギリスは2020年にEUを脱退したが、それで国が2つに分裂してしまった。イタリアも何度か脱退を試みたが引き戻された。
統一後のドイツは経済成長を続け、2000年代にEUの事実上の領袖となったが、ロシアから安い石油やガスを輸入して産業を発展させ、製品を中国に輸出するというビジネスモデルは、ウクライナ紛争が始まった直後の2022年3月に失速した。アメリカからロシア制裁を強制されて石油やガスが輸入できなくなったドイツの産業や経済は急速に衰えつつあり、中国との貿易もアメリカから強い圧力を受けている。
強国としてのし上がろうとするたびにアメリカにつぶされるというドイツのパターンがまたくり返されているように見える。第一次世界大戦・第二次世界大戦に続き、ドイツは3度目の敗戦を迎える可能性があり、ドイツが弱体化すればEUも危うくなる。
アメリカとイギリスの関係では、結びつきと対立がともに大きくなった。本書でも「米英」という表現をよく用いているように、アメリカとイギリスは同じアングロサクソンの国として利害や信条が共通している部分も大きいが、じつは根本的な対立もまた根が深いのだ。
プーチンを支える勢力「シロビキ」の正体
ロシアがどん底から這い上がることができたのは、エリツィンを排除する機会をさぐっていた愛国派がようやく力を回復し、元KGBのプーチンをリーダーに据えることができたためだった。
プーチンはよく言われるような独裁者ではなく、このグループを代表する顔なのだ。このグループはシロビキと呼ばれる安全保障・軍関係の勢力に支えられており、党の官僚出身のゴルバチョフやエリツィンのように甘くはない。プーチンは1990年代にロシアを崩壊させたオリガルヒたちを押さえ込み、アメリカが「テロとの戦争」に気を奪われている間にコーカサス地方を安定させ、ヨーロッパへの石油の輸出を増やして経済と軍を再建した。
結果的に見れば、ソ連が消滅して共産主義を放棄したのはロシアにとって良い選択だった。エリツィンの時代には国内を跳梁する略奪者のおかげで地獄の苦しみを味わったが、ロシアはどん底の時代を通り抜けることで、資本主義の本質や西側の企みの正体など多くのことを学んだ。帝政ロシア時代の圧政とその後の共産主義しか知らなかったロシアは、資本主義にも精通する強国として甦っただけでなく、国際政治を最もよく理解できる国の一つになった。それはアメリカが世界を支配しながら世界の人々をほとんど理解していないのとは対照的だ。
アメリカ敵視による「中ロの接近」
中国では1993年に鄧小平の後を継いで国家主席になった江沢民が親米路線を進めたが、2003年に江沢民から胡錦濤に引き継がれると、北京の主権維持派が上海の江沢民派と衝突を始め、中国は次第にアメリカから離れ始めた。この時期は、アメリカがイラク戦争を始めて壁に突き当たり、ロシアの復活が進み始めた時期と一致する。
2008年、改革開放を始めて25年以上が過ぎ、国力を増した中国は、北京オリンピックを契機に大国としてデビューを果たした。2013年に習近平の時代になると親米派を本格的に排除し始め、ユーラシア大陸のインフラを整備して中近東やヨーロッパとつながる一帯一路計画(新シルクロード計画)をスタートさせた。2015年には中国の上海協力機構にロシアが主催するユーラシア経済連合を合併させる計画が始まり、翌年に大ユーラシア・パートナーシップ構想が発表された。中国とロシアは歴史的に複雑な関係をたどってきたが、こうして戦略的同盟を結んだのだ。もともと仲が良いわけではなかった中露がこのような方向に進んだのは、アメリカによる敵視の結果だった。
現在を深刻な対立に導いた「火種」
東西ドイツの統一は1990年9月に関係6ヵ国が条約に署名して10月3日に成立した。統一ドイツの誕生は冷戦がまもなく終了することを世界に示す歴史的な出来事ではあったが、その合意に至る過程で、後の世界を再び深刻な対立に導く種が蒔かれていた。
ドイツ統一に向けた協議で最も大きな問題になったのは、統一後のドイツはNATO(北大西洋条約機構)に加入するのか、ソ連軍はドイツ東部にとどまるのか、東欧はNATOへの加入を許されるのか、などといった点だった。もしドイツがNATOに加入すれば、米軍はNATO軍としてドイツにとどまり、米軍の核兵器もドイツに残ることになる。そうなった場合、米軍はそれまで東ドイツだった領域にも入って来るのか、ということもソ連にとって重大な関心事だった。またNATOはソ連を仮想敵としているため、ソ連に隣接する東欧諸国がNATOに加入すればソ連の安全保障は大きく損なわれることになる。
ソ連の外務省、国防省、軍の参謀本部、KGB、共産党政治局は、「ドイツの統一は、新しく生まれるドイツがNATOとワルシャワ条約機構との間で中立の立場を取るという条件のもとでなら受け入れる」との考えだった。統一後のドイツを中立にするとは、米英軍が西ドイツから引き揚げ、ソ連軍も東ドイツから引き揚げ、ドイツはNATOに加入しないということだ。
公的な場で最初にこの問題が語られたのは、西ドイツのゲンシャー外相が1990年1月に行ったスピーチだった。ゲンシャーは「ドイツ統合のプロセスは、ソ連の安全保障を毀損するものであってはならない。したがって、NATOは東方に拡大してソ連との国境に近づくべきではないし、現在の東ドイツにあたる地域には(統一後も)NATO軍を配備しない」と述べた。
アメリカのブッシュ(父)政権も、「ソ連がドイツの統一を認めるなら、我々はNATOを東に拡大させない」とゴルバチョフ政権に確約していた。それは次のような経緯による。
ゴルバチョフとアメリカのベイカー国務長官との運命の会談は、1990年2月9日に行われた。ベイカーはその2日前にモスクワに到着し、シェワルナゼ外相と会談して「もしかすると、この話し合いで、(現在の)東ドイツ(にあたる領域)にはNATO軍を配備しないという保証がなされるかもしれません。いや、実際のところ、それは禁止されるでしょう」と述べている。それは西ドイツには米軍が残ることを意味するが、ベイカーは手書きの備忘録に「(西ドイツの)NATOの管轄権は東側に動かない」と記している。
シェワルナゼ外相との会談後、ベイカーは9日のゴルバチョフとの会談でこう言った。
「もしソ連がドイツの中立と米軍の撤退に固執し、その結果、米軍がドイツから引き揚げてしまえば、ドイツは将来またヒトラーのような野望が首をもたげて核を持とうとするかもしれません。あなたはNATO軍も米軍もいなくなったためにドイツがそのようになる事態を望みますか? それともNATOが残って、しかし今の位置から1インチも(東に)拡大しないほうがよいと思いますか?」
これが有名なベイカーの「NATOは1インチも動かさない」発言だ。
ブッシュもサッチャーも約束を反故にした
だが、どれほどアメリカのベイカーが言葉で保証しようが、ソ連軍がカウンターバランスとしてドイツ東部にとどまらない限り、アメリカがNATOを東に拡大させないなどということを信じるロシア人がいただろうか。ゴルバチョフが犯した最大の誤りは、ベイカーの言葉を条約のなかで成文化するよう要求しなかったことだった。
翌2月10日、西ドイツのコール首相はゴルバチョフと会談して「我々はNATOの活動領域を拡大すべきではないと考えている」と述べ、ゴルバチョフから「NATOが東に向けて拡大しない限り、統一後のドイツのNATO加入に基本的に同意する」との重大な言葉を引き出した。ゴルバチョフのその言葉は、前日のベイカーの発言を受けたものだ。
同年5月に開始された東西ドイツ、アメリカ、ソ連、イギリス、フランスの6ヵ国による前述の協議でもその件は話し合われ、9月12日に最終合意して成文化された条約には、西ドイツのゲンシャー外相がその年の1月にスピーチで提示した「現在の東ドイツにあたる地域にはNATO軍を配備しない」という一節が入れられた。だが「NATOは東方に拡大してソ連との国境に近づくことはない」とは記されていなかったのだ。
5月31日にワシントンで行われたブッシュ(父)とゴルバチョフのサミットで、ブッシュ(父)はこう語っている。
「ドイツのNATO加入は、けっしてソ連に対する牽制ではありません。私を信じて下さい。我々はドイツの統合を(無理やり)プッシュしているのではないのです。そしてもちろん、我々にはソ連をいかなる方法でも害しようなどという意図はありません。そんなことは微塵も考えていません」
アメリカとイギリスは、「NATOは軍事的な側面を減らし、政治的な同盟とする方向に変えていく」と明言し、イギリスのサッチャーも6月8日にロンドンでゴルバチョフと会談した時に、「私たちはヨーロッパの未来に関するディスカッションにソ連に全面的に入ってもらうために、ソ連が確実に安全保障を(得られると)確信できる方法を見つけなければなりません」と述べている。
こうしてゴルバチョフは、西側のトップたちから「西側がNATOを東方に拡大してソ連の安全保障に脅威を与えることはない」と確約され、ドイツの統合に同意したのだ。合意文書に署名するのが9月になったのは、ソ連が国内の意見を調整したり、西ドイツから融資を受ける交渉などに時間を必要としたためだった。
翌1991年3月になっても、イギリスのメージャー首相はゴルバチョフに「我々はNATOの強化など話し合っていません」と断言していた。後にソ連の国防相が「東欧諸国はNATOに入りたがっているのではないか」と質問すると、メージャーは「そんなことは一切ありません」と否定した。同年の7月にソ連最高会議の議員たちがブリュッセルのNATO本部を訪れて事務総長と会談した時も、事務総長は「我々はソ連をヨーロッパ共同体から孤立させるべきではないと考えており、私もNATO会議もNATOの拡大には反対しています」と語っていた。
だがCIAのロバート・ゲイツ長官(後にブッシュ[子]政権・オバマ政権の国防長官)は、「ゴルバチョフがNATOの東方拡大はないと信じ込まされている間に、彼らはそれを押し進めていた」と批判していた。NATOがロシア国境に向かって拡大を始めたのは、東欧からソ連軍が引き揚げ、ワルシャワ条約機構が解散してから8年後の1999年だった。
新冷戦─現在のウクライナにつながる新たな闘い
アメリカは2002年にABM条約(弾道ミサイル迎撃ミサイルを制限する条約)から、2019年にはINF全廃条約(中距離核戦力全廃条約)から、ともに一方的に脱退し、ポーランドとルーマニアに弾道ミサイル迎撃ミサイルの発射システムを配備した。この発射システムはモスクワを標的とする中距離弾道ミサイルの発射が可能で、むしろそちらのほうが本当の目的だったとも言われている。ポーランドやルーマニアから核弾道ミサイルが発射されれば、モスクワには7〜8分で着弾する。ロシアの強い抗議は無視された。
さらにNATOは毎年、リトアニアや黒海のルーマニア沖などの、ロシアとの国境に近い地域で実弾発射演習や上陸演習を行っている。これらはみな、地政学で言うところの「ハートランド」、つまりロシアを攻めようとする動きのデモンストレーションに他ならない。
ウクライナでは2014年に政権転覆クーデターが起きた後、東部のロシア系住民が住む地域でロシア系住民の民兵とウクライナ軍の武力衝突が発生した。紛争を解決するため、2015年にロシア、ウクライナ、ドイツ、フランスの間で「ウクライナ政府はドイツとフランスの監督のもとで、東部のロシア系住民が住む地域の自治権を認める法律を制定する」というミンスク合意がなされたが、ドイツもフランスもウクライナも行動せず、武力衝突は止まらなかった。むしろウクライナ軍とロシア系住民の民兵組織の戦闘は激化し、ウクライナ東部は内戦状態になった。ウクライナ軍はロシア系住民が住む地域に砲撃を続け、8年間に1万数千人のロシア系住民が殺された。ミンスク合意は反故にされたのだ。
2021年12月上旬、ロシアのプーチン大統領はアメリカのバイデン大統領からの電話会談のリクエストに応じ、「これ以上NATOをロシアとの国境に向けて東に拡大しない」との「法的拘束力のある保証とその成文化」を要求し、「ロシアのレッドラインはウクライナにも適用される」と伝えた。バイデンは返答しなかった。
同月下旬にはロシアからのリクエストで再び電話会談が持たれ、ロシア外務省が声明を発表した。それには上記の要求のほか「モスクワをターゲットとするミサイルを、ロシアと国境を接する国に配備しない」「NATOや米英などの国はロシアとの国境近くで軍事演習を行わない」「NATOの艦船や軍用機は、ロシアとの国境から一定の距離を保つ」「ヨーロッパに中距離核ミサイルを配備しない」などを保証する条約を結ぶよう求める内容が記されており、ロシア外務省はアメリカとNATOに条約のドラフトを送った。だがアメリカもNATOも返答しなかった。事情に詳しい欧米の国際政治通の間では、ロシアがこの条約案で示した要求は事実上の最後通牒だったとの見方で一致している。
2022年になるとウクライナ軍はロシア系住民地域を総攻撃するために主力部隊を東部に移動させ、ウクライナのゼレンスキー大統領はNATOへの加入を申請し核武装する意思があると発言した。ウクライナ軍の攻撃が迫った2022年2月24日、ロシアは軍を侵攻させた。
そして闘いは続いていく
こうしてポスト冷戦時代は完全に終わりを告げ、2010年代なかばから姿を現し始めていた新冷戦の時代に本格的に突入した。ロシアは国家の存亡を賭けており、かつてのソ連のように「最後はアメリカに一歩譲る」ことはもうできないと考えている。
米英はなぜこのように危険な「現代のグレートゲーム」を続けているのか。ブッシュ(子)政権時代に国務長官を務めたコンドリーザ・ライスは、以前こう語ったことがある。
「ロシア人は世界の人口の2パーセントでありながら、ロシアは地球の陸地の15パーセントを占め、おもな天然資源の30パーセントを保有しています。私たちはこのような状態を永遠に続けるわけにはいきません」
戦後の世界を形作り、今日の世界を動かしているのは、欧米支配層のこうした考えではないだろうか。
参考文献・参考資料
アメリカとソ連が備えた「互いを破滅させる」ための「ヤバすぎる最終兵器」の全容 (msn.com)
なぜ世界はここまで「崩壊」したのか…「アメリカ」と「ロシア」の戦いから見る「ヤバすぎる現代史」(玉置 悟) | 現代新書 | 講談社(1/5) (gendai.media)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

