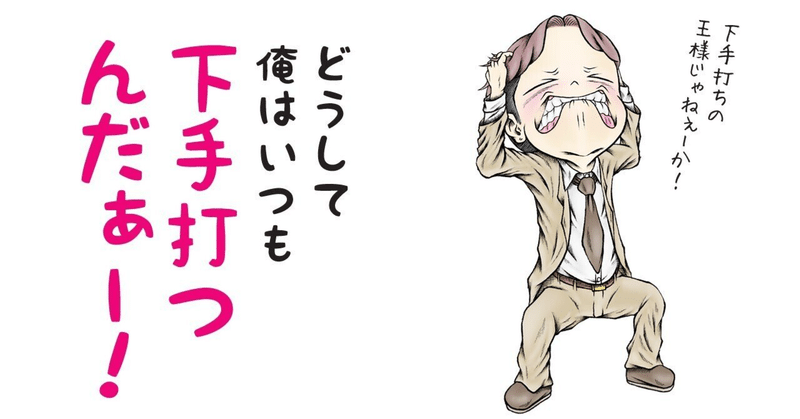
政治講座ⅴ1782「被害者意識の中国」
経済力と軍事力がついて過去の歴史の悔しい想いを臥薪嘗胆で耐え忍んだ結果が今の中国の暴挙に繋がっているのであろう。歴史的に日本を格下、つまり、四夷(しい)あるいは夷狄(いてき)として見下していたのであるが、明治以降、大日本帝国に侵攻されたことが、彼らの歴史的汚点となり、それ故、経済援助で経済発展したことに感謝せずに、未だ反日教育する理由であると考える。中国の知識人や富裕層は故郷を捨てて日本に帰化か永住権取得しようとして、中国大陸から脱出を試みている。だから帰国する中国人の知識人を見せしめの為に反スパイ法で拘束し、粛清するのである。反日教育や愛国(愛党)教育は、心底従うことの逆効果を生み出しているのが現状であろう。「中国は法治国家と言う」が近代化しきれない人法国家の域を抜けきれない前近代国家のままであろう。中国に魅力がないことは、日本や米国から中国へ亡命した話は聞いたことが無いで分ることである。
今回は垂秀夫・前駐中国大使の中国に関する報道記事の意見も紹介する。
皇紀2684年5月16日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
なぜ共産党なのか?習近平氏の出した答えが「強い中国」 垂秀夫前駐中国大使が解説する「四つの視座」とは【中国の今を語る(1)】
47NEWS によるストーリー

中国の強権的な習近平体制は、突然誕生したわけではない。当然ながら共産党としての歩みがあり、故鄧小平氏がつくった集団指導体制からの連続性の中で出てきた。その連続性を理解しないといけない。中国問題も社会科学だ。さまざまな社会事象の中に法則性を見つけ出すアプローチが大切。私はそれを“視座”と呼んでいる。「変わる中国」と「変わらない中国」という側面がある。「問題提起」と「命題」は変わらない。だが、その「答え」は常に変わってくる。これが大事なポイントだ。(聞き手・共同通信中国総局長 芹田晋一郎)
▽「豊かになるから」と答えられず
第1の視座は、中国共産党の正当性の問題。中国はわれわれの体制とは明らかに違う。選挙がなく民主主義体制ではないので、なぜ共産党がこの広大な中国を統治しているのかについて、人民に答えなければいけない。
建国当初、毛沢東の時代は「なぜ中国共産党なのか」の答えは、旧日本軍と戦って建国した、立ち上がったからということだった。この正当性の問題についてそれほど大きな疑義を挟まれることはなかった。建国の英雄だったからだ。
ところがその毛沢東自身が、1950年代から大躍進や反右派闘争という失敗を犯し、1960年代になると文化大革命に入って、相当おかしくなり、1970年代になると通用しなくなってきた。文革が終わり、信用していた共産党を、もう信用できなくなってきた。その時に鄧小平氏が台頭した。鄧小平氏は共産党についてくれば「豊かになれる」という新たな答えを出した。つまり「なぜ共産党なのか」という命題は変わらないが「答え」が変わったということだ。
私の言う「鄧小平時代」は、鄧氏および彼に続く江沢民元国家主席、胡錦濤前国家主席時代も含めている。この時代は「豊かになる」という道を突っ走った。共産党の連続性があるので、習近平国家主席の時代になっても「なぜ共産党なのか」に答えなければならない。その命題は変わらないので。だが「豊かになるから」とは答えられなかった。胡錦濤時代の後半あたりから、高い経済成長が保てなくなってきていたからだ。

そこで習近平氏が出した答えは「強くなる」「強い中国」だった。これによって国民をひきつけようとした。あるいは「中華民族の復興」「中国の夢」とうたって、人民を鼓舞しようとした。これが、習近平氏の正当性。共産党の連続性の中にあって、ずっと変わらない命題があり、それぞれの時代背景に応じて、それぞれの指導者が答えを出してきた。
だから習近平氏にとって台湾問題も大切になる。中国建国は毛沢東のレガシー(政治的遺産)。香港返還は鄧小平氏のレガシー。習近平氏がレガシーを考えるときに、台湾問題であることは間違いない。ただ経済がここまで悪くなって、軍の腐敗汚職が極めて深刻な状況になっており、今は戦争をできる状況にはない。
▽「党」が「人」に変わった
第2の視座は、習近平氏の時代になって「一党支配」が「一人支配」になったこと。鄧小平氏は、本当は“ミニ毛沢東”にもなれたが、あらゆる自分の個人的権力、権威を使って集団指導体制を作った。集団指導体制なので、共産党トップが誰でも国を率いることができるようになった。一党支配だ。
ところが習近平氏がトップになった時に漢字で言えば「党」が「人」になっただけだが、全く似て非なるものになった。共産党は表面的には何も変わっていないにもかかわらず、政策決定過程は大きく変わった。最高指導部である「政治局常務委員」の7人は、党規約上は基本的に全員が同格だ。今は、習近平氏以外の6人は習氏の部下になった。以前は「班長制」と言って、7人にそれぞれの担当があった。今は習近平氏には担当がない。全てを担当するから。

しかし習近平氏も1人の人間で、1人で決められる能力も時間も有限だ。決められない部分が山ほどある。その決められない部分が一体どうなるのか。大きく分けて二つある。一つは、事なかれ主義で、待ちの態勢になる。何も決まらないから何もしない。もう一つは、きっと習近平氏ならこうするだろうと、いわゆる忖度。「事なかれ主義」と「忖度」がはびこることになる。
かつては党政治局員の誰かが間違っても、その1人の問題として処理することで、共産党としては誤っていないというストーリーがつくれた。党の無謬性。だが今は1人。その1人が誤ることはない、失敗することはないというストーリーになってしまい、神格化につながっていく。それでも1人支配の方が効率よく強い中国を作れるし、なおかつ、そうしないと、この危機を乗り越えられないと考えているのだろう。

▽国家戦略目標が「国家の安全」に
第3の視座は、習近平氏にとって「国家の安全」が最重要になっているということ。つまり国家戦略目標が鄧小平時代の経済建設から国家の安全に変わったということだ。これが現代的意義にとって最も大切な点である。われわれが常に中国について見誤っているのは何か。中国を見るときに、どうしても“鄧小平中国”を想定している。だから「経済が悪い」とか「なぜ戦狼外交ばかりやるのか」という考え方になる。
鄧小平時代は国家の戦略目標である経済発展のために、安定した国際環境が必要で対米関係や対日関係も比較的安定した政策を採った。なおかつそれが社会の安定につながった。ところが、胡錦濤氏の時代になって、経済成長が減速しただけではなく、三つの大きな問題も出てきた。
(1)腐敗汚職の問題が深刻化し
(2)環境破壊がとてつもなく進み
(3)経済格差があまりにも広がった。
それによって社会不満も非常に強まった。
当局が発表している数字でも1日数百件の「群衆性事件」、いわゆる暴動、デモが起きた。2008年12月18日に、胡錦濤氏は「政権与党としての中国共産党の地位は永遠でも不変でもない」という極めて深刻なスピーチを行った。そこまでの危機意識があった。その後でバトンタッチされた習近平氏も同様の問題意識を持っていた。

それに対する習近平氏の答えは「中国を強くする」ということだった。高い経済成長はもう達成できないし、経済建設よりも大事なものは「国家の安全だ」という考えになった。あるいは「党の安全」や「体制の安全」だ。先の三つの問題に対しては、まず反腐敗を徹底的にやった。環境問題も大幅に改善した。経済格差については、貧困層対策をして「絶対的貧困」はなくなったと宣言し、富裕層に対しては「共同富裕」をスローガンに多額の寄付をさせた。
強い中国を目指し、国家の安全を守るための外交となると「戦狼外交」になる。だから対米関係でも対日関係でも衝突する。習近平氏は既に彼なりの答えを出しているが、彼の認識と、外から中国を見た時の認識のギャップが非常に大きい。
今、なぜ経済がここまで悪いかと言うと、この体制から来ている。かつての党の無謬性が、今は1人の無謬性になっている。たとえ経済政策を間違ったとしても、認めることはできない。経済低迷が体制から来ている以上は、政策転換に相当な時間がかかるし、それまでに大変な状況になるだろう。
ただ習近平氏からすれば、暴動も起きておらず「国家の安全」が保たれているので、国家運営はうまく行っていると考える。彼自身の答えとして今の政策に突き進んでいるのだから、今の中国を変えようとしても変わらない。
▽覇権ではなく「被害者意識」
第4の視座は、1840年のアヘン戦争以降の被害者意識。なぜ中国があれだけ痛めつけられたのかということに対して、「あの時代には力がなかったからだ」という答えを出した。だからこそ「今は力が必要だ」という考えになっている。
「中国は覇権を求めている」とよく言われるが、私は全く同調できない。中国は一切覇権をやっているつもりはない。中国は常にいじめられている、痛めつけられている、取り囲まれていると思っている。それへの対処が、昔のように弱い国だったときは、周辺国が「中国は被害者意識が強い」と思うぐらいだったが、今はこれだけ政治的にも軍事的にも経済的にも強い国になって、まだ被害者意識を持って、中国自身がそれを一生懸命ひっくり返そうとしている。

そうすると、われわれからは覇権的行為に見える。南シナ海や東シナ海での動きもそうだ。昔は、例えば沖縄県・尖閣諸島の周辺でも、公船を送る能力がなく、全部日本にやられたと思っている。南シナ海も、ベトナムやフィリピンに昔やられたと思っている。国際社会では、多くの人が「中国が領土を取りに行っている」と考えているが違う。中国はやられたと思っている。被害者意識だ、全て。ただ、力を持っている者がやり返したら、覇権に見える。中国の外と中で認識が全然違う。
経済大国になって、政治的にも力を持ってきたときに、どう見ても今は米国主導の国際政治経済秩序で、これは合理的でも公平でもないと認識するようになった。「グローバルサウス」と呼ばれる新興国・途上国にとって、とりわけ中国にとって、公平かつ合理的な秩序を作る必要があるという認識がある。
中国は、米国からあれだけ制裁関税を課された。自立したサプライチェーン(供給網)をつくろうとしているのは「経済産業の安全」の問題で、全ては「国家の安全」につながっている。自分たちを守るためだ。ただ中国からすれば「覇権」のつもりはなくとも、われわれからすれば、それは経済的威圧だ。

新型コロナウイルス禍で、中国は世界中にワクチンを配って「ワクチン外交」をやった。各国の指導者にとって、ワクチンを集めれば自分の支持率につながる。それで各国の内政を助けた。習近平氏は、アフリカなどのほぼ全ての途上国の大統領や首相と電話会談をした。米国も日本もやっていない。
日米欧など西側諸国は「対中包囲網構築」と考えているが、今囲まれているのは西側だ。中国はグローバルサウスとの関係で大成功している。「大家族」対「小グループ」の対立軸。それを日米などは過小評価している。中国の外交は、一部だけを見て「覇権だ」「戦狼だ」というのではなく全面的な理解が必要だ。
× × ×
垂秀夫氏(たるみ・ひでお) 1961年、大阪府出身。海外勤務は中国本土4回、香港1回、台湾2回で、外務省の中国語研修組としても極めて異例の経歴を歩んできた。幅広い人脈や情報収集能力に定評があり「中国が最も恐れる男」と称されることもある。2020年9月から3年余り、中国大使を務めた。写真撮影はプロ級の腕前で、退官後に写真家に転身。今年4月から立命館大教授。
中国はどのように「世界の覇権」を握るのか
篠田 英朗 によるストーリー
中国とはどのような国家か?
中国とは、地政学の観点から見て、どのような国家か。この問いは現代世界において決定的な重要性を持っている。
ところが意外にも簡単には答えられない。ある者は、ランド・パワーの雄だと言う。大陸系地政学の観点からは、アジアの覇権国という位置づけになるかもしれない。
だがたとえばスパイクマンの理論を参照するならば、中国は「両生類(Amphibia)」である。中国は、大陸に圧倒的な存在感を持って存在している一方で、遠大な大洋に通ずる沿岸部を持っている。中国は、歴史上、大陸中央部からの勢力による侵略と、海洋での海賊等も含めた勢力による侵食の双方に、悩まされてきた、「両生類」として生きる運命を持っている国家だとも言える。
中国とドイツの共通点
かつて二度の世界大戦を仕掛けて敗北したドイツは、ランド・パワーとシー・パワーに挟まれた国家であった。ドイツの帝国としての存在の歴史的淵源は、神聖ローマ帝国にあると言えるが、プロイセン主導でオーストリアを排除する形で19世紀に成立したドイツ帝国は、神聖ローマ帝国と比して、大きく沿岸部にその存在の比重を移動させた国家であった。
そのためやがて、ヨーロッパ大陸における覇権を求めつつ、同時に海洋におけるイギリスとの間の競争に乗り出した。その結果、ランド・パワーのロシアと、シー・パワーのイギリスに囲まれる構図で戦争に突入することになった。同じ図式は、ナチス・ドイツの第二次世界大戦にもあてはまる。
これはドイツの外交安全保障政策の失敗として描写される経緯であるかもしれないが、より構造的には、ドイツ特有の地理的位置づけによってもたらされる事態である。もっともそれはスパイクマンの英米系地政学の理論の枠組みにそって言えることである。
大陸系地政学の理論にそって圏域を重視する視座を採用すれば、ドイツはヨーロッパの覇権国となろうとしたが、拡張主義を警戒されすぎたために、隣接する圏域の覇権国と衝突することになった、という説明になるだろう。

英米系地政学にそって、中国が「両生類」であるとすると、かつてのドイツと同じ地政学上の位置づけにある、ということだ。かつて近代化に後れを取って国家としての存在が危うかった20世紀の中国は、陸上兵力を中心とした軍事力を整備していた。ところが今日の中国は、海軍力の面において目覚ましい進展を遂げている。陸でも、海でも、覇権国としての地位を固めようとしている。大陸系地政学の理論枠組みにそって言えば、中国は、東アジアに自国の生存圏/勢力圏/広域圏を確立することを狙っており、その覇権を陸上においても海上においても確立することを狙っている。
西洋とは全く違う中国の世界観
中国には中華帝国の伝統が根強く存在しているとされる。中華思想の特徴は、世界で最も進んだ文明が中国の首都にあり、それが世界の中心として観念されることである。いわゆる朝貢制度とは、中華帝国の威光を知る周辺諸国が、力の格差を確認するために朝貢品を持って中華帝国の首都に参上する制度である。
地域研究の分野で「曼荼羅国家」と呼ばれる領域性が曖昧な性格を持つ国家群が、アジアでは伝統的に存在していたと論じられる。「曼荼羅」はヒンドゥー教の宇宙論に由来する概念で、中心点とそこから同心円状に広がる空間によって政治体の存在が確かめられる場合に「曼荼羅国家」という概念が用いられる。これは一般にはインドや東南アジアの複数の政治権力が併存している場合に用いられるのだが、政治体が、明確な境界線ではなく、中心点で定義される点では、中華帝国も同じような性格を持っていたと言える。
中華帝国もまた、広大な領地を持っていることは確かだとして、ヨーロッパ近代国家のような明確な国境線を持って国家領土が定められていたわけではなかった。圧倒的な力を持つ政治権力があり、その威光が届く限り国家存在が確かめられる。大陸系地政学が生存圏/勢力圏/広域圏と観念するものが、アジアでは歴史的な国家存在の本質である。その典型例が、中華思想に裏付けられる中華帝国の伝統である。
この中華帝国の範囲は、明確な国境線によって制限されず、周辺国との力の格差によって裏付けられた威光の広がりによって確かめられるため、陸上のみならず、海上においても、広がっていく。
東シナ海や南シナ海に存在するとされるいわゆる「九段線」は、現代の国際法が認める中国の国境線とは異なるが、歴史的に中華帝国の威光が海上においても広がっていたとされる範囲を示す。

現代国際法秩序の原則を重視し、英米系地政学を標榜する「シー・パワー」連合が決して認めることはできないが、大陸系地政学の理論にしたがえば、海洋に広がっている歴史的な中華帝国の生存圏/勢力圏/広域圏がありうるのである。
このような中華思想の伝統を受け継ぐ広大な「圏域」を持つ「両生類」の中国は、ユーラシア大陸の深奥の不毛な土地から不凍港や肥沃な土地を求めて本能的に領地の拡大を求めるロシアとは、全く異なる発想方法を持つ。その点を見誤ると、中国の超大国としての存在を地政学的に把握する試みは、全て的外れに終わるだろう。
なぜアメリカも台湾に注目するのか
中国の超大国化に伴って、台湾海峡をめぐる緊張感は高まり続けている。中国の台湾侵攻の脅威は、中国共産党の支配地域の範囲の問題であり、中国の実効支配領土の範囲の問題であると考えられている。そしてそれは、もちろん正しい。
だが地政学の視点から見れば、台湾問題は、より大きな問題を内包している。つまり、大陸系地政学理論にしたがって中国が海洋にまで広がる勢力圏を確立するのか、英米系地政学理論にしたがってシー・パワー連合が中国のリムランドの覇権を阻止するのか、という問いと直結している。中国のみならず、アメリカおよび日本が、台湾問題の帰趨を、死活的な国益のかかる問題だと認識している理由である。21世紀の米中対立が象徴する大陸系地政学と英米系地政学の世界観の相克は、台湾問題をめぐって最も劇的に展開していくことになるだろう。

中華帝国としての中国の存在を地政学的に見てみると、決定的に重要な分析上の問いに辿り着く。中国の地政学上の位置づけを把握するために重要なのは、英米系地政学にそって「両生類」とみなしていくか、大陸系地政学にそって広大な生存圏/勢力圏/広域圏を持つアジア・西太平洋地域の覇権国とみなしていくか、という問いを検討することである。この問いは、大きな分析の視点の分かれ道を示している。
恐らくは、急速な国力の拡充を果たした中国は、まだ地政学上の問いに完全に明晰に答えることができる存在になっていない。中国の指導者たちは、そもそも中華帝国の伝統にそって国力を充実させる中国は、必ずしも欧米主導の地政学の視点による分析にはなじまない存在であると考えているかもしれない。
中国人のみならず、周辺諸国の人々、あるいは中国の影響を受けている世界中の人々が、これから長期にわたって考え続けていかなければならない問いである。しかしそれだけに、二つの異なる地政学の視点で、中国がどう捉えられるかが、21世紀の国際政治における大問題である。
【中国】歪んだ「愛国教育」が習近平政権を崩壊に導く“国民に見透かされた末路”
アサ芸biz の意見

中国の国際関係は過ってないほど悪化している。見逃せないのが、習近平政府が小学生から大学生に至る全学生に向け今年1月、「愛国主義教育法」を施行したことだ。これは、欧米、日本を含めた旧西側世界の分断策に対して愛国心を鼓舞させ、中国共産党の存在感を揺るぎのないものにするためのものである。
しかし後述するが、「愛国教育」による民族主義の強引な高揚は、中国社会に想定外の事態をもたらす危険を孕んでいる。
まず知っておきたいことは、「愛国教育」は最近になって始まったことではないということ。もともとは毛沢東が1949年に中華人民共和国を建国すると、「人民を苦難の中から解放し、まともな暮しをできるようにしたのは共産党である」として、共産党を「愛し」「尊敬する」よう求めて始まったものだ。要するに、愛国教育の本音は「愛党」教育である。
本当に愛国教育が狙いなのであれば、4000年の歴史が誇る漢字や火薬、漢方などの「文化」が教育の基本になるはずだ。しかし、共産党が建国されると政治闘争が繰り返され、文化大革命に象徴されるように古い文化を根こそぎ消し去ろうとした時代が続いた。
そうした中、毛沢東時代の国民は、学校や職場で「共産党がなければ『新中国』が存在しない」といった訓話を毎日聞かされ、愛国歌謡を歌わせられた。当時は、徹底した鎖国主義の時代だったから、愛国キャンペーンで人民は完全に洗脳され、「党」は権威を保った。
毛沢東に次いで、愛国教育に力を入れたのが、鄧小平氏の押しで国家主席となった江沢民氏である。
政権基盤が弱かった江沢民氏は1991年にソ連が崩壊すると、共産党の存在が「危うい」と恐れ、「愛国主義教育実施要項」を打ち出して日本叩きに異常な熱を注いだ。抗日戦争関連の映画やドラマが連日放映され、江沢民氏引退後の2005年には中国全土が反日暴動で揺れ、熱狂の反日時代となった。
だが、共産党が厳しい監視体制を確立したうえで、さらに愛国教育を進めようとしたものの、今や大多数の中国人はインターネットや海外旅行で外の情報を手に入れており、共産党になびいたフリをする知恵を持っている。
経済低迷で閉塞感が広がる中で、愛国教育すればするほど中国の実情を知る人々の不満が高まり、求心力が問われる共産党は対処できなくなるだろう。(団勇人・ジャーナリスト)
中国でスパイ容疑の元北海道教育大教授 懲役6年の実刑判決
朝日新聞社 によるストーリー

袁克勤・北海道教育大元教授がスパイ行為に関わった疑いがあるとして中国当局に身柄を拘束された事件で、袁氏が今年1月に中国・吉林省の裁判所で反スパイ法違反の罪で懲役6年の実刑判決を受けていたことがわかった。袁氏の支援者が明らかにした。
袁氏は同大に在籍していた2019年に一時帰国した際に拘束された。その後、中国外務省が、検察当局が袁氏を起訴したと明らかにしていた。
袁氏は中国籍で、中国の大学を卒業後に日本に留学。一橋大大学院の博士課程を修了した。道教大では東アジアの国際政治を研究しながら教壇に立ち、21年3月に定年退職した。
研究者らでつくる支援団体は「冤罪(えんざい)だ」として袁氏の早期釈放を求めていた。団体では、詳しい判決内容などがわかり次第、会見を開くとしている。
中国外務省の汪文斌副報道局長は14日の定例会見で袁氏の状況を問われ、「具体的な状況は主管部署に尋ねてほしい」と答え、「中国は法治国家であり、法律に基づいて事件を審理している」と付け加えた。
参考文献・参考資料
なぜ共産党なのか?習近平氏の出した答えが「強い中国」 垂秀夫前駐中国大使が解説する「四つの視座」とは【中国の今を語る(1)】 (msn.com)
中国はどのように「世界の覇権」を握るのか (msn.com)
【中国】歪んだ「愛国教育」が習近平政権を崩壊に導く“国民に見透かされた末路” (msn.com)
中国でスパイ容疑の元北海道教育大教授 懲役6年の実刑判決 (msn.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

