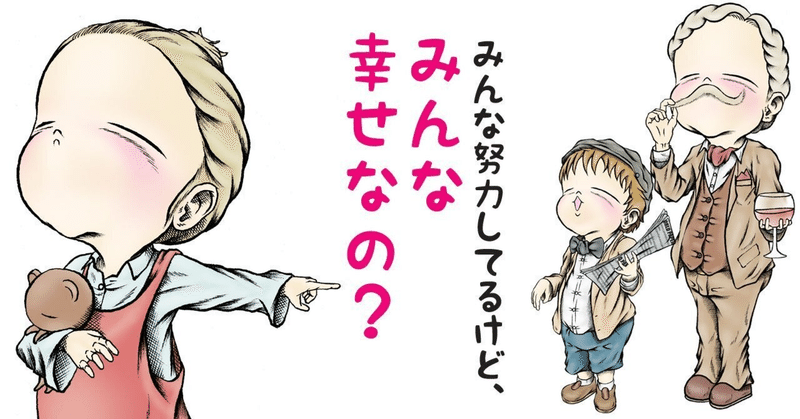
政治(金融・経済)講座ⅴ1011「購買力平価GDPでは見えない世界の動きと中国の虚像に怯える人々へ」
前回、ドルの基軸通貨(ドル覇権)と米国の凋落の解説をした。中国が主導して米国から覇権を奪い取ろうとする試みが何度も行われているが、中国の経済覇権を果たせそうもない。「一帯一路」とアジアインフラ投資銀行(AIIB)の金融構想は発展途上国に債務の罠という「新植民地政策」という危機感を与えた。今度はBRICSの新開発銀行(NDB)構想のようである。
読者に報道記事の注意点を申し上げる。中国共産党の報道出先機関の記事については、ニュースソースを十分ご注意いただきたい。これから掲載するレコードチャイナの報道はプロパガンダが十分含まれている。「元」を基軸通貨化して「元」での為替決済覇権を握ろうとする意図とドル覇権の破壊の意図が見え隠れする。「元」の自由化の意図がない中国共産党は基軸通貨になりえない。「元」の通貨発行権による世界覇権構想が見え隠れする。それは、米国が歩んできた覇権を構築した軌跡に他ならない。中国の経済は不動産バブル崩壊による債務を隠蔽しながらの投資勧誘の姿を見るにつけて哀れさを禁じざるを得ない。AIIBの姿が中国は口ほどでないことが分かるのである。中国のプロパガンダにより、世界の工場と持てはやされた姿は今は虚像であることが分かる。中国のGDPは実態を反映せずに作られた数字であると言われて久しい。それは旧ソ連の虚像を見ていた頃とオーバーラップされる。ソ連の崩壊の原因は主因は軍事クーデタとされているが本質は米国との軍拡競争による軍事費増加による経済破綻をきたした状態が隠蔽されて、ペレストロイカ(政治改革)とグラスノスチ(情報開示)により崩壊することになった。今まさに、中国はその轍を踏まないように、政治改革に対しては民主化を求める人民を弾圧で対処し、人民に対する情報は遮断して「隠蔽」することに力を注いでいる。米国は「中国人民と中国共産党の2分割統治法」で対処しようとしている。悪いのは「中国共産党」という位置づけである。
米国の本質を見誤った中国共産党の誤算である。以前のブログでも開設したが、米国は「商業国家」という側面と「軍産複合体」の二つの顔を持つ。日本と米国は中国が裕福になると民主化されるだろうという期待を見事に裏切り、自国はまだ発展途上国と嘯き、日本からのODAは人民の生活向上に使わないですべて軍事増強に軍事費としてまるまる見事に使い、東シナ海や尖閣諸島に脅威を与えているのである。ここに至って、日本や米国の安全保障上の脅威に中国は明らかになったのである。ここで米国の「軍産複合体」の逆鱗に触れることになって、商業上の「競争相手」から、「敵」と言う認識に変わったのである。米国のえげつないところは、「豚は太らせて食う」的なところがある。中国には孫子の兵法などと幾多の兵法書があるが、西洋の戦い方はもっとえぐいのである。今は人権!人権!と騒いで、中国のジェノサイドを非難しているが、近代史ではナチスドイツのホロコーストであり、時代をさかのぼると西欧は全世界を植民地にして、他民族を奴隷にしたり、抵抗する民族は根絶やしにして来たのである。えぐさは中国と西欧米は50歩100歩なのである。1900年代の初期は日本が大国として台頭してきたが、それを快く思わない米国の人種差別主義者のルーズベルト大統領とトルーマン大統領は国際法を無視して広島と長崎に原爆で非戦闘員の子供・女性を瞬時に灰にして殺した。その燃えた黒い灰と化したものが雨として降った。これが、有名な黒い雨なのである。人道上も決して許されることではない。平然と国際法と言う法を無視した米国が、東京裁判で裁かれるべき国であったと思う。翻って現在のロシアは核の恫喝でウクライナを脅し、世界も恫喝している。彼らロシアは米国が日本に広島・長崎で核兵器を使用したという前歴を公然と抗弁として主張している。やはり、米国は日本に正式に謝罪すべきであろう。オバマ大統領だけが広島に来たことは評価に値する。
今回は経済面から見た世界経済と中国の動きと経済状況を占う報道記事を紹介する。
皇紀2683年4月16日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
米中ロの購買力平価GDP、米国は23兆ドル、ロシアは4.8兆ドル、中国は?―中国メディア
Record China によるストーリー •
2023年4月12日、中国のポータルサイト・捜狐に、中国のGDPは購買力平価で計算した場合すでに米国を大きく上回っているとするセルフメディア至味財経の文章が掲載された。

文章は、世界各国のGDPを計算する方法として為替レート法と購買力平価があり、為替レート法がより一般的に使われているとする一方、為替レートが大きく変動した時には各国の経済発展レベルをリアルに反映することが難しくなると紹介。その例として、22年に前年から7000億ドル余り減って4兆2000億ドルとなった日本のGDPは急激な円安ドル高がマイナス成長の主要因であり、円ベースで計算した場合には前年比1%の増加になることに言及した。
そして、昨年は米国が利上げを続けて大量の米ドルが米国に回流したことで米ドルが非常に強くなり、他国の通貨が軒並み下落したと指摘。この状況では、米国のGDPが過去最高を記録し、他国のGDPが縮小するという為替レート法の数値はもはや経済の実態を完全に反映できないとしたほか、そもそも米国のGDPは中国が含めていない収入項目まで幅広く算入しており「水増し分」が大きいと論じた。
その上で、購買力平価によりGDPを算出すると、21年の米国は23兆ドルで為替レート法とほぼ同じになる一方、為替レート法で18兆ドルの中国は27兆ドルを超えて米国を上回ると紹介するとともに、購買力平価GDPでは中国が16年時点ですでに米国を抜いて世界一になり、差をどんどん広げていることを紹介。また、為替レート法で1兆7800億ドルのロシアも4兆8100億ドルで英国、フランスを抜いて世界6位になるとした。
文章は、購買力平価GDPのランキングは中国が1位、米国が2位となり、3位はインド、4位以下は日本、ドイツ、ロシア、インドネシア、フランス、ブラジルとなるとし、「どっちの算定法が理にかなっているだろうか」と疑問を投げかけた。(翻訳・編集/川尻)
【ルポ】中国「空きコンテナ山積み」の現場を歩く 仕事激減にあえぐトレーラー運転手の悲哀
財新 Biz&Tech の意見 • 12 時間前

中国のコンテナ港は、「世界の工場」のいわば出荷口にあたる。そこに今、かつて目にしたことがない光景が出現している。海外から戻ってきた空きコンテナが溢れんばかりに積み上がり、さらに増え続けているのだ。
ウクライナ危機をきっかけに加速した世界的なインフレ高進が、欧米諸国で消費後退を招き、中国の輸出に打撃を与えたことが背景にある。コンテナ港では実際にどんな変化が起こり、そこで働く人々は何を感じているのか。現場を歩いた『財新』の写真ルポをお届けする。
浙江省の寧波舟山港は、コンテナの年間取扱量が3300万TEU(20フィートコンテナ換算)を超える中国最大級のコンテナ港だ。なかでも同港の「北侖港区」は、広大な埠頭に多数のガントリー・クレーンが立ち並ぶコンテナ輸送ビジネスの中心地である。
【写真】埠頭近くの巨大な駐車場には、開店休業のコンテナ・トレーラーが約3000台ならぶ
2023年3月上旬、北侖港区を訪れた財新記者の目に飛び込んできたのは、色とりどりのコンテナが港区内に溢れ、積み上げられた高さが6~7段に上っている光景だった。

これらはすべて貨物が入っていない「空き箱」だ。なぜなら、貨物が入ったコンテナは(重量上の制限で)5段までしか積めないからだ。
トレーラーの半数が休眠状態
北侖港区には「横舗車場」と「北侖集運基地」という、コンテナ・トレーラー専用の巨大な駐車場がある。そこには、運ぶべきコンテナがなく開店休業のトレーラーが約3000台もひしめいていた。

「49台のトレーラーは、49人のドライバーの生活を支えているんだ。それなのに、今日の受注は22箱しかなかった」。コンテナ物流会社の天旭国際物流を経営する豆中旭さんは、そう言って溜息をついた。彼の会社は、北侖港区に軒を連ねる約4000社の中小物流会社の1つだ。
豆さんは駐車場に置いた擦り切れたビジネス・チェアーに身を沈め、日なたぼっこをしていた。彼の会社のトレーラーは、ほぼ半数が休眠状態だ。ドライバーの誰に仕事を与え、誰に与えないか。豆さんのような経営者にとって、日々の頭の痛い問題になっている。


46歳のドライバーの鄭華さんは、トレーラーを横舗車場に乗り入れてから2週間余りになる。彼は1日のほとんどの時間を、この駐車場の敷地内で過ごしている。
新型コロナウイルスの流行期、中国の国際貿易港には厳しい防疫体制が敷かれ、港湾地区の出入口にはトレーラーの長い行列ができた。そんななかでも、ドライバーたちは最低でも月に1万元(約19万円)の収入を得ることができたと、鄭さんは話す。
だが、彼はこの2週間で2往復しかコンテナを運べず、1往復当たりの収入はわずか550元(約1万600円)だった。この稼ぎでは家族の暮らしを支えるどころか、自分1人の日々の生活もままならない。
「コロナが去り、仕事も消えた」

コンテナ・トレーラーは、たとえ走らせなくても費用がかかる。別のドライバーの張文海さんが、その概算を教えてくれた。
「1日当たりの(トレーラー購入の)ローン返済が400~500元(約7700~9600円)、減価償却費が100元(約1900円)、保険代が100元、駐車場代が40元(約770円)。たとえドライバーが飲まず食わずでも、(仕事がなければ)1日700〜800元(約1万3500~1万5400円)の損失なんだ」
1990年代からコンテナを牽引してきた古株ドライバーの周金生さんは、「コロナ禍が去った後に仕事がなくなるとは思いもしなかった」と嘆く。他の多数のドライバー仲間と同じく、彼は出費を切り詰めるため、港区内の宿泊所を出て自分のトレーラーの運転台で寝泊まりしている。


北侖港区の管理当局によれば、同港区には1日当たり約5万台のコンテナ・トレーラーが出入りする。そのドライバーたちの消費は、周囲の飲食店、修理工場、クリーニング店、マッサージ店などの商売を支えてきた。
深夜12時過ぎ、北侖集運基地の出入口の近くで普建波さんが営む屋台では、今夜も餃子の具が余っていた。「以前なら、2つのボウルに山盛りの具が売り切れていた。でも今は、1つのボウルの半分も売れない」と、普さんは肩を落とす。

仕事を終えたドライバーたちは、トレーラーを駐車場に停めた後、いつもここに集まって酒を酌み交わし、料理をたらふく食べていた。だが、今は誰もが倹約しており、「1日1食しか食べない仲間もいる」と、前出のドライバーの周さんは話す。
最後の従業員に帰省の切符
北侖港区の一角でトレーラーの修理工場を営む張さんは、作業場の賃料の支払いが心配でならない。彼の修理工場では、以前は1カ月に700〜800本のエンジンオイルが売れていた。それが今では200本にも届かない。
「トレーラーの走行距離が少なくなり、メンテナンスに来るドライバーが減ってしまった」と、張さんはこぼす。以前は彼のほかにも4人の従業員が働いていたが、今も残っているのは張さんの兄弟1人だけだ。
張さんは最近、その兄弟を故郷の東北地方に帰省させる飛行機のチケットを予約した。理由を尋ねたところ、「いまなら田植えの時期に間に合うからね」と、張さんは苦笑いを浮かべた。

(写真と本文:財新記者 陳亮)
中国の為替介入、段階的な廃止が可能=人民銀行総裁
Reuters によるストーリー • 2 時間前
[ワシントン 15日 ロイター] - 中国人民銀行(中央銀行)の易綱総裁は15日、同国の為替介入について、規模と頻度を徐々に減らすことで段階的な廃止が可能とし、人民元の国際化に向けた決意を示した。

実質金利が潜在成長率をわずかに下回るよう金融政策を運営するとも述べた。
総裁はワシントンで開催された国際通貨基金(IMF)・世界銀行の春季会合のセミナーで「これまで為替レートの安定維持を目指してきた。永遠に続ければ、いつか市場が中銀を打ち負かすことになるだろう」と発言。「金融政策が適切であれば、為替レートが市場で決まり、介入(を最小限にする)体制を目指すだろう」と語った。
中国には市場が混乱した局面で介入する権利があるが、当局は為替レートの決定で市場原理をさらに働かせる必要があると主張。「金利がカギであり、為替レートは市場で決まる。これが私の伝えたい基本的なメッセージだ」と述べた。
総裁は、中国はこれまで為替レートと金融政策を通じてインフレ率を2%前後で「非常に安定的」に維持してきたと指摘。経常収支は黒字ではなく「均衡」を目指していると述べた。
新興5カ国の連携称賛訪中のブラジル大統領
2023/4/13 18:44

中国を訪問したブラジルのルラ大統領は上海で13日、新興5カ国(BRICS)が設立した「新開発銀行」の本部を訪れた。ロイター通信によると「これまでの国際金融機関への服従から新興国を解き放つものだ」と称賛した。
米国に本部がある国際通貨基金(IMF)や世界銀行を念頭にした発言。ルラ氏は「(新開発銀行は)新興国の連携が世界に社会的、経済的な変化をもたらし得ることを示している」と述べた。
BRICSを構成するブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカは2015年、米欧主導の国際金融体制に対抗し、発展途上国を支援する新開発銀行を設立した。今年3月からはブラジルのルセフ元大統領が総裁を務めている。
ルラ氏は12~15日の日程で訪中しており、14日に北京で習近平国家主席と会談する。(共同)
ブラジル大統領、BRICSに自国通貨による決済を呼びかけ
2023年4月14日 17:24 発信地:中国

【4月14日 CGTN Japanese】上海を訪問中のブラジルのルラ大統領は13日、新開発銀行(NDB)本部を訪れた際に、BRICS諸国に向けて、自国通貨で決済するよう呼び掛けました。
ルラ大統領は新開発銀行でのあいさつで、「私はいつも、なぜすべての国が米ドルで決済せねばならないのか、なぜ人民元やその他の通貨が国際決済通貨になってはならないのかと考えている」、「(BRICS諸国は)なぜ、自国の通貨で決済できないのか。このことについて、われわれは忍耐してきた。そして中国人は、忍耐とは何かを知っている」「皆がドルを使い慣れているのは分かっている。しかし、われわれは21世紀に、異なることをしてもよい」などと述べました。
新開発銀行はBRICS5か国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)が2015年に共同設立した国際開発銀行であり、世界的な多元的国際開発金融機関となることを目指して、国連の全加盟国に会員資格を開放しています。そして2021年には、バングラデシュ、ウルグアイ、アラブ首長国連邦、エジプトを新たなメンバー国として迎えました。
ブラジルのルラ大統領は大規模な代表団を率いて12日夜に上海入りして、中国訪問を始めました。今回のルラ氏の訪中は5回目で、公式訪問としては3回目です。
中国商務部によると、2022年には中国とブラジルの二国間貿易額が1714億9000万ドルに達しました。中国は14年連続でブラジルにとって最大の貿易相手国でありつづけ、ブラジルにとっての重要な直接投資の供給国です。一方でブラジルは、中国が輸入する大豆や鶏肉などの最大の供給国です。トウモロコシなどの重要な農産物の対中輸出も実現し、急増しているとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News
BRICS銀行 次期総裁にブラジル元大統領で合意

ロシア、ブラジル、インド、中国、南アフリカの5カ国からなるBRICSの国際開発金融銀行「新開発銀行(BRICS銀行)」の次期総裁に、ブラジルのジルマ・ルセフ元大統領が内定したことが分かった。ブラジルメディア「Globo」が関係者の話として伝えている。
「Globo」によると、BRICS5カ国はルセフ元大統領を総裁にする案で合意した。今月中にも正式に任命される見込み。
現在の総裁はブラジルのボルソナロ前大統領によって任命された、外交官のマルコス・トロイオ氏が務めており、任期は2020~2025年までとなっている。だが、ボルソナロ大統領の政敵であり今年1月に大統領に返り咲いたルラ大統領は、総裁を交代させる考えを示していた。

「西側のメカニズムは頼りにできず」=ラブロフ露外相、BRICS共通通貨について
1月25日, 06:56
新開発銀行はBRICSによって2014年に設立された。主に加盟国や発展途上国のインフラ・開発発展プロジェクトへの投資を担っている。
ルセフ氏は第一次ルラ政権(2003~2011年)でエネルギー相や官房長官を務め、ルラ大統領の右腕ともいわれた存在。2011年1月にはルラ大統領の跡を継ぐ形でブラジル史上初の女性大統領になった。だが、サッカーワールドカップ杯への巨額投資や自身周辺の汚職疑惑などで国民の不満が高まり、2016年の弾劾裁判では議会の3分の2以上の賛成で大統領職を罷免されていた。
ブラジル大統領 中国との関係やBRICS協力を有望視
2023年4月15日(土)17時30分 Record China

写真を拡大
中国を訪問しているブラジルのルーラ大統領は13日、ブラジルと中国の関係発展やBRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国)の協力について、「友情はワインの如く、時間が経てばたつほどより味深くなる」というブラジルのことわざで評価しました。
ルーラ大統領はこの日、上海浦東にある新開発銀行(NDB)の本部を訪れ、ブラジルの元大統領のジルマ・ルセフ氏のNDB総裁就任式に出席しました。
ルーラ大統領はBRICS協力やNDBの発展を有望視し、「新興国家によって創設された初めての多国間開発銀行として、NDBは貧困の削減、不平等レベルの低減、持続可能な世界の創出に取り組み、世界の変革を促している。これは先進国の主導している“伝統的な銀行”とは全く違うものだ」と述べました。
ルーラ大統領はまた「長い間、途上国は自分の投融資工具を作る夢を見てきた。NDBはこの夢を実現してくれたと言える。途上国の真の需要を理解しているため、途上国の現状を改善する面で大きなポテンシャルに恵まれている」と期待を寄せました。(提供/CRI)
購買力平価(PPP)とは?基礎から活用方法までわかりやすく解説!
・購買力平価って何?
・どうやって投資に活用できるの?
このようなお悩みにお答えします。
この記事の結論
購買力平価とは、為替レートの決定メカニズムの仮説の一つ
購買力平価を応用したものとして、ビッグマック指数がある
購買力平価を学び、インフレ対策のために投資も勉強しよう!
テレビのニュース等でインフレの話題になり、「購買力平価」という言葉を耳にすることがあるでしょう。
購買力平価とは為替レートの決定メカニズムの仮説の一つで、長期的な相場シナリオを考える際に役立つものです。
購買力平価とは
購買力平価は1921年にスウェーデンの経済学者G・カッセルによって提唱された理論で、「 一物一価の法則」 を前提としています。
一物一価の法則
「ある時点における同一の商品・サービスは、ひとつの価格になる」 という法則。
一物一価の法則が成り立つ時、「同一のものはどこで買っても同じ」という状況へと行き着きます。
関税や輸送費・手数料が関わってくる場合だったり、非貿易財にはこの法則が適用されないので注意だワン!
この理論では、自国通貨と他国通貨の購買力の比率から中長期的な為替レートを求めることができます。
別の言い方をすると、「ある国の通貨建ての資金の購買力が他の国でも等しい水準となるように為替レートが決定される」という考え方です。
購買力平価は計算方法の違いで以下の2つに分けることができます。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
絶対的購買力平価
絶対的購買力平価は、「為替レートは長期的には2国間の通貨の購買力によって決定される」という理論です。
この理論では輸出入が自由で関税も輸送コストもない世界を想定しており、同じ財バスケット(一定の財・サービスの数量の集合)の価値が同じになります。
この同じバスケットの値段が2カ国で同じになるような為替レートを、絶対的購買力平価レートと言います。
相対的購買力平価
相対的購買力平価は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決まる」という理論です。
実際の経済では様々な貿易の上の障害があり、それを考慮した理論が相対的購買力平価です。
相対的購買力平価では以下のステップを踏んで考えていきます。
為替レートが2カ国の国際競争力にほぼ見合っていたと考えられる基準時点を選ぶ
この基準時点から、2カ国の一般物価水準がどれくらい変化しているかを測定する
基準時点の名目為替レートが2カ国のインフレ格差分だけ変化した場合の名目為替レートを計算し、これを現在の購買力平価レートとみなす
【相対的購買力平価】=基準となる為替レート×(自国の物価上昇率÷相手国の物価上昇率)
物価の上昇率が高い国の通貨が減価する(安くなる)んだね!
日米間の相対的購買力平価を求める基準としては、1973年(昭和48年)4月~6月時点の平均値の1ドル=265円が基準として選ばれているワン!
購買力平価の問題点
購買力平価は長期的な相場シナリオを考える際に役立つ一方で、問題点もあります。
購買力平価にはどんな問題点があるの?
1つ目の問題点は、各国独自の事情までは考慮されていないことです。
例えば、食品にかかる間接税(消費税)は考慮されていません。
そのため、購買力平価は必ずしも厳密な経済指標として機能しているわけではありません。
2つ目の問題点は、この理論は貿易障壁のない完全な自由競争市場が成立していることを条件としていることです。
同じ国内や地域で同じ商品を売るときは、需要と供給が一致する価格へ市場の調整が働き自然と均衡していきます。
しかし、国家間の取引では関税や輸送費などが関わります。
そのため、国家間取引では購買力平価が現実の市場と外れた値となるケースがあります。
購買力平価の考え方を使う時は、この2つの問題点を考慮すべきだね!
購買力平価の例
購買力平価を活用したものとして代表的な2つの例を説明します。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
GDP購買力平価
GDP購買力平価は、GDPに対応すると考えられる商品群を算定の対象として計測したものです。
ECの加盟分担金の算定を目的に元々始められたものですが、 現在はOECD(経済協力開発機構)によって独自に作成されています。
ビッグマック指数
イギリスの経済専門誌『エコノミスト』が考案したものとして、ビッグマック指数があります。
ビッグマック指数は、マクドナルドの販売するビッグマックの価格をもとに購買力平価を算出するものです。
なんでビッグマックが基準になっているの?
理由は2つあります。
ほぼ全世界で同一品質のものが販売されている
原材料費や店舗の光熱費・店員の労働賃金などさまざまな要因を元に単価が決定される
上記の理由で、総合的な購買力の比較に使いやすいのでビックマックが基準になっています。
また日本のビッグマック指数は、対象国54か国中41位と下位に沈んでいます。
これは同時に、世界的に日本の労働力が安くなっていることをさします。
順調にADBの下請機関と化しつつあるAIIBの現状
コロナ禍の影響もあったのでしょうか、ようやく、AIIBの融資残高が増え始めました。2022年12月末時点における本業融資額は222億ドルで、また、昨日時点における承認済みプロジェクトは206件、これらの融資がすべて実行に移された場合の融資総額は約400億ドル、といったところでしょう。ただ、ADBの1372億ドルという金額と比べればまだまだ融資額は小さく、また、現実のAIIBの融資案件を眺めてみると、事実上、ADBの下請けのような存在でもあります。
中国が主導するAIIBの現状
当ウェブサイトでずいぶんと以前から追いかけ続けているテーマのひとつが、中国が主導する、「アジアインフラ投資銀行」と呼ばれる国際開発銀行の財務諸表の分析です。
この銀行に出資を約束している国は、現時点で世界91ヵ国に達しており、出資約束額は1000億ドル近くに達しています。
また、コロナ直前までは、毎年のプロジェクト承認件数は多くてもせいぜい30件弱で、承認金額もせいぜい年間40億ドルくらいでしたが、2020年にコロナ禍が生じるや、コロナ関連のプロジェクトが激増。これに伴い、本業の融資の額も少しずつ伸びている、という状況です。
日米を除くすべてのG7が参加
まずは、出資国の状況です(図表1)。
図表1 AIIB出資国(2023年4月10日時点)
出資国(出資年月)出資約束額議決権
1位:中国(15/12)297.80億ドル26.59%
2位:インド(16/1)83.67億ドル7.60%
3位:ロシア(15/12)65.36億ドル5.98%
4位:ドイツ(15/12)44.84億ドル4.16%
5位:韓国(15/12)37.39億ドル3.50%
6位:豪州(15/12)36.91億ドル3.46%
7位:フランス(16/6)33.76億ドル3.18%
8位:インドネシア(16/1)33.61億ドル3.16%
9位:英国(15/12)30.55億ドル2.89%
10位:トルコ(16/1)26.10億ドル2.50%
その他(81ヵ国)279.66億ドル36.99%
合計(91ヵ国)969.65億ドル100.00%
(【出所】AIIBウェブサイト “Members and Prospective Members of the Bank” を参考に著者作成)
ちなみにAIIBの拒否権は4分の1だそうで、中国は議決権の26.59%を保有しているため、単独で拒否権を持っています。これが「中国が事実上、AIIBを支配している」などといわれるゆえんでしょう。
また、出資約束額は総額969.65億ドルで、1位の中国を筆頭に、G7諸国のうち英国、ドイツ、フランス、カナダ、イタリアが参加しているほか、日本の隣国である韓国、日米とともに「クアッド」を構成しているインド、豪州なども加わっています。
また、「G20」諸国だけを抜き出しても、日本、米国、メキシコ、南アフリカ以外の15ヵ国がこぞってAIIBに参集している状況です(ちなみに南アフリカはAIIBが2015年に発足した当初から参加を表明しているものの、いまだに国内の加盟手続が終了していないそうです)。
AIIBに参加しているG20諸国
いずれにせよ、G7のなかでAIIBに参加していない国は日本と米国のみです。
AIIBの本業融資は200億ドルを突破し、順調に伸びる
次に、AIIBの貸借対照表から判明する、主要な資産の内訳を、図表2にまとめています。
図表2 AIIBの個別貸借対照表の推移

「本業融資と思しき項目」には、C8の金銭債権( ”Loan investments, at amortized cost” )とC9の債券投資( “Bond investments, at amortized cost” 、おそらくは私募債)の金額を合算しています。
2020年6月頃まで本業融資が「鳴かず飛ばず」だったのが、コロナ関連融資に対する需要が伸びた影響もあってか、現在では本業融資の金額は200億ドルを超え、222億ドルに達しました(うち債権176億ドル、債券46億ドル)。
AIIBのプロジェクト承認状況
続いて、プロジェクトの承認状況です。
AIIBのプロジェクトの承認状況については、図表3のとおり、件数、金額ともに2020年と21年に急増していることが確認できます。22年には前年比で件数、金額ともに落ち込みましたが、コロナ関連融資が減ったためでしょう。
図表3 AIIBのプロジェクト承認件数・金額
(【出所】AIIBウェブサイト “Our Projects” を2023年4月10日時点で閲覧し、全集計したもの)
なお、2023年の承認件数・金額が激減しているように見えるのは、2023年については4月10日までの承認分(つまり約3ヵ月分)しか集計されていないだけの話であり、べつに異常値ではありません。2023年の承認件数(10件)・金額(約16億ドル)を4倍したら、どちらもほぼ2022年なみです。
AIIBの目論見と実情
通貨別に見ると206件中3件がユーロ建て、残りはすべてドル建て
ちなみにAIIBの承認済みプロジェクトは現時点までに206件あり、これらすべてが実行されれば400億ドル弱に達しますが、その一覧を眺めているとユーロ建てが3件で6.5億ユーロ分あるのを除き、残り203件の案件はすべて米ドル建てです(図表4)。
図表4 AIIBの承認済みプロジェクトの実行通貨
通貨件数金額(百万)米ドル20338,432ユーロ3650人民元00日本円00英ポンド00合計206―
(【出所】AIIBウェブサイト “Our Projects” を2023年4月10日時点で閲覧し、全集計したもの。なお、金額はドルとユーロが混じっているため合計していない)
AIIBがアジアのインフラ金融を牛耳っている!?
以上が、AIIBの最新の概況です。
これを、どう見るべきでしょうか。
本業融資が伸び始めているというのは、ある意味では予想されていた動きでもあります。なぜなら、2020年半ば以降、プロジェクトそのものの承認が急速に進んだからです。通常、プロジェクトが承認されてから融資が実行されるまで、タイムラグがあります。
いわば、AIIBはコロナによって資金需要が急増したことに助けられた格好であり、これによりAIIB発足より7年近くもかけて、やっと本業融資が200億ドルの大台に乗りました。承認済みのプロジェクト総額は400億ドルですので、これらの融資が順次実行に移されれば、もう少し本業融資は伸びるでしょう。
もっとも、世界91ヵ国から1000億ドル近い出資金を集めてはいますが、その規模と比べると、実行済みの融資額はまだまだ少ないと言わざるを得ません。
ちなみにこの1000億ドルは、現時点では「出資約束額」であり、全額払い込み済みではありません。払い込まれている金額は約194億ドルで、出資約束額の20%程度です。また、これら以外にもAIIBは市場で245億ドルほどを借り入れているため、バランスシートはトータルで474億ドルほどに膨らんでいます。
AIIBという組織の資本効率の悪さ
ただ、この474億ドルのうち、本業融資に回っている金額は222億ドルです。
残額はいったい何に使われているのか――。
じつは、AIIBのバランスシートを見ると、現金・現金同等物が31億ドル、定期預金が67億ドル、売買目的投資が127億ドル計上されています(合計すればだいたい224億ドルほどです)。いわば、余ったお金を証券会社や銀行のおススメする商品に運用している、という状況だと思えば良いでしょう。
何のことはない、AIIBは世界各国から出資を集め、最高格付を取得しておカネを調達したまでは良かったものの、コロナ禍直前の2020年なかばまで使う当てがなく、仕方なしに余資運用に廻されていた、という実態が見えて来ます。大変資本効率の悪い組織です。
コロナのおかげで本業融資が伸びたにせよ、設立から7年もかけて、いまだに出資約束額に対してまだ5分の1ほどしか融資が出ていない組織です。しかも、融資案件の多くはアジア開発銀行(ADB)や世界銀行などとの協調融資が多く、少なくとも「アジアのインフラ金融を牛耳っている」という形跡はありません。
AIIBの野心とその実情
このあたり、2015年当時は、AIIBに日本や米国が参加を見送ったことなどを巡り、さまざまな主張がありました。いちばんおもしろいものとしては、「これからはAIIBの時代だ」、「日本はアジアのインフラ金融から除け者にされる」、といったものですが、それだけではありません。
「AIIBは中国による一帯一路金融を支える金融機関となる」、「中国はAIIBを活用し、人民元建ての国際融資を一気に増やし、米ドルの覇権を奪いに行くつもりだ」、といったものもありました。
また、「AIIBは脅威が、日本はうまく付き合う必要がある」といった主張もあれば、「AIIBには油断すべきではないが、日本は距離を置くべきだ」と言った主張もありましたが、これらの主張の共通点は、「AIIB脅威論」、といったところでしょう。
さて、蓋を開けてみて、このAIIBという組織のせいで、日本がアジアのインフラ金融から「除け者」にされているという事実はあるのでしょうか?AIIBが人民元の国際化を推進する組織となっているのでしょうか?
敢えて批判を覚悟で結論を述べておくならば、AIIBは現状、アジアのインフラ金融の世界において、毒にも薬にもならない存在として、ひっそりと自分の立ち位置を確保している、というのが現状でしょう。
正直、融資額こそ200億ドルを超え、将来的には500億ドルも視野に入っていますが、この規模だと、アジアのインフラ金融の世界において存在感はありません。『マネー面から見た「日本が関係を深める国・薄める国」』でも指摘したとおり、日本の金融機関の対外与信は4.6兆ドルで、ケタが違います。
参考文献・参考資料
米中ロの購買力平価GDP、米国は23兆ドル、ロシアは4.8兆ドル、中国は?―中国メディア (msn.com)
【ルポ】中国「空きコンテナ山積み」の現場を歩く 仕事激減にあえぐトレーラー運転手の悲哀 (msn.com)
中国の為替介入、段階的な廃止が可能=人民銀行総裁 (msn.com)
ブラジル大統領、BRICSに自国通貨による決済を呼びかけ 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
BRICS銀行 次期総裁にブラジル元大統領で合意 - 2023年2月11日, Sputnik 日本 (sputniknews.jp)
購買力平価(PPP)とは?基礎から活用方法までわかりやすく解説! | いろはに投資 (bridge-salon.jp)
新興5カ国の連携称賛訪中のブラジル大統領 - 産経ニュース (sankei.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

