
やさしい物理講座ⅴ65「ハッブル氏の観測の赤方偏移は『光のエネルギー減衰理論』が妥当。その光の真空中の減衰作用は暗黒物資の素粒子『アクシオン』かも知れない」
前回のブログの
やさしい物理講座ⅴ64「『光のエネルギー減衰理論』」|tsukasa_tamura (note.com) 本件はこれに続く詳細の投稿である。今回は物理学者の投稿を紹介するが、吾輩はこの内容に異論があるので自論も併せて述べる。
皇紀2684年5月3日
さいたま市桜区
理論物理研究者 田村 司
結局、宇宙は有限?無限? 宇宙ファンも混乱する問題を物理学者がとことん解説
須藤靖 の意見

宇宙はどのように始まったのか──。そんな宇宙にまつわる疑問に対して、私たちは間違った解釈をしているかもしれない。物理学者の須藤靖氏は、「宇宙はビッグバンから誕生した」は誤解だと指摘する。どういうことなのか。朝日新書『宇宙する頭脳 物理学者は世界をどう眺めているのか?』から一部を抜粋、再編集して解説する。
* * *
■ビッグバンは爆発ではない
宇宙は点が爆発して始まった。
いわゆるビッグバンの説明としてこのような記述を見かけることが多い。そこには、「宇宙はビッグバンから誕生した」、「ビッグバンは爆発現象だ」、「宇宙はかつて点であった」という三つの主張が含まれている。しかしこれらは控えめに言っても誤解を与える表現、端的に言えば、間違いである。
まず、宇宙がいかにして誕生したのかは全くわかっていない。
次に、ビッグバンは、バン(bang)という英単語が用いられているにもかかわらず爆発ではない。
しかし、宇宙は「誕生直後に」極めて高温かつ高密度の状態を経験したことは確実だ。そして、「その状態」をさしてビッグバンと呼ぶのが普通である。
最後に、宇宙を過去に遡ると、その体積は0になる、すなわち「数学的な意味での」点であると考える根拠は間違っている(その結論が間違っているかどうかまでは未だ断言はできないとしても)。
今回は、最後の「宇宙はかつて点だった」という広く流布しているとおぼしきこの宇宙最大の誤解の周辺を掘り下げてみたい。

■結局、宇宙は有限か無限か
今から138億年前に発した光を含む平面はいわば「現在の我々が観測できる宇宙の限界」に対応する。この考察を全天に広げれば、この限界は我々を中心とする半径138億光年の球面となる。
しかしながらこれは宇宙に果てがあり、有限のサイズを持っていることは意味しない。それどころか宇宙には果てがなく無限の体積を持つと考えられている。
にもかかわらず、一般解説書には、宇宙の大きさは3000メガパーセクだとか、宇宙は光が138億年の間に到達できる半径を持つ、とか書かれていることが多い。
「宇宙は有限なのか、無限なのか、はっきりしろ」と怒りを覚える方がいらっしゃるのも当然である。
この混乱の元凶は、「我々が現在観測できる宇宙」と「観測できるかどうかに関係なくその外に広がっている宇宙」という二つの異なる概念を明確に区別せずに説明しているためだ。その違いはとても大切であるにもかかわらず、説明し始めるとそれだけで講演会が終わってしまうほど時間がかかる可能性がある。
そのため、「くどくなくわかりやすい」説明を心がける大多数の専門家は、暗黙のうちに「我々が現在観測できる宇宙」という意味で単に「宇宙」という単語を用いている。このような専門家の善意が、宇宙ファンの多くの方々を混乱させているようだ。
そこでとりあえず、ある講演会のあとで寄せられた質問「宇宙の大きさはどの位ですか」に対する、私のくどくてわかりにくいものの実直な回答を紹介しておこう。
現在の標準的宇宙論では、宇宙は無限に広がっており果てもないと解釈されています。その意味において、宇宙の大きさは無限大です。ただし、天文学者が単純に「宇宙」と呼ぶ場合、それは「我々が現在(原理的に)観測できる領域の宇宙」(地平線球)をさすことがほとんどです。
その意味での宇宙の大きさ、すなわち「我々を中心として、現在観測できる宇宙」の半径は、宇宙誕生以来138億年の間に光が進む距離となります。大まかには138億光年と考えて十分なのですが、宇宙が膨張している効果を考慮してより正確に計算すると約470億光年になります。
実はこれこそが「宇宙は点が爆発して始まった」という単純な言い回しを誤解してしまう原因でもある。「現在我々が観測できる領域内の宇宙の体積を138億年前の宇宙誕生の瞬間まで遡れば(ほとんど)点とみなせるほど小さくなる」と丁寧に言い換えるならば、科学的裏付けのある正しい結論である。
しかし、我々が現在観測できない宇宙(マルチバースと考えてもよい)までを含めるならば、決してそれは正しいとは言えない。その外にある宇宙が現在無限に広がっているとすれば、過去に遡ってもやはり無限に広がっているはずで、少なくとも我々が考えるような意味の点ではない。
冒頭のビッグバンに関する説明、「宇宙は点が爆発して始まった」は、より正確には次のように置き換えるべきである。
我々が現在観測できる半径138億光年内の宇宙は、138億年前にはサイズが極めて小さい体積の、高温かつ高密度の状態にあった。しかし、宇宙全体はその領域を超えてはるかに広がっており、無限の体積を持っていたと考えても、現在の観測事実とは矛盾しない。
ただし、数学的な意味での無限大の体積を持つ宇宙が、物理的に実在するかどうかは、直接観測で証明できるものではなく、むしろ哲学的な問題に帰着する。
おもわず誰かに話したくなる。サクッと読める宇宙の雑学まとめ
編集部 によるストーリー

約465億光年の広さと言われている宇宙は、私たちの知らないことで溢れています。時間に余裕のあるゴールデンウィークの真っ只中、ちょっとだけ宇宙について学んでみませんか?
誰かに話したくなっちゃうような、サクッと読めるおもしろい話をまとめてみました。
惑星の“輪っか”は何モノかに支えられているらしい

土星と天王星の間に位置する小惑星「カリクロ」。土星のようなリング(環)を持っていることは知られてたんですが、そのリングの存在を支える、謎の衛星がいるらしいことが裏付けられました。
カリクロの周りには2本のリングがあることが、2013年のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡での観測でわかっていました。そして最新の論文によれば、2本のリングをリングたらしめているのは、カリクロの「衛星」かもしれないんだそう。
このリングの幅は数kmほど。惑星のリングは時間とともに自然に拡散していくものですが、「このリングがこれほど細くあり続けるためには、そこに物質を閉じ込めて拡散を防ぐようなメカニズムがあるはず」と研究チームは仮定。
チームは、衛星がカリクロのリングを維持する様子をモデル化すべく、リングを構成する無数の粒子の動きをシミュレーション。その結果、衛星のサイズは半径約3.73マイル(6km)と推定されました。
この惑星のリングをキープしている衛星は「羊飼い衛星」と呼ばれ、たとえば土星のリングのひとつもそんな衛星に支えられているんだそうですよ。
詳しくはこちら↓
太陽の500兆倍? 宇宙一明るい天体を発見

今年の2月、太陽の500兆倍明るい天体を発見したとオーストラリア国立大学の研究チームが発表しました。
今回見つかった明るい天体(クエーサー)は「J0529-4351」と呼ばれ、地球から120億光年以上先の宇宙で発見されました。
クエーサーとは宇宙初期の天体で、超大質量ブラックホールをエネルギー源としているため宇宙のなかでも一際明るい光源であり、莫大なエネルギーも放出しています。
このまばゆい光の正体はJ0529-4351の中心にあるブラックホールが吸い込んだガスとちり。
内部では物質同士の摩擦によって、温度が数十万度以上に上昇、物質はプラズマ化してしまい、X線や可視光線などの電磁波を放出するように。それらが光り輝いてクエーサーの源となっているのです。
ちなみにJ0529-4351は、直径7光年でそのサイズも宇宙最大規模なんだそうですよ。
太陽の500兆倍…。やっぱり宇宙は桁違いのスケールでした。
詳しくはコチラ↓
宇宙人は“紫色の星”にいるらしい
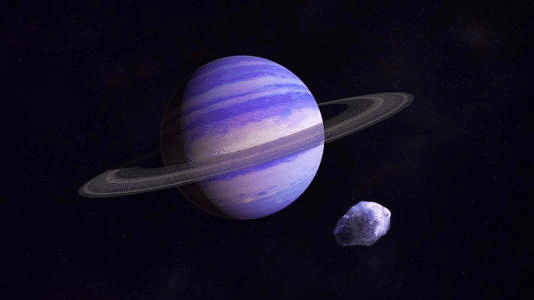
最後は宇宙人のお話。
もし宇宙のどこかに生命を宿した惑星が存在しているとしたら、そもそもそれは地球のように青く輝いていないかもしれない。むしろ、かなり大胆な紫色かもしれないんです。
研究者チームが発表したところによると、地球外生命体の痕跡を探す上で重要視されるべきは紫色の惑星なのだそう。
この紫色の正体は、紅色細菌。彼らは幅広い環境条件において繁茂するうえに、その星全体に独特な反射率スペクトル(要はどぎつい紫色)を与えます。
紅色細菌には水生と陸生の両タイプがあり、いずれも光合成を行ない、可視光や酸素をほとんど必要としない微生物。地球上でも遠浅の海や海岸沿い、湿地帯、または深海の熱水噴出孔などに生息しています。
そして実のところ、この紅色細菌こそが、30億年前に地球上に生命が誕生したときにもっとも多く繁殖した生命体のひとつであるとも考えられているんだとか。
空から降ってくる「地球外物質X」…素粒子とはいったい何者なのか
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 によるストーリー
138億年前、点にも満たない極小のエネルギーの塊からこの宇宙は誕生した。そこから物質、地球、生命が生まれ、私たちの存在に至る。しかし、ふと冷静になって考えると、誰も見たことがない「宇宙の起源」をどのように解明するというのか、という疑問がわかないだろうか?
本連載では、第一線の研究者たちが基礎から最先端までを徹底的に解説した『宇宙と物質の起源』より、宇宙の大いなる謎解きにご案内しよう。
*本記事は、高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所・編『宇宙と物質の起源「見えない世界」を理解する』(ブルーバックス)を抜粋・再編集したものです。
空から降ってくる「地球外物質X」
私たちは原子でできていて、その原子をどんどん細かくしていくと、アップクォーク、ダウンクォーク、電子という3種類の素粒子にまで分解できます。私たちの身の回りのものはすべて、この3種類の素粒子からできています。では、この宇宙はアップクォーク、ダウンクォーク、電子の3つだけでできているのでしょうか。
実は、この宇宙にはもっとたくさんの素粒子が存在しています。ものをつくっている素粒子は3種類だけなのですが、何もないと思っていた空間をよく調べてみると、いろいろな素粒子が飛んでいたのです。

これらの素粒子は、宇宙からやってくる放射線(宇宙線)が大気中の窒素や酸素などの原子核にぶつかることでつくられます。このようにしてつくられる素粒子の1つがミューオン(ミュー粒子)です。
普段の生活ではまったく聞かない名前です。実は、発見した当時の物理学者たちも「何だ、それは!?」と思いました。というのも、ミューオンはものをつくるのにはまったく関係なく、何に使われているのかがわからなかったからです。ミューオンの役割があまりにもわからなかったために、高名な物理学者が「いったい誰がこんなものを注文したのだ」と叫んだというエピソードがあるくらいです。
いったい、ミューオンって何?
ミューオンは、電子より200倍も重い粒子です。重さ以外は電子と同じ性質をもっています。宇宙線が大気にぶつかって、たくさんのミューオンがつくられ、たくさんのミューオンが、この地上に降ってきています。このミューオンもこれ以上細かくならない素粒子で、大きさは電子やクォークと同じように、10-18メートルより小さいとしかわかっていません。
ミューオンは、1平方センチメートル当たり毎分1個の割合で地上に降ってきていて、私たちの体を通過していきます。もし、ミューオンを見ることができる「ミューオンめがね」があれば、私たちの手のひらを1秒に1個ぐらいの割合で、ポツ、ポツと雨粒のように通過するミューオンを見ることができるでしょう。ミューオンは、電子に変化するという性質があるために、すべて電子に変わってしまいます。
地上で観測される素粒子は、ほとんどが宇宙線と大気がぶつかってできます。地球と宇宙の境目あたりでつくられるので、厳密に言うと、宇宙から降ってくる物質ではありません。
宇宙からの物質が直接地上にやってこないのは残念な気もしますが、そのおかげで地球は守られているとも言えます。宇宙線は、とてもエネルギーが高い放射線の一種です。そのままの状態で地上までやってくると、生物の遺伝子を傷つけてしまい、その傷が多くなると生物は生きていけません。大気とぶつかってたくさんの素粒子ができることで、エネルギーが低くなり、私たちが暮らせるようになっています。
では、遠い宇宙から降ってくる地球外物質は、まったくないのでしょうか? あります。ニュートリノです。

2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊博士は、大マゼラン雲で誕生したニュートリノを地球上で観測することに成功しました。ニュートリノは、この宇宙にあるほとんどの物質を通り抜けることができて、しかも寿命が長い(他の素粒子に変化しない)ので、はるか彼方の宇宙の様子を知る手掛かりになることからも注目されています。
ちなみにニュートリノは、ミューオンとは比べものにならないほどたくさん地上に降り注いでいます。その数は1平方センチメートル当たり毎秒660億個。私たちの体を通過するのは毎秒600兆個にもなります。だから、「ニュートリノめがね」をつくることができれば、ゲリラ豪雨のようにニュートリノが地上に降っている様子を目にすることになるでしょう。このニュートリノもまた、大きさがわかっていない素粒子なのです。
数々のノーベル賞を生んだ「魔法の箱」
宇宙線でつくられる粒子はミューオンだけでなく、湯川秀樹博士が予測した中間子などもあります。中間子はクォークと反クォーク(後述します)の組み合わせでできている粒子で、名前は電子と陽子の中間の重さだったことに由来します。これらの粒子を観測することで、素粒子の世界がだんだんとわかってきました。ただし、宇宙線でつくられた粒子たちは、私たちのそばをいつも飛んでいるのですが、目で見ることはできません。これらの粒子を見るには特別な装置が必要です。
実は、宇宙線でつくられる粒子を見ることに初めて成功したのは、気象学者でした。イギリスの気象学者チャールズ・ウィルソン博士が、実験室で雲や霧を再現する箱形の装置をつくったところ、その中を白い筋状のものがたくさん飛ぶのが見えたのです。それが、宇宙線でつくられた電気を帯びた粒子でした。
この箱の中には、とても冷やされた水蒸気がたくさん入っています。そこに電気を帯びた粒子が飛んでくると、その粒子が空気を蹴散らすことで電気のトンネルがつくられます。電気のトンネルに集まってきた水蒸気が小さな水滴になり、粒子の軌跡をなぞる飛行機雲のようなものが見えるのです。この装置は、「ウィルソンの霧箱」と名付けられました。
ウィルソンの霧箱の原理はとても簡単で、身近なものを使って簡単につくることができます。私たち高エネルギー加速器研究機構(KEK)の出張授業でも、この霧箱をつくって観察するプログラムがあります。

でも霧箱が発明された当時は、たくさんの物理学者が驚きました。顕微鏡でも見ることのできない小さな粒子を見ることができたからです。実際には、粒子そのものではなく、小さな粒が通過した跡(飛跡)が見えるのですが、飛跡の密度から電荷を算出でき、磁石を使って飛跡の曲がり具合から粒子の勢いがわかります。このように工夫をすれば必要な情報を十分に得ることができることから、人類は粒子そのものを観測できなくてもいいのだと気が付きました。
最初に素粒子を観測した装置が霧箱でしたが、その後、飛跡の通過位置や時刻をより正確に記録するために電気信号を利用するなどと発展し、現代の素粒子測定器につながっています。ウィルソン博士は、この霧箱の発明によって1927年にノーベル物理学賞を受賞しました。
物理学史上、最も独創的な装置
ウィルソンの霧箱は、物理学の歴史を通じて最も独創的な装置といわれています。それは、この装置により数々の重要な発見がなされたからです。
まず1つは、アメリカの物理学者カール・デイヴィッド・アンダーソン博士による陽電子の発見です。陽電子とは電気的な性質だけが反対になっている電子のことです。電子はマイナスの電気をもっているので、陽電子はプラスの電気をもっています。それ以外の性質は電子とまったく同じという、変わった粒子でした。プラスの電気をもつ陽電子の存在は1928年にイギリスの物理学者ポール・ディラック博士が予測していたのですが、アンダーソン博士が1932年に発見するまでは、本当に存在するとはあまり信じられていませんでした。地球上では発生してもすぐに消えてしまうので、誰も気付かなかったのです。
ところが、当時27歳のアンダーソン博士が霧箱を使って陽電子の飛跡の写真を発表したことで物理学の常識が書き換わり、世界の物理学者の間で大騒ぎになりました。アンダーソン博士は、霧箱を使って撮影したこの1枚の写真のおかげで、1936年にノーベル物理学賞を受賞しました。そしてまた、陽電子の存在を理論的に予測したディラック博士自身はアンダーソン博士が陽電子を発見した翌年の1933年にノーベル物理学賞を受賞しています。

図「アンダーソン博士が霧箱を使って撮影した陽電子の飛跡」はアンダーソン博士が論文に発表した、霧箱を使って陽電子を発見したときの写真です。
アンダーソン博士は霧箱の中央に6ミリメートルの鉛の板を置きました。霧箱が捉えた陽電子の飛跡は、左下から左上に伸びる髪の毛のような細い線です。霧箱全体が磁場の中に入れられているので、荷電粒子の飛跡は曲げられます。鉛の板を通過した後は荷電粒子は勢いを落とすので、曲がり具合が大きくなります。この写真では、荷電粒子が左下から入って左上に抜けたことがわかるのです。
記録された荷電粒子の飛ぶ向きが判明したので、磁場情報からこの荷電粒子はプラスの電気をもつことが判明しました。また、撮影された荷電粒子が形成した飛跡の密度から電荷の大きさがわかり、電子のもつ電荷の絶対値に一致したのです。
対で生まれる素粒子
アンダーソン博士が発見した陽電子は、実は、人類が初めて出会った「反物質」でした。反物質というのは、普通の物質と電気的な性質が反対の物質のことです。
陽電子は、マイナスの電気をもっている電子の反物質になるので、プラスの電気をもっていて、その他の性質は電子とまったく同じです。電気の性質さえ関係なかったら見分けがつきません。なぜ、そんな粒子がこの世界に存在するのかというと、それは素粒子の生まれ方に関係があります。
ものをつくるのに関わっている電子やクォークなどの物質素粒子は、基本的に独りぼっちで生まれることはありません。いつも自分とパートナーになる反物質と一緒に生まれます。
後から詳しくお話ししますが、素粒子のもととなるのはエネルギーです。何もないように見える場所でも、エネルギーがあれば素粒子が生まれます。でも、電気を帯びた素粒子が1個だけ生まれてしまうと、電気の量のバランスが崩れてしまいます。そのバランスを保つために、その素粒子と電気的な性質が反対の、対になる反物質が生まれる仕組みになっています。
一緒に生まれた素粒子と反物質は、とても仲良しなので、消滅するときも一緒です。電子と陽電子のように、その素粒子と対になる反物質がぶつかると、消えてなくなってしまいます。合体してエネルギーになってしまうのですね。このように素粒子が反物質と一緒に生まれることを「対生成」、一緒に消滅することを「対消滅」と言います。

イギリスのパトリック・ブラケット博士は、光が電子と陽電子に変化する現象を見つけました。光は電気をもっていないので、霧箱で観察してもその飛跡を見ることはできません。でも、電子や陽電子が通ると飛跡が見えます。
ブラケット博士は、何もなかったところから、突然、2本の飛跡が生まれる現象を発見しました。しかも、その2本の筋は磁力をかけると逆方向に曲げられたことから、マイナスの電気をもった電子と、プラスの電気をもった陽電子だということがわかりました。つまり、ブラケット博士は、電子と陽電子が対生成する瞬間を撮影したのです。霧箱を使ったこの対生成現象の確認に対して、1948年にノーベル物理学賞が贈られています。
* * *
たった「10億分の1秒」で、この世界のすべてが爆誕…!138億年前の宇宙で「物質が生まれた瞬間」
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 によるストーリー
138億年前、点にも満たない極小のエネルギーの塊からこの宇宙は誕生した。そこから物質、地球、生命が生まれ、私たちの存在に至る。しかし、ふと冷静になって考えると、誰も見たことがない「宇宙の起源」をどのように解明するというのか、という疑問がわかないだろうか?
本連載では、第一線の研究者たちが基礎から最先端までを徹底的に解説した『宇宙と物質の起源』より、宇宙の大いなる謎解きにご案内しよう。
*本記事は、高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所・編『宇宙と物質の起源「見えない世界」を理解する』(ブルーバックス)を抜粋・再編集したものです。
太陽系で観測される元素
加速器が発明された20世紀初頭、加速器で加速した原子核を他の原子核に当てて原子核反応を引き起こし、原子核の性質などを調べる原子核物理学が急激な発展を遂げました。同時に、原子核物理と宇宙の成り立ちや星の性質などを調べる宇宙物理・天文観測が結び付き、元素の起源を解明する天体核物理学が産声を上げました。そこで得られた知識をもとに、天然に存在する94種類の元素の歴史をひもといていきましょう。
「図:太陽系で観測された元素の存在量」は、われわれの住む太陽系で観測される元素の存在量を示しています。横軸は、原子番号で表される元素の種類です。縦軸は、太陽系で観測された元素の存在量を、原子番号14のケイ素(シリコン)の存在量を106としたときの相対値で示しています。

太陽系で観測された元素の存在量© 現代ビジネス
存在量の全体的な傾向を見ると、原子番号が小さいほど多く、原子番号が大きくなるにつれ少なくなっていきます。存在量が多いのは原子番号1の水素と2のヘリウムで、全体の98%程度を占めています。原子番号6の炭素(C)、8の酸素(O)、10のネオン(Ne)、14のケイ素(Si)、そこから少し離れた原子番号26の鉄(Fe)の存在量も多いです。
それ以上の原子番号で存在量がやや多いものとして、32のゲルマニウム(Ge)や38のストロンチウム(Sr)、54のキセノン(Xe)や56のバリウム(Ba)、78の白金(Pt)や79の金(Au)、82の鉛(Pb)などがあります。それらの元素は、原子核が中性子を吸収(捕獲)して生成されました。
原子番号3のリチウム(Li)、4のベリリウム(Be)、5のホウ素(B)の量は、水素やヘリウムに比べて8桁も少ないです。これは質量数5および8に安定な同位体がない、という原子核の特徴によるものです。
不安定な原子核では、構成する陽子や中性子が、周囲の安定な原子核よりも緩く結合しています。そのため、原子核反応や原子核の崩壊が起こりやすく、存在量としては少なくなってしまいます。
現代の元素の起源に関する知識によれば、水素、ヘリウム、リチウムの大半は138億年前の初期宇宙の環境で生成され、鉄の周囲までの元素は光り輝く星の内部で生成され、鉄より重い元素は進化に伴う星の表面や極端な天体環境で起きた中性子捕獲を起源にもつ、と考えられています。なぜそのように理解できるのか、もう少し詳しく見てみましょう。
初期宇宙の元素合成
宇宙はその誕生直後から、ビッグバン、つまり英語で「大きな爆発」と名付けられるような激しい膨張を経験してきました。それは、大爆発と言うように、宇宙全体を包み込む光の塊が激しく膨張する現象です。光の塊とは、多くの素粒子が激しく光りながら衝突している状態です。それが時間とともに大きく膨張するのです。
宇宙膨張とは、素粒子自体が膨張するのではなく、それら粒子と粒子の間隔を広げながら膨張していくことを意味します。当時小さかった宇宙の中では、粒子の密度が高く粒子同士の散乱が激しくて、飛び交う光子などの素粒子が高エネルギーの状態のまま閉じ込められて、火の玉のようになっていたのです。
例えば、太陽の光っている部分(光球)の様子は、その状況に極めて似ています。太陽の光球は、5500度を超える高温の光が、粒子との散乱により太陽の中に閉じ込められている状態なのです(本書では断りのない限り、温度の「度」は絶対温度[K]を意味します)。

宇宙初期の火の玉は、約1000億度を超える温度でした。この火の玉が138億年かけて膨張し、それとともに温度が下がり、現在の138億光年(その間、膨張を続けているので、正確には約440億光年)先まで広がる絶対温度約3度(マイナス270℃)の極低温の宇宙となったのです。
初期宇宙の元素合成の物語は、宇宙の年齢が約10億分の1秒よりずっと前、宇宙の火の玉の温度が約1000億度よりずっと高いころから始まります。大きさが約30センチメートルにも満たない火の玉の中には、光子、電子、ニュートリノ、クォーク、グルーオンなどの素粒子とその反粒子が、ぎゅうぎゅう詰めに閉じ込められ、激しく反応していました。このころに、ある機構によりクォークの数と反クォークの数の間に非対称が生まれたと考えられています。
このクォーク・反クォークの間の非対称性、つまり物質と反物質の間の非対称性の誕生は、「バリオン数の生成機構」と呼ばれます(バリオン数とは、正味の原子の数のことです)。このときより、クォークの数が反クォークの数より約10億個に1個だけ多い宇宙となったのです。これが厳密な意味で、宇宙における物質の誕生です。
その後、宇宙の年齢が約1万分の1秒後、温度が約1兆度のころになると、若干多い物質と若干少ない反物質とで非対称に存在したクォークとグルーオンから、陽子と中性子がつくられます。陽子は、水素原子の原子核です。このころ、陽子と中性子は、弱い力(弱い相互作用)で電子とニュートリノを交換しながら激しく入れ替わっています。弱い力は、大きさは電磁気力より弱いですが、この時期は陽子と中性子にとても高い頻度で作用していたのです。このときの陽子に対する中性子の割合は、ちょうど1:1です。中性子はわずかに陽子より重いため、その比は時間とともにだんだん変わってきます。
宇宙の年齢が約1秒まで進み、温度が約10億度になると、弱い相互作用をするニュートリノが、火の玉の中の散乱だけでは閉じ込められなくなって、自由に飛び回るようになります。そして、このころに、同じく弱い相互作用による陽子と中性子の入れ替わりの反応が止まってしまいます。なんとそのとき、理論計算によりわかることなのですが、中性子の数は、陽子の数の約7分の1にまで減ってしまっています。そして、この7分の1という中性子の数が、後の宇宙全体のヘリウムの量を決めてしまうのです。
火の玉の中でおきた「2つの粒子の衝突」
この火の玉の中で、2つの粒子が衝突して、より重い元素を一歩一歩つくる反応を起こします。
まず、宇宙の年齢が約3分になるまでに、陽子と中性子が衝突して重水素をつくるようになります。そして、つくられた重水素と重水素が衝突して三重水素もしくはヘリウム3(陽子2個と中性子1個からなる)をつくり、三重水素もしくはヘリウム3と重水素が衝突してヘリウム4(陽子2個と中性子2個からなる)をつくります。三重水素は放射線(ベータ線)を出して崩壊してヘリウム3をつくります。ここまでが約5分で完了します。

続いて、ヘリウム4に三重水素やヘリウム3が衝突することにより、リチウムやベリリウムなどのさらに重い原子核がつくられました。ここまで、約10分です。このようにして、宇宙全体で核融合反応が次々と起きたのです。ベリリウムは、150日後にリチウムに崩壊します。こうして、宇宙全体でリチウムまでがつくられます。
恒星の中のようなもっと高密度の環境ならば、2つの粒子が衝突する核融合反応によってさらに重い元素もつくられたかもしれませんが、ビッグバン直後の宇宙全体の密度では、ここまでです。この宇宙初期の元素合成は、「ビッグバン元素合成」と呼ばれます。
ヘリウム4は、ビッグバン元素合成によってつくられる元素の中でもとても安定であるため、元素の重量比にして実に約4分の1という多くの量が合成されるのです(約4分の3は水素です)。宇宙の年齢が約1秒のとき、中性子の数は陽子の数の7分の1でした。宇宙にある中性子がほとんどすべてヘリウム4に取り込まれると仮定して計算すると、合成されるヘリウム4は、重量比にして元素全体の4分の1となります。理論的に導き出されたこの値が、観測データと完全に一致するのです。このことからビッグバン元素合成は、ビッグバン宇宙モデルを支える3つの観測事実の1つとなっています(他の2つは、宇宙膨張と宇宙マイクロ波背景放射の存在です)。
さて、とても皮肉ですが、昨今あらゆる電子機器に使用されているリチウムイオン電池に用いられるリチウムは、実はビッグバン元素合成が主な源ではありません。その多くは、高エネルギー宇宙線陽子などによる、恒星の表面での炭素、窒素、酸素の破壊によってつくられた成分なのです。つまり、太陽系が生まれるもっと前に存在していた恒星の表面でつくられたリチウムが、その恒星の死後、他の元素とともに45.4億年前に地球に取り込まれたのです。
そうした複雑な元素の起源のバリエーションが生まれる理由は、われわれの太陽系が銀河系の円盤部分に誕生したことにあります。銀河の円盤部は宇宙線の量が多く、また、頻繁に恒星が生死を繰り返す環境だったのです。
* * *
やさしい物理講座v35「光の真空中の減衰作用は暗黒物資の素粒子『アクシオン』かも知れない」|tsukasa_tamura (note.com) より以下一部再掲載する。
以下一部再掲載内容
アクシオン(英語: Axion)
あるいはアキシオンとは、素粒子物理学において、標準模型の未解決問題のひとつである強いCP問題を解決する仮説上で、その存在が期待されている未発見の素粒子である。冷たい暗黒物質の候補の一つでもある。
アクシオンは強いCP問題の解決策の1つとして提唱された未発見の粒子である。アクシオンはペッチェイ・クイン対称性(英語版)の自発的対称性の破れに伴って出現する(擬)南部・ゴールドストーン粒子である。ペッチェイ・クイン対称性は量子色力学に対してアノマリーを持ち、この性質によりアクシオンは量子色力学の位相を動的に吸収することが可能となっている。
想定される性質(光子と反応する)
様々な実験や観測を考慮した結果、アクシオンの質量は電子の約1億分の1以下という非常に微小なものだと考えられている。
また、光子と非常に弱いながらもお互いに反応するため、光子との反応を使った探索方法が有力なものの一つとなっている。
特に、磁場とアクシオンの反応によって光子を作る逆プリマコフ変換を利用した実験は数多くある。
観測実験
様々な理論により観測が試みられている。
代表的な検出原理[4]
プリマコフ効果でアクシオンを光子に転換
光子を検出
X線領域 : 太陽アクシオン - 半導体検出器による検出
マイクロ波領域 : 暗黒物質アクシオン - CARRACK , ADMX[6]
アクシオンは強い磁場の中で光に変わると予測されており、この性質を利用した検出が世界各国で試みられている。たとえば東京大学のグループは、太陽から飛来するアクシオンに強磁場を印加してX線に変換し検出する試みを行っている。暗黒物質の候補にもあげられているため、京都グループはリドベルグ原子を用いて検出する独自の着想により探索を続けている。アメリカのグループは、超伝導磁石を用いた強磁場の元で暗黒物質のアクシオンが電磁波に変換して検出を試みる最先端にいる。最近では素粒子実験物理学のメッカであるヨーロッパのCERNにおいても、太陽から飛来するアクシオンを大変高い感度で検出を試みる実験が進められている。
観測機器
望遠鏡
太陽中心では原子核や電子と黒体放射光子の相互作用により、平均エネルギー 4KeV のアクシオンが作られている可能性がある。このアクシオンを直接観測するため太陽アクシオン望遠鏡(東京アクシオンヘリオスコープ)が作られ観測が行われている。この望遠鏡は、磁場中でアクシオンをX線に変換することにより観測を試みている。
CARRACK
強磁場中に置かれた共振空胴内で光子に転換したアクシオンをリュードベリ原子に吸収させる。そしてこの原子のみをイオン化しその電子を計数する方式。
観測成果
2019年、京都大学、東北大学の研究グループは、原始惑星系円盤の観測によるアクシオンの探査法とその研究結果について発表した。原始惑星系円盤は同心円状の偏光パターンを持っており、アクシオンが存在すれば偏光パターンに渦巻き状の乱れが生じるとされる。研究グループはすばる望遠鏡の取得した原始惑星系円盤の観測データを用いて分析を試みたが、偏光パターンの乱れは見つからなかった。この研究により、アクシオンが光に与える影響度合いを示す「結合定数」の上限値を、これまでの研究の10分の1以下に小さく更新することに成功した。
2020年6月、イタリアのグランサッソ国立研究所で実施されているXENON1T実験において、「予想外の過剰な事象」が検出され、この原因としてアクシオンが関与している可能性が発表された。ただし、同じエネルギースペクトルにはトリチウムの崩壊によって生じる電子があるほか、ニュートリノが関与している可能性も排除されていない。
観測の精度は過去最高の99.98%に達したが、素粒子物理学の世界で発見と認められるには、99・9999%が必要とされる。そのため、今後さらに大規模で高感度なXENONnT実験によって真因が明らかになることが期待されている。
暗黒物質の候補でもあるが、2020年6月に3σで検出されたアクシオンは暗黒物質とは直接関係しない別のタイプのものとなる。
アクシオンの再解説
蓑輪 眞(物理学専攻 教授)
アクシオン(axion)は存在が予言されながら未発見の素粒子で,わずかに質量をもつと考えられ,暗黒物質の候補となっている。
連続的対称性の破れにともなって発生する南部・ゴールドストーンボソン(理学部ニュース2006年5月号「理学のキーワード第1回」参照)の一種である。 素粒子の弱い相互作用では粒子と反粒子の入れ替えについての不変性(CP不変性)が保たれていないことが分かっている(小林・益川理論)。 原子核をまとめている力,すなわち強い相互作用においても,それを記述する量子色力学(QCD)の基礎方程式には,理論では決まらない任意の「角度」に比例してCP不変性を破る項が含まれている。 ところが実験的には,強い相互作用においてはCP不変性が良い精度で保持されており,理論と実験が矛盾することから,「強い相互作用のCP問題」とよばれている。 1977年にR. ペッチャイ(Roberto Peccei)とH. クィン(Helen Quinn)は,「角度」変数を素粒子の場に関係する量とみなしてそのまわりの回転対称性を要請した上で,その対称性が破れて自然に安定点に落ち着くことで強い相互作用をCP不変に保つ仕組みを提唱した(PecceiQuinn機構)。 この対称性の破れに対応して南部・ゴールドストーンボソンの存在が同時に予言されて,アクシオンとよばれている。
アクシオンは強い磁場とレーザー光によりアクシオンと光子の結合を調べる非加速器素粒子実験によって精力的に探索が行われているが未発見である。 また,身の回りに希薄な密度で充満し,宇宙の暗黒物質を形成していると思われるアクシオンを,強力な磁場中でマイクロ波に変換してとらえる実験が,アメリカおよび京都大学でそれぞれ行われている。 筆者の研究室では,太陽の中で発生すると考えられるアクシオンを超伝導磁石による専用の望遠鏡(愛称Sumico)で探索する実験が行われている(理学部ニュース2004年7月号「望遠鏡ものがたり4」参照)。
My Opinion.
仮説:素粒子の存在が『光のエネルギーの減衰』という作用を及ぼす
第一候補の素粒子は「アクシオン」である。
暗黒物質で光子に影響力を及ぼすとされる未発見の素粒子アクシオンが「光のエネルギー減衰」作用の候補である。
もし、アクシオンの発見と光粒子(電磁波)とに「光の真空中の減衰」作用の影響が確認されるならば、今までの、赤方偏移の理由が「ドップラー効果」から「光の真空中の減衰作用」への宇宙天文学理論の180度の転換になる大事件となるであろう。
宇宙背景放射の原因
宇宙の暗黒物質の素粒子が光粒子(素粒子:電磁波)と親和性があり、138億光年先から伝播してくる光はその素粒子(候補:アクシオン)にエネルギーを与え、光エネルギーの減衰作用をおこした結果が赤方偏移と考える。恒星が観測者に対して運動した結果(ドップラー効果)の赤方偏移ではないことが明確になるのである。減衰した分のエネルギーは素粒子(アクシオン)から放出・拡散され、その結果が宇宙マイクロ背景放射の原因となるものと考える。それが宇宙の一様性問題の解決となる。
宇宙マイクロ波背景放射の温度は10万分の1の精度で等方的(方向に依存しない)。地球から見て、まったく逆の方向からやってくる電波の温度が一緒なのだ。逆の方向からやってくる宇宙マイクロ波背景放射が放出された場所は、現在の宇宙で約920~940億光年離れている(宇宙膨張説によると半径460~470億光年)といわれている。
色々な事実を俯瞰して見ると、これほどの距離だけ離れた場所が、示し合わせたように同じ温度だったということは、宇宙に散在する恒星からの光が前述した素粒子(候補アクシオン)によって放出・拡散されたことを示唆しているのである。
表題の「光のエネルギー減衰作用が暗黒物資の素粒子『アクシオン』かも知れない」が明白になるならば、天文物理学・理論物理学の一大騒動になるであろう。
以前掲載したブログの紹介
やさしい物理講座ⅴ60「ビックバン理論に疵瑕がある。相対性理論の否定と光の減衰理論」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座ⅴ59「重力波は検出できない」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v54「相対性理論の否定」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v49「天の川銀河の裏側の記事と自論」|tsukasa_tamura (note.com)
運動する媒質中の光速度|tsukasa_tamura (note.com)
「時間の遅れ(time dilation)」の錯誤|tsukasa_tamura (note.com)
光粒子(電磁波)の「chain理論」 副題 「量子entanglement(量子もつれ)」|tsukasa_tamura (note.com)
ミュオン(μ粒子)の寿命と仮説|tsukasa_tamura (note.com)
時間とキログラムの定義の解説|tsukasa_tamura (note.com)
私がビックバン理論(宇宙膨張説)を信じない理由 副題 光の減衰理論(仮説)|tsukasa_tamura (note.com)
特殊相対性理論(錯誤)で「思考停止」|tsukasa_tamura (note.com)
一般相対性理論(等価原理)の錯誤 副題 光は重力の影響を受けない|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v43「ニュートリノ(幽霊粒子)の有難い御利益(ごりやく)で新真実の解明か」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v42「途方に暮れる悩める人々のために『重力赤方偏移による原子時計の遅れ』を考察と慣性力の解説」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v41「光の重力の影響を重力赤方偏移で検証した実験への反証(メスバウアー効果の原因の追究)」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v40「”速く走ると重くなる”は否定される。質量のあるニュートリノを加速すると光速度を超える。」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v39「光時計の思考実験の検証(再解説・掲載)」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v37「花盛りのSF化した宇宙論」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v36「宇宙膨張説・ビックバン理論・宇宙インフレーション論の矛盾解消のため、『光の真空中の減衰理論』に道を譲るべき時期であろう」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v35「光の真空中の減衰作用は暗黒物資の素粒子『アクシオン』かも知れない」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v34「引力と斥力、反物質に対する重力の影響、宇宙膨張の斥力は? 暗黒物質・暗黒エネルギーの存在は?」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v32「光より速い素粒子(ニュートリノ)の真偽」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v31「ブラックホールが宇宙空間ガス物質で作り出す現象の光の屈折」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v28「『温度』と『熱』は何か」 |tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v27「『作用と反作用』、これが無重力の宇宙空間で移動することができる原理」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v26「いよいよ特殊相対性理論と一般相対性理論の終焉である。」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v25「数学者も解けない物理学における三体問題と摂動の解(怪)」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v24「『量子のもつれ』の原因は光が伝播する方向は逆方向も同時発生する」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v23「運動している物質中の光の振る舞い」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v22「放射光と慣性力」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v21「未発見の重力子、そしてKAGRA計画の重力波測定の研究成果の出ない理由」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v18「『オームの法則』には温度の条件も考慮が必要」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v17「量子力学から考察した素粒子の光子(フォトン)と重力子(グラビトン)とヒッグス粒子の考察」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v16「光粒子(素粒子:電磁波)と物質の相互作用」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v15「『近接場光』という不思議な『飛ばない光』とは何か」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v14「E=mc²の検証・・・まだ仮説のまま実証されていない、呵々。」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v13「光の真空中の減衰理論」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v12「三日月が輝く晩に太陽からの光に邪魔されず、星の輝きが見える訳」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v11「仮説を仮定の式で証明する。これは本当の証明にはならず数学的遊戯である」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v7「狂った時計で時間を測定する愚行、"Time Dilation”の詐術にご用心」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v6「『重力で光は曲がる』&『重力が空間を歪める』との主張に反論」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v5「光子(素粒子)には慣性力が働かないから『光時計』は理論的に機能しない。それは『時間の遅れ』の証明にはならない」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座v4「光子(素粒子)は質量0で重力の影響を受けない。」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座V3「素粒子を粒子と見ないで『場の考え方』が必要」|tsukasa_tamura (note.com)
今回の参考文献・参考資料
結局、宇宙は有限?無限? 宇宙ファンも混乱する問題を物理学者がとことん解説 (msn.com)
やさしい物理講座ⅴ64「『光のエネルギー減衰理論』」|tsukasa_tamura (note.com)
やさしい物理講座ⅴ63「空想が花盛りの宇宙論」|tsukasa_tamura (note.com)
おもわず誰かに話したくなる。サクッと読める宇宙の雑学まとめ (msn.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
